不動産投資に興味はあるけれど、多額の資金や物件管理の手間が心配――そんな悩みを抱える人が増えています。実は、上場不動産投資信託(REIT)なら数万円から間接的にオフィスビルや物流施設に投資でき、管理や賃貸業務は専門家に任せられます。本記事では「REIT 始め方」をテーマに、口座開設から銘柄選び、税制まで最新情報を交えてわかりやすく解説します。最後まで読むことで、今日から実践できるステップと注意点を具体的にイメージできるはずです。
REITとは何かを押さえよう
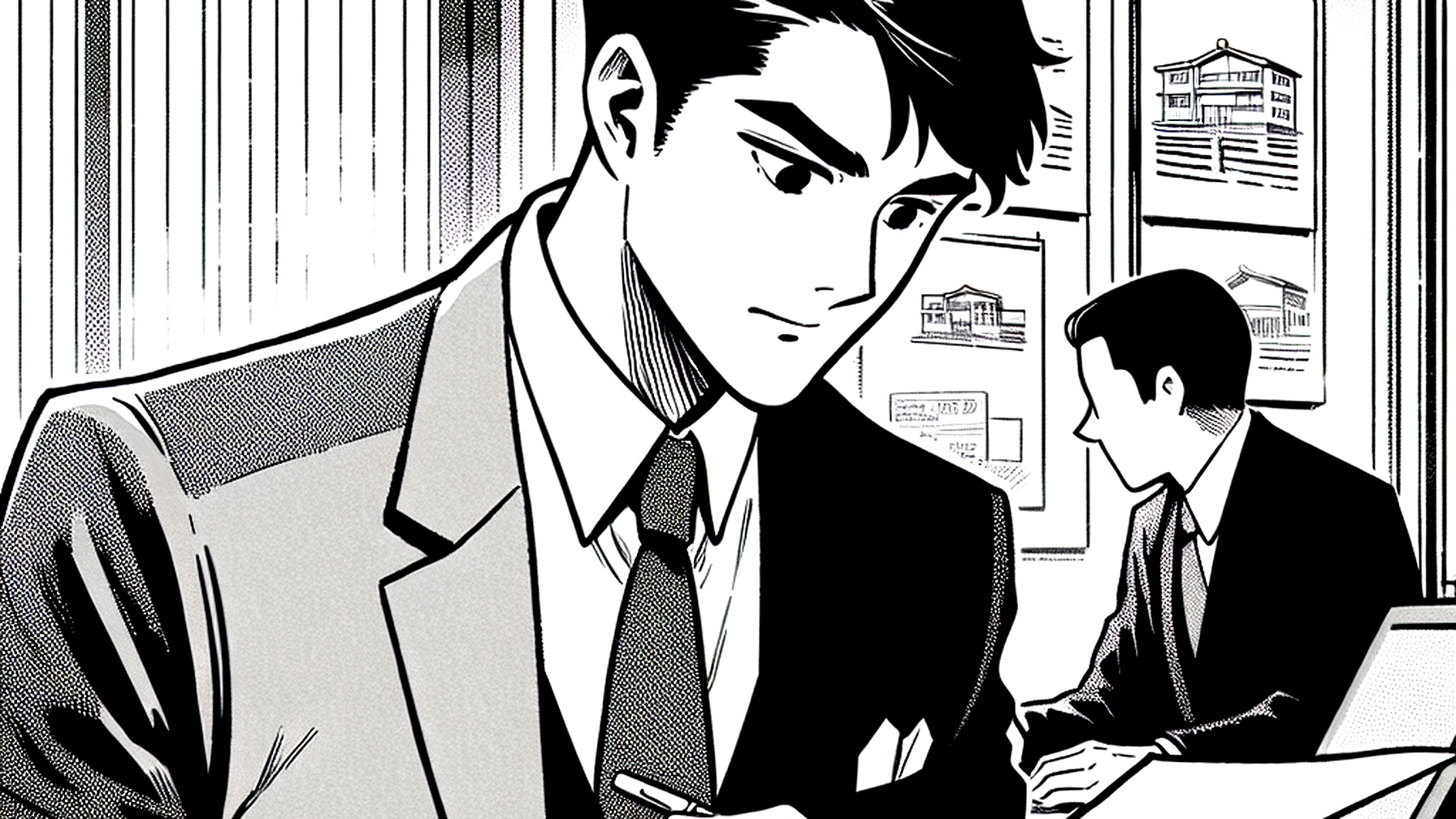
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口化して株式と同じように取引できる金融商品という点です。投資家は証券取引所を通じて投資口を購入し、家賃収入や物件売却益が分配金として還元されます。財務省の2024年度法人企業統計によると、国内REITの総資産は約23兆円に拡大しており、市場規模は年々厚みを増しています。
REITの魅力は配当利回りの高さです。東証REIT指数の平均分配金利回りは2025年8月時点で約4.1%と、長期国債利回りを大きく上回ります。さらに、不動産を直接所有する場合と異なり、空室対応や修繕計画を自分で行う必要がありません。つまり、本業が忙しい人でも少額かつ手間なく不動産収益を目指せるのです。
一方で、株式同様に価格変動リスクがあります。特に金利上昇局面では分配金期待が低下し、価格が調整する傾向があります。そのため、REITは「高配当の債券代替」ではなく、「不動産株式」という性格を持つ点を理解しておくことが重要です。
口座開設と銘柄選びのステップ
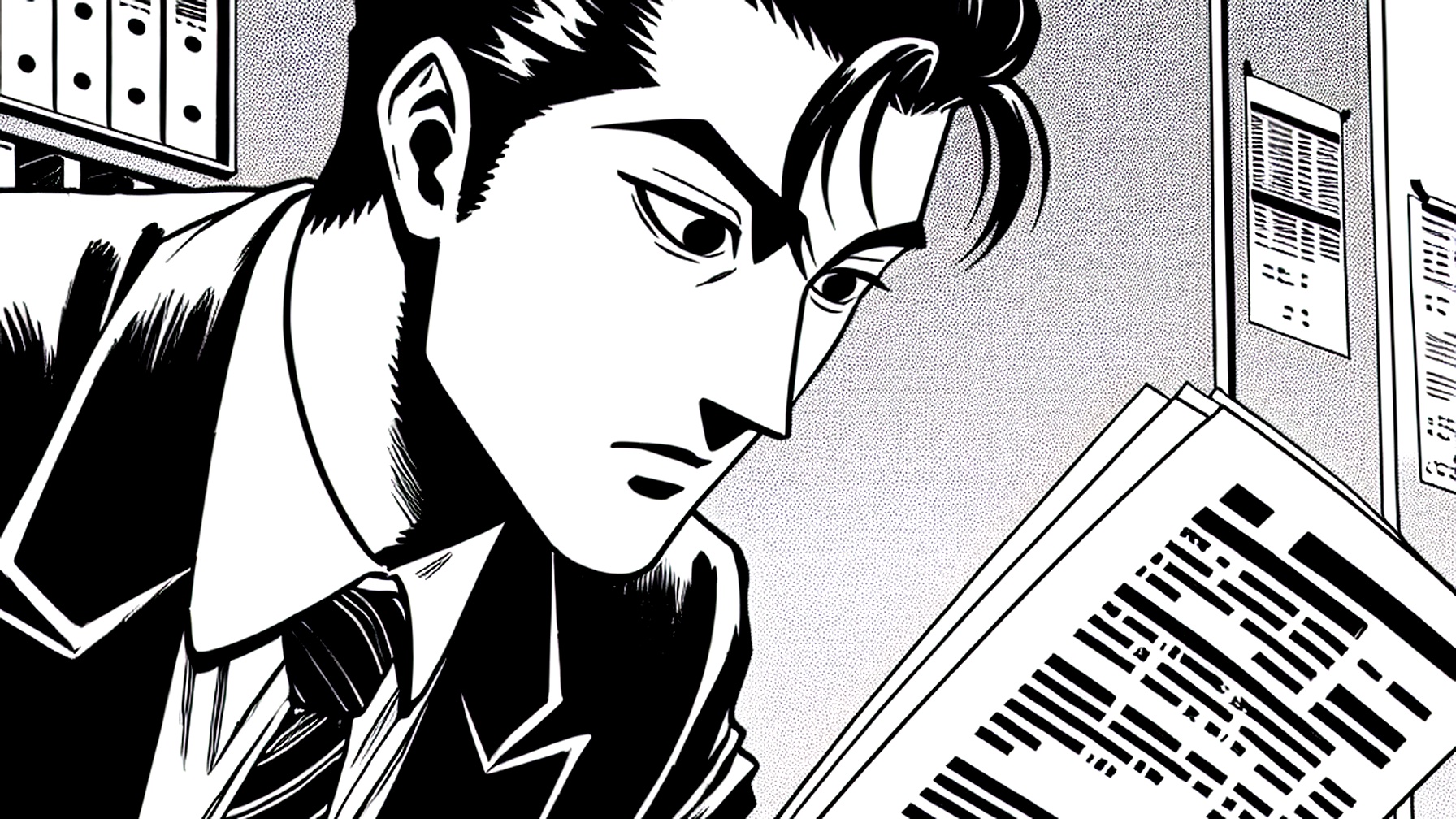
ポイントは、ネット証券で証券口座を開くことから始める点です。おおまかな流れは以下のとおりです。
- 本人確認書類を提出し、証券口座を開設
- REITを購入できる一般口座・特定口座を選択
- つみたて投資枠や成長投資枠を活用したい場合は新しいNISA口座も同時に申し込む
手続きはオンラインで完結し、最短翌営業日で取引が可能です。銘柄選びでは、資産タイプと経営指標をチェックしましょう。例えば、オフィス特化型は景気敏感度が高く、物流特化型はEC需要の増加で安定性が高い傾向があります。加えて、LTV(総資産有利子負債比率)が50%以下、NOI利回り(純営業利益/取得価格)が4%以上を目安にすると、過度な借入リスクを回避できます。
銘柄分散も忘れてはいけません。日本取引所グループのデータによれば、2025年9月時点で東証には63銘柄が上場しており、テーマや地域を組み合わせることでポートフォリオを柔軟に構築できます。まずは1〜3銘柄に均等投資し、値動きや分配金の推移を観察しながら追加購入するとリスクを抑えられます。
分配金と税金の基礎知識
重要なのは、分配金が株式配当と同じく「配当所得」として課税される点です。通常は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。ただし、2024年にスタートした新しいNISAの成長投資枠を使えば、年間240万円までの投資で得られる分配金が非課税となります。この枠は2025年度も存続しており、非課税保有期間が無期限に延長されているため、長期投資と相性が良い制度です。
また、特定口座を利用すれば年間の損益を自動計算してくれるので、確定申告の手間が省けます。万一、REITの価格下落で譲渡損が出た場合、株式やETFの配当益と通算できる点も覚えておきましょう。言い換えると、税金面の優遇策と損益通算をうまく使うことで、手取り利回りを高められるのです。
分配金の支払い時期は銘柄ごとに異なりますが、年2回が一般的です。決算月をずらして組み合わせれば、年間を通じて安定的にインカムゲインを得ることができます。実際、3月決算のJ-REITと9月決算の物流REITを組み合わせると、ほぼ半年ごとに分配金を受け取れる構成になります。
2025年度の制度と市場動向を読む
まず押さえておきたいのは、インフラ長寿命化とGX(グリーントランスフォーメーション)推進がREIT市場に追い風となっている点です。国土交通省「2025年度不動産関連施策概要」によると、省エネ性能の高いビルへ投資するREITには、低利融資や補助率2/3の改修支援が用意されています。これにより、環境性能を高めた物件は維持コストが下がり、分配余力が向上するという好循環が期待できます。
また、日本銀行が2024年にマイナス金利を解除し、政策金利を0.25%に引き上げたものの、長期金利は1%前後で安定しています。この水準では、借入コスト増よりも不動産収益の伸びが上回るケースが多く、REIT全体の分配金利回りは高水準を維持しています。日本取引所グループの月次レポートによれば、2025年7月の個人投資家によるJ-REIT売買代金は前年同月比18%増と、関心の高さがうかがえます。
さらに、政府が進めるスタートアップ支援策でオフィス需要が底堅く推移している点も見逃せません。産業別オフィス空室率は東京都心部で4%台に低下しており、賃料の上昇が分配金の押し上げ要因になっています。ただし、地方オフィスやホテル型REITは地域格差が大きいため、物件ポートフォリオの偏りには注意が必要です。
リスク管理と長期戦略
ポイントは、価格変動と金利リスクを計画的にコントロールすることです。具体的には、毎月定額で購入するドルコスト平均法を活用し、価格調整局面でも淡々と買い増す姿勢が効果的です。東証REIT指数は過去10年間で年率6〜7%の値動きを示しており、短期的な上下動よりも長期的なインカムとキャピタルゲインの合計がリターンの大部分を占めます。
また、分配金が減少した際の売却基準をあらかじめ設定しておくと、感情的な取引を避けられます。例えば、直近2期平均で分配金が15%以上減少したら一部売却するルールを設けると、財務悪化リスクを早期に切り離せます。さらに、ポートフォリオにインフラファンドや海外REIT ETFを混ぜることで、地域と通貨を分散する方法もあります。
最後に、毎年の決算報告書と資産運用報告書を確認する習慣が欠かせません。運用会社の戦略や資金調達状況を把握することで、次の資産入れ替えや増資による希薄化リスクを事前に察知できます。つまり、長期的に成功するには「買ったら終わり」ではなく、定期的なモニタリングとメンテナンスをセットで行う姿勢が求められるのです。
まとめ
REITは少額から始められ、手間なく不動産収益を得られる便利な投資手段です。市場規模の拡大と2025年度の省エネ支援策により、環境性能の高い物件を保有する銘柄には成長余地があります。一方で、金利上昇や分配金減少のリスクも存在するため、銘柄分散と定期的な情報チェックが欠かせません。今日紹介した口座開設から銘柄選び、税制活用、リスク管理の流れを実践し、自分に合った投資額で「まず一歩」を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産・建設経済局 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo
- 財務省 法人企業統計 – https://www.mof.go.jp
- 金融庁 NISA特設ページ – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 統計データ – https://www.boj.or.jp

