不動産クラウドファンディングに興味はあるものの、「そもそも誰が投資できるのか」「どうやって始めればいいのか」と迷っている方は多いでしょう。株式やREITより少額で不動産投資に参加できる点は魅力ですが、仕組みやリスクを理解せずに飛び込むと期待外れに終わる恐れがあります。本記事では、2025年10月時点の最新ルールを踏まえ、投資対象者の範囲と申し込み手順を中心に分かりやすく解説します。読み終えれば、自分が参加できるかどうかを判断でき、具体的なスタート方法までイメージできるはずです。
不動産クラウドファンディングとは
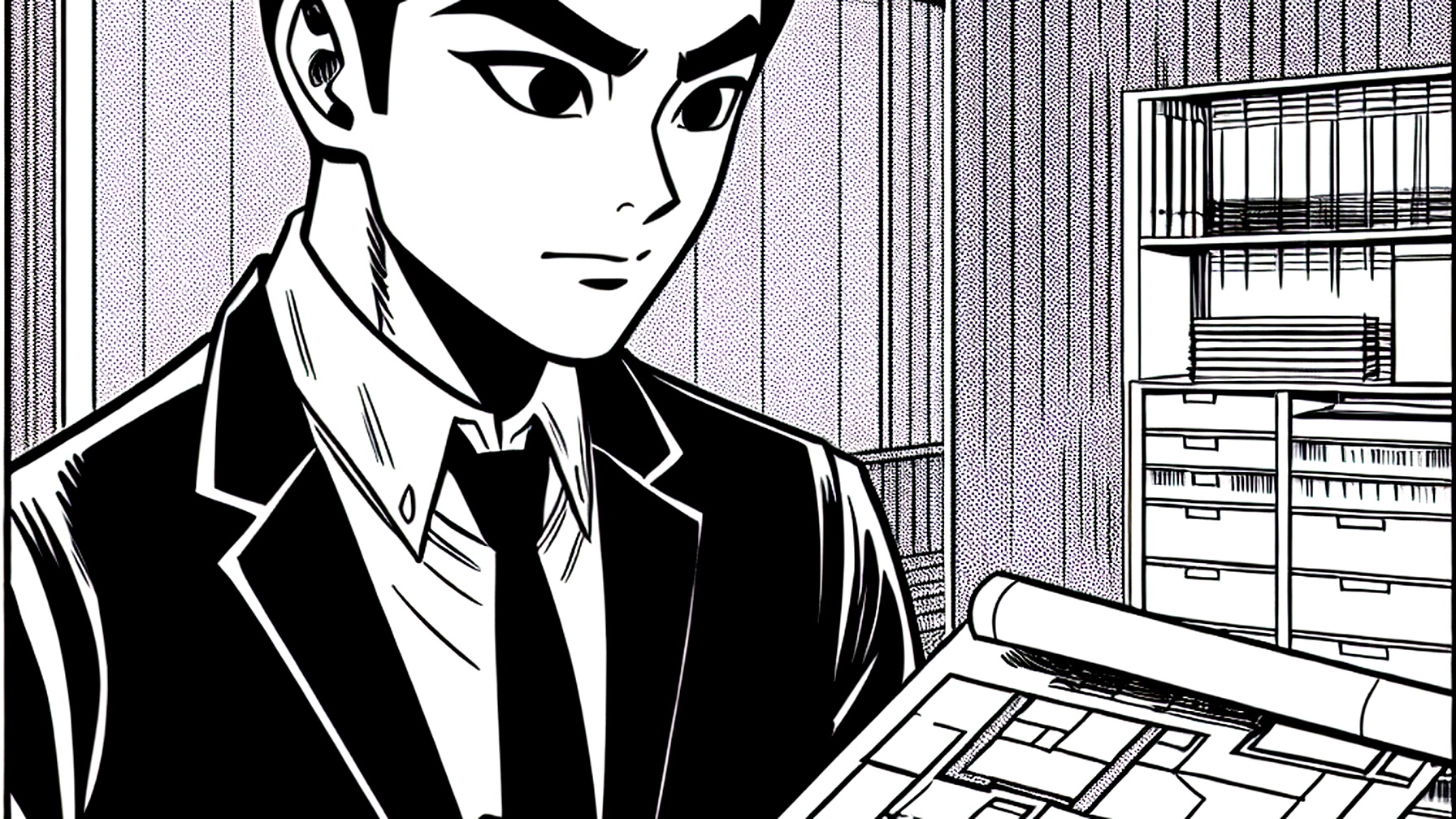
重要なのは、不動産クラウドファンディングが「不動産特定共同事業法」を根拠とする小口化スキームである点です。オンライン上のプラットフォームを通じ、多数の投資家が少額ずつ資金を出し合い、運営会社が物件を取得・運用し、その収益を分配します。金融庁の「電子取引業務に関するモニタリング結果」(2024年度版)によると、2020年以降の年間募集総額は毎年20%以上増加し、2024年度は1,500億円を突破しました。つまり、需要が高まりプレイヤーも急増している成長市場といえます。
一方で、多くの人が「クラウドファンディング」という言葉の柔らかな響きに油断しがちですが、実態はれっきとした不動産投資です。元本保証はなく、運営会社の倒産リスクや物件の空室率悪化リスクがつきまといます。また、運用期間中は途中解約ができない案件が大半で、流動性が低い点も忘れてはいけません。したがって、株式投資より安全でも、預金よりリスクが高い中間的な金融商品だと理解することが第一歩です。
参加できる「誰が」の範囲
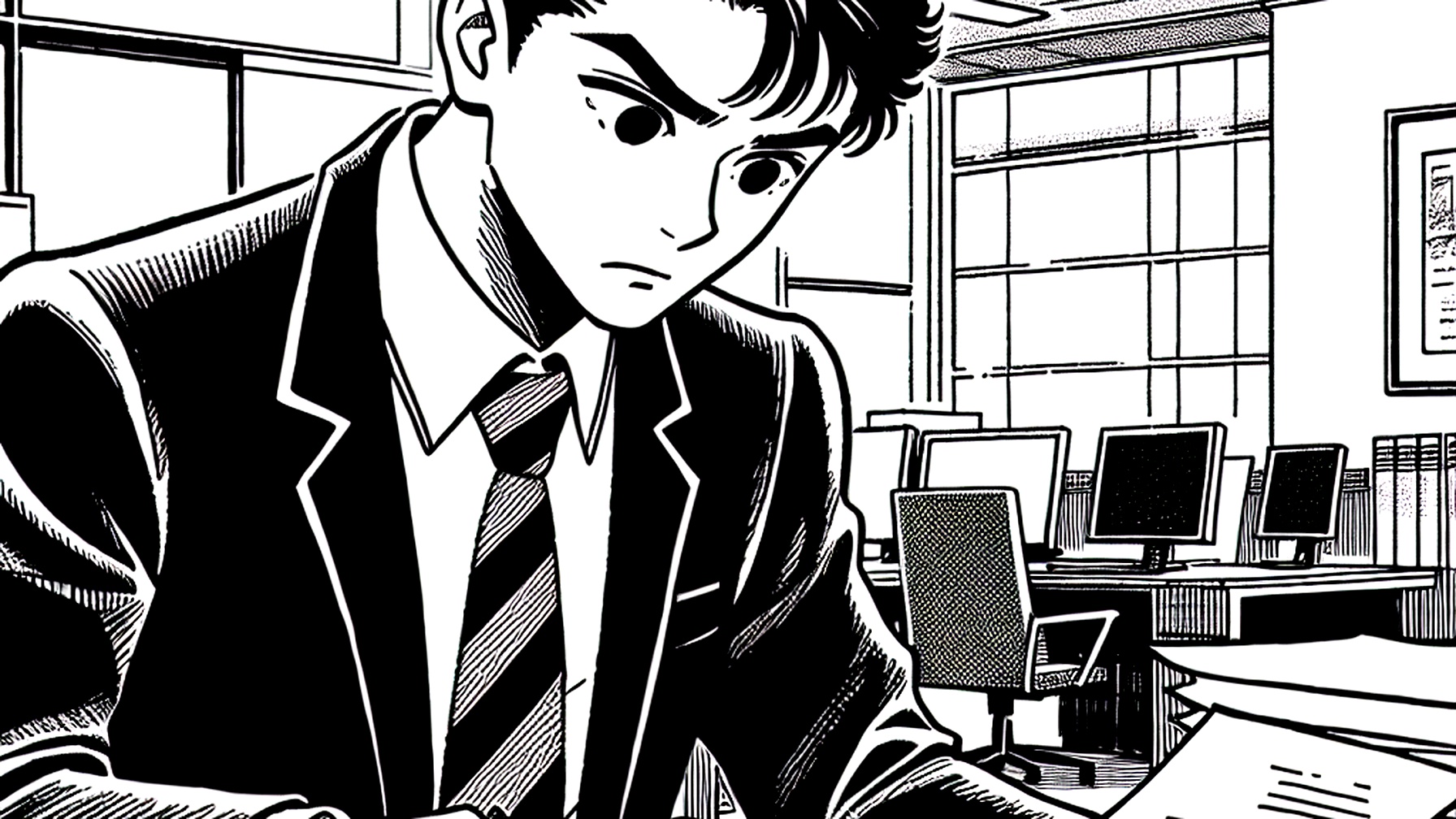
まず押さえておきたいのは、個人・法人いずれも原則として参加可能であることです。多くのプラットフォームは、満20歳以上の日本在住者であれば申し込みを受け付けています。未成年者の口座開設は2025年10月時点で認められていませんが、一般NISAと異なり、ジュニア向け枠の創設予定も公表されていません。
一方で、反社会的勢力に該当しない、外国PEPs(重要公的地位にある外国人)でない、といった犯罪収益移転防止法上の確認が必須です。本人確認に必要なマイナンバーカードや運転免許証を用意できない場合、口座開設はできません。また、法人の場合は登記簿謄本や決算書の提出が求められ、審査に2〜3週間かかることが多いです。つまり、個人の方が手続きは簡素ですが、職業・年収などによって投資上限額を設定する事業者もあるので、自身の属性と募集要項を照合しましょう。
海外居住者の扱いは事業者によって異なりますが、多くは日本国内に生活の本拠があることを条件にしています。税務上の扱いが複雑になるためで、マイナンバーの提出と国内銀行口座の紐付けが基本ルールです。したがって、長期出張や海外赴任を予定している方は、居住先変更のタイミングで利用継続が難しくなる可能性があります。
口座開設から投資までの始め方
ポイントは、①無料会員登録、②本人確認、③入金、④案件選定、⑤応募、⑥分配受取という流れを事前に把握することです。ここでは平均的な所要日数を示しながら、各ステップの注意点を説明します。
最初にプラットフォームの公式サイトでメールアドレス登録を行い、基本情報を入力します。その後、スマホで本人確認書類を撮影し、eKYC(オンライン本人確認)を済ませます。総務省の「デジタルID普及状況報告」(2025年6月)によれば、eKYC導入事業者は全体の92%で、郵送方式に比べ開設期間が平均4日短縮されたとされています。撮影不備を防ぐため、書類の四隅が写るように撮ることがコツです。
本人確認が終わると、運営会社が指定する入金口座がメールで届きます。入金は自身名義の銀行口座から行う必要があり、クイック入金(リアルタイム入金)サービスを使えば、即日反映される場合もあります。ただ、クイック入金は提携銀行が限定されているため、地方銀行を利用している人は振込手数料を考慮しましょう。
入金後に案件一覧を閲覧し、想定利回りや運用期間、優先劣後出資比率を比較検討します。優先劣後構造とは、運営会社が劣後出資者となり、一定割合まで損失を吸収する仕組みを指します。国土交通省「不動産特定共同事業に関するガイドライン」(2025年改訂版)では、劣後出資比率20%以上を推奨していますが、実際は10%未満の案件も散見されるため注意が必要です。応募はクリック一つで完了しますが、募集開始直後に満額成立する人気案件も多いので、事前にリマインダー設定を活用しましょう。
失敗しないためのチェックポイント
実は、想定利回りだけに目を奪われるとリスクを見落とします。たとえば同じ年利5%でも、運用期間が6カ月なのか3年なのかで複利効果と資金拘束期間が大きく異なります。短期案件は回収サイクルが早く資金を再投資しやすい半面、募集手数料を繰り返し負担する点がデメリットです。
さらに、貸付型(融資型)か不動産保有型かを見極める必要があります。貸付型は物件を保有せず、借り手の返済が焦げ付けば全損リスクがあります。一方、不動産保有型は物件を売却すれば一定の回収が見込めるものの、予定より売却が長引くと分配時期が延びる点がネックです。つまり、自分の資金計画に合わせて「安全性重視」か「流動性重視」かを選択することが重要と言えます。
手数料の内訳も確認しましょう。多くの事業者は投資家手数料無料をアピールしますが、実際には物件取得費や管理費を匿名組合契約内に含めており、利回りで相殺しているケースがあります。FSA(金融庁)の「ファンド費用に関する調査」(2024年度)は、手数料の透明性が高い事業者ほどリピート率が15%高いと報告しています。開示資料に「運用報酬◯%」と明記されているかどうかが見極めポイントです。
2025年度の制度と税制優遇を押さえる
まず、2024年に始まった新NISAは不動産クラウドファンディングの対象外ですが、税負担を抑える方法は存在します。2025年度も継続される「所得税の損益通算規定」により、雑所得として扱われる分配益は他の雑所得と合算でき、20万円以下なら確定申告が不要です。ただし、給与所得が2,000万円を超える方や、副業所得がある方は別途申告義務が生じる場合があります。
さらに、国土交通省が2025年度に延長を決定した「不動産特定共同事業電子取引業務試行許可」は、電子取引を行う事業者に対する登録要件を緩和し、オンライン完結を後押ししています。期限は2027年3月までと定められており、事業者の参入が今後も拡大する見込みです。投資家にとっては選択肢が増える一方、玉石混交になりやすいため、登録番号(例:東京都知事第◯号)を必ずチェックしましょう。
住民税については、分配益に対して5%が源泉徴収される仕組みが2025年も維持されます。海外不動産を扱う案件では外国税が差し引かれることもあり、二重課税防止のため「外国税額控除」の適用可否を確認しておくと安心です。税務処理に不安がある場合、国税庁のチャットボット「ふたば」(2025年正式リリース)を利用すれば、基本的な質問に24時間対応してくれます。
まとめ
不動産クラウドファンディングは、少額で不動産収益を狙える手軽さが魅力ですが、投資家自身がリスクを理解し、信頼できる事業者と案件を選ぶ姿勢が欠かせません。参加できるのは原則として日本在住の20歳以上の個人・法人で、口座開設から分配受取までオンラインで完結します。運用期間、優先劣後比率、手数料の透明性を比較し、2025年度の制度改正に伴う登録番号や税務ルールを確認すれば、失敗リスクを大幅に減らせるでしょう。まずは無料登録で案件資料を読んでみるところから一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省デジタル庁(デジタルID普及状況報告) – https://www.digital.go.jp
- 国税庁(外国税額控除ガイド) – https://www.nta.go.jp
- 不動産特定共同事業協会 – https://www.j-fta.or.jp

