不動産投資を始めたいものの、「税金が重いのでは」「木造とRC造(鉄筋コンクリート造)の違いが分からない」と悩む方は多いはずです。実は構造が変わるだけで減価償却期間や維持費が大きく変わり、節税効果にも差が生まれます。本記事では、2025年9月時点で有効な税制に基づき、RC造を軸にした不動産投資で賢く節税する方法を詳しく解説します。読み終えたころには、減価償却の仕組みから法人化の判断基準まで、初心者でも自信を持って意思決定できるようになります。
RC造が節税と相性が良い理由
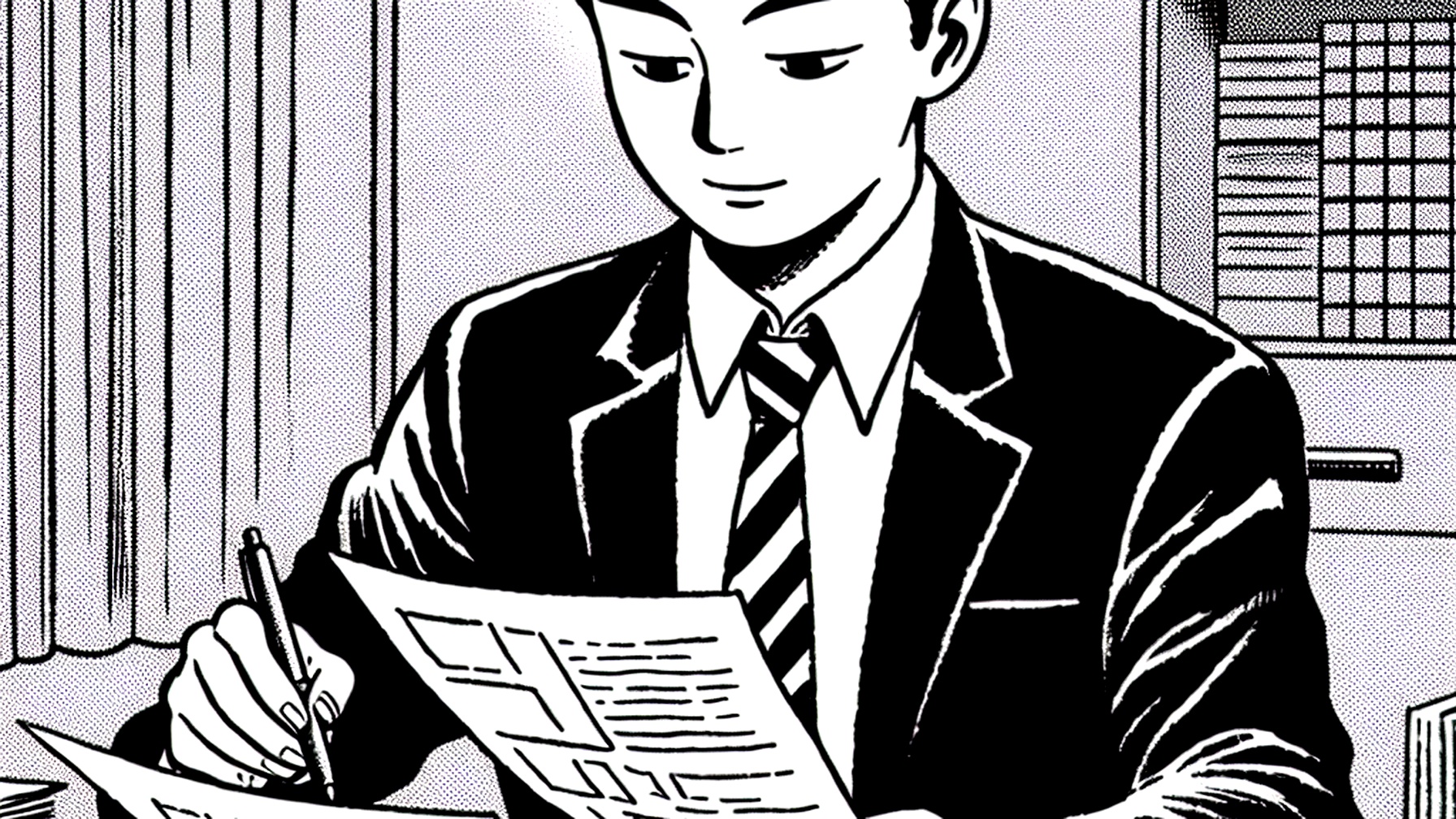
重要なのは、RC造が法定耐用年数47年という長期資産に分類される点です。耐用年数が長いほど減価償却費の計上期間が伸び、毎年の経費額をコントロールしやすくなります。また、木造より修繕頻度が低いため、突発的な支出が読みにくい初心者でも資金計画が立てやすいと言えます。さらに、金融機関が担保評価を高めに設定しやすい点も見逃せません。
国土交通省の住宅着工統計によると、都市部ではRC造の新築比率が10年前より約15%上昇しています。背景には、防災意識の高まりだけでなく、長期保有を前提とした富裕層や法人の節税ニーズがあると指摘されています。つまり、構造が投資戦略に直結する時代だと理解しましょう。
一方で、RC造は取得価格が高いため、最初の資金調達がハードルになります。しかし、長く安定した家賃収入を重視する金融機関が増え、2025年度の平均融資期間は木造より5〜7年長く設定される例が多くなっています。返済年数が伸びればキャッシュフローが改善し、節税効果と資金繰りを両立しやすくなります。
減価償却を最大化する実務ポイント
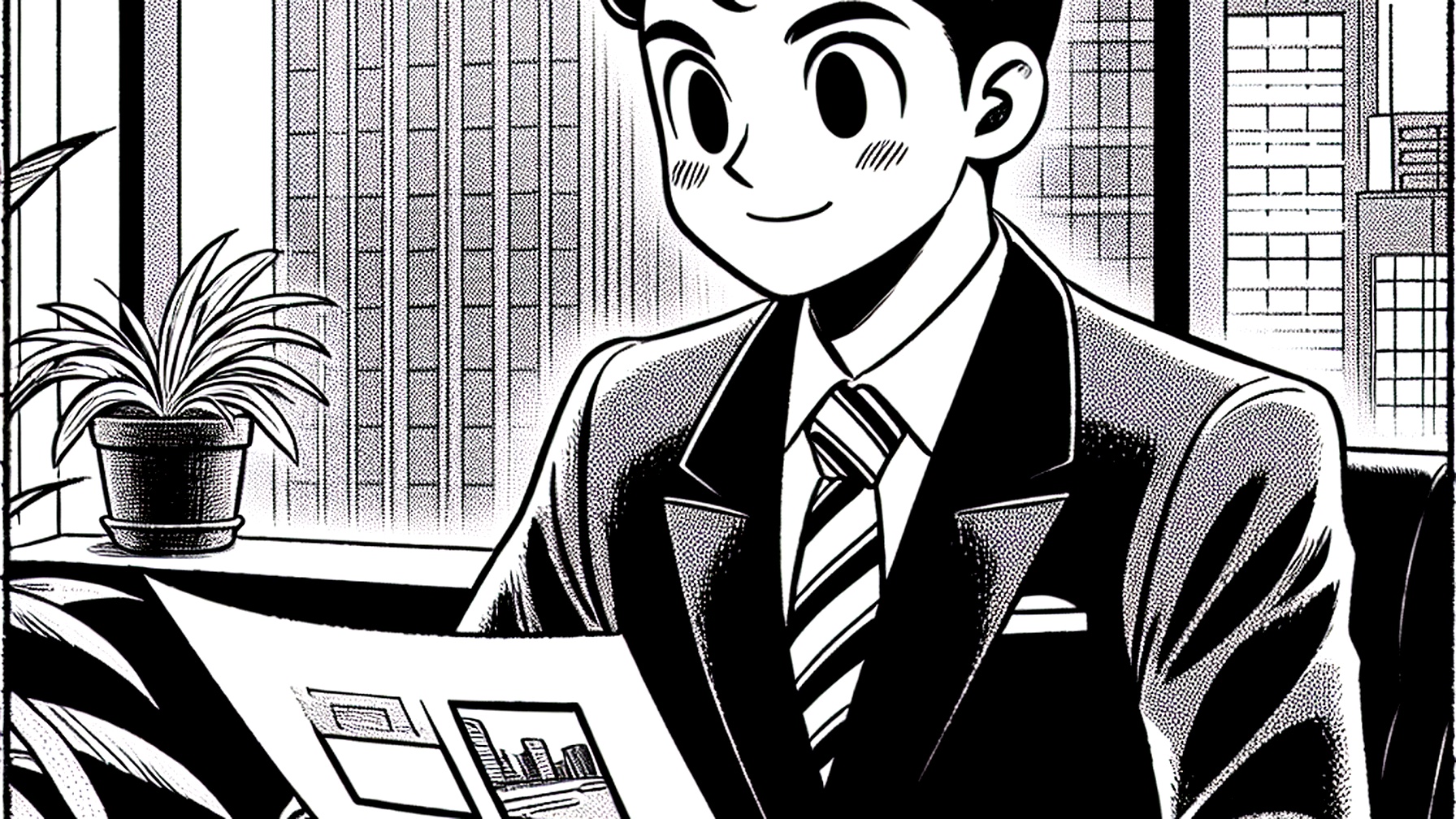
まず押さえておきたいのは、RC造の減価償却方法が定額法のみである点です。定率法と比べると初年度の費用計上額は小さくなりますが、その分、長期にわたり安定して経費計上できるメリットがあります。これにより、給与所得との損益通算や法人の黒字圧縮が計画的に行えます。
次に、建物価格と土地価格を適切に按分する作業が欠かせません。国税庁の「財産評価基準書」を参照しつつ、周辺取引事例の単価を比較して建物割合を高めに設定できれば、減価償却費をより多く計上できます。ただし、根拠のない按分は税務調査で否認されるリスクがあるため、鑑定評価書や不動産鑑定士の意見書を添付し、合理性を示すと安心です。
さらに、付属設備の区分にも注意が必要です。エレベーターや共用配管は法定耐用年数が15年以下となる場合が多く、建物本体とは別に償却できます。設備ごとに細かく分ける「区分資産方式」を用いれば、前半10年での経費計上額を高められ、キャッシュフローが改善します。
最後に、2025年度から適用される「中小企業投資促進税制」の拡充により、法人が取得する一定の省エネ設備は即時償却が可能になりました。RC造の大規模修繕時に高効率空調を導入するなど、制度と修繕計画を組み合わせることで追加の節税効果が得られます。
区分所有と一棟投資、それぞれの戦略
ポイントは、投資規模と資金計画に応じてRC造をどう選ぶかです。区分所有は自己資金が少なくても始めやすく、賃料下落のリスクを限定できます。一方、一棟投資は建物価格の割合が高まり、減価償却をより大きく取れるため、節税効果が拡大します。
たとえば、築20年のRC区分マンション(価格2,000万円、建物割合70%)なら、残存耐用年数は計算上27年となり、年間約52万円を経費計上できます。対して、同条件の一棟マンション(価格2億円、建物割合80%)では、年間約592万円の経費計上が可能です。金額規模の差がそのまま節税余地に反映される点を押さえましょう。
ただし、一棟投資は空室リスクが集中します。日本政策金融公庫のデータによると、2025年の全国平均空室率は12%ですが、都市部のRC造は9%前後と比較的低く安定しています。それでも、立地選定や賃料設定を誤ると収支が崩れるため、管理会社との連携やリフォーム計画が不可欠になります。
区分所有で複数物件を組み合わせる戦略も有効です。異なるエリアや間取りを選び、空室リスクを分散しながら、建物割合を意識した購入を繰り返せば、安定収益と節税のバランスを取れます。つまり、投資家のリスク許容度と資金量に応じて最適解は変わるのです。
法人化のメリット・注意点
実は、所得が年間900万円を超え始めたころから法人化を検討すると節税効果が高まりやすくなります。法人税率は段階的に引き下げられ、2025年度の中小法人の実効税率は約25%です。一方、個人の高所得層は最大45%の所得税に住民税10%が加わります。法人化により税率差を活かしつつ、役員報酬や退職金で所得を分散できるわけです。
さらに、RC造の長期保有を前提にすると建物の減価償却費が長く続き、法人の黒字圧縮に貢献します。金融機関も法人スキームによる一棟RC物件への融資に積極的で、長期固定金利を提案されるケースが増えています。
しかし、法人化にはコストと手間も伴います。設立費用は約25〜30万円、毎年の決算申告や税理士報酬も必要です。また、小規模宅地等の特例など相続時の優遇措置は個人名義に比べて限定される場合があります。したがって、家族構成や将来の相続計画まで含めて総合的に判断することが大切です。
法人と個人のハイブリッド運用も一案です。初期は個人名義で区分所有を増やし、所得が一定ラインを超えた段階で法人を設立し、一棟RC物件を取得する方法なら、両者のメリットを活かしながらリスクを抑えられます。
2025年度の税制変更と今後の見通し
まず、2025年度税制改正大綱では、不動産所得の損益通算に大きな制限は設けられませんでした。これにより、RC造で計上した減価償却費を他の所得と通算する戦略は今後も有効です。また、地震対策や省エネ改修に対する固定資産税の減額措置が延長され、2027年度末まで認められることになりました。
一方で、空室対策としてのリフォーム費用を資本的支出として計上するか修繕費として全額経費計上するかの判断基準が、国税庁通達でより厳密化されました。具体的には、工事金額が建物取得価額の15%を超える場合は資本的支出と認定されやすく、減価償却での費用化が求められます。したがって、工事計画と年度ごとの節税戦略を連動させる必要があります。
加えて、海外不動産で広く用いられた短期償却スキームへの監視が強化され、国内物件にも実態調査が拡大しています。RC造だからといって過度な建物割合設定や不自然な鑑定評価を行うと、追徴課税のリスクが高まる点に注意しましょう。
長期的には、カーボンニュートラルの流れから、再生可能エネルギー設備に対する税額控除の拡充が検討されています。RC造物件の屋上スペースや共用部に太陽光パネルを設置し、余剰電力を売電するビジネスモデルが普及する可能性が高まるため、早めに情報収集しておくと先行者利益を得やすくなります。
まとめ
RC造を活用した不動産投資は、耐用年数の長さを武器に計画的な減価償却ができる点で節税効果が高いと言えます。建物と土地の按分、設備の区分償却、そして法人化のタイミングを正しく設定すれば、キャッシュフローと税負担を同時に最適化できます。また、2025年度の税制改正では主要な優遇措置が維持され、固定資産税減額や省エネ投資の即時償却など追加のメリットも期待できます。まずは自分の所得水準と資金計画を整理し、RC造を選択肢に入れつつ、信頼できる専門家と連携してシミュレーションを行うことが、安定した資産形成への近道となるでしょう。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資動向 – https://www.jfc.go.jp
- 中小企業庁 中小企業投資促進税制 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 総務省 固定資産税措置 – https://www.soumu.go.jp

