不動産投資を始めたばかりの方は、「表面利回りが高いほどお得」と単純に考えがちです。しかし実際にマンションを購入して運営を始めると、空室や修繕費が利益を圧迫し、「思ったほど手元に残らない」という声をよく聞きます。本記事では、マンション投資 表面利回り ポイントを中心に、数字の意味や見えづらいコストの捉え方、2025年度の最新データを使った判断基準まで丁寧に解説します。読み終えるころには、利回りの落とし穴を避けて堅実に収益を積み上げる具体的な行動手順が見えてくるはずです。
表面利回りとは何か
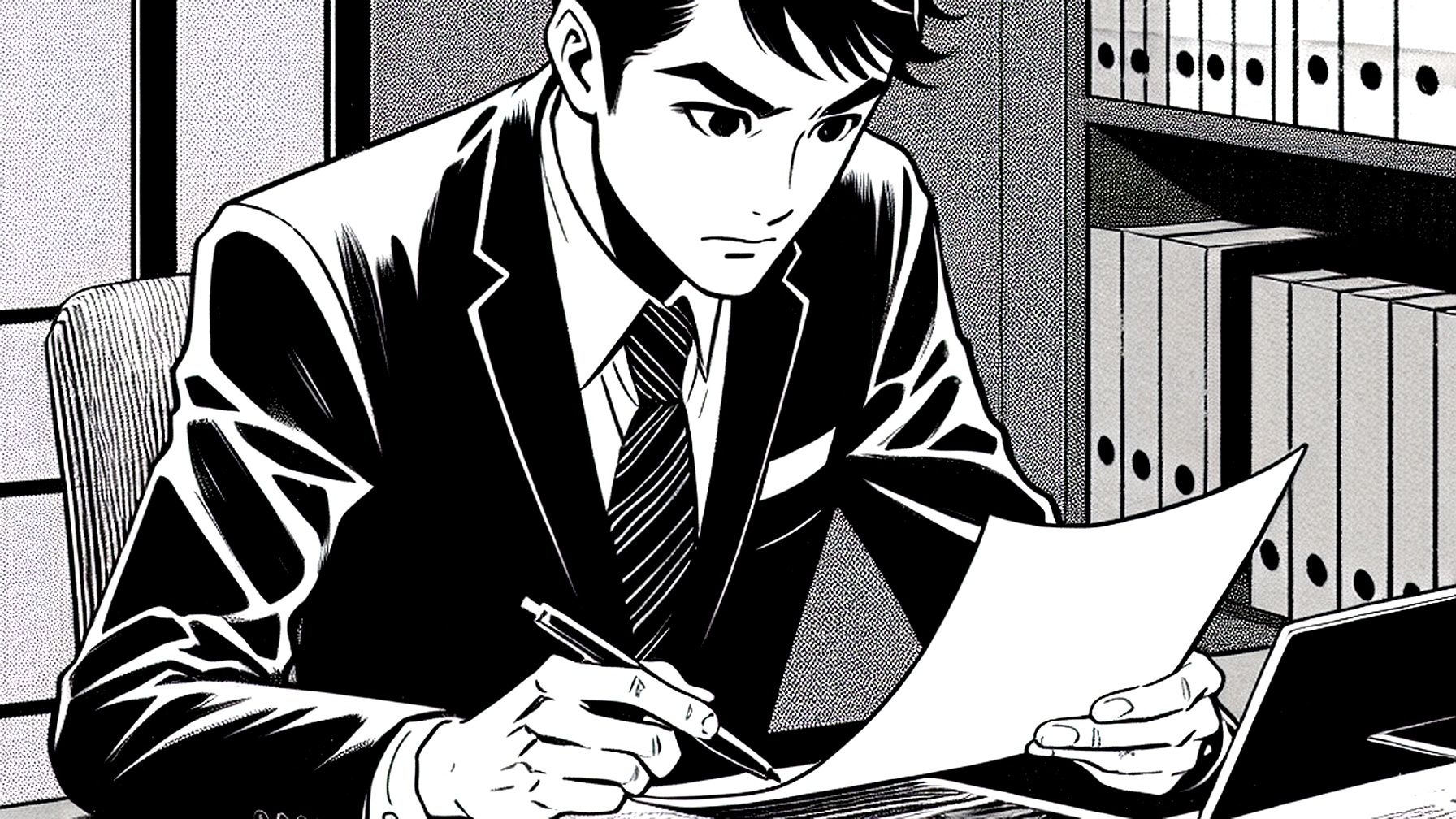
まず押さえておきたいのは、表面利回りが「年間家賃収入÷物件価格」で算出される単純な指標だという点です。計算が簡単なぶん、市場の比較には便利ですが、管理費や固定資産税などの経費を含まないため、実際の手残りを示すわけではありません。つまり、表面利回りだけで投資判断を下すと、思わぬ出費でキャッシュフローが赤字に転じる危険があります。
実は、金融機関も融資審査では表面利回りより実質利回り(ネット利回り)を重視します。実質利回りは「年間家賃収入−年間経費」を分子にするため、物件ごとに差が大きく出ます。管理会社への委託手数料やエレベーター保守費用などのランニングコストが高いと、表面利回りが良く見えても実質は低いというケースが典型です。
重要なのは、購入前に「ランニングコスト早見表」を作り、修繕積立金の将来計画まで確認しておくことです。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインによれば、築20年を超える区分マンションでは修繕費が築浅期の約1.5倍に増える傾向があります。数字の裏側に隠れたリスクを先読みする姿勢が、収益を安定させる第一歩になります。
数字だけに惑わされない見方
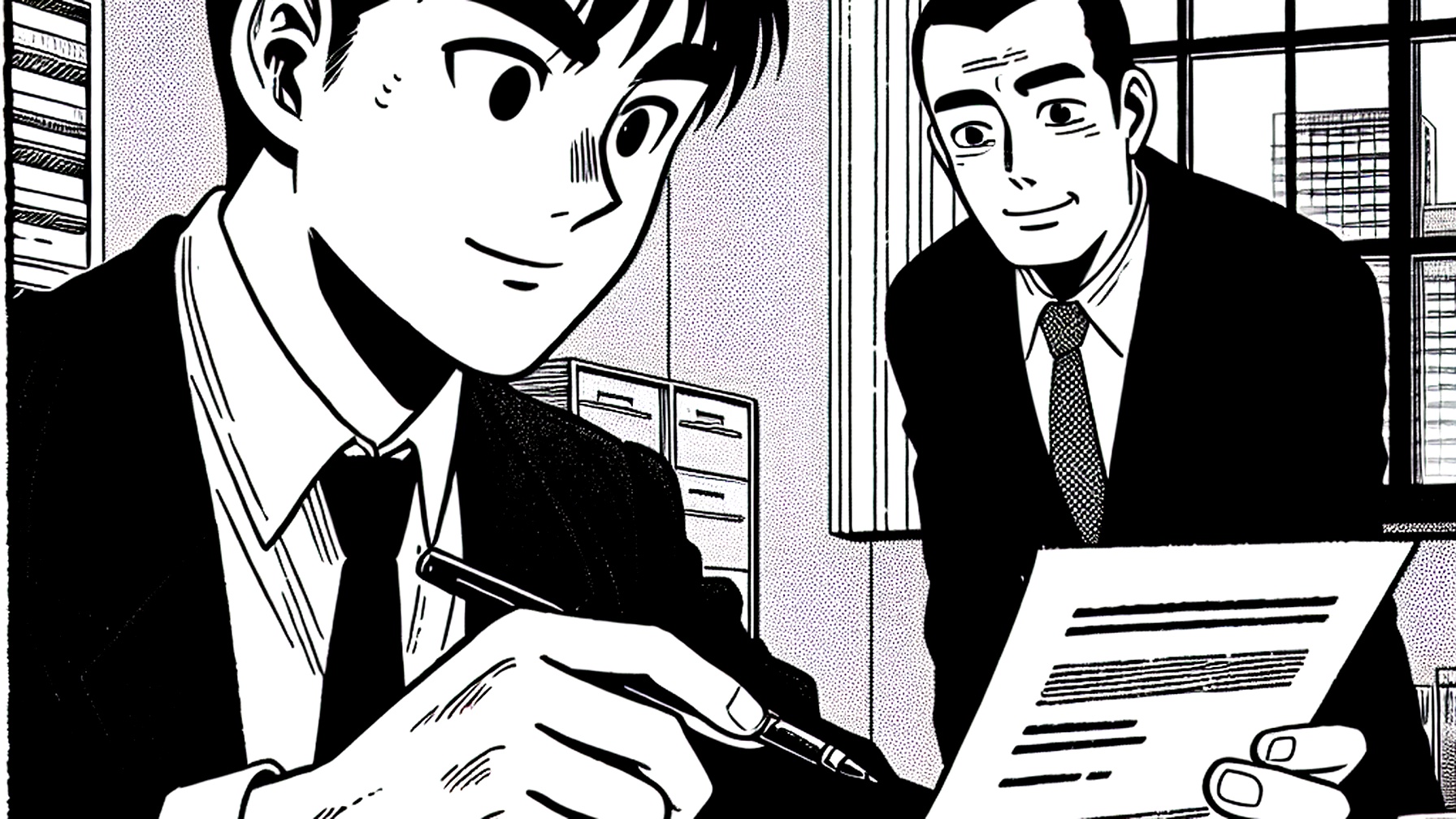
ポイントは、同じ利回りでも「家賃が高く空室が多い物件」と「家賃が低くほぼ満室の物件」ではリスクが異なるという事実です。たとえば、都心ワンルームで表面利回り4.2%とされる平均的な事例でも、空室期間が年間1か月あれば実質利回りは約3.8%に下がります。一方で、郊外アパートは表面利回り5.1%の例があるものの、入居付けに3か月以上要するエリアが少なくありません。
また、不動産会社が提示する利回りは「新築時の家賃設定」で計算されている場合が多いです。家賃下落率を加味せず購入すると、5年後には収入が5〜10%減ることも珍しくありません。東京都住宅供給公社のデータでは、築10年時点の平均家賃は新築時比マイナス7%という統計が出ています。将来の下落幅を保守的に見込むことで、計画と現実のギャップを縮められます。
さらに、税引き後のキャッシュフローも見逃せません。減価償却費を適切に計上すれば、課税所得が下がり、手残りが増えるケースがあります。税制は複雑ですが、2025年度も「建物部分の定額法」「耐用年数の短縮ルール」は継続しています。税理士と連携してシミュレーションを行い、数字を「表面」だけでなく「税引き後」まで深掘りすることが賢明です。
都心物件と郊外物件の比較ポイント
基本的に、都心部は価格が高く表面利回りが低い傾向にありますが、空室率は全国平均より2〜3ポイント下回るため、収益のブレが小さい点が強みです。日本不動産研究所の調査によると、2025年9月時点で東京23区の空室率はワンルームで3.1%、ファミリータイプで2.4%となっています。
一方、郊外は取得価格が抑えられ、表面利回りで1〜2%程度上乗せが狙えます。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、郊外ベッドタウンの人口が今後10年で4〜7%減少するとされています。人口減とともに賃貸需要も縮小するため、家賃の維持が難しくなるリスクを抱えます。
つまり、投資家が取るべき戦略は「低利回りでも安定を選ぶ」か「高利回りだが空室リスクを取る」かの二択ではありません。実際には、都心で中古を狙い購入価格を下げる、あるいは郊外で駅徒歩5分以内に限定するなど、利回りと需要を同時に確保する方法があります。選択肢を二元論で考えず、立地と価格のバランスを細かく調整することが成功の鍵になります。
2025年度の市場データから学ぶ
まず、データを活用する最大のメリットは「自分の感覚」を数字で検証できる点にあります。不動産経済研究所によると、2025年9月の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円、前年比3.2%上昇しました。価格が上がる一方で、表面利回りが横ばいという状況は、購入後の値上がり益(キャピタルゲイン)を意識する戦略を取りやすいことを示唆します。
しかし、価格上昇局面で無理に新築を買うと、利回りがさらに低くなる恐れがあります。そこで注目したいのが築15年前後の「価格調整済み物件」です。国土交通省レインズの成約事例では、築15年区分マンションの平均成約単価は新築比で約30%低く、家賃は20%程度の下落にとどまるケースが多いです。このギャップを利用すれば、実質利回りを押し上げながら将来的な価格回復も狙えます。
また、2025年度は住宅ローン金利が歴史的低水準を維持しています。主要都市銀行の投資用ローン変動金利は年1.8%前後で推移しており、金利上昇リスクを織り込んでもキャッシュフローが黒字化しやすい環境です。ただし、日銀は物価上昇に伴い緩やかな利上げを示唆しているため、返済比率を年収の35%以内に抑えるなど余裕を持った資金計画が必須です。
利回り改善のためにできる工夫
重要なのは、物件を買った後に利回りを「育てる」視点です。まず、小規模リフォームで家賃を1割上げる手法があります。照明をLEDに交換し、アクセントクロスを使っただけで掲載写真の印象が変わり、募集開始から1週間で申し込みが入った事例は少なくありません。
さらに、インターネット無料設備の導入も効果的です。総務省の通信利用動向調査では、入居者の約65%が「ネット無料」を物件選定の必須条件に挙げています。月額1,800円程度のコストで家賃を3,000円アップできれば、表面利回りは確実に向上します。
加えて、家賃保証付きのサブリース契約は安定収入を約束するように見えますが、保証賃料は市場家賃の80〜90%に設定される点に注意が必要です。長期的に利回りを高めるには、賃料査定の見直しを自主的に行い、管理会社と密に連携して募集条件を柔軟に変える姿勢が欠かせません。
まとめ
本記事では、表面利回りの基礎から実質利回りとの違い、都心と郊外それぞれのリスク、2025年度の最新データを踏まえた投資判断の考え方まで詳しく解説しました。結論として、マンション投資では「見るべき数字を正しく選び、購入後も利回りを育てる工夫を続ける」ことが成功の最短ルートです。まずは気になる物件の収支シートを自作し、空室率や家賃下落のシナリオを組み込んでみてください。数字を味方に付ければ、不安は自信に変わります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 レインズマーケットインフォメーション – https://www.reins.or.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 – https://www.ipss.go.jp
- 総務省 通信利用動向調査 – https://www.soumu.go.jp

