円安が長期化するなか、「円建ての家賃収入は目減りしないのか」「海外資材の値上がりで修繕費が高騰しないか」と不安を抱く投資家が増えています。為替は個人の努力で変えられませんが、影響を理解して対策を講じればリスクを限定できます。本記事では円安の仕組みから具体的なデメリット、さらに2025年9月時点で使える制度まで整理します。読み終えたとき、あなたは円安時代でもブレない投資判断の軸を持てるはずです。
円安が続く背景と不動産市場への影響
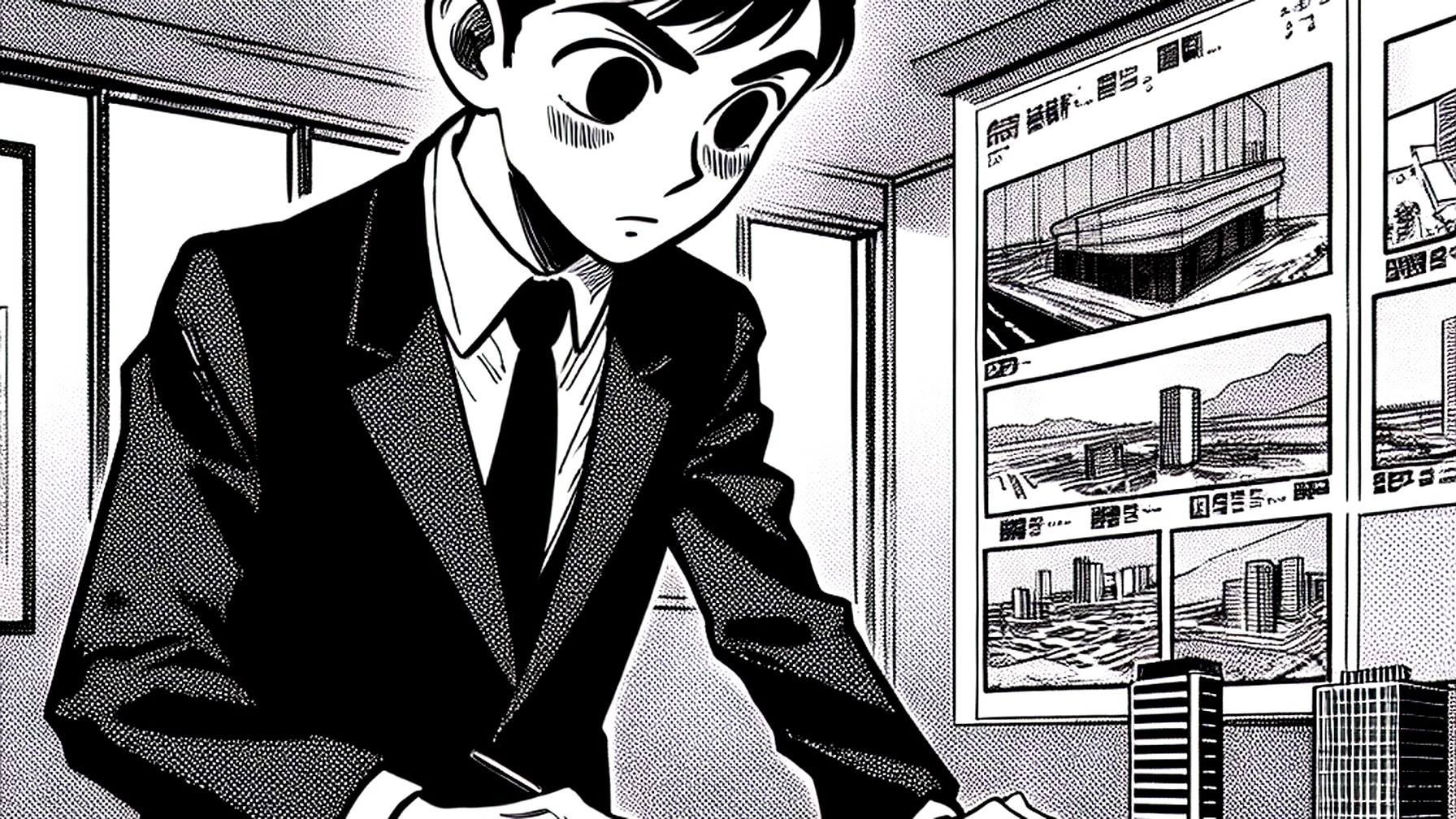
まず押さえておきたいのは、なぜ円安傾向が続くのかという点です。日銀が長期にわたりマイナス金利政策を維持し、米国や欧州の金利が高水準で推移しているため、金利差が拡大し円が売られやすい構図が続いています。国際決済銀行の実質実効為替レートによれば、2025年8月の円の価値は1990年代半ばと比べておよそ30%低い水準です。
為替が下落すると、建築資材や住宅設備の多くを輸入に頼る日本ではコストが跳ね上がります。新築価格が上がれば中古物件の評価額も連動して高くなり、結果として投資家の取得費用が増大します。また、同じ家賃収入でもドル換算では減少するため、海外ファンドが日本の不動産を割安と判断し参入しやすくなる点も見逃せません。この流入は価格上昇を後押しする一方で、利回りの低下を招く可能性があります。
実は円安そのものが悪いわけではなく、資金調達コストや運営費用とのバランスでリスクが顕在化します。そこで次章からは具体的なデメリットと対応策を掘り下げます。
融資コストとキャッシュフローを圧迫する為替要因
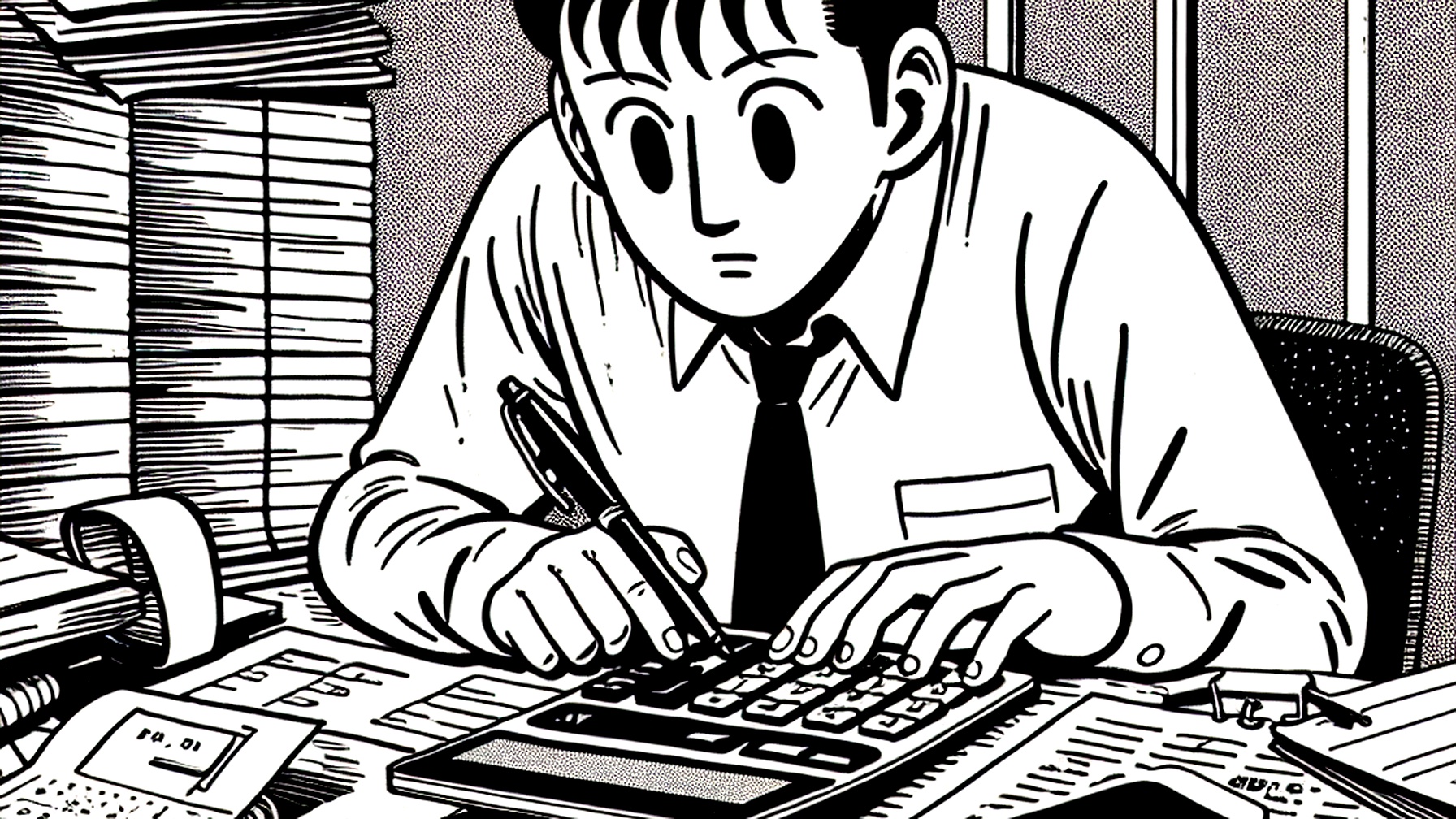
重要なのは、「低金利=安全」と短絡的に考えないことです。現在の国内金利は歴史的に低水準ですが、円安でインフレ圧力が強まると金利上昇に転じるリスクが潜んでいます。たとえば変動金利ローンで借入4,000万円、金利1.5%から2.5%へ上昇すると、毎月返済額はおよそ1万9,000円増え、年間で約23万円のキャッシュアウトになります。
さらに外国人投資家の需要増によって物件価格が高止まりすると、自己資金比率が低いまま高値で買わざるを得ない場面が増えます。金融庁の2024事務年度検査方針では「返済原資を家賃収入みずからが確実に生み出すか」を重視すると明記されており、借入審査は以前より厳格化しています。つまり、想定利回りが低い物件では融資可否そのものが課題になるのです。
対策としては、固定金利期間を最低10年確保する、返済比率を家賃収入の40%以下に抑えるなど保守的な計画が有効です。また、円建てローンでも将来の金利上昇に備え、平均金利+1%でシミュレーションしておくと資金繰りに余裕が生まれます。
修繕費と管理費が上がる構造的リスク
ポイントは、円安が続く限り建物維持コストもじわじわ上がるという事実です。国土交通省「建設工事費デフレーター」によると、2021年から2025年にかけて建築資材全体の価格は約18%上昇しています。特にエレベーターや給湯器など設備機器の輸入割合は高く、部品不足と為替安が重なると修繕費用の見積もりが大きく跳ねます。
例えば15年目にエレベーター更新が必要なワンルームマンションでは、2020年時点で700万円だった工事が2025年には900万円超の提示を受けるケースも珍しくありません。オーナーが長期修繕計画を見直していないと、突発的な資金繰り難に陥ります。
言い換えると、円安時代は「購入時よりも保有中のコスト管理」が収益を左右します。毎月の積立修繕金だけに頼らず、1戸当たり年間1万円程度の独自修繕積立を設けることで、将来的な資材高に備えられます。また、小規模物件でもLED化や省エネ設備に更新すれば、光熱費削減によってネット利回りを維持しやすくなります。
外国人投資家の参入と競争激化のデメリット
実は円安メリットを享受するのは海外資本です。ドルやユーロで見れば日本の不動産価格は「セール状態」に映り、ホテルやオフィスに限らず居住用物件へも資金が流入しています。日本不動産研究所の2025年7月調査によると、東京23区の区分マンション価格指数は前年比9%上昇し、国内個人投資家の利回りは平均0.3ポイント低下しました。
価格高騰は出口戦略を描きにくくする一方で、賃料上昇は物価上昇を上回らないペースです。結果として賃貸利回りが圧縮され、「買った瞬間に利回り5%未満」という物件が増えるのがデメリットです。
しかし、全エリアで競争が激化しているわけではありません。地方中核都市でも人口微増が続くエリアや、再開発が進む駅近区画はまだ歪みが残っています。エリア選定の際は、国勢調査や自治体の将来人口推計に基づき、世帯数が10年間横ばい以上の地域を候補とすることで、過度な価格競争を避けやすくなります。
2025年度の公的制度を活用したリスク低減策
最後に、2025年度に実際に利用可能な制度で円安デメリットを軽減する方法をまとめます。住宅ローン減税は投資用物件には使えませんが、自宅を購入して賃貸へ転用する「マイホーム投資」では適用が可能です。控除率は年末残高の0.7%、借入限度2,000万円(省エネ住宅は3,000万円)と縮小していますが、10年間の減税額は最大140万円となり、取得コストを事実上下げられます。
加えて、国土交通省の「既存住宅省エネ改修補助金(2025年度)」は、賃貸物件でも断熱改修や高効率給湯器の導入に対し最大250万円が支給されます。補助対象は2026年3月末着工分までのため、計画的に申請すれば資材高騰の影響を一部打ち消せます。
結論として、制度はあくまで補助的ツールであり、キャッシュフローとリスク管理を軸に据えることが欠かせません。それでも円安で高騰する建材費を補ううえで、使える制度は積極的に取り込む価値があります。
まとめ
円安が長引く現在、不動産投資には「取得費の上昇」「金利上昇リスク」「修繕費高騰」「外国人投資家との競争」といった複合的デメリットが生じます。しかし、固定金利の長期化、保守的な返済比率、独自の修繕積立、人口動態に基づくエリア選定、そして2025年度の省エネ改修補助金など公的制度の活用によって、影響をコントロールすることは可能です。読み終えた今こそ、自身のポートフォリオを点検し、円安時代でも持続可能な投資戦略へアップデートしてみてください。
参考文献・出典
- 日本銀行 – https://www.boj.or.jp
- 国際決済銀行(BIS) – https://www.bis.org
- 国土交通省 建設工事費デフレーター – https://www.mlit.go.jp
- 日本不動産研究所 価格指数調査 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省 国勢調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 2024事務年度検査方針 – https://www.fsa.go.jp

