不動産投資に興味はあるものの、「多額の借入は怖い」「空室が出たらどうするのか」といった不安を抱えていませんか。実は、リスクやデメリットを正しく把握し、再現性のある手順を踏めば、初心者でも安定した資産形成が狙えます。本記事では、失敗を避けるために押さえるべき注意点と、購入から運用までの流れを具体的に整理します。読後には、不動産投資 デメリット 手順を自分ごととして理解し、最初の一歩を踏み出す判断材料が得られるはずです。
不動産投資で見落とされがちな主なデメリット
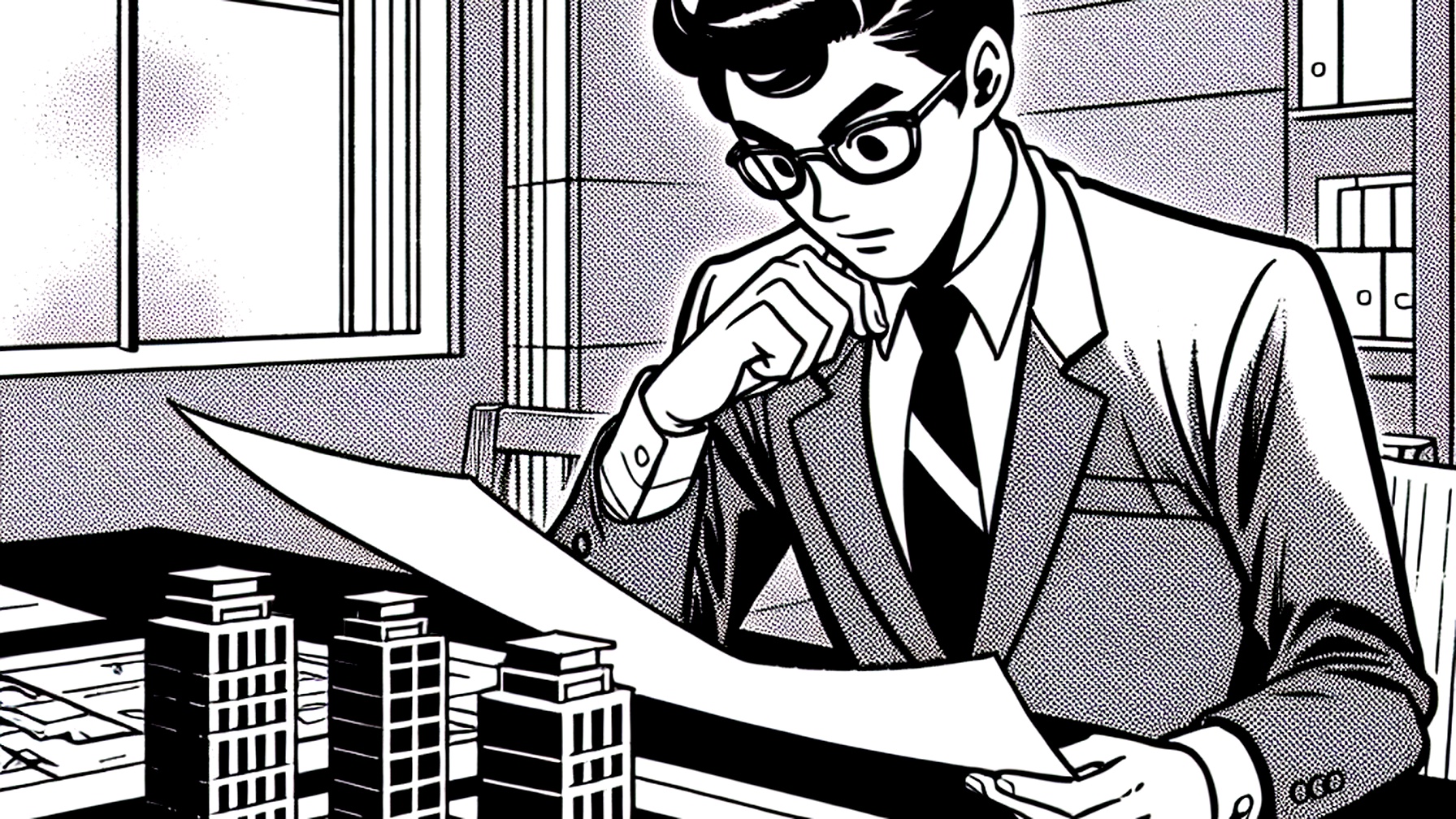
まず押さえておきたいのは、投資対象が「動かせない資産」であることです。不動産は売却まで時間がかかるため、株式のように即座に現金化できません。この流動性の低さが、キャッシュを早期に必要とする場面では大きな負担になります。
次に、空室リスクは常に存在します。総務省の住宅・土地統計調査によると、2023年時点の全国平均空室率は13.8%でした。人口減少が続く地域では、地方中心部でも15%を超えるエリアが珍しくありません。家賃収入がゼロになる期間を想定し、ローン返済や管理費をまかなう余裕資金を持つ必要があります。
さらに、修繕費のインパクトは想像以上です。国土交通省「マンション大規模修繕実態調査」では、30年周期の外壁改修費用は専有面積1平方メートルあたり平均1万5千円とされています。戸建や木造アパートでも、屋根や配管交換に数百万円が必要になるケースも珍しくありません。保険で全てを賄うのは難しいため、積立方式で備えることが重要です。
加えて、金利上昇はキャッシュフローに直結します。日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除し、2025年9月現在の長期金利は1.3%前後で推移しています。固定金利で借りていれば影響は限定的ですが、変動金利の場合は返済額が膨らむリスクを忘れてはいけません。
資金計画と融資選択で失敗を防ぐ
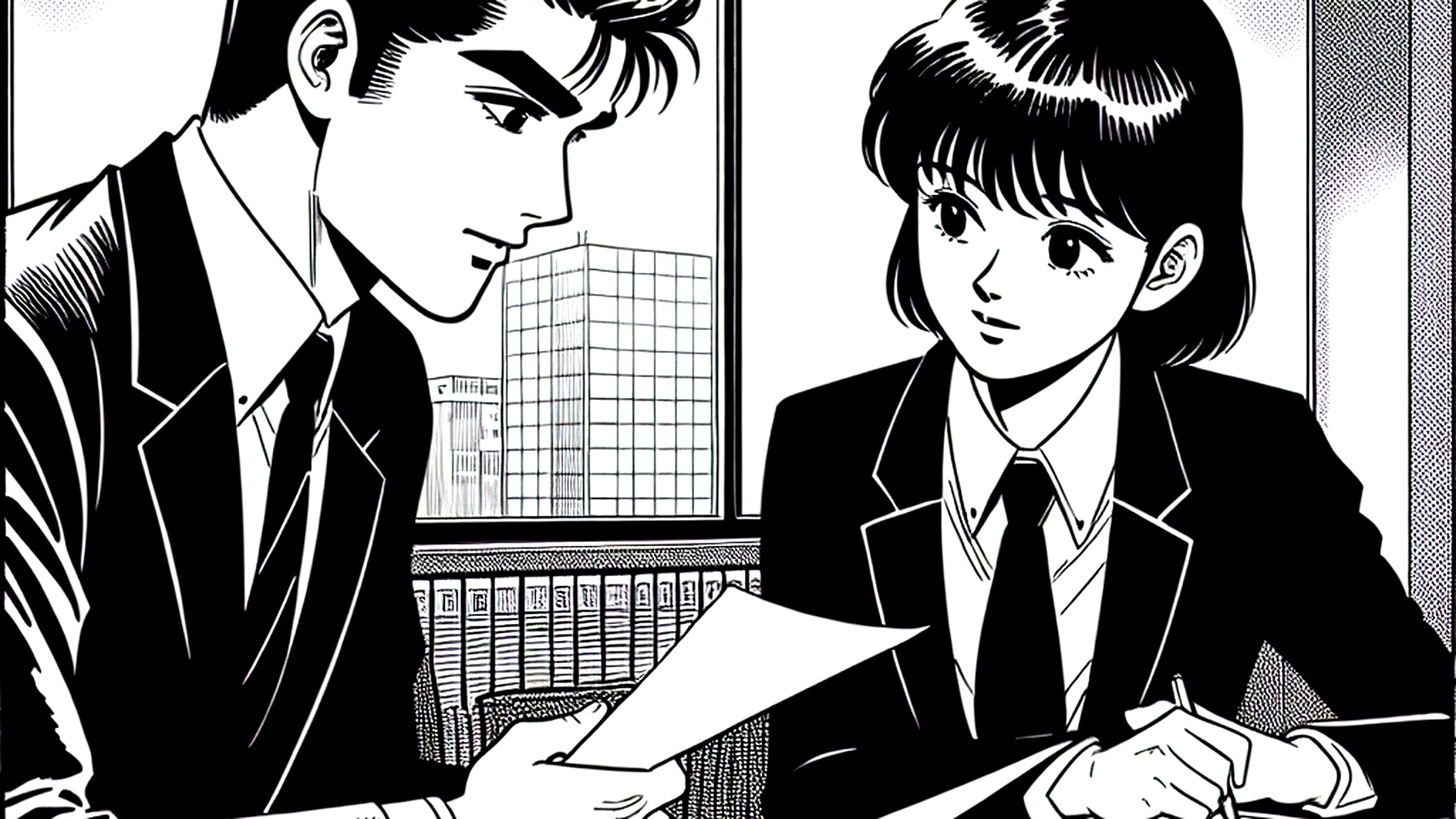
重要なのは、自己資金と借入金のバランスを最初に決めることです。目安として物件価格の20〜30%を自己資金で用意すると、金融機関の審査が比較的通りやすくなり、返済比率も下がります。また、固定資産税や設備更新費を考慮して、購入時点で家賃収入の半年分を予備費として取っておくと安心です。
融資を受ける際は、複数行に同時打診する方法が効果的です。住宅ローン専門のネット銀行は金利が0.4%台から提示される一方、地銀や信金は1%台後半が多いものの、築古物件や法人融資に柔軟に対応します。つまり、金利と融資対象の範囲を天秤にかけ、自分の投資戦略に合った金融機関を選ぶ必要があります。
返済計画を作るときは、空室率15%、金利上昇2%といった厳しめのシナリオでキャッシュフローを確認しましょう。収支が黒字であれば、想定より好条件になった際の利益がそのままリスクヘッジになります。一方で、赤字になる場合は自己資金を追加投入するか、そもそも物件価格を見直すべきです。
加えて、2025年度の住宅ローン減税は居住用が対象ですが、投資用物件を自宅と共有する「賃貸併用住宅」なら一定の控除が得られます。ただし、控除割合や適用面積に条件があるため、税理士と事前に試算し、適合物件かどうかを確かめてください。
物件選びから購入までの具体的な手順
ポイントは、エリア分析と物件評価を分けて考えることです。人口動態や将来の再開発計画を調べ、長く需要が続く地域を選んだうえで、利回りではなく「実質収益」を比較します。
実際の流れは次の四段階です。
- エリア選定:自治体の人口推計や都市計画図、主要駅の乗降者数をチェックし、単身者かファミリーかターゲットを定める。
- 物件調査:築年数、構造、修繕履歴、家賃相場を確認し、同タイプの周辺物件より高くても稼働率が高い理由を探る。
- シミュレーション:固定費、空室率、修繕費を入れた10年キャッシュフロー表を作成し、自己資金回収年数を算出する。
- 売買契約・融資実行:重要事項説明でリスクを洗い出し、融資承認後に手付金を払い、決済日までに保険や賃貸管理委託を手配する。
この手順を形式的にこなすだけでは不十分です。たとえば、収支表の利回りが10%でも、築40年の木造アパートなら耐震補強や屋根改修が必要になり、実質利回りが5%以下に落ち込むケースがあります。現地調査で配管の材質や電気容量を確認し、長期的な修繕費を割り戻した利回りを基準に判断することが欠かせません。また、区分マンションの場合は管理組合の積立金水準と修繕計画が適正かどうかを議事録から読み取ることが必須です。
運用フェーズで直面するリスクとその対策
まず押さえておきたいのは、賃貸管理の質が収益を左右するという事実です。管理会社が入居募集を怠ると、わずか1か月の空室でも年間利回りが1%以上下がる場合があります。管理委託契約では、広告料の基準や原状回復費の負担割合を細かく定め、オーナーと入居者双方のトラブルを回避しましょう。
家賃下落リスクにも備える必要があります。不動産流通推進センターのデータでは、築20年を超えると平均家賃は新築比で25%下がる傾向があります。そこで、間取り変更や設備グレードアップによるバリューアップ工事が有効です。実質利回りを維持するには、50万円の設備投資で年間家賃を6万円上げるような、投下資本利益率12%以上の施策を目標とします。
入居者トラブルや自然災害にも目を向けましょう。火災保険だけでなく、家賃保証付きの少額短期保険を組み合わせることで、滞納時のキャッシュフロー悪化を抑えられます。また、2025年9月現在、自治体の「耐震改修促進補助金」は存続しており、耐震診断や工事費の一部を補助しています。上限額や申請期限は市町村ごとに異なるため、公式サイトを確認のうえ、早めに申し込むことが大切です。
2025年度に利用できる公的支援策
実は、投資用でも条件を満たせば活用できる制度があります。代表例が、国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。2025年度は、賃貸住宅も対象になり、耐震・省エネ・劣化対策の改修費用に最大200万円(補助率1/3)が支給されます。これにより、築古物件の性能向上と家賃アップを同時に狙えるメリットがあります。
また、東京都など一部自治体は「ゼロカーボン東京賃貸住宅助成」を継続しています。省エネ性能を高めるリフォーム費の2/3、上限300万円が補助されるため、高効率給湯器や断熱窓の導入コストを大幅に削減できます。省エネ性能は入居者の光熱費削減につながるため、競合物件との差別化にも効果的です。
ただし、補助金は予算上限に達すると受付終了となります。申請には施工前の事前承認が必須で、補助金が確定するまで着工できない制度が多い点に注意してください。時間軸を考慮し、購入計画と補助金スケジュールを逆算して組み立てることが、資金効率を高めるコツです。
まとめ
本記事では、不動産投資の代表的なデメリットを整理し、資金計画から物件購入、運用、補助金活用までの手順を時系列で解説しました。重要なのは、空室・修繕・金利という三大リスクを数値化し、厳しめのシナリオでも耐えられるキャッシュフローを構築することです。そのうえで、自治体の補助制度や長期優良化リフォームを活用すれば、築古でも収益力を高められます。今日紹介したステップを自分の状況に当てはめ、小さな物件から実践することで、着実に資産を積み上げていきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「マンション大規模修繕実態調査」 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行「長期金利の推移」 – https://www.boj.or.jp/
- 不動産流通推進センター「不動産市場動向レポート」 – https://www.retpc.jp/
- 独立行政法人住宅金融支援機構「2025年度住宅ローン金利動向」 – https://www.jhf.go.jp/

