不動産投資の税金が複雑で頭を抱えていませんか。とりわけ鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションは高額な分、節税効果が大きいと聞くものの、具体的にどう活用すれば良いかは分かりにくいものです。本記事では、2025年9月時点で有効な税制を踏まえながら、初心者でも理解しやすい形で「節税 RC造」のポイントを解説します。読み終えるころには、減価償却からキャッシュフローの組み立て方、さらには相続対策まで、RC造投資の全体像をつかめるはずです。
RC造が節税に向く理由
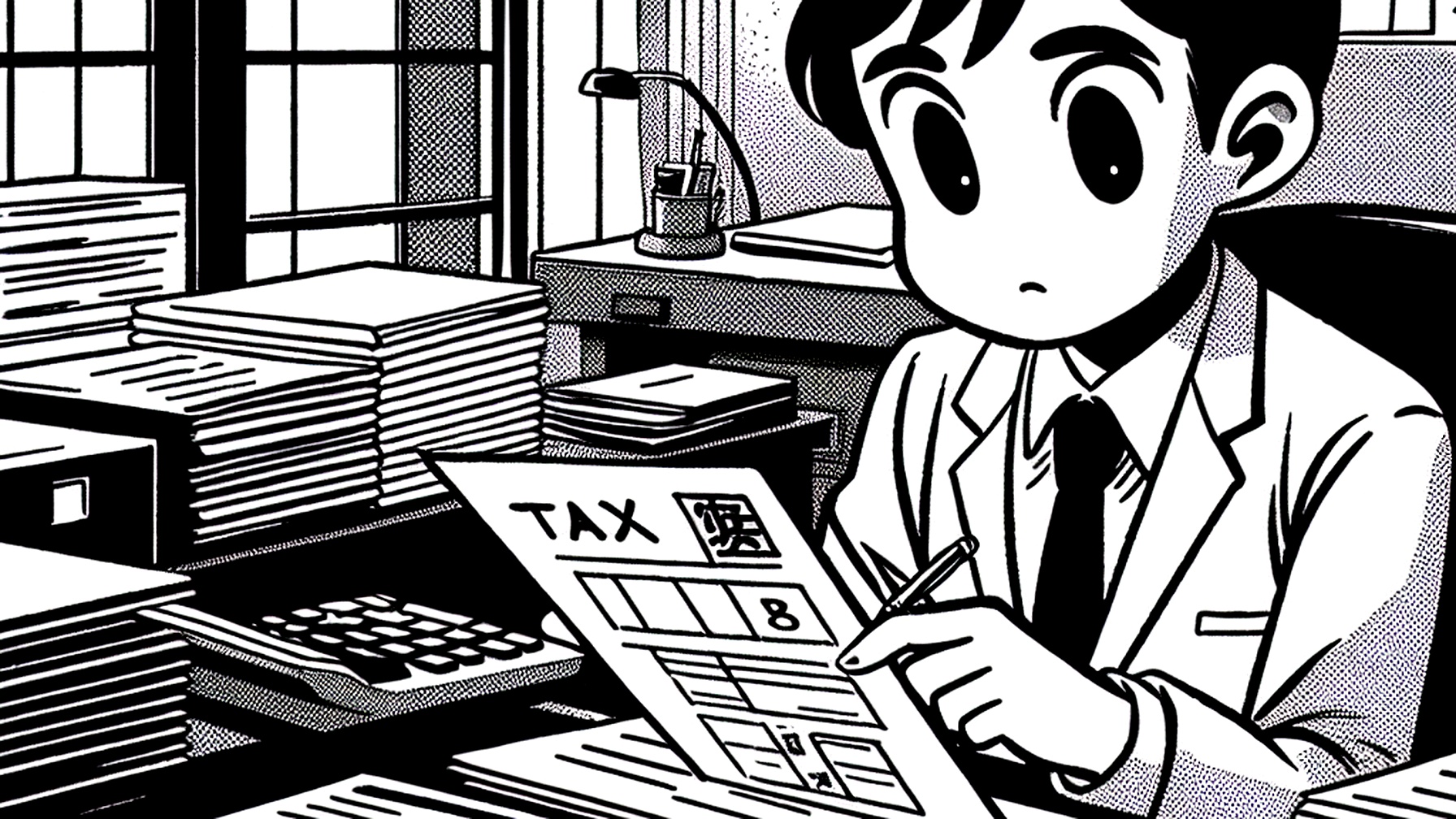
重要なのは、RC造の耐久性がそのまま節税余地につながる点です。国税庁の耐用年数表では、RC造の法定耐用年数は47年に設定されています。木造の22年や軽量鉄骨の34年に比べて長いため、建物価格をゆっくりと経費化でき、長期間にわたり所得を圧縮できるわけです。つまり、高額な建物でも毎年の減価償却費が確実に計上でき、安定的に税負担を軽減できます。
一方で、長い耐用年数は「節税スピードが遅い」と誤解されがちです。しかし実際には、建物価格そのものが大きいため、年額の減価償却費は木造より高くなるケースが多々あります。加えてRC造は修繕周期が長いので、長期保有時のメンテナンス費用を平準化しやすいという利点も見逃せません。
さらに、RC造は金融機関の評価が高く、2025年現在も最長35年程度の長期融資を受けやすい状況です。長い融資期間は月々の返済額を抑え、キャッシュフローを安定させるため、減価償却による節税メリットを享受しつつ手元資金を厚く保てます。
減価償却を最大限に活かす方法
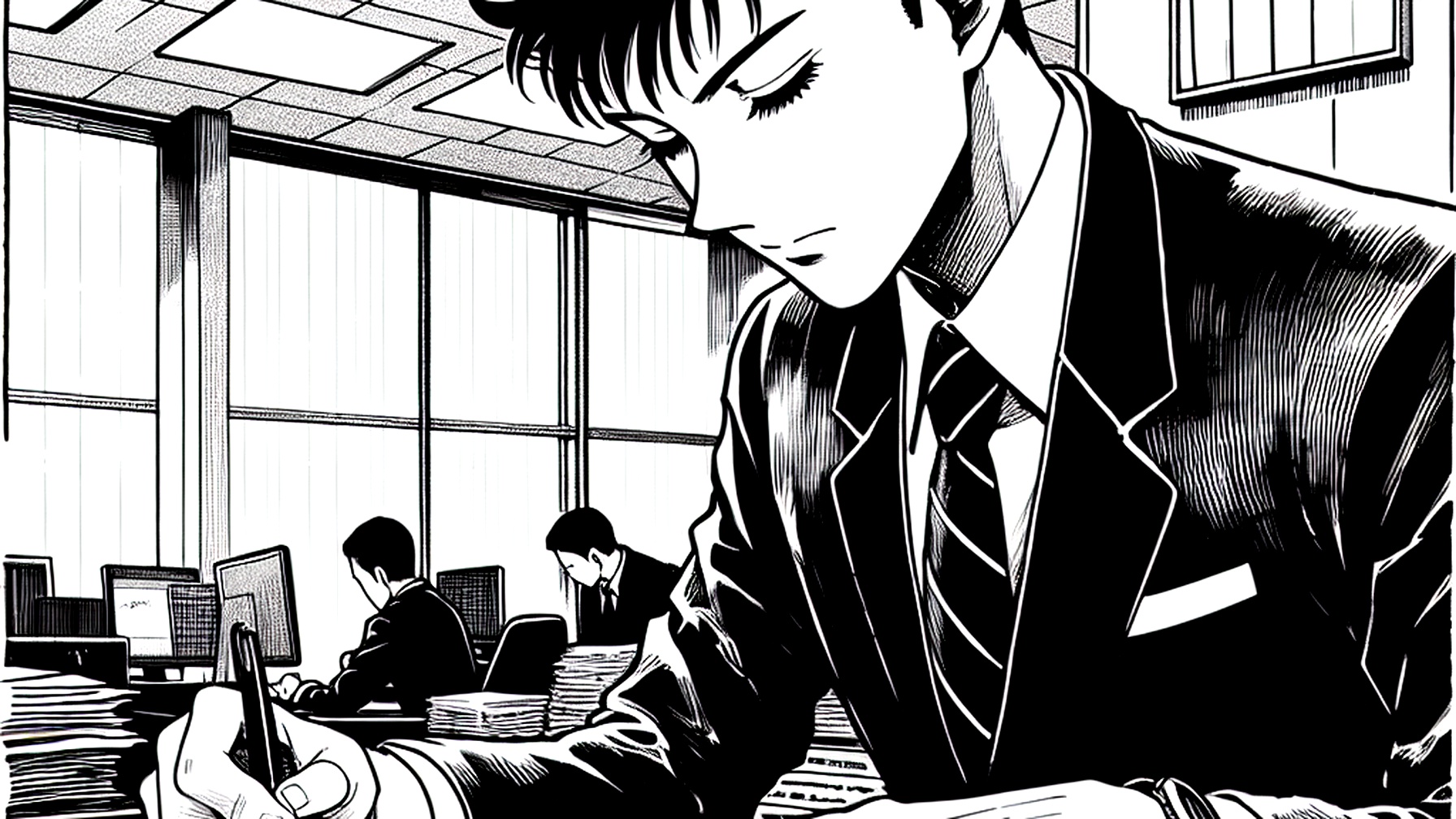
まず押さえておきたいのは、建物と土地を正確に区分し、建物割合を適切に設定することです。建物価格が高いほど減価償却費も増えるため、購入時の売買契約書における按分は大きな意味を持ちます。国税庁の「個別評価による按分方法」を参考に、近隣の土地取引事例や固定資産税評価額を根拠にすれば、税務調査でも説得力を保てます。
次に有効なのが「定率法」を使った初期加速度の確保です。2025年度の所得税法では、2023年4月以降取得のRC造については定率法が適用可能で、初年度の償却率は0.042。定額法より高い償却費を初期に計上できるため、所得の高い時期に税負担を抑えやすくなります。ただし、将来の償却費が目減りする点を踏まえ、長期的な資金計画を必ずシミュレーションしましょう。
また、中古RC造を購入する場合は「簡便法」により耐用年数を短縮できる点が魅力です。具体的には、法定耐用年数の20%に当たる残存期間を再設定でき、たとえば築30年のRC造なら残りは9年となります。短い期間に高額な減価償却費を取れるため、早期に節税効果を得たい人には有効です。ただし、9年目以降は償却費がゼロになるため、キャッシュフローの再構築を念入りに行う必要があります。
キャッシュフローと節税のバランス
ポイントは、節税効果だけを追い求めると現金が足りなくなる点です。減価償却で所得税が下がっても、実際の返済や修繕費は現金支出として発生します。国土交通省の住宅着工統計によると、RC造の大規模修繕は15年〜20年周期で1回当たり1000万円規模になる例もあります。修繕積立金を月1万〜2万円程度積み立てておくと、将来の資金ショックを回避できます。
また、銀行返済と減価償却のタイミングを合わせると、税引き後キャッシュフローを安定させやすくなります。たとえば35年ローンで購入した場合、毎年の元金返済額は徐々に増えるため、償却費が定額のままだと手残りが減る傾向があります。そこで、定率法を選択して初期返済の負担を償却費で相殺し、元金比率が高まる10年目以降に返済額の見直しや繰り上げ返済を検討すると効果的です。
さらに、税効果と利回りを総合評価するために「税引き後キャッシュオンキャッシュリターン」を使いましょう。これは年間の手残り現金を自己資金で割った指標で、8%以上を目安に組めれば長期で安定した運用が期待できます。節税により所得税・住民税が80万円下がったとしても、空室が想定以上に増えればリターンは急減します。空室率の保守的な設定と家賃下落シナリオを織り込む姿勢が欠かせません。
2025年度の税制とRC造投資の注意点
実は、2025年度の税制改正大綱でも不動産所得の損益通算について大幅な変更は予定されていません。したがって、RC造の減価償却費を給与所得と相殺する基本戦略は引き続き有効です。ただし、国税庁は赤字の恒常化を「租税回避目的」としてチェックを強化しているため、将来黒字化する合理的な収支計画を持っておくことが求められます。
加えて、賃貸住宅の省エネ性能向上を目的とした「賃貸住宅省エネ改修促進税制(2025年度末申請分まで)」が利用できます。一定の断熱改修を行い、一次エネルギー消費量を20%以上削減すると、改修費用の10%(上限200万円)が法人税・所得税から控除可能です。新築RC造でなくても改修で節税できる点は覚えておきましょう。
一方で、2025年から適用されるインボイス制度の猶予終了に伴い、課税売上1,000万円以下のオーナーも消費税課税事業者になるべきか判断が迫られます。RC造は高額な修繕が多いため、仕入税額控除を受けられる課税事業者を選択する方が有利なことが多いものの、毎年の申告コストも高まります。税理士に試算を依頼し、長期の節税額と手間を比較することが肝心です。
長期保有で得られる相続・贈与メリット
基本的に、RC造は相続税評価額が時価より低く算定されやすい点も強みです。土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価するため、実勢価格の7割程度に圧縮されるケースが一般的といわれます。高額なRC造マンションを保有することで、現金よりも相続税を抑えられる可能性があります。
さらに、2024年に改正された生前贈与加算の範囲拡大を踏まえ、早めの贈与計画も検討しましょう。RC造マンションの持分を毎年110万円ずつ贈与する方法に加え、「家族間売買」で子ども名義のローンを組ませる手法も有効です。ローン残高があると相続税評価がさらに下がるため、所得水準が高まる30代からの子世代への早期移転が効果的です。
とはいえ、相続・贈与対策は物件の含み益や将来の空室リスクを伴います。日本銀行の金融システムレポートが示すように、人口減少で地方の賃貸需要は縮小傾向です。賃料下落のリスクを加味しつつ、都市部の駅近など長期需要が見込める立地に絞ることが、相続後の家族を守る最善策と言えます。
まとめ
ここまで「節税 RC造」をテーマに、減価償却のテクニックからキャッシュフロー管理、2025年度税制の最新動向、相続まで幅広く見てきました。RC造は耐用年数の長さと金融機関からの高評価を活かせば、安定した節税と資産形成を両立できます。ただし、修繕費や空室リスクを見据え、税引き後キャッシュフローを常に確認する姿勢が欠かせません。次の一歩として、物件選びとローン条件のシミュレーションを行い、税理士や不動産専門家へ早めに相談することを強くおすすめします。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp
- 不動産流通推進センター 市場動向レポート – https://www.retpc.jp

