不動産投資に興味はあるものの、実際にアパートを所有してみると「空室が埋まらない」「家賃を下げるしかないのか」と悩むオーナーは少なくありません。とくに近年は新築物件の供給が続き、入居者の目も厳しくなっています。そこで本記事では、2025年9月時点の最新データを踏まえながら、具体的かつ実践的な空室対策を整理しました。読み終えるころには、自分の物件に合った打ち手を選択し、アパート経営 空室対策 解決の糸口を見いだせるはずです。
需要動向を正しく読み解く
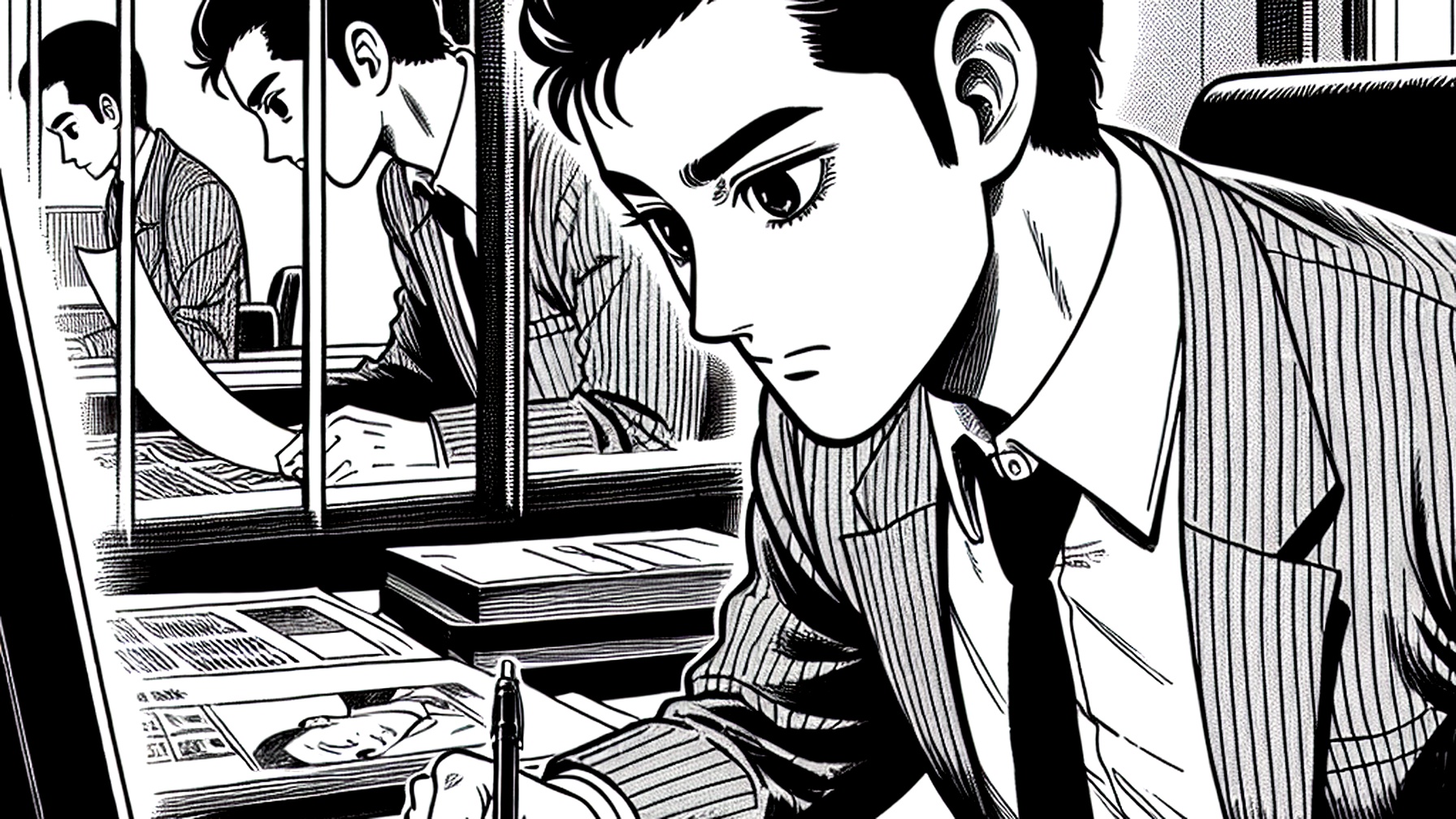
まず押さえておきたいのは、空室が生まれる背景には需要の変化があるという事実です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しましたが、地域差は依然として大きいのが現状です。需要が堅調なエリアと減少傾向のエリアを見誤ると、どれほど物件を磨いても入居が決まりません。
実は地方都市でも駅前再開発が進むエリアでは、単身者向け需要が回復しています。反対に都心周縁のベッドタウンではテレワーク普及の影響で、ファミリー層の転居が減少しました。つまり全国平均の数字に惑わされず、自分の物件が属する商圏の人口動態や雇用環境をこまめに確認する姿勢が重要です。
次に、賃貸検索サイトの閲覧数や問い合わせ数を仲介会社に聞き取り、リアルタイムの温度感を把握しましょう。数日単位で需要が動く繁忙期には、この情報が空室期間を大きく左右します。また、周辺物件の平均家賃と設備スペックを一覧化し、自身の物件が競争力を持っているか検証することが欠かせません。
最後に、学生向けか社会人向けかといったターゲット層の再確認を行います。新築時に設定した想定入居者が、数年後もそのまま有効であるケースは意外と少ないものです。ターゲットが変われば、必要なリフォームや広告手法も変わるため、この段階で方向性を明確にしておくと後の施策がぶれません。
立地とターゲットの再設定
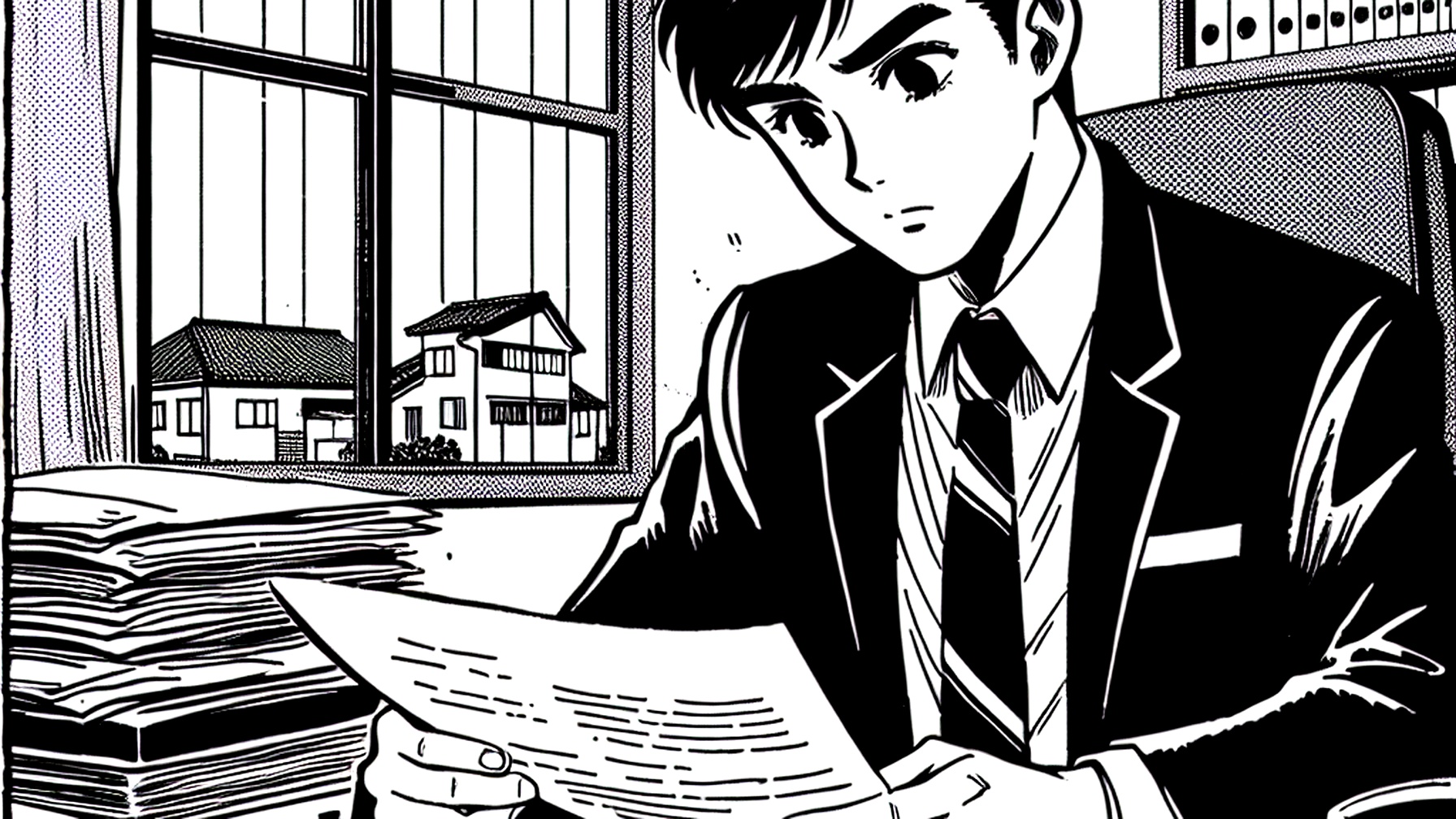
ポイントは、立地条件を「変えられない前提」と決めつけないことです。物件から最寄り駅までの距離が長い場合でも、送迎サービスやシェアサイクルの設置で実質的なアクセスを改善する試みが増えています。こうした取り組みは、築年数がやや古いアパートでも競争力を取り戻す助けになります。
さらに、ターゲット層のニーズを細分化すると対策が具体的になります。例えば単身社会人であれば、宅配ボックスと高速インターネットが最優先条件に挙がることが多いです。一方、高齢者向けに転換するなら、手すりの追加や段差解消のほか、見守りサービス連携が決め手になります。これらは大規模な構造変更を伴わずとも導入できる場合があり、投資効率が高い点が魅力です。
また、近隣大学と連携して合格発表日に合わせた内見イベントを行うなど、ターゲットが明確だからこそ実現できるプロモーションも存在します。入居者像がぼやけていると、こうした施策を企画することすら難しくなるため、定期的に見直す意義は大きいと言えます。
結果として、立地のハンデを補う施策とターゲット選定がかみ合えば、相場より家賃を下げることなく空室解消へとつながります。家賃値下げは最後の手段であり、まずは付加価値アップで勝負する発想が長期的な収益安定を生みます。
設備投資とリフォームのコツ
重要なのは、リフォームを「費用」ではなく「投資」と捉える視点です。築20年を超える物件でも、室内洗濯機置き場の新設だけで成約率が目に見えて向上するケースがあります。このように、入居者が感じる不便を解消する改修は、投下資本の回収期間が短くなる傾向があります。
一方で、流行に合わせた過度なデザインリノベーションは慎重を要します。入居者の目が肥えた現代では、奇抜な内装がかえって敬遠されるリスクがあるためです。シンプルかつ機能的なリフォームを基本にし、アクセントクロスや間接照明で個性を添える程度が好まれる傾向にあります。
設備投資の優先順位を決める際には、入居者アンケートが役立ちます。退去時のヒアリングで不満点を収集し、その項目に高評価を得られるよう改善する流れを繰り返せば、空室期間は着実に短縮します。また、故障リスクの高い給湯器やエアコンを先回りで更新することで、入居者の緊急トラブル対応コストを抑えられるメリットも見逃せません。
なお、2025年度の「賃貸住宅省エネ改修支援事業」では、高効率給湯器や断熱窓の導入に対し最大120万円の補助が受けられます。期限は2026年3月末までですが、予算上限に達し次第終了となるため、申請スケジュールを逆算しながら計画的に進めると良いでしょう。このように公的支援を活用すると、自己資金を抑えつつ競争力アップを図れます。
管理体制とマーケティングの強化
まず、管理会社に任せきりにしない姿勢が空室対策の大前提です。リーシング担当者との定期的な打ち合わせを設定し、内見結果のフィードバックを共有しましょう。内見数に対して申込みが少ない場合、写真の質や募集条件に課題が隠れていることが多いため、データをもとに改善策を協議します。
また、募集広告の露出先を広げると新たな層にリーチできます。SNS広告や短尺動画を組み合わせると、従来のポータルサイトに頼るだけでは得られなかった反響が得られる事例が増えています。特に20代〜30代はスマートフォンで物件を探す割合が高く、視覚的な訴求が効果的です。
さらに、内見時の第一印象を高めるため、共用部の清掃頻度を上げるだけでも成約率が変わります。エントランスに季節の花を置く、廊下照明をLEDに替えるといった小さな工夫が、写真では伝わりにくい「現地の雰囲気」を底上げします。入居希望者が「ここに住みたい」と感じる瞬間を演出することが、競合との差別化に直結します。
最後に、入居者満足度を高める取り組みを継続すると退去抑制につながります。無料インターネットの速度改善やアプリでの設備故障受付など、日常の利便性を高める施策は入居者に選ばれ続ける物件の共通点です。退去が減れば空室対策に費やすコストも下がるため、管理体制の強化は収益改善に二重の効果をもたらします。
補助金と税制優遇の上手な活用
実は、空室対策の一環として公的支援を利用すると収益性が大きく改善します。2025年度も継続している「住宅セーフティネット補助金」では、高齢者や子育て世帯の入居を想定した改修に対し、改修費の1/3(上限100万円)が支給されます。高齢者向け手すり設置やバリアフリー化といった需要の高い改修が対象になるため、空室解消と社会貢献を同時に実現できます。
また、耐震改修に伴う固定資産税の減額措置は2026年3月31日まで延長されました。工事完了翌年度の固定資産税が50%減額されるため、大規模修繕を検討している物件には大きなメリットがあります。税負担を抑えた分をリフォーム費用に回すことで、キャッシュフローを圧迫せずに魅力向上を図れます。
さらに、設備の省エネ性能を高めると所得税の特別償却が利用可能です。具体的には、断熱改修や高効率空調への更新費用の15%を上乗せ償却できるため、初年度の減価償却費が増え、課税所得を圧縮できます。これらの制度は申請書類の不備で却下されるケースもあるため、必ず専門家に確認してから手続きを進めると安心です。
こうした補助金や税制を組み合わせると、実質的な改修コストを大幅に軽減できます。空室期間中の家賃損失を考慮すれば、改修を先延ばしにするメリットはほとんどありません。むしろ早期に投資して入居率を高めたほうが、長期的なリターンは大きくなると言えるでしょう。
まとめ
ここまで、需要動向の分析、ターゲット再設定、設備投資、管理体制強化、そして補助金活用という五つの視点から空室対策を解説してきました。重要なのは、自物件の状況を客観的に把握し、最も効果的な打ち手に資金と時間を集中させることです。入居者が求める価値を継続的に提供できれば、家賃を無闇に下げずとも空室は減り、キャッシュフローも安定します。今日からできる小さな改善を積み重ね、アパート経営 空室対策 解決を一歩ずつ実現していきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 環境省 賃貸住宅省エネ改修支援事業 2025年度概要 – https://www.env.go.jp
- 厚生労働省 住宅セーフティネット制度 2025年度案内 – https://www.mhlw.go.jp
- 総務省 固定資産税減額制度 2025改正内容 – https://www.soumu.go.jp
- 国税庁 省エネ改修に伴う特別償却の手引き(令和7年度版) – https://www.nta.go.jp

