不動産投資に興味はあるけれど、「多額の資金や専門知識がないと始められないのでは」と不安を抱えていませんか。実は少額から参加できるREIT(リート)なら、その悩みを大幅に軽減できます。本記事では、REITの仕組みを基礎から解説し、2025年9月時点で有効なメリットや注意点を具体例とデータを交えながら紹介します。読み終える頃には、あなたがどのようにREITを活用すれば良いかがクリアになり、次の一歩を踏み出す準備が整うはずです。
REITとは何かを押さえよう
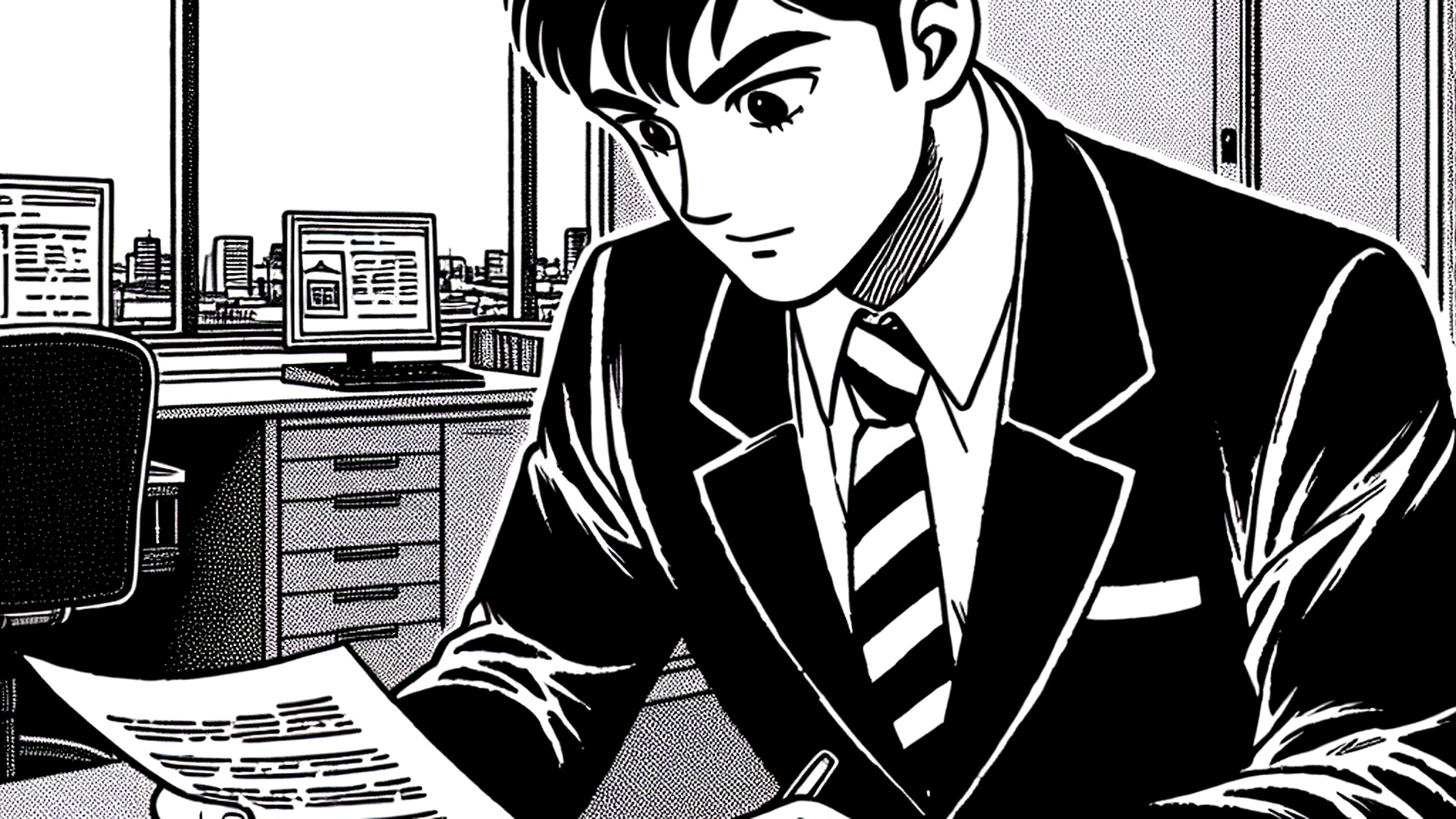
重要なのは、REITが「投資信託」の形で不動産を保有し、賃料や売却益を投資家に分配する仕組みである点です。言い換えると、株式のように証券取引所で売買できる「不動産ファンド」と考えるとイメージしやすいでしょう。
まずREITは、多数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、物流倉庫など複数の物件を購入します。このポートフォリオ効果により、特定物件の賃料変動リスクを分散できるのが特徴です。また、投資法人が得た利益の90%以上を分配すれば法人税が実質的に免除される「みなし配当課税」が適用されるため、高い分配金利回りを維持しやすい点も押さえておきたいポイントです。
さらに、東京証券取引所のJ-REIT市場では2025年9月時点で63銘柄が上場し、時価総額は約20.4兆円(日銀統計)に達しています。市場が成熟し、情報開示のルールも厳格化されたことで、個人投資家でも企業分析がしやすくなりました。結果として、投資初心者でも安心して参加できる環境が整っています。
個人投資家にとってのREIT メリット
まず押さえておきたいのは、「少額投資」「高い流動性」「安定的なインカム」という三つのメリットがそろっていることです。この組み合わせが、現物不動産投資にはない魅力を生み出します。
最初のメリットは、10万円前後から始められる少額投資です。都心マンションを一室購入するには数千万円が必要ですが、REITなら単元株のように一口単位で購入できます。資金面のハードルが下がることで、投資デビューの第一歩として選ぶ人が増えています。
次に、株式市場で取引されるため売買の流動性が高い点も見逃せません。たとえば、想定外の資金需要が生じた場合でも、平日の日中であれば即日で現金化できます。現物不動産のように数カ月かかる売却手続きは不要なので、資金効率を高めやすいわけです。
三つ目が、比較的安定した分配金です。オフィス系J-REITの平均分配金利回りは2025年5月時点で3.7%(東証データ)となっており、長期国債利回り1%前後を大きく上回ります。しかも分配金は年2回が一般的で、配当と同様に定期的なキャッシュフローが得られる点が家計管理にも役立ちます。
リスクと上手な付き合い方
実はメリットが多い一方で、REITにも価格変動リスクや金利上昇リスクが存在します。投資効果を最大化するには、それらを理解したうえで対策を講じることが不可欠です。
価格変動リスクの主因は景気循環です。景気後退局面ではオフィス空室率が上昇し、賃料が下落しやすくなります。その結果、分配金の減少が懸念され株価も下がりやすいのです。対策として、用途が異なる複数のREITを組み合わせる「銘柄分散」を行うと、景気の影響を均しやすくなります。
一方で金利上昇は、借入比率(LTV)が高いREITほど収益を圧迫します。たとえば、LTVが50%で平均借入金利が1%上昇すると、分配金が10%程度減少するケースも報告されています(不動産研究所試算)。そこで、財務健全性を示す指標としてLTV40%以下、長期固定金利比率70%以上の銘柄を選ぶと、金利上昇局面でも影響を抑えやすいと言えます。
そして、自然災害リスクも忘れてはいけません。特に物流施設やホテルはエリア集中しがちなので、物件所在地を公式サイトの保有資産一覧で確認し、多地域に分散できているかをチェックすることが大切です。
2025年時点の市場動向と選び方
ポイントは、人口動態や新しい働き方の変化を踏まえてセクターを選ぶことです。2025年9月現在、テレワーク定着によるオフィス需要の調整と、EC拡大による物流施設需要の伸長という二極化が進んでいます。
まず物流系REITは、稼働率98%超の物件が多く、分配金の安定度が高い傾向にあります。国土交通省の物流統計では、国内EC市場規模が毎年8%前後で拡大しており、今後も倉庫需要は底堅いと予想されます。実際、物流特化型J-REITの平均NAV倍率は1.25倍で、投資家が成長性を織り込みつつあることが読み取れます。
一方、オフィス系は空室率が上昇しているものの、賃料の下げ止まり感も出ています。特に丸の内や虎ノ門などプレミアエリアでは、再開発による新築ビルが先行して満床になる例もあり、選別が進んでいます。つまり、立地と築年数を見極めればオフィス系でも割安な掘り出し銘柄が見つかる可能性があります。
また、2025年度のNISA(少額投資非課税制度)は年間投資枠が360万円に拡大され、成長投資枠を使えばJ-REITも非課税で購入できます。配当課税約20%がゼロになる恩恵は大きく、分配金利回りをそのまま受け取れるため、長期保有戦略との相性が抜群です。非課税枠をフル活用し、複数セクターを組み合わせることでリスクを抑えながらリターンを狙えます。
まとめ
ここまでREITの特徴とメリット、そしてリスク対策を見てきました。少額から始められ、流動性が高く、安定した分配金が期待できる点は、現物不動産にはない大きな魅力です。もっとも、景気や金利の変動リスクは避けられませんので、銘柄分散や財務健全性のチェックなど基本を丁寧に押さえることが長期的な成果につながります。NISA拡充という追い風も受け、今こそ学びを行動に移す好機です。まずは証券会社のサイトで銘柄を比較し、少額から実践してみてください。
参考文献・出典
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行「資金循環統計」- https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「物流拠点整備に関する調査」- https://www.mlit.go.jp
- 不動産研究所「J-REITレビュー2025」- https://www.reinet.or.jp
- 財務省「令和7年度税制改正大綱」- https://www.mof.go.jp

