アパート経営に興味はあるものの、「初期費用が高そうで踏み出せない」「本当にメリットがあるのか知りたい」と感じる方は少なくありません。自己資金を投じて物件を購入する以上、失敗は避けたいと誰もが考えます。そこで本記事では、2025年9月時点の最新情報をもとに、初期費用の内訳から資金調達の現実的な方法、さらにメリットとデメリットまでを丁寧に整理します。読み終えた頃には、自分に合った戦略が描けるようになるはずです。
アパート経営に必要な初期費用の内訳
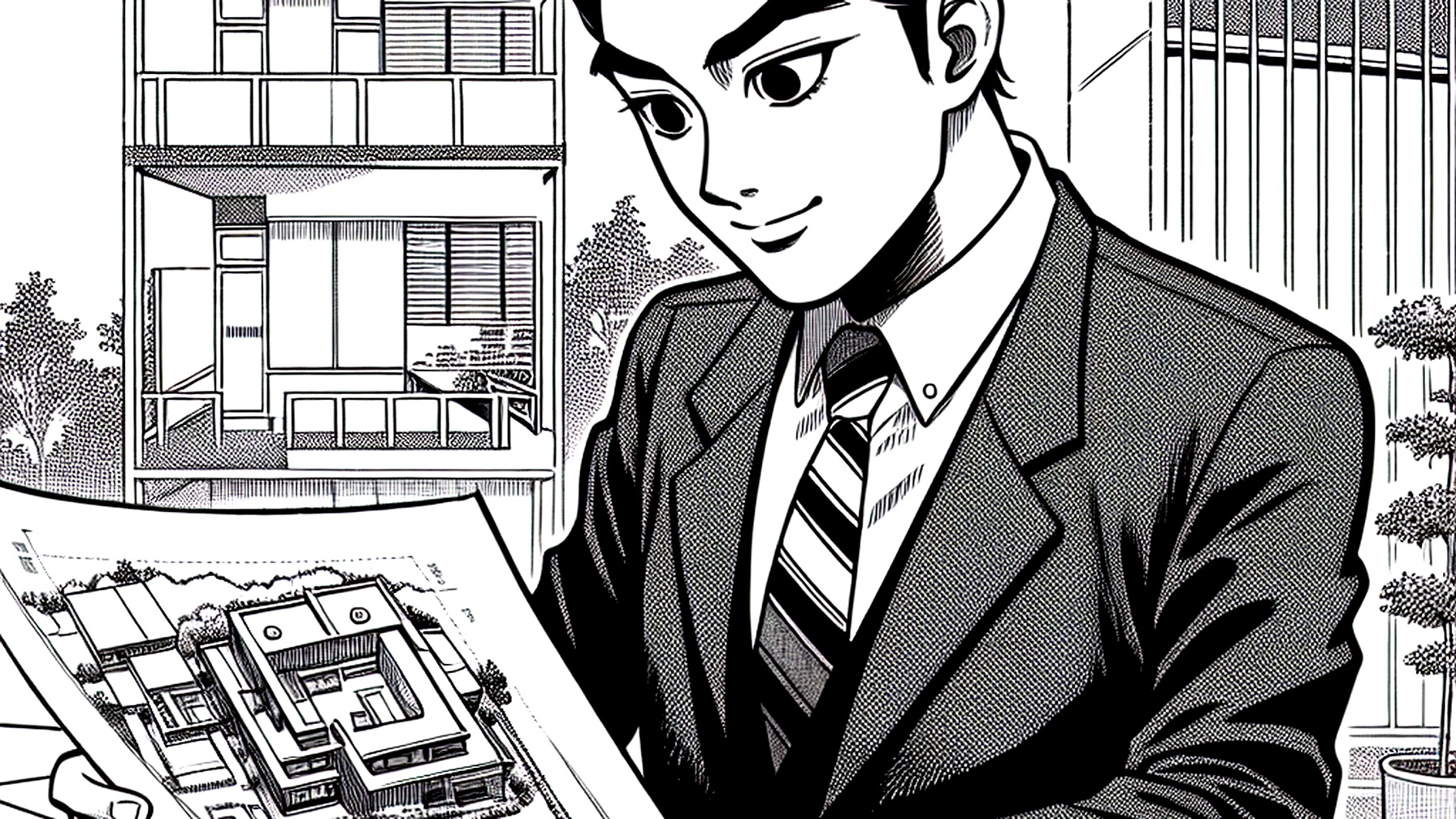
まず押さえておきたいのは、アパート経営に必要な初期費用が「物件価格+諸費用」で構成される点です。物件価格だけを見て資金計画を立てると、契約直前に資金が足りない事態になりかねません。
重要なのは、諸費用が物件価格の7〜10%程度かかるという事実です。仲介手数料や登記費用のほか、固定資産税・都市計画税の清算金も発生します。2025年現在、木造アパート1棟(価格4,000万円)を想定すると諸費用は約320万円から400万円です。
また、金融機関から融資を受ける場合には、事務手数料や保証料が別途必要です。金利1.6%・期間25年の融資で事務手数料2.2%がかかるとすると、4,000万円の借入に対して約88万円が初期費用に上乗せされます。
さらに、入居者募集の広告費や火災保険料も開業前に支払う必要があります。広告費は1戸あたり家賃1〜2か月分が目安で、10戸のアパートなら最大で家賃20か月分に相当するケースもあるため、資金計画には余裕を持たせましょう。
資金を準備するための現実的な方法
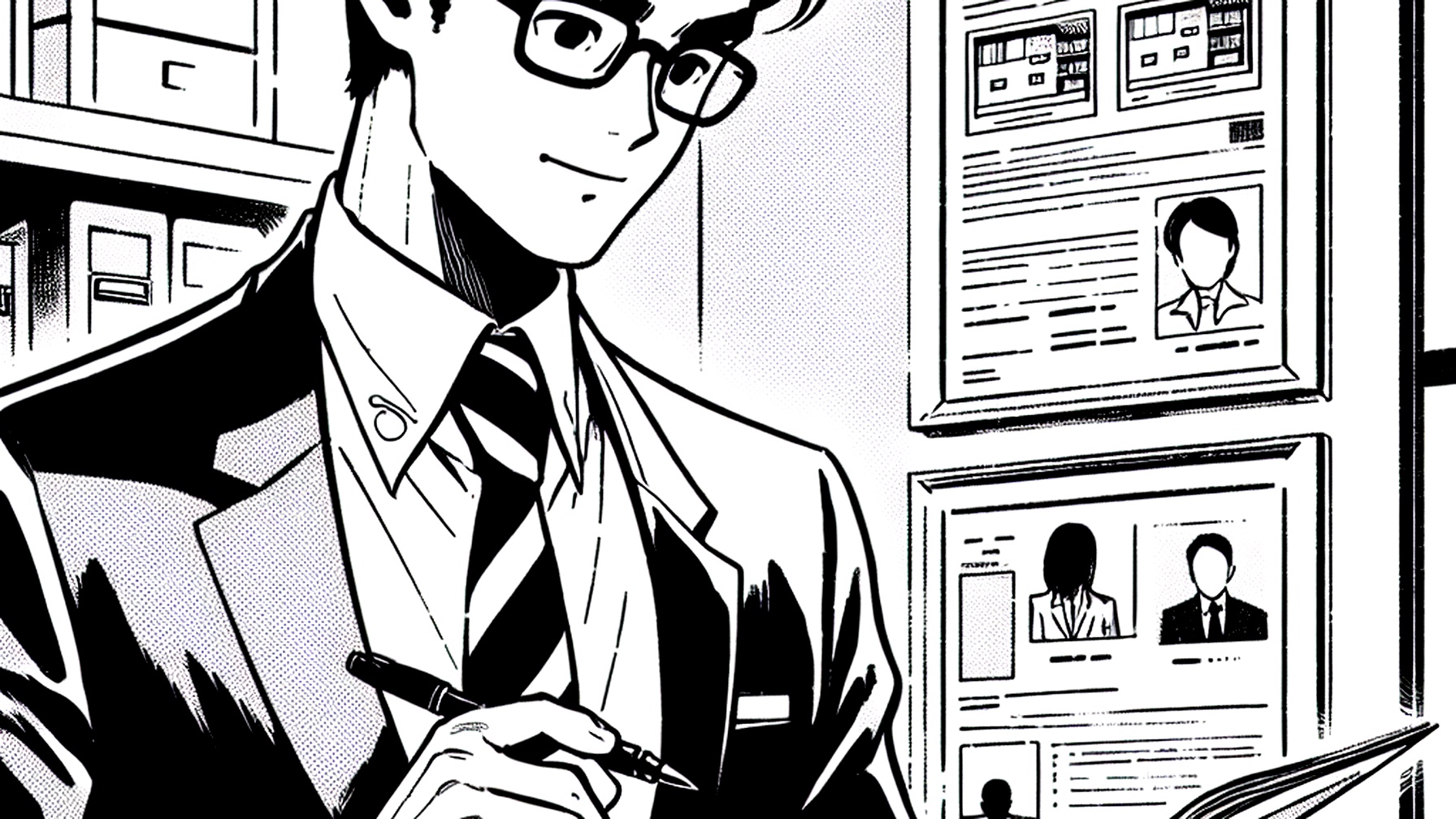
ポイントは、自己資金と融資をバランス良く組み合わせることです。自己資金比率20〜30%を確保すると、金融機関の審査をクリアしやすくなるだけでなく、毎月の返済負担が軽くなります。
一方で、自己資金をすべて物件購入に充てると、修繕や空室に対応するキャッシュを失う恐れがあります。2025年7月の全国アパート空室率は21.2%(国土交通省住宅統計)で、前年より0.3ポイント改善したとはいえ、空室リスクは依然として無視できません。運転資金として家賃6か月分を別枠で用意するのが現実的です。
融資先の選択肢としては、都市銀行・地方銀行・信用金庫に加え、日本政策金融公庫も活用できます。同公庫の「国民生活事業」では、耐用年数超過物件でも最長15年の融資が可能で、自己資金1割からの相談に応じています。複数機関に事前相談し、金利や融資期間、団体信用生命保険の条件を比較することが成功の近道です。
加えて、2025年度も継続する「住宅省エネ2025キャンペーン(国交省・経産省)」のうち、賃貸住宅の省エネ改修費補助を利用すれば、入居促進と節税を同時に狙えます。新築時に高断熱仕様を採用すると、補助額上限100万円/戸を受け取れる可能性があるため、資金計画で漏れなく検討しましょう。
アパート経営の主なメリット
実は、アパート経営の魅力は家賃収入だけにとどまりません。最大の利点は安定性です。株式や暗号資産と比較すると価格変動が緩やかで、長期的なインカムゲイン(継続収入)が期待できます。
また、融資を利用することでレバレッジ効果が働きます。自己資金1,000万円で4,000万円の物件を取得すれば、家賃収入と元本返済を合わせた年間キャッシュフローは自己資金利回りで10%以上を実現するケースもあります。時間とともにローン残高が減少し、資産が自動的に増える仕組みが働く点は大きなメリットです。
節税面でも恩恵があります。減価償却費を計上できるため、所得税・住民税の圧縮が可能です。2025年度税制では、耐用年数超過物件でも定額法による償却が認められ、課税所得の圧縮余地は依然として大きいといえます。
さらに、将来の年金対策としても有効です。ローン完済後は家賃の大部分が純粋な手取りになり、インフレに強い収入源を確保できます。金融資産と異なり、賃料は物価上昇に合わせて調整しやすいため、老後の購買力維持に役立ちます。
注意すべきデメリットとリスク管理
一方で、アパート経営にはデメリットも存在します。まず、空室リスクです。前述のとおり全国平均で21.2%の空室率があり、エリアや築年数によってはさらに高い数字になることもあります。入居募集の計画とリフォーム予算を十分に確保しておかなければ、収支が成立しません。
次に、修繕コストの負担です。屋根や外壁の塗装は10〜15年ごとに必要で、1棟あたり100万円単位の支出が見込まれます。法定共用部点検やエレベーター保守も定期的に発生し、長期修繕計画の策定が欠かせません。
金利上昇リスクにも注意が必要です。変動金利で1%の上昇が起こると、4,000万円・25年ローンの総返済額は約500万円増加します。金利上昇局面に備え、固定金利への借換えや繰上返済用の余裕資金を準備しましょう。
最後に、災害リスクがあります。気象庁によると近年は大雨の発生頻度が増加しており、洪水ハザードマップの確認は必須です。火災保険と地震保険を適切に組み合わせ、資産毀損時のキャッシュフローを守る体制を整えてください。
2025年度に活用できる支援制度
基本的に、アパート経営で使える国の支援制度は限定的ですが、2025年度(令和7年度)に有効なものとして次の二つを押さえておくと有利です。
・住宅省エネ2025キャンペーン 高断熱窓や高効率給湯器を採用すると、1戸あたり最大100万円の補助。集合住宅も対象で、交付申請は2026年2月末までです。
・中小企業経営強化税制 個人事業主や資産管理会社が対象設備を導入した場合、即時償却または10%税額控除が選択可能。2025年3月末取得分まで延長されているため、共用部LED化や防犯カメラ設置時に検討できます。
これらを組み合わせれば、初期費用の一部を削減し、キャッシュフロー改善を図ることができます。ただし、申請には専門家による証明書が必要になるケースがあるため、早めに手続きを始めると安心です。
まとめ
アパート経営で成功する鍵は、初期費用を正確に把握したうえで適切な資金計画を立てることにあります。物件価格のみに目を奪われず、諸費用や運転資金まで含めて資金を確保し、自己資金と融資をバランス良く組み合わせましょう。メリットとしては安定収入や節税効果が挙げられますが、空室や修繕、金利といったデメリットにも備えが欠かせません。2025年度の省エネ補助や税制優遇を上手に活用すれば、キャッシュフローを強化できます。まずは信頼できる金融機関や専門家に相談し、自分のリスク許容度に合った計画を立てることから始めてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年7月速報) – https://www.mlit.go.jp/
- 国税庁 令和7年度税制改正大綱 – https://www.nta.go.jp/
- 日本政策金融公庫 国民生活事業 融資制度 – https://www.jfc.go.jp/
- 経済産業省・国土交通省 住宅省エネ2025キャンペーン – https://jutaku-shoene2025.go.jp/
- 気象庁 気候統計情報(大雨の発生頻度) – https://www.jma.go.jp/

