不動産投資を始めたいのに「保証人を立てられるか不安だ」と悩む人は少なくありません。親族に頼みにくい、人間関係が気まずくなる、保証人の責任が重い――こうした理由で二の足を踏むケースが目立ちます。本記事では、保証人が求められる背景から、保証人なしで融資を受ける方法までを解説します。2025年9月時点の金利動向や審査基準を踏まえ、リスクと対策を整理しますので、最後まで読めば自分に合った資金調達の道筋が見えてくるはずです。
保証人が必要となるケースを理解する
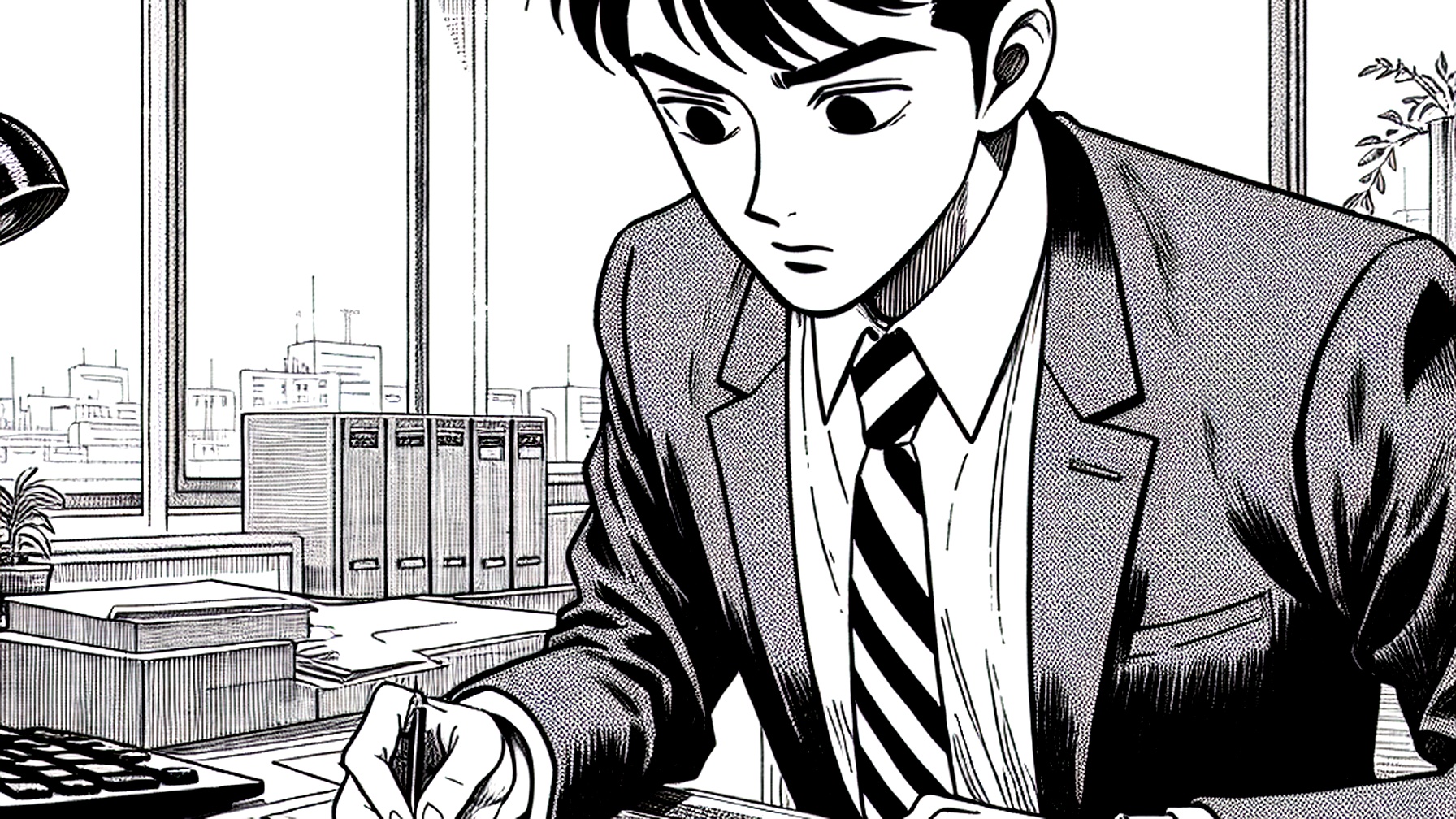
まず押さえておきたいのは、保証人を求める金融機関が減少傾向にある一方で、一定の条件下では今も保証人が必要だという現実です。不動産投資ローンは無担保ローンと違い、物件自体が担保となりますが、収益性が読みにくい物件や自己資金が少ない場合、銀行は追加の信用補完策として保証人を要求します。
日本政策金融公庫のガイドラインでは、自己資金が物件価格の一五%未満だと連帯保証人を求める可能性が高まると示されています。さらに、個人信用情報に延滞履歴がある場合、保証会社によるカバーが難しく、結局は親族保証に頼る構図になりがちです。つまり、自己資金と信用力が十分なら保証人を避けられる余地がある一方、準備不足だと保証人の壁が立ちはだかります。
一方で、メガバンクや地方銀行の多くは、保証会社と提携することで保証人を省略する仕組みを整えています。ただし保証料は年〇・三〜〇・五%程度かかり、表面利回りが低い物件ではキャッシュフローを圧迫します。保証人を立てる負担と保証料のコストを比較し、自分の投資計画に合う方法を選ぶことが重要です。
連帯保証人と保証会社の違い
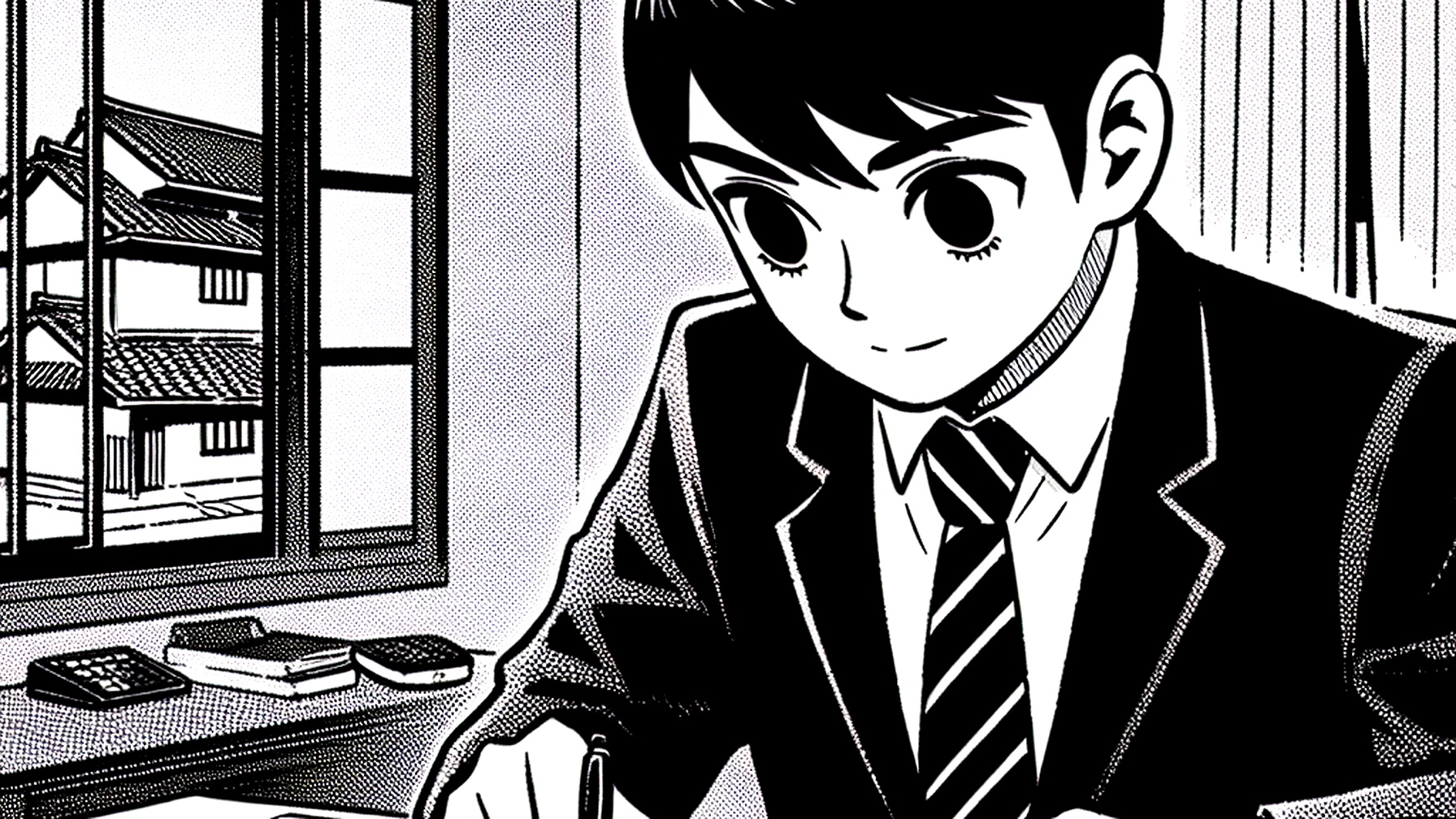
重要なのは、連帯保証人と保証会社では責任範囲もコスト構造も大きく異なる点です。連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負い、債権者は本人を飛ばして保証人に請求できます。このため、万一返済が滞ると保証人の信用情報に傷が付き、資産まで差し押さえられる可能性があります。
一方、保証会社は金融機関に対して保証料を受け取り、債務者が返済不能になった際に代位弁済を行います。債務者は保証会社へ求償を受けますが、個人保証よりも手続きが制度化されているため、親族や友人に迷惑をかけずに済む点がメリットです。ただし、代位弁済後の取り立ては厳格で、競売や任意売却を含む処理が速やかに進む傾向があります。
保証料は物件価格と借入期間によって変動します。二〇二五年時点で三五年ローンなら総借入額の二%前後が目安です。例えば三千万円を借りた場合、保証料は約六十万円となり、初期費用として一括払いか金利上乗せで支払います。保証人不要の利便性と費用負担のどちらを取るか、試算して判断する姿勢が欠かせません。
2025年度の融資審査と保証人の影響
ポイントは、二〇二五年度の融資審査が「キャッシュフロー重視」にシフトしていることです。全国銀行協会の調査によると、収益還元評価を導入する地方銀行は七〇%を超えました。家賃収入から維持費、返済額を差し引いた後も手元に余裕資金が残るかどうかが、保証人要否の分岐点になっています。
変動金利は一・五〜二・〇%、固定一〇年は二・五〜三・〇%が相場で、金利上昇リスクを織り込んだシミュレーションが不可欠です。試算上、金利が一%上がっても毎月の返済比率が四〇%以下に収まるなら、保証会社利用のみで承認されやすくなります。逆に金利上昇で比率が五〇%を超えると、銀行は連帯保証人による追加担保を検討し始めます。
また、個人の与信スコアを算定するフィンテック審査が広がり、過去のクレジットカード利用履歴や公共料金の支払い状況までチェックされます。このスコアが一定基準を下回ると、自己資金を増やすか保証人を入れるよう提案されやすいのが現実です。つまり、家賃収入だけでなく自身の生活実績が保証人の必要性に直結する時代になったといえます。
保証人を立てずに借りる実践策
実は、保証人なしで不動産投資ローンを組む方法は存在します。最も現実的なのは、自己資金を二〜三〇%まで厚くすることです。物件価格三千万円に対し九百万円を頭金として入れると、貸倒れリスクが下がるため、銀行も保証会社のみで応じやすくなります。
さらに、築浅で入居率の高い物件を選ぶと、収益予測の精度が上がり、保証人抜きでも審査が通る確率が高まります。人口減少が続く地域よりも、都心ターミナル駅から徒歩圏内のワンルームや、再開発エリアのファミリータイプなど、需要が読みやすい立地が望ましいでしょう。空室率が五%未満に抑えられる想定なら、銀行はキャッシュフローの安定を評価し、保証要求を緩和する傾向があります。
法人化も有効な選択肢です。合同会社や株式会社を設立し、代表者保証のみで借り入れれば、個人の親族にまで責任が及びません。法人名義なら経費計上の自由度が上がり、返済余力も可視化しやすいため、金融機関は保証会社との併用でリスクヘッジしやすくなります。ただし、設立費用や税務申告の手間が増える点は事前に把握しておきましょう。
保証人を頼む前に確認したいリスク
保証人を引き受けてもらう前に、リスク説明を十分に行うことが信頼関係を守るカギです。保証人は借入残高全額を肩代わりする可能性があり、長期にわたり信用情報が制限されます。たとえ返済が順調でも、保証期間中は住宅ローンや教育ローンの審査に影響が出る場合があるため、家族の将来設計に重くのしかかります。
保証解除が容易ではない点も見逃せません。借入額の一部を繰上返済して残債が減っても、原則として保証契約は存続します。保証人を外すには、銀行が改めて再審査を行い、保証会社への切り替えなどを認める必要があります。手続きには数週間かかり、追加の事務手数料が発生することもあります。
結論として、保証人への依頼は最終手段と考え、まずは自己資金の増強、物件選定の精度向上、法人化といった代替策を検討することが賢明です。そのうえでやむを得ず保証人を必要とする場合は、公正証書で契約内容を明確にし、トラブル防止に努めましょう。
まとめ
この記事では、不動産投資ローン 保証人の仕組みと回避策を解説しました。保証人が必要になるのは、自己資金が薄く信用力に不安がある場合です。保証会社を利用すれば親族に頼らずに済みますが、保証料がキャッシュフローを圧迫します。自己資金を二〇%以上投入し、収益性の高い物件を選べば、保証人なしでも融資は可能です。最終的には、資金計画と物件選定の精度が保証人要否を左右することを忘れず、準備を整えてから金融機関に臨むようにしましょう。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 不動産業ビジョン – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資ガイド – https://www.jfc.go.jp
- 住宅金融支援機構 住宅ローン統計 – https://www.jhf.go.jp
- 一般社団法人全国不動産協会 市場レポート – https://www.zennichi.or.jp

