不動産投資に興味はあるものの「自分でも本当にできるのか」と迷っていませんか。とくに収益物件を初めて購入する際は、価格や立地、融資など検討事項が多く、何から手を付ければよいのか途方に暮れる方が少なくありません。本記事では、15年以上の実務経験で得た知見と2025年9月時点の最新データをもとに、初心者が収益物件を選ぶ手順から資金計画、そして税制メリットまでを順序立てて解説します。読み終えるころには、具体的な第一歩を踏み出すための判断軸が身につくはずです。
収益物件とは何か
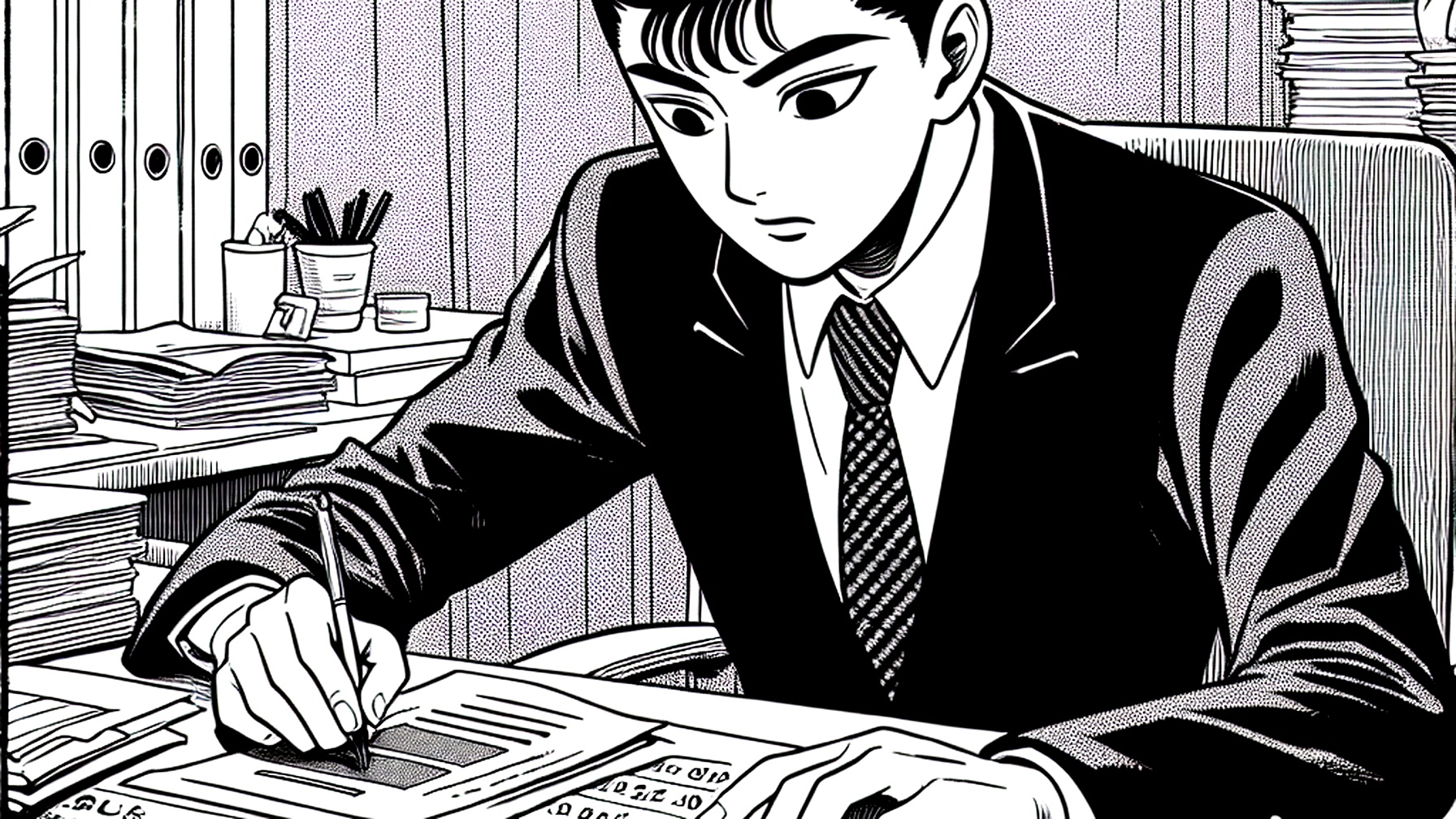
まず押さえておきたいのは、収益物件という言葉が指す範囲です。収益物件とは家賃やテナント料などのインカムゲイン(運用益)を得るために保有する不動産を指します。マンション一室から一棟アパート、オフィス、倉庫まで多岐にわたりますが、初心者は管理のしやすさと資金規模の面で区分マンションから始めるケースが目立ちます。
実は、同じ家賃10万円でも手元に残るキャッシュは物件ごとに大きく異なります。毎月のローン返済や管理費、修繕積立金が差し引かれるからです。そこで重要なのは、表面利回りだけではなく、諸経費を差し引いた実質利回りを比較する視点です。たとえば月額家賃10万円の区分マンションで年間家賃収入120万円、諸経費が年30万円なら、実質利回りは物件価格2,000万円に対し4.5%になります。
さらに、賃借人が退去するごとに発生する原状回復費や、将来の大規模修繕積立も見逃せません。国土交通省「賃貸住宅管理業実態調査」によると、2024年の平均空室期間は27日ですが、築20年超の物件では45日まで延びる傾向があります。空室期間が長引けば、実質利回りは簡単に2~3ポイント低下するため、築年数と修繕計画をセットで考えることが欠かせません。
なぜ今、初心者でも収益物件を持つべきか
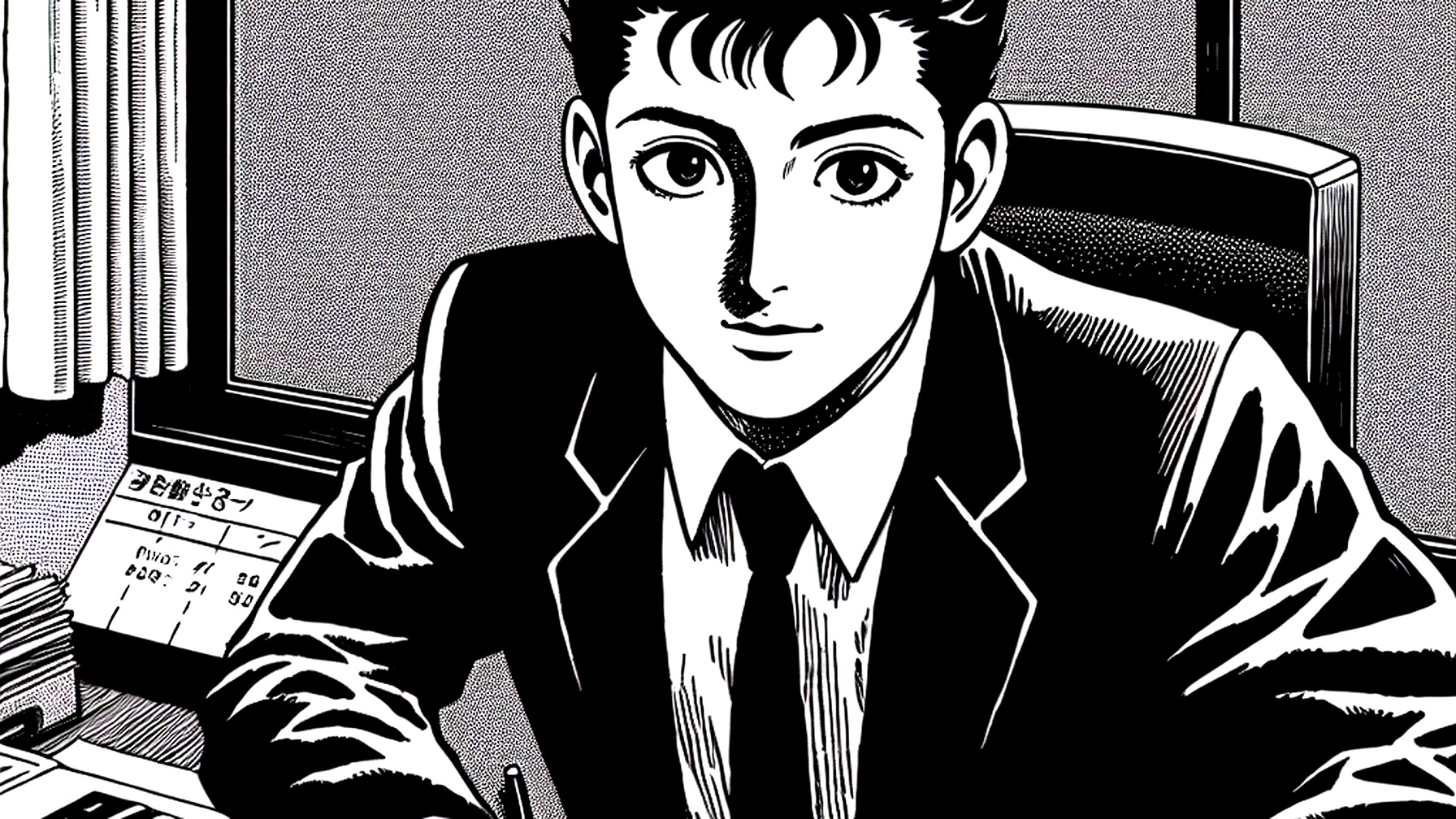
ポイントは、日本全体で見ると人口減少局面に入っている一方、都市部の単身世帯は増え続けているという事実です。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によれば、2024年の東京都転入超過は77,850人で3年連続の増加です。つまり、都心や主要駅近くのコンパクト物件では、しばらく需要が底堅いと考えられます。
また、2025年度の住宅ローン金利は依然として低位で推移しています。日本銀行のマイナス金利政策が一部修正されても、長期固定金利(フラット35)は1.9%前後で推移し、過去20年平均より0.5ポイントほど低い状態です。これにより、同じ家賃収入でもキャッシュフローが改善しやすいため、初心者でも資金計画を描きやすい環境が続いています。
一方で、インフレ傾向が続くと現金の購買力は目減りします。不動産はインフレヘッジ(価値保存)の役割を果たすため、将来の年金原資や教育資金づくりとして取り組むメリットがあります。言い換えると「時間を味方につけられる資産」が収益物件なのです。
初心者が押さえるべき物件選びの視点
まず押さえておきたいのは「立地、賃貸需要、管理体制」の三本柱です。立地については駅徒歩10分圏内を基本とし、周辺に大学や企業が集まるエリアなら単身向け需要が見込めます。ただし、既存物件が多い地区では賃料競争になりやすいので、築浅か、差別化できる設備があるかを確認しましょう。
賃貸需要を測る簡易指標として、国交省「住宅着工統計」の地域別空室率が参考になります。2024年度の都心三区(千代田・中央・港)の空室率は4%台と低い水準ですが、郊外では10%を超える地域もあります。数字が高いエリアでも、最寄り駅周辺の再開発が進む場合は需要増につながることがあるため、開発計画も合わせてチェックしてください。
一方で、管理体制を甘く見てはいけません。共用部が清潔に保たれているか、管理会社のレスポンスが早いかなどは入居者満足度と直結します。初心者は自主管理よりも、手数料5%前後で客付けから家賃回収まで代行してくれる専門会社に任せるとリスクを抑えやすいです。面談時には「24時間緊急対応の実績件数」「原状回復費の平均単価」を具体的に聞き、比較検討しましょう。
資金計画と融資の基本
重要なのは、自己資金と融資のバランスを適切に保つことです。自己資金を20~30%入れると、金融機関の評価が高まり金利優遇を受けやすくなります。たとえば2,000万円の区分マンションで500万円を自己資金として投入し、残り1,500万円を金利1.6%、期間25年で借り入れた場合、月々の返済額は約6.1万円です。家賃が10万円なら、管理費などを差し引いても月2万円以上の純収益を見込めます。
融資を受ける流れを簡単に整理すると、
- 事前審査申込
- 収支シミュレーション提出
- 金融機関による物件評価
- 本審査・契約
の四段階です。各段階で必要書類を漏れなく用意し、自己資金と返済原資を説明できれば、審査期間を短縮できます。
一方で、金利タイプの選択も大切です。変動金利は当面の返済負担を軽くできますが、金利上昇局面ではキャッシュフローが目減りします。固定金利は初期負担がやや重いものの、長期的な返済計画が立てやすい利点があります。住宅金融支援機構のシミュレーションでは、金利が1%上昇すると返済総額は約10%増えると試算されています。収支計算は、変動金利が2%まで上がった場合でも黒字が維持できるかを基準にすると安心です。
2025年度の税制・補助活用ポイント
実は、税制優遇を理解するだけで手取り収入が大きく変わります。2025年度も不動産所得は減価償却や損益通算が認められ、所得税・住民税の節税に活用できます。木造築20年超やRC造築40年超の区分マンションなら耐用年数を過ぎているため、4年定額で償却でき、初期数年間は大きな経費計上が可能です。
さらに、環境配慮型リフォームを行う場合、2025年度の「住宅省エネ2025キャンペーン」(補助上限60万円/戸)は賃貸物件も対象です。ただし、交付申請は2026年3月末までと期限があるため、購入後すぐにプランを立てる必要があります。二重窓設置や高効率給湯器の導入で実質利回りが低下しないよう、補助金と家賃アップ効果をセットで試算しましょう。
固定資産税については、新築住宅の減額措置が2026年度入居開始分まで延長されました。区分マンションの場合、床面積50~120㎡の範囲で課税標準が3年間2分の1になります。築浅物件を購入しても対象期間は残存しないため、新築一棟アパートなどを検討する際に活用すると効果的です。
まとめ
ここまで、収益物件を初めて購入する際に押さえるべき視点を解説しました。立地と需要を見極め、実質利回りで比較し、自己資金と低金利を組み合わせた資金計画を立てれば、安定したキャッシュフローを実現できます。税制優遇や2025年度の省エネ補助も上手に活用し、手残りを最大化してください。まずは気になるエリアで3件ほど物件情報を取り寄せ、本文で紹介した指標を使って数字を比較することから始めましょう。行動を起こせば、数年後に家賃収入が家計を支える大きな柱となるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅管理業実態調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 住宅金融支援機構 金利情報・シミュレーション – https://www.jhf.go.jp

