不動産投資を始めたいものの「税金が複雑で不安」「RC造は高そう」という声をよく耳にします。実は鉄筋コンクリート造(RC造)は木造より初期費用が大きい一方、減価償却期間の長さや維持管理コストの低さから、長期で見ると税務メリットを享受しやすい構造です。本記事では2025年9月時点で有効な制度の範囲内で、取得時・保有中・売却時の税金を整理し、初心者の方でもRC造投資を数字で判断できるように解説します。読み終える頃には、税負担を最小化しながらキャッシュフローを最大化する考え方が身につきます。
RC造とは何かと税務上の特徴
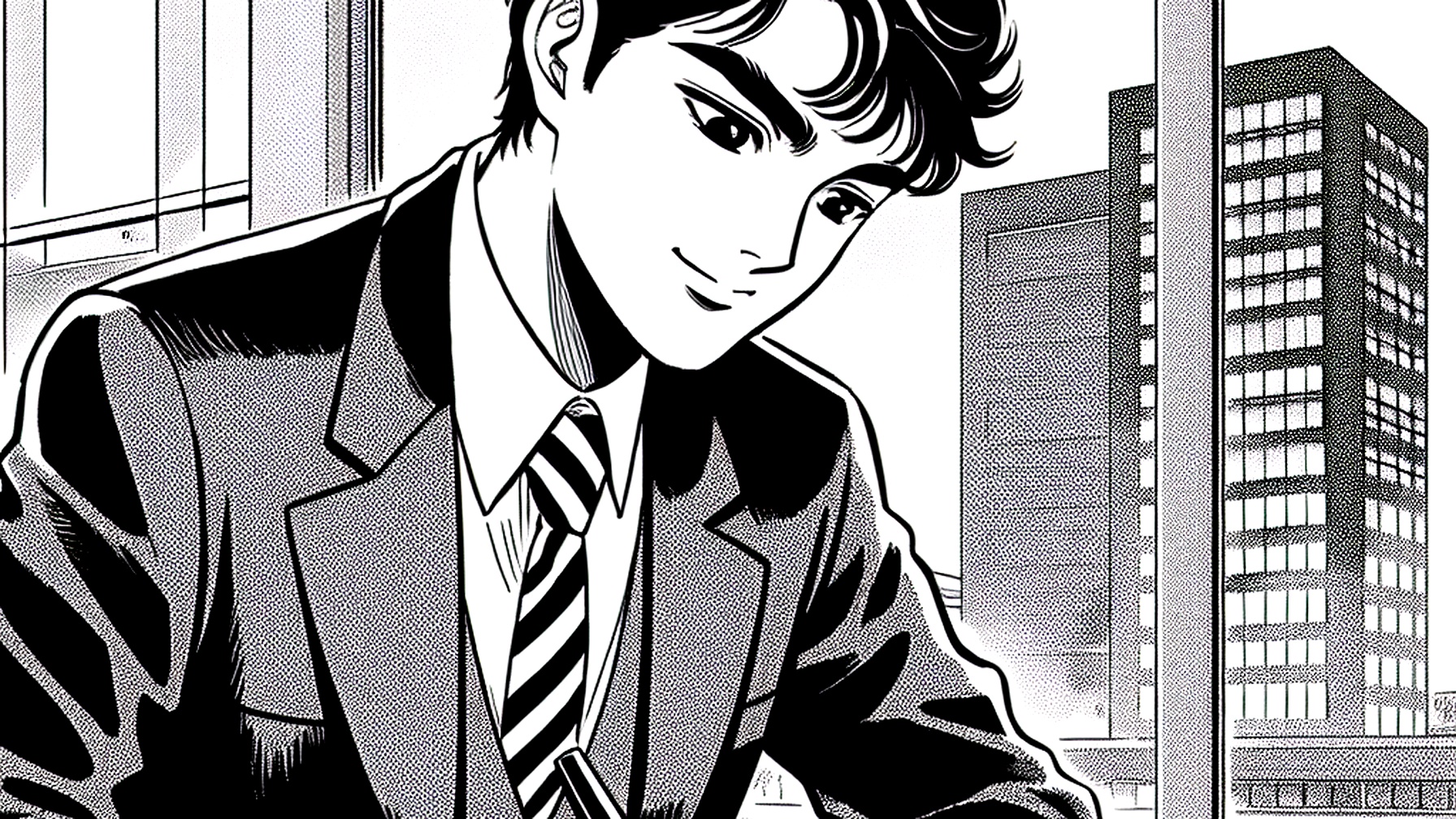
まず押さえておきたいのは、RC造が「鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)」の略で、鉄筋とコンクリートを組み合わせた頑丈な構造だという点です。総務省の「住宅・土地統計調査」によると、RC造の平均築年数は木造より約10年長く、耐火性能も高いため保険料を抑えられる可能性があります。この長寿命は税務面では減価償却の期間に直結し、木造の法定耐用年数22年に対し、新築RC造は47年と倍以上です。つまり毎年の減価償却費が薄く伸び、その分だけ課税所得を安定して圧縮できます。また、建物部分の消費税仕入控除を将来の大規模修繕費と相殺しやすい点もRC造ならではの利点です。
一方で、取得価格が高くなると固定資産税評価額も上がりやすいという弱点があります。しかし、RC造特有の耐用年数の長さから減価償却費が残る期間に固定資産税の総額を相殺できるケースも多く、トータルで見れば収支が安定する傾向にあります。投資判断では「購入価格だけでなく、耐用年数×節税効果」で比較する姿勢が重要です。
取得時にかかる税金の仕組み
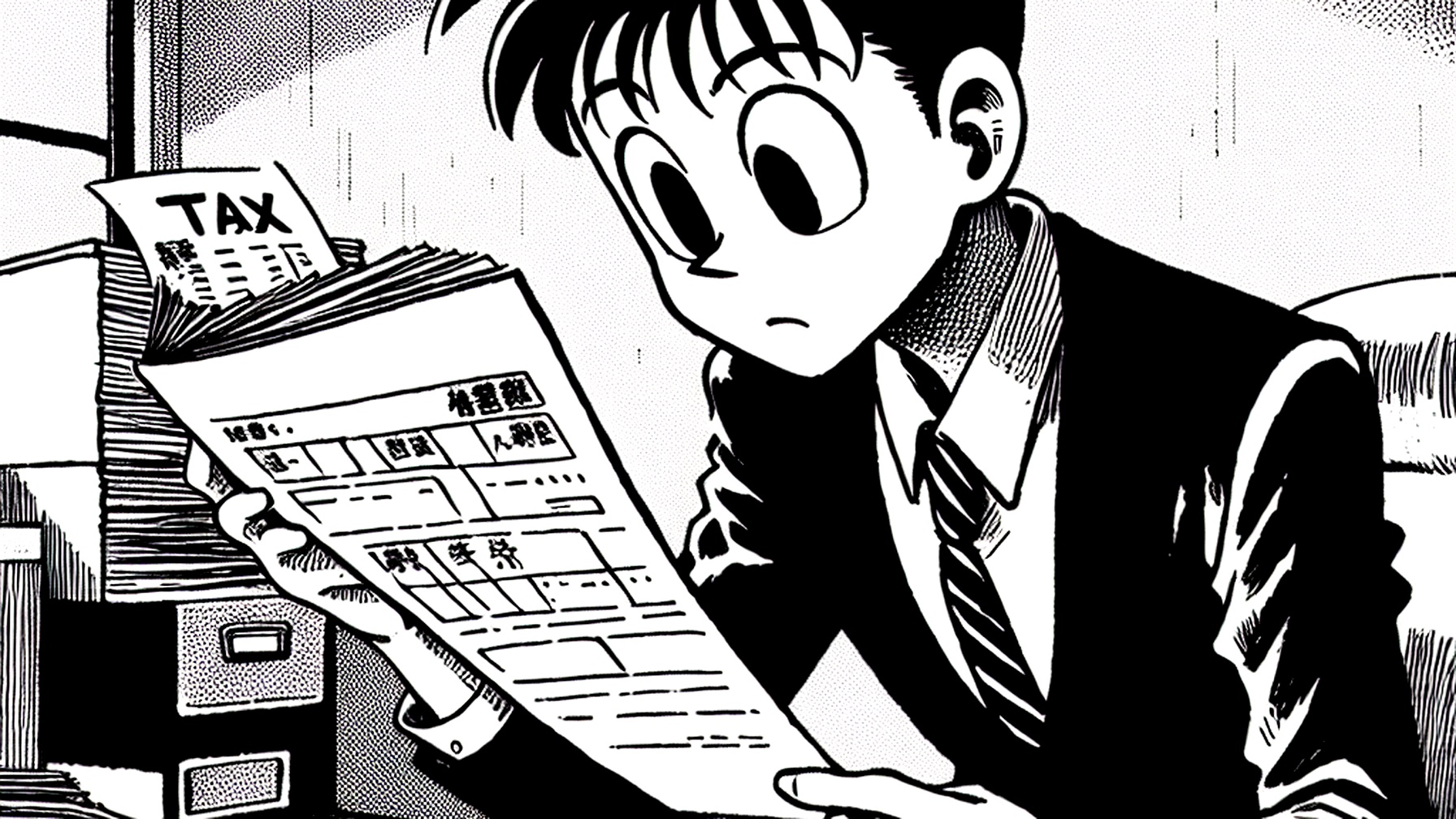
ポイントは、RC造を取得するときに発生する税金が四つあることです。具体的には登録免許税、不動産取得税、消費税(建物のみ)、そして印紙税です。登録免許税は建物表題登記と所有権移転登記で課税され、2025年度の税率はそれぞれ0.4%と2.0%が標準ですが、一棟投資の場合は土地と建物を分けて評価するため課税標準のチェックが欠かせません。
不動産取得税は都道府県税で、建物評価額×4%が基本です。ただし、新築住宅の軽減措置は投資用賃貸には適用されません。そこでRC造投資家が意識すべきは、土地評価額の1/2が課税標準になる特例です。固定資産税評価証明書で土地の評価が高いと感じたら、自治体に「地積規模の大きな宅地の特例」適用可否を確認しましょう。
建物にかかる消費税は、売主が課税事業者の場合のみ発生し、2025年9月現在の税率は10%です。住宅として貸す場合は家賃が非課税取引になるため、仕入税額控除が制限されます。よって法人名義で購入し、テナントフロアを一部設けるなど課税売上割合を上げる工夫が有効です。印紙税は契約金額1億円以下なら1万円から6万円で済むため、総額に対しては比較的小さな負担にとどまります。
保有期間の税金: 減価償却と固定資産税
重要なのは、RC造の長い保有フェーズで「減価償却と固定資産税のバランス」を取ることです。減価償却は取得価額を耐用年数で割り、定額法で毎年費用計上します。築20年の中古RC造を個人が購入した場合、残存耐用年数は(47年-経過年数)ではなく「法定耐用年数×20%」の簡便法、つまり47年×0.2=9年が使えます。9年間で加速度的に償却を取り、10年目以降は簿価1円で保有する形になるため、最初の9年は所得圧縮効果が大きくなります。
固定資産税と都市計画税は評価額×1.4%と0.3%が標準ですが、3年ごとの評価替えで減価補正が進むと税額も下がります。総務省の統計では、築30年を超えるRC造の評価額は新築時の35%前後まで落ちている例が一般的です。保有開始から10年程度で減価償却費は減る一方、固定資産税はゆるやかに軽減されるため、キャッシュフロー管理には「修繕計画と保険の見直し」をセットにして考える姿勢が必要です。また、法人名義なら退去時の原状回復費を損金に計上しやすく、実効税率約30%分の節税効果が見込めます。
売却・承継時の税金と節税ポイント
実は、RC造の出口戦略で最も差がつくのが譲渡所得税の扱いです。所有期間5年超なら長期譲渡となり、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%が課税されます。RC造は耐用年数が長いため、築古になっても金融機関評価が残りやすく、売却益が出やすい点が特徴です。ただし簿価を大幅に下げていると売却益が大きく計上されるため、事前に買換え特例を検討することが重要です。2025年度も譲渡所得の課税繰延べ制度(租税特別措置法第37条の5)は継続しており、取得後3年以内に事業用資産を買い替えれば課税を先送りできます。
相続を視野に入れる場合、RC造は「貸家建付地評価減」と「貸家評価減」の二重効果で相続税評価額を下げられます。国税庁の財産評価基本通達によると、貸家建付地は自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で評価し、RC造は高い入居率を保ちやすいため賃貸割合を高く設定しやすい点が有利です。生前に法人へ売却して現金化し、贈与年110万円非課税枠を活用しながら段階的に資産移転する戦略も選択肢となります。
2025年度制度を踏まえた資金計画の立て方
まず押さえておきたいのは、2025年度の税制改正で個人版の「青色申告特別控除65万円」が電子帳簿保存義務とセットになった点です。不動産所得を最大化するには、会計ソフトで電子帳簿を保存し、控除要件を満たすことが欠かせません。RC造は修繕費が高額になりやすいので、複式簿記で費用計上を漏れなく管理するだけで所得税が緩和されます。
さらに、2025年度も「中小企業投資促進税制」が継続され、法人がRC造の外壁改修に1000万円以上投資した場合、取得価額の7%税額控除または30%特別償却が選択可能です。個人投資家でも法人設立を検討するだけで、修繕時期を前倒ししてキャッシュフローを改善できる計算になります。
金融機関の融資姿勢にも制度的な追い風があります。住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資」では、2025年度もRC造に対し最長35年、金利1%台前半(機構債連動型)のメニューが提供されています。減価償却期間より長い返済期間を確保できるため、キャッシュフローに余裕が生まれやすいのです。結論として、制度を正しく活用し、長期の資金計画を立てれば、RC造投資は税金面で木造以上の優位性を発揮します。
まとめ
この記事ではRC造の基本構造から取得時・保有中・売却時の税金までを網羅し、2025年度の最新制度を踏まえた資金計画のポイントを示しました。長い耐用年数による安定した減価償却、買換え特例や相続評価減など出口戦略の多彩さ、さらには法人活用で広がる税額控除がRC造の魅力です。今日紹介した仕組みを活用し、数字に基づいた収支シミュレーションを行うことで、税負担を抑えながら堅実に資産を拡大できます。まずは物件選定と並行して、税理士や金融機関と早めに相談し、自分に合った節税プランを具体化してみてください。
参考文献・出典
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 財産評価基本通達 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 不動産市場動向レポート – https://www.mlit.go.jp
- 東京都主税局 固定資産税の仕組み – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp
- 住宅金融支援機構 賃貸住宅融資商品概要 – https://www.jhf.go.jp

