不動産投資に興味はあるものの、「1億円もの資金を投じて本当に回収できるのか」「利回りが低いと損をするのでは」と悩む方は多いはずです。特に初めての投資では、物件選びや融資の組み立てに不安がつきまといます。しかし、適切な利回りの把握とキャッシュフロー管理さえできれば、大きな資金でも着実に増やすことが可能です。本記事では、1億円を投資する際の考え方から、2025年9月時点の最新データを用いた利回り計算、制度活用までを体系的に解説します。読み終える頃には、「1億円規模でも怖くない」と感じられるはずです。
1億円という資金規模の考え方
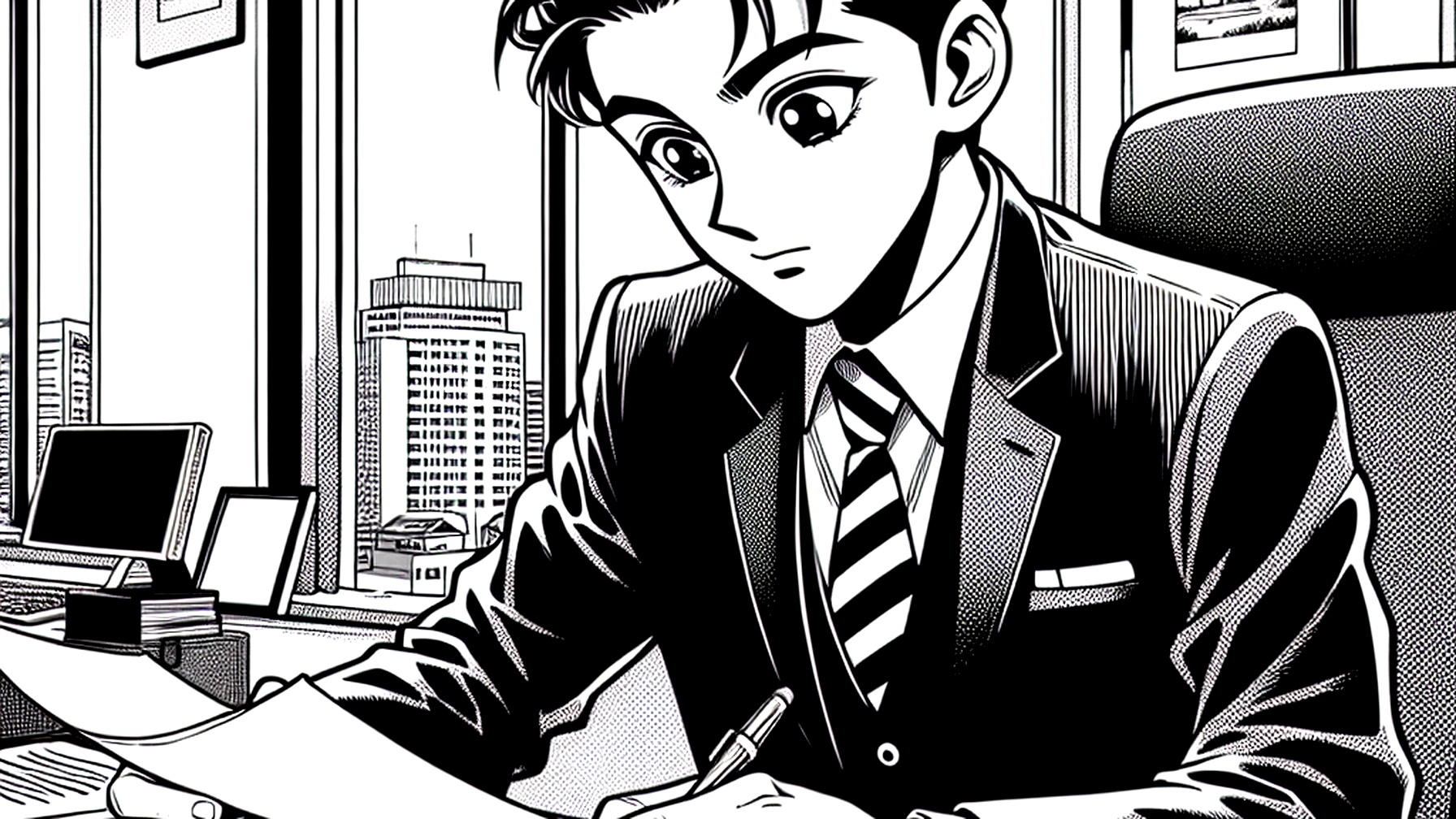
ポイントは、1億円を「一度に全て現金で支払う額」ではなく「自己資金と融資を組み合わせる投資総額」として捉えることです。自己資金を2~3割に抑え、金融機関から低金利融資を引き出せば、手元に余裕を残したまま大きな資産を築けます。
まず、自己資金3,000万円・融資7,000万円のケースを想定しましょう。現在の都市銀行の投資用ローン金利は年1.8~2.3%がボリュームゾーンです。仮に2.0%・30年元利均等返済で借入すると、年間返済額は約310万円です。ここで表面利回り4.5%の物件を1億円で取得すれば、年間賃料収入は450万円となり、返済後に約140万円のキャッシュフローが残ります。
さらに、減価償却費や各種経費を差し引くと、課税所得は抑えられます。つまり1億円という大きな数字でも、適切なレバレッジをかければ手残りを確保しつつ資産形成が可能です。一方で、空室や修繕を考慮した実質利回りを見誤ると赤字転落のリスクがあるため、次章で計算方法を詳しく確認していきます。
キャッシュフローと表面利回りの基本
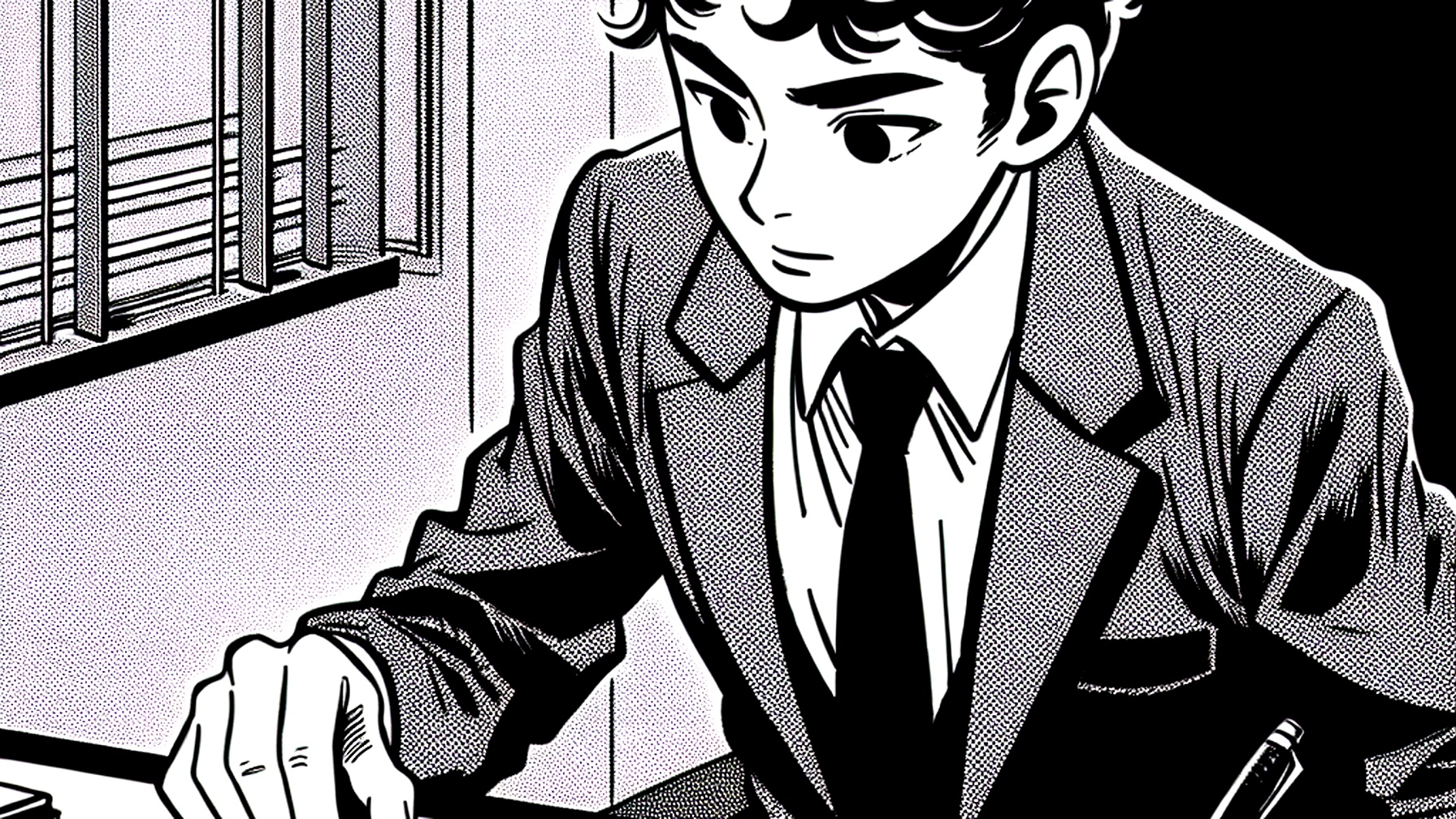
重要なのは、表面利回りと実質利回りの差を正しく理解することです。表面利回りは「年間家賃収入÷物件価格」で求められますが、経費や空室率を加味しないため過大に評価されがちです。
たとえば東京23区のワンルーム平均表面利回りは4.2%(日本不動産研究所、2025年9月)です。家賃年間420万円の物件を1億円で買う計算になりますが、固定資産税や管理費、修繕積立金で概ね収入の15%が消えるのが一般的です。さらに空室率5%を見込むと、実質利回りは約3.3%まで下がります。この数値がローン金利を上回って初めて、キャッシュフローがプラスになるわけです。
実は、家賃下落や大規模修繕を想定してシミュレーションすることが肝心です。私は通常、空室率を10%、経費率を18%に設定したうえで、金利を現在より1%高く見積もります。ここまで厳しく見ても手残りが出る物件こそ、1億円を託す価値があるといえます。
物件タイプ別リターンとリスクの比較
まず押さえておきたいのは、物件タイプによって求められる利回り水準が大きく異なる点です。都心の区分マンションは価格が高く利回りが低めですが、流動性が高く出口戦略を描きやすい特徴があります。
一方で、木造アパートは5.1%と比較的高い表面利回りが期待できます(同出典)。しかし、建物の老朽化や入居者属性のばらつきにより、将来的な修繕費が膨らむリスクも無視できません。郊外の一棟アパートでは、6%超の利回り提示も珍しくありませんが、人口減少による空室リスクが重くのしかかります。
つまり、1億円投資なら「都心区分を複数戸に分散」「駅近鉄骨造アパート一棟買い」など、リスク・リターンのバランスを意識する必要があります。私の経験では、東京都心に4,000万円の区分を2戸、残りの資金で中規模アパートを組み合わせるハイブリッド戦略が、安定収益と資産価値維持の両立に有効でした。資産の半分を流動性重視、半分をキャッシュフロー重視に振り分けるイメージです。
融資戦略と税務の注意点
ポイントは、金融機関ごとに審査基準と金利が異なるため、事前に複数行を当たって比較することです。都市銀行は金利が低い代わりに自己資金を多めに求める一方、ノンバンクは敷居が低くても金利が高い傾向があります。
また、2025年度の税制では、減価償却期間が短い築古木造を選ぶと、年間の損益通算で大きな節税効果が期待できます。ただし、短期保有で売却すると譲渡所得税が高税率になるため、少なくとも5年以上の長期保有を前提に計画を立てると安心です。
さらに、インボイス制度への対応も忘れてはいけません。賃貸住宅は原則非課税ですが、テナントビルのように課税売上が発生する場合は、課税事業者選択の可否で消費税還付額が変わります。税理士と連携し、キャッシュフローだけでなく所得税・消費税まで含めた総合収益を把握する姿勢が欠かせません。
2025年度の支援制度と市場展望
まず2025年度に実際に利用できる制度として、住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資(サステナブル仕様)」が挙げられます。省エネ基準を満たす木造アパートを建築・購入する場合、金利が0.3%優遇され、借入上限は1戸あたり7,000万円です。期限は2026年3月実行分までとされているため、計画を急ぐ価値があります。
一方で、中小企業庁の「事業用不動産省エネ補助金(2025年度)」では、断熱改修や高効率設備導入費の1/3を上限1,500万円まで補助します。賃貸マンションの共用部LED化などに適用でき、運営コスト削減と空室対策の両面で効果的です。
市場全体を見ると、日本不動産研究所の予測では、2025年以降の東京23区人口は微増傾向が続く一方、郊外は緩やかな減少が進むとされています。つまり、都心物件は利回りが多少低くても資産価値が守られる可能性が高く、郊外物件は賃料下落を織り込んだ割安購入が鍵になります。制度を活用して物件性能を高めつつ、立地選定でリスクを分散することが、1億円投資の成否を分けるでしょう。
まとめ
ここまで、不動産投資 利回り 1億円というテーマを、資金計画・利回り計算・物件選び・融資と税務・制度活用の順に見てきました。要するに、表面利回りだけに惑わされず、実質利回りとキャッシュフローを徹底的に検証する姿勢が成功の鍵です。さらに、低金利融資と2025年度の優遇制度を組み合わせることで、1億円という大きな資金でもリスクを抑えて運用できます。最後に、必ず複数シナリオで収支シミュレーションを行い、保守的な条件でも黒字を確保できる物件に絞り込んでください。行動を起こせば、堅実な資産形成への道は確実に開けます。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 住宅金融支援機構 – https://www.jhf.go.jp
- 中小企業庁 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 国土交通省「土地総合情報システム」 – https://www.land.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp

