コロナ禍が落ち着いた今、「投資で資産を守りたいが株は値動きが激しくて不安」と感じる人が増えています。マンション投資はミドルリスク・ミドルリターンといわれるものの、空室や金利上昇など心配は尽きません。そこで本記事では、アフターコロナの市場変化を踏まえながら、表面利回りを軸に物件を選び、リスクを抑えて収益を伸ばす方法を解説します。初心者でも理解できるよう基本から順に説明するので、読み終えたころには自分に合った投資イメージが明確になるはずです。
アフターコロナで変わった需要の潮流
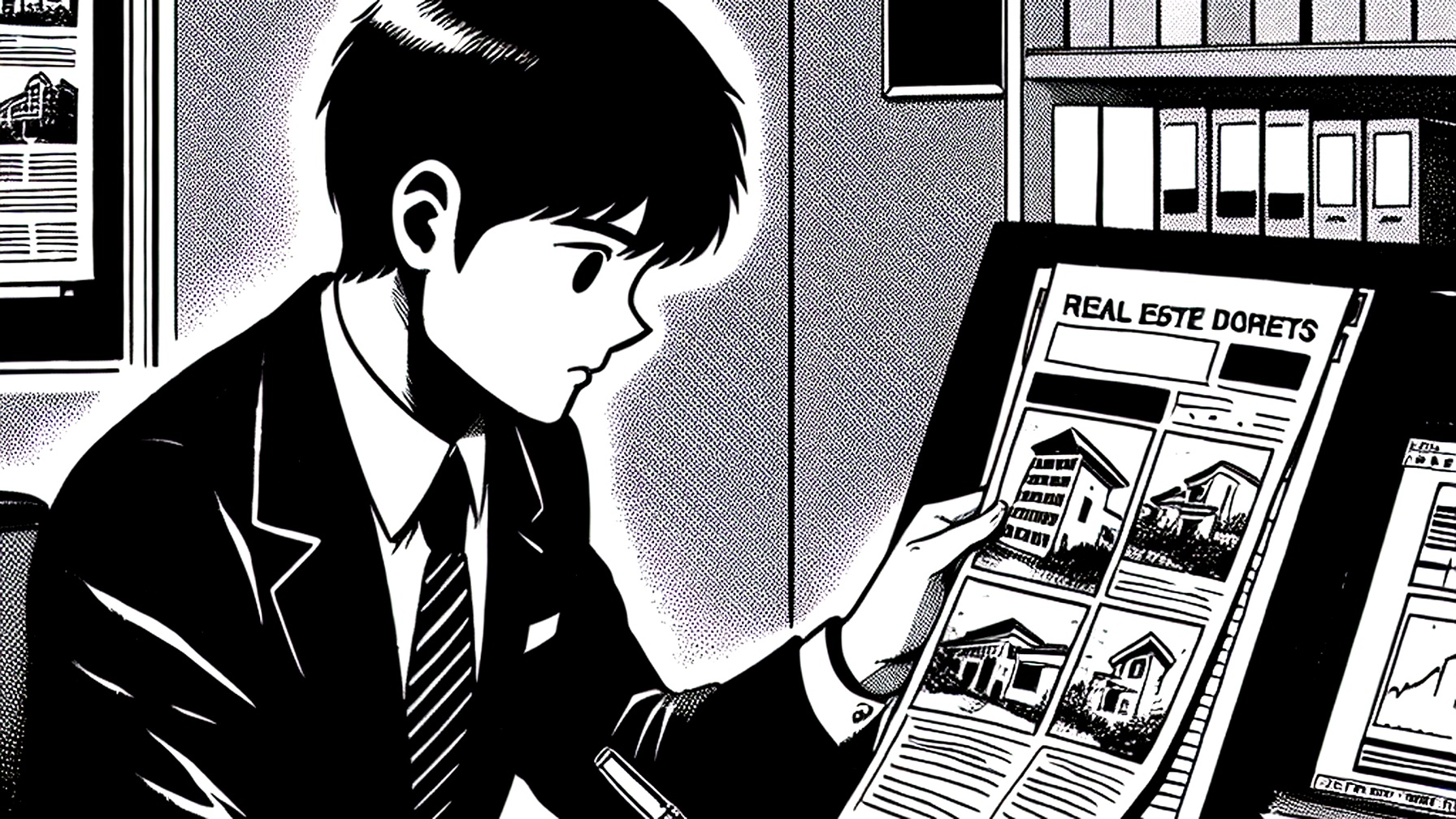
まず押さえておきたいのは、コロナ収束後に賃貸ニーズがどう動いたかという点です。テレワークが定着し、郊外志向が強まったと言われますが、総務省の住民基本台帳人口移動報告では2024年から東京23区の転入超過が再び拡大しています。つまり都心回帰の動きが戻りつつあり、単身者向けワンルームに安定した需要が続く状況です。
一方で在宅勤務を前提に「もう一部屋」を求めるファミリー層も増えています。国土交通省の住宅市場動向調査によると、2025年の賃貸住宅でリモートスペース付き物件を選ぶ割合は調査開始以来最高です。こうしたニーズの多様化は、物件タイプごとに異なる表面利回りの分析をより重要にしています。
さらに海外からのインバウンド需要も戻り、短期賃貸やマンスリーマンションの稼働率が上昇傾向にあります。観光庁のデータでは2025年上期の訪日客数がコロナ前比95%まで回復しました。短期貸しは運営の手間がかかる半面、高い利回りが期待できるため、戦略の選択肢として検討する価値があります。
表面利回りの基礎と最新水準を押さえる
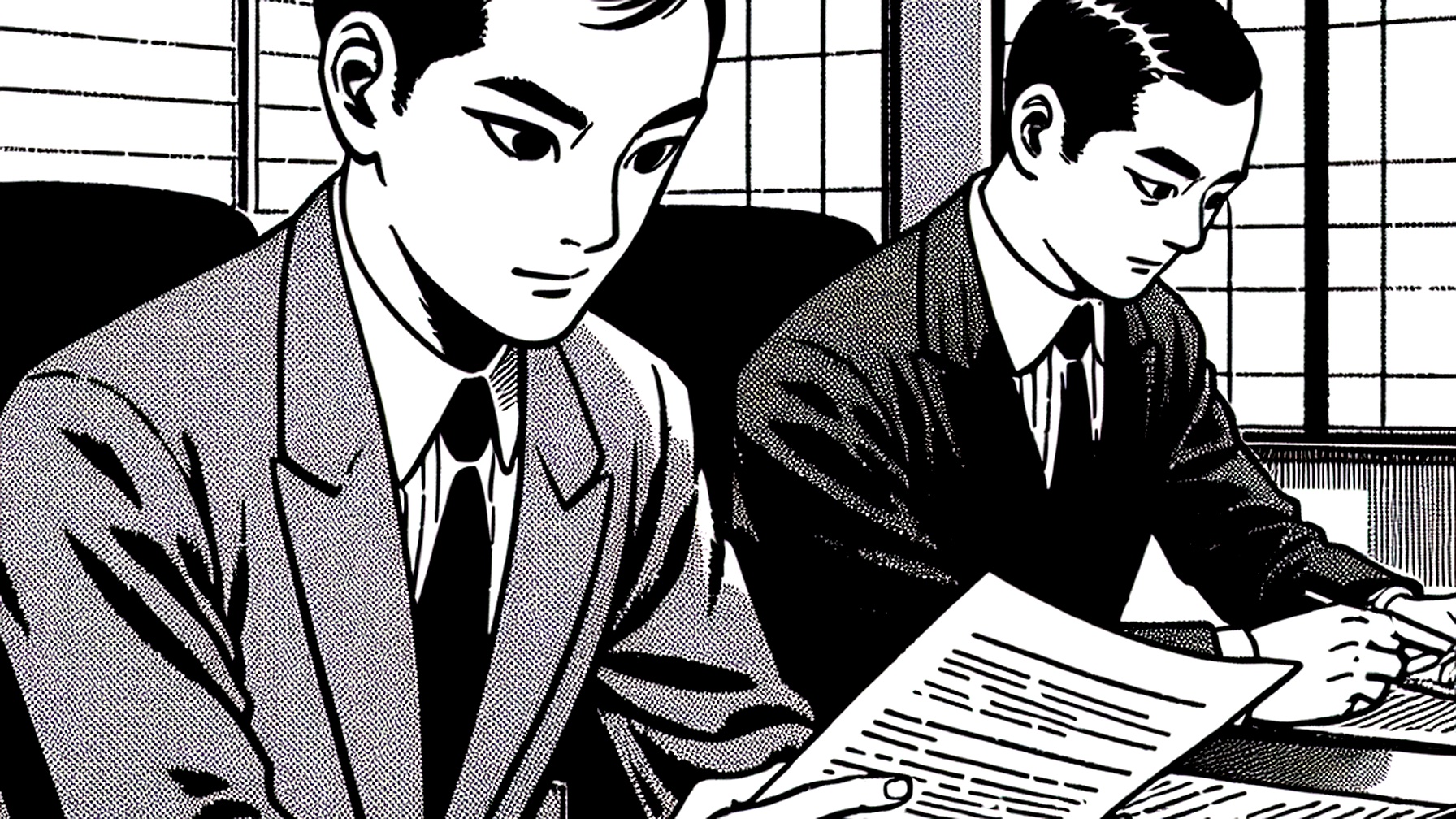
ポイントは、表面利回りが「物件価格に対して年間家賃が何%か」を示す指標であり、融資返済や諸経費を差し引く前の数字だということです。実際の手取りを示す実質利回りとは違うので、まず両者の違いを認識しましょう。
日本不動産研究所の2025年9月データによれば、東京23区の平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリーマンション3.8%、木造アパート5.1%です。新築マンションの平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しており、物件価格が伸びる分、利回りはやや低下傾向にあります。つまり利回りを高めるには、家賃設定を工夫するか、割安な中古物件を狙う必要があるわけです。
しかし数字だけを追うと落とし穴があります。利回りが高くても、入居付けが難しければ空室期間が延び、実質利回りは簡単に下がります。国交省の賃貸住宅市場レポートでは、空室期間が1カ月延びると年間実質利回りが約0.4ポイント低下するという試算があります。利回りの数字を見るときは、立地と設備が需要に合っているか必ず確認してください。
立地戦略と物件タイプ別の収益性
重要なのは、表面利回りを求めつつ空室リスクを抑えるバランスです。都心ワンルームは取得価格が高いぶん利回りが低めですが、空室期間が短く家賃下落も緩やかです。一方で郊外ファミリーマンションは広さと家賃のバランスが良く共働き世帯に人気ですが、人口減少エリアでは長期的な賃料維持が課題になります。
また木造アパートは利回りが高く、自己資金が少なくても始めやすい点が魅力です。ただし築年数が進むと修繕費がかさみ、金融機関の融資期間も短く設定されがちです。物件タイプごとのメリットとデメリットを比較し、自分の資金計画と投資期間に合致するか見極める必要があります。
実は交通利便性だけでなく「生活利便施設」が近いかどうかが入居率に直結します。東京都都市整備局の調査では、徒歩10分圏内にスーパーとドラッグストアがある物件は、ない物件に比べ平均入居期間が1.3年長いと報告されています。つまり立地選定では、駅距離と合わせて日常利便性を評価することで長期安定収入につながりやすくなるのです。
リスク管理とキャッシュフローの安定化
まず押さえておきたいのは、キャッシュフロー計算を保守的に行うことです。金利は2025年現在、主要都市銀行の投資用ローン変動金利で2.3%前後ですが、長期的には上昇余地があります。金融庁のストレステストシナリオにならい、金利+1%でも月々の返済に耐えられるか試算しておくと安心です。
さらに修繕積立を毎月キャッシュフローから差し引き、10~15年後の大規模修繕に備える姿勢が欠かせません。日本賃貸住宅管理協会の統計では、築20年時点の共用部改修費は1戸当たり平均85万円とされています。あらかじめ月1万円程度を積み立てるだけでも、突発的な資金ショートを防げます。
一方で火災保険は補償内容を定期的に見直すとコスト削減につながります。2024年以降、築古物件の保険料が引き上げられていますが、特約を整理すれば年間3万円以上節約できるケースもあります。キャッシュフローの安定化は、こうした細かなコスト管理の積み重ねで実現することを忘れないでください。
2025年度に使える支援制度と税制優遇
ポイントは、制度を活用して初期費用と毎年の税負担を抑えることです。まず2025年度も住宅ローン控除の投資用物件版は適用されませんが、所得税の損益通算が可能な減価償却費は強力な節税手段です。特に中古木造アパートは法定耐用年数が短く、早期に大きな経費を計上できるため節税効果が高まります。
次に不動産取得税の軽減措置は、取得後60日以内に申告すれば課税標準を最大1,200万円控除できます。登録免許税も、2025年3月31日までに取得した既存住宅で一定の耐震基準適合証明を受けた場合、税率が0.3%へ下がります。期限があるため、取得スケジュールを逆算して進めましょう。
また国交省の「賃貸住宅省エネ改修補助金」は2025年度も継続予定で、断熱改修費の三分の一(上限120万円)が補助されます。省エネ性能を高めることで家賃アップと空室抑制の両方が期待できるため、築古物件を購入する際は活用を検討すると良いでしょう。
まとめ
アフターコロナで変化した賃貸ニーズに合わせ、表面利回りをどう高めるかがマンション投資成功の鍵です。利回りの数字だけでなく、立地や物件タイプごとの入居需要、将来の修繕費や金利上昇まで織り込んで計画すれば、安定したキャッシュフローが見込めます。さらに2025年度の軽減税率や補助金を活用すれば初期費用も抑えられ、実質利回りを底上げできます。まずは利回り4%超を目安にシミュレーションを作成し、資金計画とリスク対策を万全にして一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 住生活実態調査 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 原状回復・修繕費用調査 – https://www.jpm.jp

