REITに興味はあるけれど、税金が複雑そうで一歩を踏み出せない。そんな悩みを抱える初心者は少なくありません。税率や口座の違いを理解しないまま投資を始めると、想定外のコストが利益を圧迫します。一方で、制度を正しく活用すれば手取り収益を大きく伸ばすことが可能です。本記事では、REITの分配金と売買益にかかる税金の仕組みから、2025年度NISAを活用した節税戦略まで、最新情報をやさしく解説します。
REITの仕組みと利益の流れ
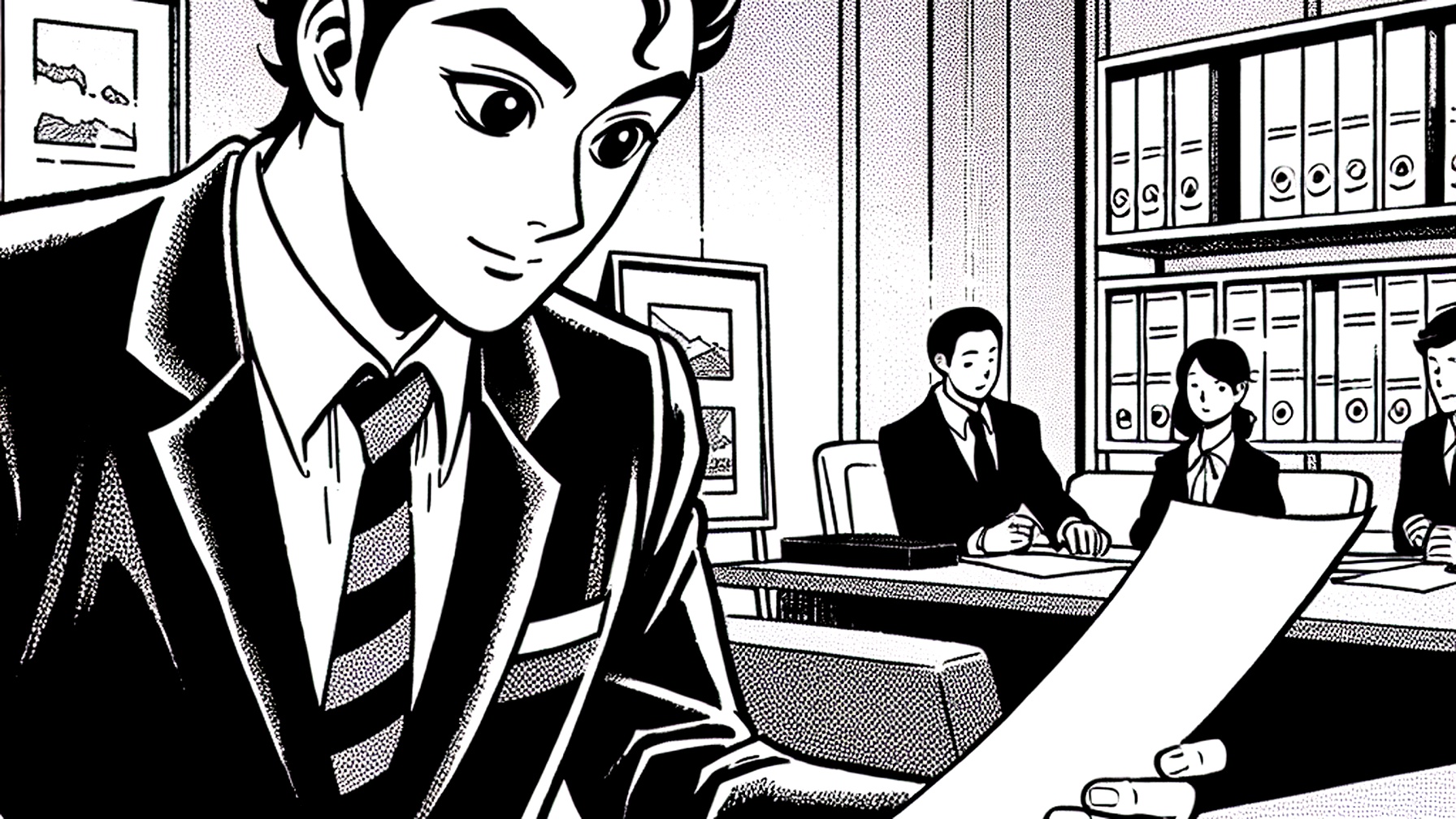
重要なのは、REITの利益が投資家に届くまでのルートを把握することです。REITとは不動産投資信託のことで、多数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設を購入・運用します。運用で得た賃料収入や売却益の大半は、分配金として投資家に還元されます。
まず、REITは「投資法人」という法人格を持ちます。会社法上の株式会社とは異なり、収益の90%以上を分配すれば、法人税が実質的に免除されるという特例があります。そのため、利益はできるだけ分配金として吐き出され、投資家側で課税される仕組みになっています。
また、投資家の利益は二種類に分かれます。一つは定期的に受け取る分配金、もう一つは証券市場でREIT口数を売却したときに発生する売買益です。それぞれ課税のタイミングと税率が異なるため、区別して考えることが大切です。
分配金にかかる税金の基本
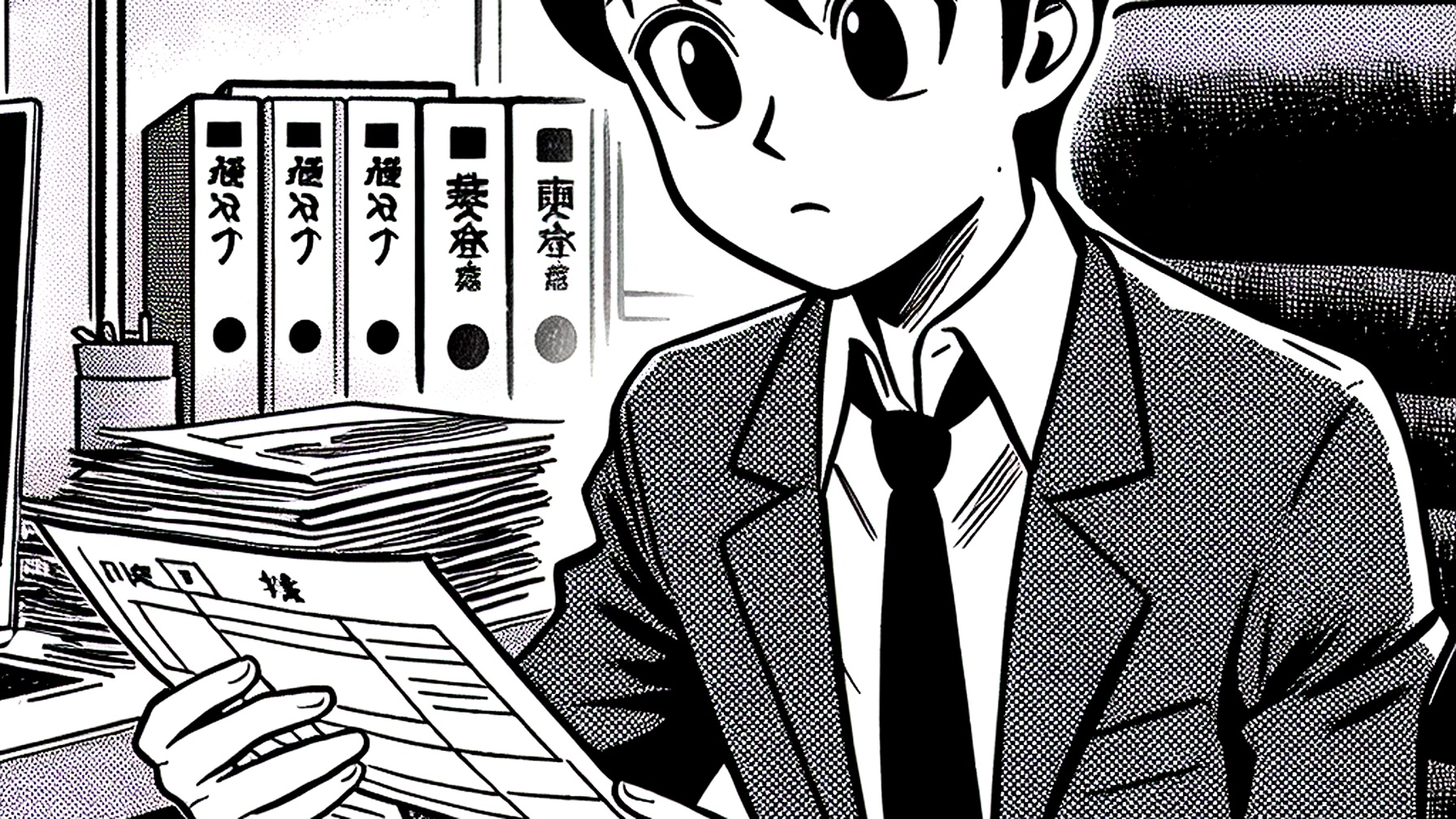
まず押さえておきたいのは、分配金は「配当所得」として課税される点です。2025年9月時点の税率は、所得税15%と住民税5%に復興特別所得税0.315%を加えた20.315%が原則となります。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、証券会社が自動で税額を差し引くため、確定申告の手間はかかりません。
一方で、給与所得や他の配当との損益通算を狙う場合、あえて「源泉徴収なし」の特定口座や一般口座を選び、確定申告で配当控除を利用する選択肢もあります。ただし、REIT分配金は総合課税扱いになり、合計所得が増えると住民税や健康保険料が上がる可能性があります。手取りを増やすつもりが負担増にならないよう、シミュレーションが欠かせません。
さらに、未成年の子ども名義でジュニアNISA口座を開き、非課税で分配金を受け取る方法は2023年で終了しました。そのため、2025年度に利用できる非課税制度は、後述するNISA(少額投資非課税制度)のみとなります。
売買益に対する課税と損益通算
ポイントは、REITを売却したときの利益が「譲渡所得」として課税される点です。こちらも分配金と同じく20.315%が源泉徴収され、特定口座なら手続きは完結します。損失が出た場合は、他の株式やETFの譲渡益と自動で通算され、余った損失は翌年以降3年間繰り越せます。
通算効果を最大化するには、分配金課税と譲渡益課税が同じ口座区分で管理されていることが前提です。複数の証券会社に分散していると、損益が相殺できずに税金を払い過ぎるケースがあるため注意が必要です。
また、譲渡損失を活用する「タックスロス・ハーベスティング」という手法もあります。年末時点で含み損があるREITを売却し、その年の譲渡益と相殺することで税負担を軽くする方法です。ただし、売却直後に同じ銘柄を買い直すと、実質的に損失を認めない「同一銘柄の30日ルール」の対象になるリスクがあるため、一定期間は別の銘柄に乗り換えるなど工夫が求められます。
2025年度NISAを活用した税負担の軽減策
実は、2024年に恒久化された新NISAが2025年度も活用可能で、REIT投資の非課税枠として強力です。年間360万円まで投資できる成長投資枠の中で、上場REITは投資対象に含まれています。NISA口座で購入したREITの分配金と売買益は、最長無期限で非課税となるため、20.315%の税率を丸ごと回避できます。
非課税メリットを十分に受けるには、分配利回りの高い銘柄を選び、長期保有でトータルリターンを伸ばす戦略が効果的です。一方で、NISA口座では損失が出ても他口座と損益通算できません。リスク管理としては、J-REIT指数連動のETFを組み合わせるなど、銘柄分散を徹底したいところです。
また、NISA枠の残高は翌年に繰り越せないため、年度内に計画的に投資する必要があります。分配金がNISA口座に入金された時点で自動的に非課税となるため、再投資で複利効果を高めることも可能です。
法人で保有する場合の税務上の注意点
まず、法人名義でREITを購入すると、分配金は「受取配当等」として課税されます。しかし、J-REITは株式と異なり、受取配当益金不算入制度の対象外です。そのため、利益の全額が法人所得に加算され、うまく節税できない点に注意が必要です。
一方で、売買益や評価損は会計上の損益に直結します。期末に含み損がある場合、金融商品会計基準に基づき時価評価損を計上すれば、法人税の課税所得を圧縮できます。ただし、評価損を計上するかどうかは税務署との見解が分かれやすいため、顧問税理士と事前に打ち合わせることが不可欠です。
さらに、投資法人債を組み合わせることで安定的な利息収入を確保し、キャッシュフローを平準化する方法もあります。しかし利息は源泉分離課税ではなく、総合課税で29.74%(法人税等の実効税率ベース)が発生するため、資金繰りを含めた総合設計が求められます。
まとめ
ここまで、REITの分配金と売買益にかかる税金の仕組み、そして2025年度NISAをはじめとする節税策を解説しました。税率は一律20.315%ですが、口座の選択や損益通算の活用で実効税率は大きく変わります。手取りを最大化するためには、制度ごとのメリットとデメリットを正しく理解し、分散投資と長期保有を基本戦略に据えることがポイントです。最後に、税制は改正が続く分野です。最新情報を常に確認し、必要に応じて専門家に相談しながら、REIT投資を賢く育てていきましょう。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁「NISA特設ページ」 – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/
- 東京証券取引所「J-REIT市場概況」 – https://www.jpx.co.jp/
- 一般社団法人投資信託協会 – https://www.toushin.or.jp
- 総務省統計局「家計調査年報」 – https://www.stat.go.jp
- 財務省「法人税基本通達」 – https://www.mof.go.jp

