不動産投資を考え始めると、「中古マンションはいつ買うべきか」という悩みに必ず直面します。価格は上がり続けているように見える一方で、金利や人口動向など不安材料も多く、タイミングを誤れば損をするのではと心配になるでしょう。本記事では、初心者が知っておくべき市場の見方、買い時を判断する具体的な指標、資金計画の立て方まで幅広く解説します。読後には「いつ マンション投資 中古」で迷わなくなるよう、2025年9月時点の最新データと実務経験を交えながらお伝えします。
中古マンション投資を始める前に押さえたい市場動向

重要なのは、東京都心と地方都市で需要構造が大きく異なる点を理解することです。2025年の不動産経済研究所によると、東京23区の新築平均価格は7,580万円で前年より3.2%上昇しました。それに対し中古マンションの価格上昇率は1.8%にとどまり、築20年以上の物件は横ばいが目立ちます。この差は、投資家にとって利回り改善のチャンスを示しています。
まず、国内人口は2025年時点で1億2,300万人を割り込みました。しかし23区の単身世帯は増加傾向が続いており、利便性の高いエリアでは需要が底堅いといえます。つまり都心近くの駅徒歩10分圏で築25〜30年の物件を選べば、購入価格を抑えつつ賃料を確保しやすい状況です。
一方で、地方中核都市は新築供給が限られるため築浅中古の競争が激しく、そのぶん価格が下がりにくい傾向があります。そのため利回りを優先するなら、築年数を妥協しても人口維持が見込める駅近エリアに絞ると効果的です。また、インバウンド需要が拡大している大阪市や福岡市では短期賃貸の選択肢も増え、出口戦略が多様化しています。
買い時を見極める3つのサイン
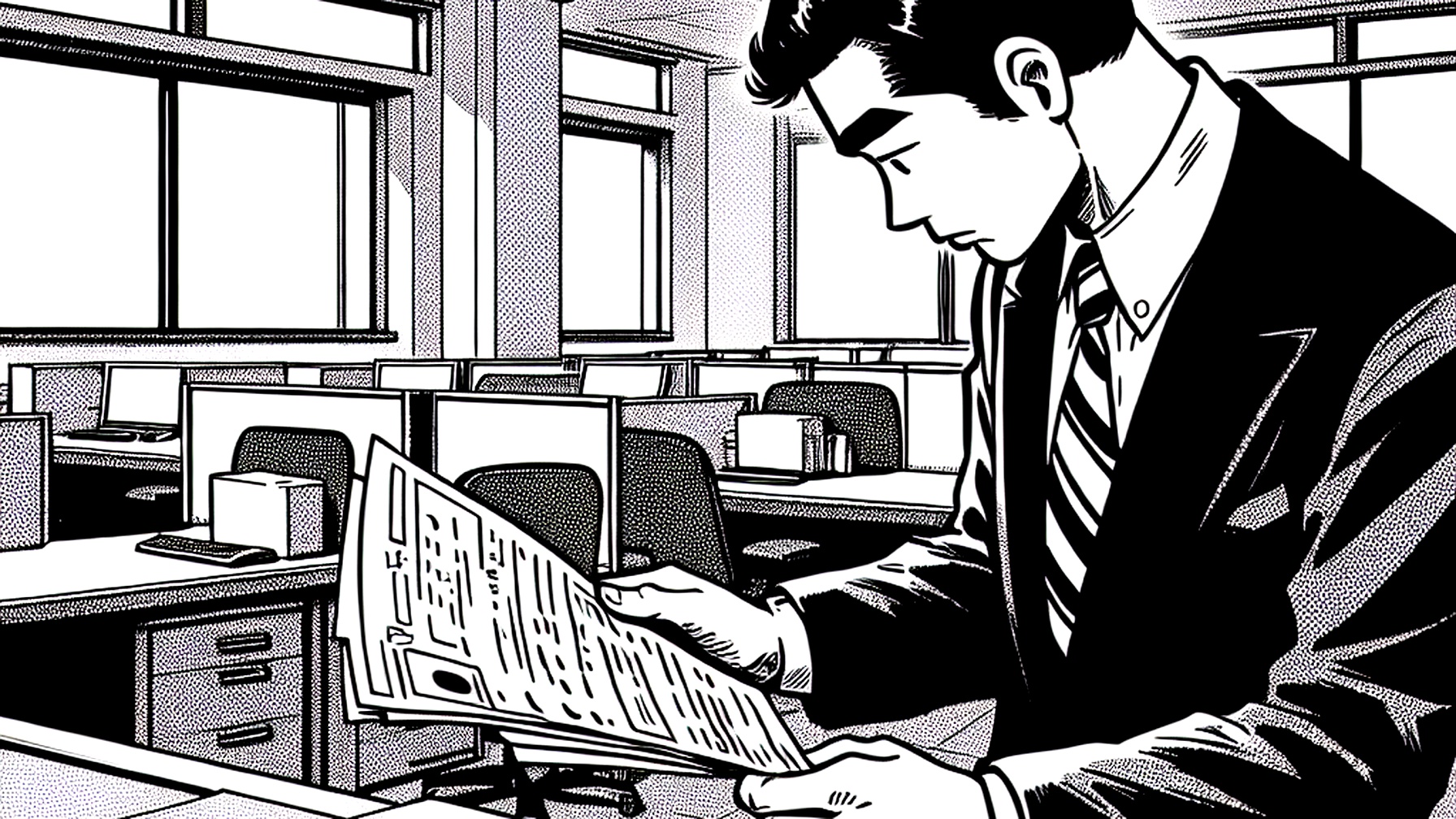
ポイントは、金利動向・在庫数・賃料指数の三つを組み合わせて判断することです。まず長期金利は2025年7月に1.0%台へ上昇し、固定金利型ローンの店頭金利も0.3%ほど引き上げられました。今後さらに上がる懸念があるため、低金利時代の終盤にあると考えた方が良いでしょう。
次に、指定流通機構(レインズ)のデータでは、2025年8月の中古マンション在庫は前年同月比で8%増加しました。これは売主が高値を期待して売り出す一方、買主が様子見をしている状態を示しています。このようなときは価格交渉が成立しやすく、実勢価格が下がる「押し目」を作りやすいのです。
さらに、不動産情報サービス各社が公表する賃料指数に注目すると、東京23区は前年より1.5%上昇、神奈川県は0.4%上昇にとどまりました。賃料の伸びが鈍化している地域は利回りの改善余地が小さいため、在庫増と賃料横ばいが重なるタイミングでの購入が合理的です。
以上を踏まえ、金利が上昇トレンドに入る前、かつ在庫が積み上がっている局面が「中古マンション投資のはじめ時」といえます。現状はその条件が重なりつつあるため、資金計画を固めて素早く動ける準備が必要です。
ファイナンスの基礎と2025年度の借入環境
実は、借入条件は物件選びと同じくらい投資成果を左右します。2025年度は金融機関の審査が一段と厳格化され、自己資金比率20%を求めるケースが増えました。返済負担率は年収に対して30%以内が目安となり、個人の信用情報がより重視されています。
まず押さえておきたいのは、固定金利と変動金利の選択です。日本銀行の政策修正により変動型も将来的な上昇リスクが高まっています。固定型で年1.6%以内、変動型で0.7%以内なら総返済額の差は限定的ですが、金利上昇局面では固定型の安心感が勝ります。
また、2025年度の「事業用不動産ローン特別保証制度」は継続しており、対象は賃貸住宅を含む事業性物件です。保証料は残高の1.0%程度で、金融機関の金利に上乗せされますが、自己資金を15%まで下げられるメリットがあります。期限は2026年3月申込分までなので、使うなら早めの検討が必要です。
最後に、減価償却費を活用した節税効果も資金繰りを安定させます。鉄筋コンクリート造の法定耐用年数は47年ですが、中古取得後は残存耐用年数を用いて加速償却が可能です。築25年なら残存22年、定額法で年間約4.5%の減価償却費を計上でき、手取りキャッシュフローを押し上げる計算になります。
購入後の運用戦略とリスク管理
まず押さえておきたいのは、購入直後から空室リスクに備える体制を整えることです。築年数が経過したマンションではリフォーム計画が収益に直結します。入居者ニーズに合わせ、水回りの更新や宅配ボックス設置など部分的な改修に留めても、賃料を3〜5%上げられるケースが多いです。
一方で、家賃下落リスクは緩やかに進行します。国土交通省の賃貸住宅市場調査では、築30年を超えると平均賃料が築10年未満の約75%になります。そこで、築古でも管理組合が修繕積立金を十分に確保している物件を選べば、外観維持により賃料下落を抑制できます。
運営コストの中でも、管理委託費と修繕費は変動幅が大きい項目です。管理委託費は賃料の5%以内、修繕費は年間家賃収入の10%を目安に予算化し、実績との差を四半期ごとに確認すると資金不足を防げます。また、災害リスクに対応するため、2025年新設の「地震保険特約拡充プラン」を活用すれば、免責金額を半減させつつ保険料を約15%抑えられます。
出口戦略としては、保有5年目でのリファイナンスや、10年目以降に価格が横ばいになる前に売却を検討する方法があります。資産価値が維持されているかを定期的に査定し、含み益が出ているうちに売却することで、トータルリターンを最大化できるでしょう。
税制優遇・補助制度を活用するコツ
ポイントは、確実に使える制度のみを押さえ、期限内に手続きを終えることです。2025年度も「不動産取得税の軽減措置」は継続しており、床面積50〜240㎡の居住用区分マンションなら税率が3%から1.5%へ半減します。投資用でも賃借人の居住用であれば適用可能なので忘れず申告しましょう。
また、中古取得後の大規模修繕に対しては、一部自治体で耐震改修補助金が設定されています。東京都の例では、耐震診断費用の3分の2、上限50万円まで支給される制度が2026年3月まで延長されました。補助金を活用すると表面利回りが0.3〜0.5ポイント向上するケースもあります。
さらに、2025年改正の消費税インボイス制度により、課税売上高1,000万円以下の個人でも課税事業者を選択すると仕入税額控除が可能になります。賃貸住宅の家賃は非課税ですが、リフォーム費などの課税仕入れが多い場合は還付額が増える可能性があるため、税理士と相談して適用を検討してください。
ただし、制度は年度ごとに内容が変わるため、必ず公式発表を確認し、申請書類や締切を把握することが失敗を避けるポイントです。
まとめ
ここまで、中古マンション投資の買い時を判断するための市場分析、金利と資金計画、購入後の運営、そして2025年度に実際に利用できる制度までを解説しました。金利上昇前で在庫が増えている現在は、交渉余地が生まれやすいタイミングです。一方で、物件選びと資金計画を甘く見ると収益が圧迫されるため、データを基に保守的なシミュレーションを行いましょう。最後に、制度や補助金は期限があるため、早めの情報収集と手続きが成功への近道です。ぜひ本記事を参考に、納得できる一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「不動産価格指数」 – https://www.mlit.go.jp
- 一般社団法人レインズ総合研究所 – https://www.reins.or.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合結果」 – https://www.boj.or.jp
- 東京都都市整備局「耐震改修促進事業」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

