マンション投資を検討し始めると、「新築が安心か、それとも中古で利回りを狙うべきか」という悩みに必ず直面します。物件価格や空室リスク、金融機関の融資条件まで判断材料は多岐にわたり、情報が散在しているため迷いやすい点です。本記事では、2025年9月時点の市場データと最新制度を踏まえつつ、初心者でも理解できるように両者を徹底比較します。読むことで、ご自身の投資目的に合った物件タイプを選ぶ視点と、リスクを抑える具体的な行動ステップが得られるはずです。
マンション投資の基本構造を押さえる
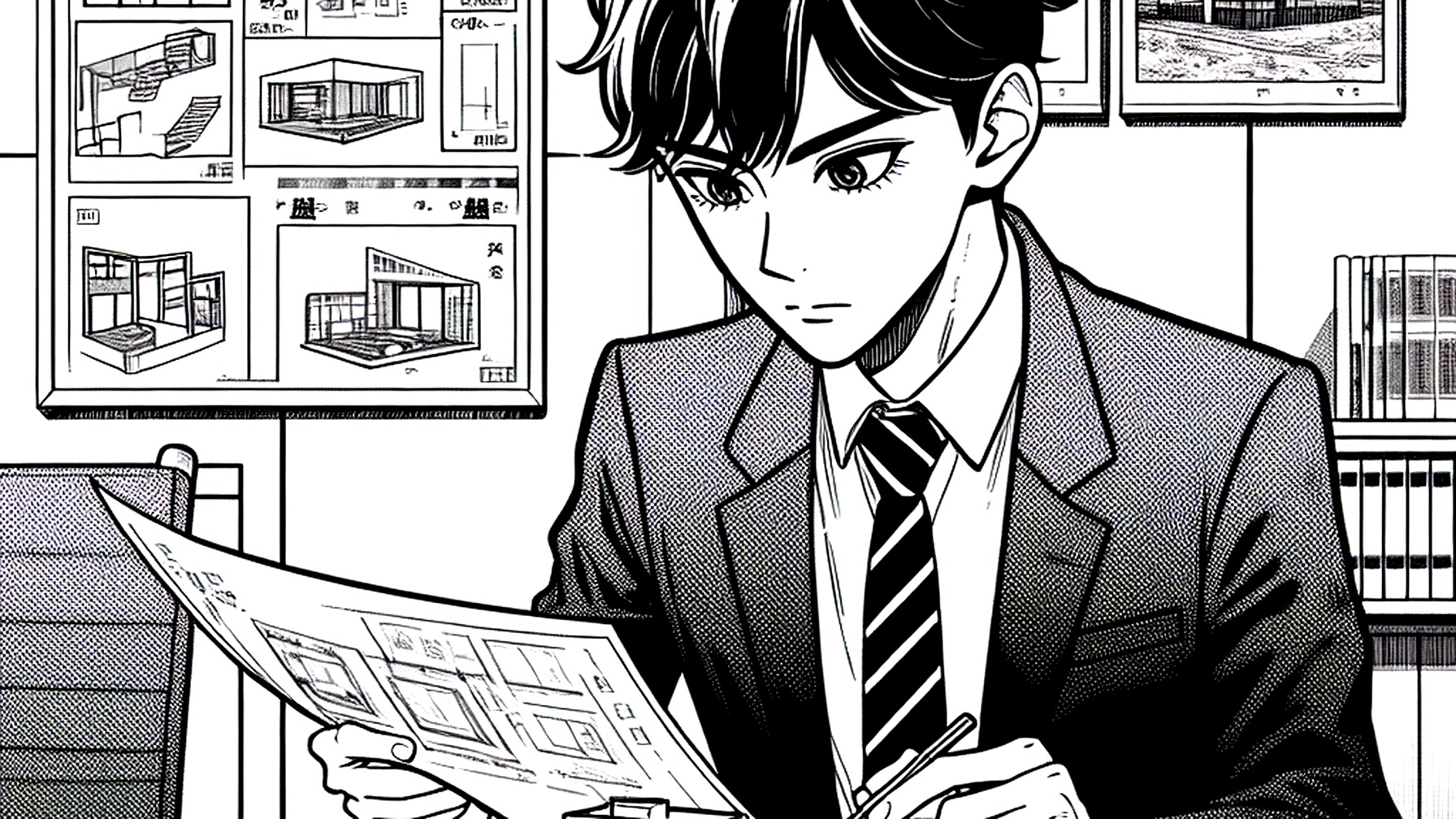
ポイントは、収益を生む仕組みと費用構造を先に整理することです。家賃収入から諸経費とローン返済を差し引いた残りがキャッシュフローであり、物件タイプによって変動幅が大きくなります。
まず家賃収入は立地と築年数で決まりやすい一方、経費には管理費や修繕積立金、固定資産税が含まれます。新築は維持費が低い代わりにローン元本が大きくなり、中古は逆に維持費が高くなる傾向です。また、所得税対策として減価償却費を計上できる点は中古が有利と言われますが、耐用年数の残り次第で節税効果が異なります。
さらに融資条件にも違いがあります。金融庁のモニタリング資料では築25年超の区分マンションは融資期間が15年程度に短縮されやすいと言及されています。期間が短いと毎月の返済額が増えるため、利回りだけでなく返済比率にも目を向ける必要があります。
こうした基本構造を把握すると、次章以降で比較する新築と中古の特徴がより具体的に見えてくるでしょう。
新築マンション投資の魅力と注意点
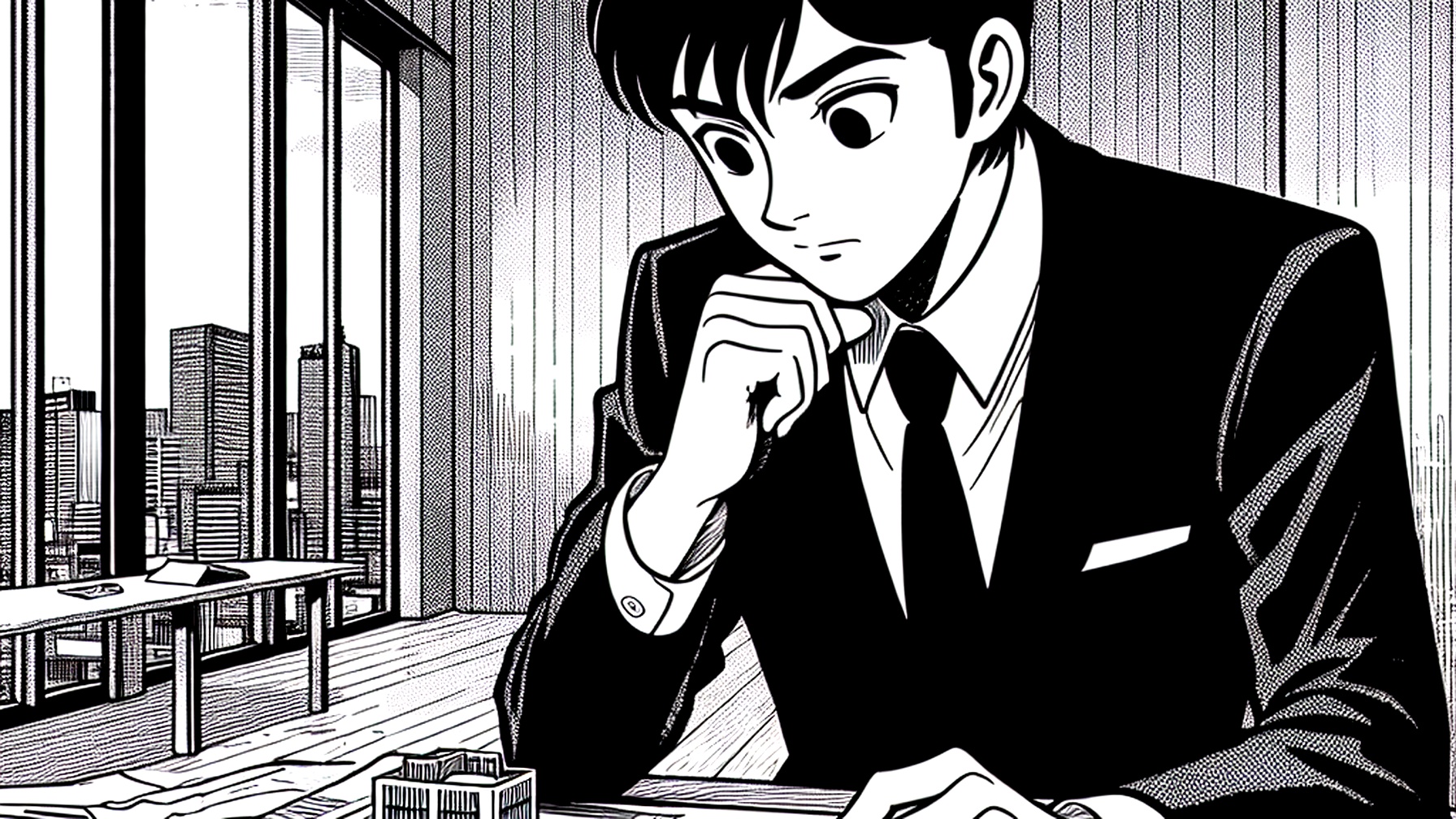
重要なのは、初期費用が高くても安定性を買える点です。東京23区の新築平均価格は7,580万円(不動産経済研究所、2025年9月)と上昇基調が続いています。価格上昇は売却益の期待値を押し上げる一方、想定家賃との差が開けば利回りは下がるため、収支計算を丁寧に行わなければなりません。
新築の大きなメリットは設備トラブルが起こりにくく、入居者募集で「築浅」の優位性を打ち出せることです。入居率データでも築0〜5年の平均空室率は3%台と、中古の約半分にとどまります。結果として家賃下落スピードも緩やかで、キャッシュフローが読みやすい点が安心材料となります。
しかし保証や管理が手厚い反面、管理費と修繕積立金は年を追うごとに増額される設計が一般的です。長期修繕計画を確認し、15年後の支出が想定家賃に対して何%になるかをシミュレーションしましょう。また、新築プレミアムと呼ばれる初期価格上乗せ分は、築10年を過ぎた頃に剥落しやすいので、短期売却の出口戦略は組みにくい点にも注意が必要です。
最後に2025年度の金融環境を確認します。メガバンクの投資用変動金利は年2.3〜2.8%が主流で、大手保証会社を利用すれば自己資金1割でも融資が通りやすい状況です。ただし、日銀のマイナス金利解除観測で金利上昇リスクが意識され始めているため、固定金利型を組み合わせる方法も検討する価値があります。
中古マンション投資のメリットとリスク
まず押さえておきたいのは、購入価格が抑えられることで利回りが高くなる点です。都心の築20年前後でも、同エリア新築価格の6〜7割で取得できるケースが珍しくありません。その分、表面利回りは新築より1.5〜2ポイント上乗せでき、キャッシュフロー改善に寄与します。
一方でリノベーション費用や設備更新費がかかる点がデメリットです。国土交通省の「住宅リフォーム調査報告」によると、給排水管の更新費用は平均120万円、フルリノベーションでは400万円を超える例もあります。購入時点での売主資料だけでなく、管理組合の修繕履歴を確認し、隠れた追加コストを見逃さないことが重要になります。
さらに法定耐用年数との関係で、税務上の減価償却が短期間に集中する場合があります。例えば鉄筋コンクリート造の残存耐用年数が10年なら、毎年の減価償却費が大きく、初期数年間は所得税の圧縮効果が高まります。ただし、償却終了後の税負担増まで見据えた長期計画が欠かせません。
融資面では金融機関による築年数制限がネックです。都市銀行は築25年以内を目安にする傾向がありますが、地方銀行やノンバンクは柔軟に対応する例もあります。複数行を比較し、最長で「残存耐用年数+10年」を借入期間に設定できる金融機関を探すと返済負担を抑えられます。
比較で見える「どっち」を選ぶ判断軸
実は、投資目的によって最適解が変わります。将来の売却益と低空室リスクを重視するなら新築、短期でキャッシュフローを厚くし節税も狙うなら中古が適します。
資金計画で見ると、自己資金を少なく始めたい人は新築が向きます。なぜなら金融機関が物件評価額の90%まで融資するケースが多く、レバレッジを効かせられるためです。逆に自己資金を多めに投入し、返済比率を30%以下に保ちたい人は中古のほうがシミュレーションが安定します。
維持コストの視点では、築浅の新築でも10年目以降に大規模修繕の積立金が増える点を考慮してください。中古の場合は修繕積立が既に高水準でも、過去の実施履歴を踏まえれば将来の跳ね上がりを予測しやすい利点があります。つまり、「コストの透明度」で比較する手法が有効です。
最後に出口戦略です。新築は長期間保有し資産価値を維持する戦略が向きますが、中古は市場サイクルを見ながら5〜8年での転売も視野に入れられます。2025年時点で東京都心の中古成約単価は前年比+1.8%と堅調で、築30年でも需要があるため、リノベ済み物件として再販する選択肢も現実味があります。
2025年度に活用できる支援策と金融トレンド
基本的に投資用マンションには直接的な補助金は少ないものの、省エネ改修を行う場合は「住宅省エネ2025キャンペーン」の対象になる可能性があります。対象工事は高断熱サッシや高効率給湯器の導入などで、上限50万円の補助が受けられるため、中古を買ってリノベする際には検討する価値があります。
また、固定資産税の新築特例は自己居住用限定で投資用には適用されませんが、耐震改修を行った場合の固定資産税減額措置(2025年度末まで)は賃貸住宅でも利用可能です。築古物件を選ぶ際は耐震適合証明の取得コストと減税メリットを比較し、トータル収支を計算すると良いでしょう。
金融面では、日銀の長期金利上限緩和の影響で10年固定金利は年2.9%前後まで上昇傾向です。ただし変動金利は1%台後半を維持しており、短期保有やキャッシュフロー重視なら変動、長期保有なら固定のミックス融資が主流になりつつあります。金利1%の上昇は30年ローンで1,000万円規模の総返済増となるため、シナリオ別の金利感応度分析を行うことが必須です。
こうした支援策と金融動向を組み合わせることで、中古でも新築でもコストを抑えながら投資パフォーマンスを最適化できます。
まとめ
本記事では「マンション投資 中古 どっち」という永遠のテーマを、価格、利回り、融資、維持費、出口戦略の五つの視点から整理しました。新築は低空室リスクと資産価値の安定が強みで、自己資金が少なくても始めやすいメリットがあります。一方、中古は取得価格の低さと減価償却による節税効果でキャッシュフローを厚くできる点が魅力です。どちらを選ぶにしても、長期の修繕計画や金利上昇シナリオを織り込んだ収支シミュレーションが欠かせません。まずは目的と資金計画を明確にし、本記事で紹介した判断軸をチェックリスト化して、自分に合った一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅リフォーム調査報告書 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 金融モニタリングレポート2025 – https://www.fsa.go.jp
- 東日本不動産流通機構(REINS)市場動向レポート – https://www.reins.or.jp
- 住宅省エネ2025キャンペーン公式サイト – https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp

