立川駅周辺の再開発が進み、商業施設や大学キャンパスが集まるにつれて「住みたい街ランキング」でも名前を見かけるようになりました。そう聞くと、マンション投資に興味を持ちつつも「都心ほど値上がりするのか」「本当に空室は埋まるのか」と不安になる方は多いはずです。本記事では、立川の市場データを読み解きつつ、初心者でも実践しやすい資金計画から物件選び、さらには2025年度の最新制度までを体系的に整理します。読み進めることで、立川エリアで長期的に安定収益を得るための道筋が具体的にイメージできるでしょう。
立川エリア市場の現在地
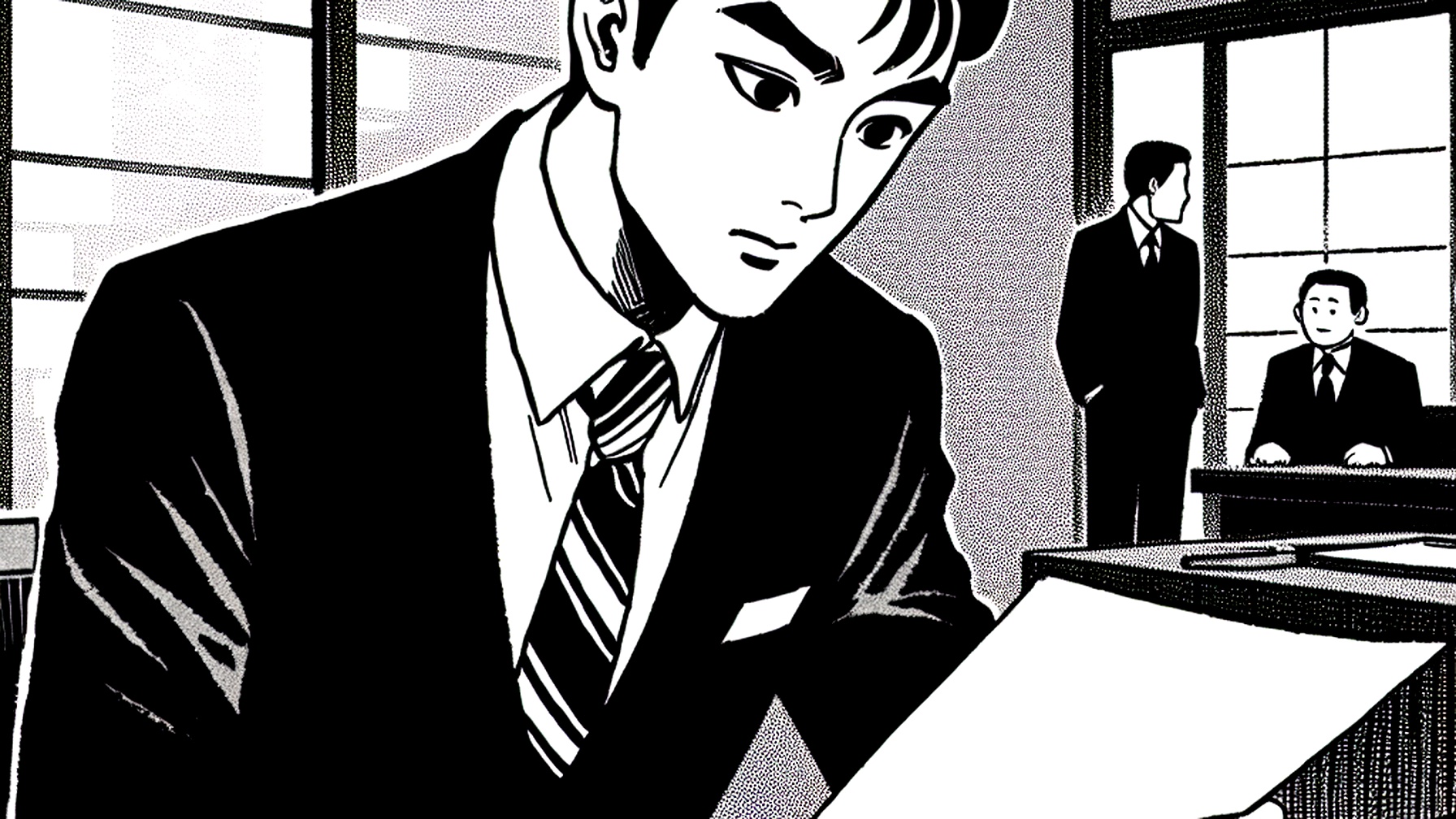
まず押さえておきたいのは、立川が「多摩の中核都市」として独自の需要を確立している点です。東京都が公表する2024年度住民基本台帳によると、立川市の人口は18万人を超え、過去5年で約2%増加しました。都心回帰が叫ばれる中でも、JR中央線・青梅線・南武線が交差する交通利便性と、大規模商業施設の集積が定住ニーズを支えています。
実はマンション価格の推移にもその勢いが反映されています。不動産経済研究所のデータでは、2025年上期の立川駅徒歩10分圏内の新築平均価格は5,780万円で、前年同期比プラス2.9%でした。23区平均の7,580万円と比べるとまだ割安感があり、購入後の値上がり余地を期待できるレンジと言えます。また賃料については、都内ワンルーム平均が9.7万円のところ、立川駅近では9.0万円前後で推移しており、利回りは4.5〜5.0%が目安です。
一方で、供給過多への警戒も必要です。2025年は再開発で300戸規模の新築分譲が予定されており、一時的に競合が増えるタイミングがあります。しかし、立川駅周辺の空室率は日本賃貸住宅管理協会の調査で4.2%と、都内平均の5.6%より低く抑えられています。つまり、需要が底堅いため、新規供給の影響は限定的と考えられますが、年間の竣工スケジュールを踏まえた購入タイミングが収益性を左右します。
以上のように、立川は価格と賃料のバランスが取りやすく、長期保有を前提とした投資に向く市場です。次章では、そのポテンシャルを最大化する資金計画の立て方を解説します。
資金計画と融資のポイント
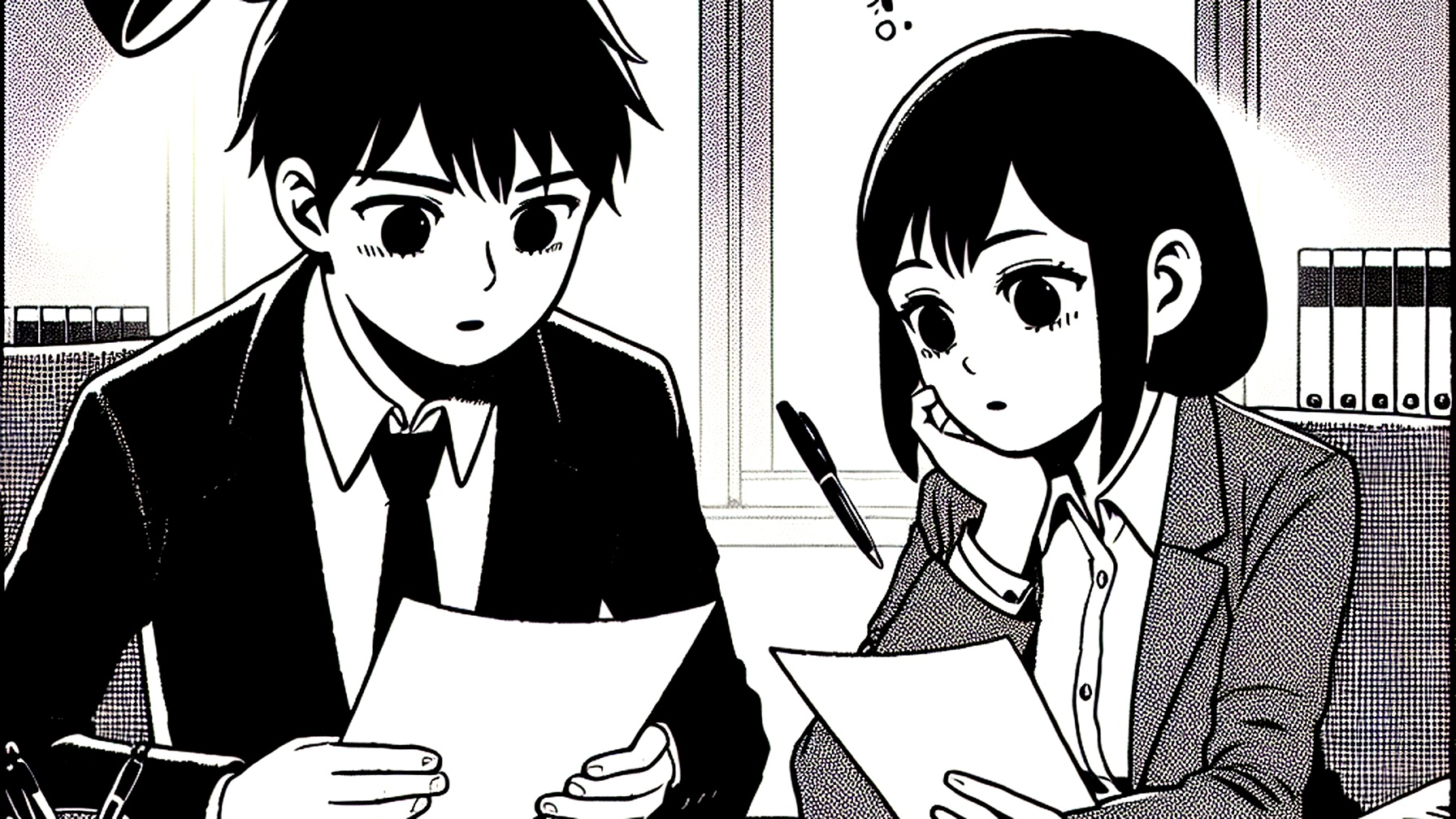
ポイントは、自己資金と融資条件のバランスを最初に固めておくことです。自己資金を物件価格の20%程度入れると、立川の平均利回りでもキャッシュフローが安定しやすく、金融機関の審査も通りやすくなります。
まず、融資金利の目安を確認しましょう。2025年9月時点で地方銀行の投資用マンションローン変動金利は年1.7〜2.1%、ネット系銀行では1.3%台も見られます。金利が0.5%下がると、5,000万円を35年で借りた場合の総返済額は約500万円減る計算です。したがって、複数行に同時打診し、金利と団体信用生命保険の条件を比較検討するとよいでしょう。
さらに、返済比率を家賃収入の50%以内に抑えると、空室や修繕発生時のリスク耐性が高まります。たとえば、月額家賃9万円のワンルームを5戸保有し、総家賃45万円の場合、月々の返済を22万円以下に設定するイメージです。返済額がこの水準なら、2戸空室でも赤字にならず、長期運用中の心理的ストレスが大幅に軽減されます。
実は融資の審査では、自己資金よりも安定した本業収入と過去の借入実績を重視する金融機関も増えています。そのため、法人設立で節税を狙うか、個人名義の与信を活かすかは、将来の追加投資計画を踏まえて選択してください。ここまでの資金計画が固まれば、次に物件選びで外さない視点を掘り下げます。
物件選びで外さない視点
重要なのは、立川ならではの賃貸ターゲットを具体的に想定しておくことです。駅近ワンルームは20代のシングル層が中心ですが、多摩モノレール沿線の1LDKは30代共働きカップルの需要が伸びています。ターゲットが明確になれば、間取りや設備投資に迷いません。
まず、築浅よりも築10年前後の「リセール物件」を検討すると利回りを高めやすくなります。具体的には、2005年以降の耐震基準を満たしながら価格が新築比2〜3割下がった物件が狙い目です。修繕履歴が透明であれば、突発コストを抑えつつ購入直後から賃料を確保できます。
さらに、立川市は大規模商業施設だけでなく、国立病院や大学も集まるため、医療・教育関係の転勤者が安定的に流入します。こうした入居者層は転居の際に法人契約となるケースが多く、家賃滞納リスクが低い点が魅力です。管理会社には「法人契約実績」を必ず確認し、対応体制が整っている企業を選びましょう。
一方で、駅から徒歩15分を超える物件は、表面利回りが高く見えても空室期間が長くなる傾向があります。独立系管理会社の月次レポートによると、立川で徒歩5分以内の平均空室日数が23日に対し、15分超では51日でした。数字が示すとおり、実質利回りは駅近の方が高くなるケースが多いのです。つまり、購入時は利回りより「埋まりやすさ」を重視する姿勢が不可欠といえます。
長期運用と出口戦略
まず押さえておきたいのは、運用期間中の修繕計画をシミュレーションすることです。国交省のガイドラインでは、外壁補修と給排水管更新を含めて30年間で室内1戸あたり約180万円が目安とされています。購入時に修繕積立金の残高と将来の値上げ予定を確認し、資金が不足する管理組合は避けるべきです。
運用フェーズでは、賃料改定のタイミングを逃さないことが収益向上の鍵になります。立川の賃料は緩やかな右肩上がりですが、募集賃料と入居中賃料の差は平均5%あります。更新時に相場を反映させるだけで、年間キャッシュフローが大きく改善します。また、IoT設備や無料Wi-Fiを導入すると、空室率を下げつつ賃料を2,000円程度上乗せできる事例も増えています。
出口戦略としては、築20年を迎える前に売却を検討する選択肢があります。築浅ニーズが根強い日本の中古市場では、築20年を境に価格下落が加速する傾向があるためです。購入時に周辺の取引事例や将来の再開発計画を把握し、想定売却価格をシミュレーションしておけば、キャピタルロスを最小限に抑えられます。
とはいえ、相続対策として長期保有する戦略も有効です。固定資産評価額が下がることで相続税の課税ベースが圧縮されるため、現金よりも税負担を軽減できます。どちらのルートを選ぶにしても、5年ごとに「保有か売却か」を再診断し、感情ではなく数字で判断する姿勢が重要と言えるでしょう。
2025年度の制度活用と税務の基礎
実は、投資用マンションにも活用できる制度がいくつかあります。2025年度の「賃貸住宅省エネ改修等推進事業」は、断熱性能向上や高効率設備の導入に対して費用の3分の1(上限120万円)が補助される仕組みです。立川の冬は多摩川からの冷たい風が強いため、二重サッシの改修は入居者満足度を高め、長期空室の防止にも直結します。
税務面では、不動産所得が赤字の場合に給与所得と損益通算できるルールが引き続き有効です。ただし、2021年度改正で損益通算が制限された「立体駐車場スキーム」のような過度な節税策は対象外となっています。適正な減価償却を行い、赤字を作り過ぎないバランスが求められます。
固定資産税については、区分所有マンションの評価見直しが進む中、2024年度に評価額が平均2%上昇しました。立川市役所の試算では、築15年のワンルームなら年間税額は約7万円です。賃料に対して1割未満なので、キャッシュフローを大きく圧迫する水準ではないものの、評価替えのタイミングで資金繰りを再確認しておくと安心です。
最後に、法人化の検討ポイントを挙げます。法人税率は実効25%程度で、所得900万円を超える個人の最高税率33%より低く抑えられます。また、小規模企業共済など退職金準備の制度を使える点もメリットです。一方で、設立費用や事務負担が増えるため、年間収支が300万円以上黒字になってから検討するのが現実的といえるでしょう。
まとめ
立川のマンション投資は、都心より手頃な価格帯ながら人口と賃貸需要が堅調で、初心者にも取り組みやすい土壌があります。市場動向を把握したうえで、自己資金割合と返済比率を調整し、駅近かつターゲットを絞った物件を選ぶことが成功の近道です。さらに、修繕計画や賃料改定を継続的に見直し、2025年度の省エネ補助金など実効性の高い制度を活用すれば、長期的なキャッシュフローは一段と安定します。まずは本記事を参考に、資金シミュレーションと物件調査から着手し、立川での投資第一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 東京都都市整備局 都市計画情報 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 立川市役所 まちづくり部統計資料 – https://www.city.tachikawa.lg.jp
- 国土交通省 住宅局 「賃貸住宅省エネ改修等推進事業」資料 – https://www.mlit.go.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 空室率調査 – https://www.jpm.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp

