不動産投資に興味はあるものの、物件を直接買うには資金も手間も重いと感じる方は多いはずです。そこで候補に上がるのが、少額で分散投資ができるREIT(リート)です。しかし銘柄数は70を超え、利回りやリスクの差も大きいため「結局どれを選べばいいのか」と迷う声をよく耳にします。本記事では、2025年9月時点の最新データを用いながら、REITを比較する具体的な手順を丁寧に解説します。読み終えたときには、自分に合った銘柄を選べる判断軸が手に入るはずです。
REITとは何かと株式との違い
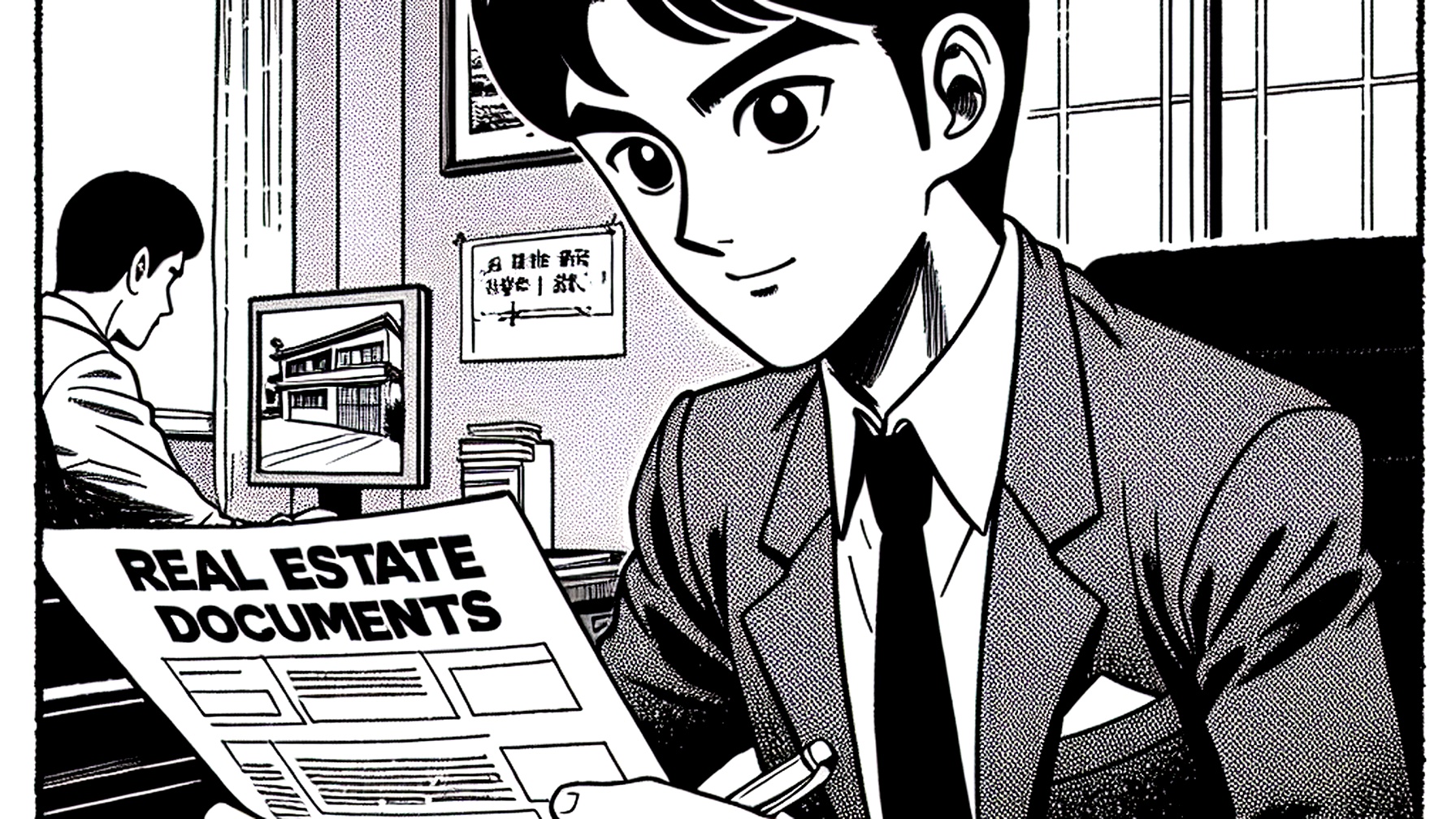
まず押さえておきたいのは、REITがあくまで「不動産を裏付け資産とする投資信託」である点です。投資家は取引所で1口単位から購入でき、株式と同様に価格はリアルタイムで動きます。一方で、賃料収入が原資となる分配金が年2〜4回支払われ、法律上90%超を配当すれば法人税が実質免除になる仕組みです。つまりインカム狙いの色彩が強く、値上がり益よりも安定収益を求める人に向いています。
日本取引所グループが公表する2025年7月末時点のJ-REIT指数は2,090ポイント前後で推移し、平均分配金利回りは3.7%です。TOPIXの配当利回り2.3%と比べ優位ですが、価格変動幅(ボラティリティ)は株式より抑えめとなっています。また、株式のように企業業績に左右されにくく、物件の稼働率や賃料改定が主なドライバーになる点も大きな違いです。
初心者が押さえるべき比較軸
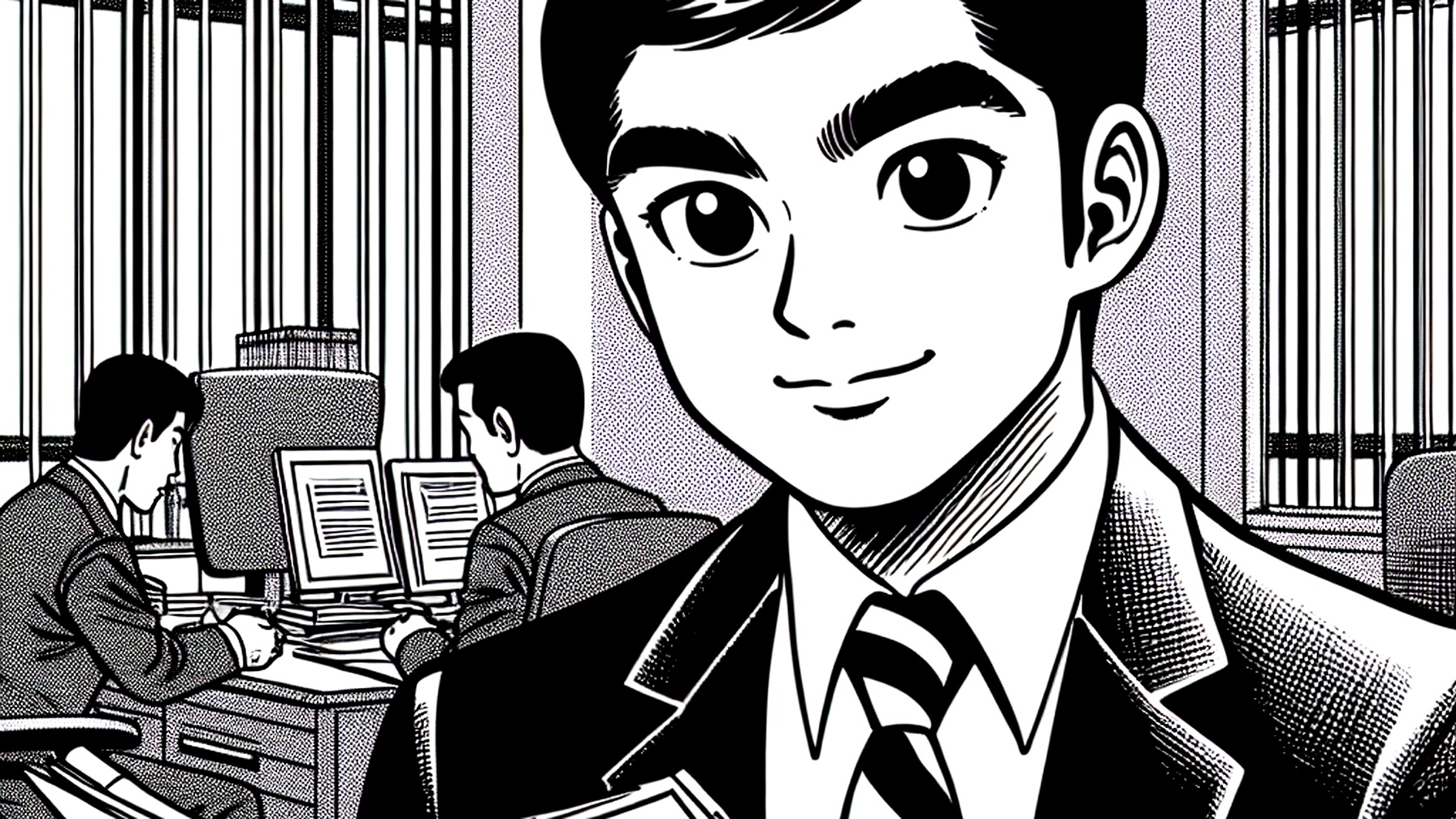
重要なのは、表面利回りだけで判断しないことです。まず分配金の原資となる「NOI(純営業収益)」の伸びを確認します。国土交通省の不動産価格指数によると、2020年以降オフィス価格はやや調整していますが物流施設は上昇基調を維持しています。そのため、物流系REITの多くはNOIが前年比5%前後で成長しており、将来の増配余地が大きいと言えます。
さらに、LTV(負債比率)も見逃せません。低金利が続く中であっても、金利上昇局面ではLTVが高い銘柄ほど分配金が圧迫されやすくなります。日本銀行の「貸出平均金利推移」では、2025年4月の長期固定金利は1.35%と前年同月比で0.2ポイント上昇しました。こうした環境下では、LTV50%以下の銘柄を選ぶことで安定性を高められます。
最後に、資産規模と物件分散度合いもチェックします。資産総額1,000億円未満の小型REITは、1物件あたりの比重が大きく、一棟の賃料改定が分配金に与える影響が大きくなりがちです。東証が開示するデータでは、資産総額3,000億円以上のREITの平均空室率は2.1%、一方1,000億円未満は3.8%と差が出ています。規模の大きさはリスク緩和の指標として有効です。
実践的なREIT比較ステップ
ポイントは、数値を一度に並べるより、段階を踏んで絞り込むことです。まず自己資金とリスク許容度を明確にし、購入予定額の上限を決めます。次に、平均利回りとLTVを軸にスクリーニングを行い、目標利回りを下回る銘柄とLTV60%超の銘柄を除外します。
第二段階では、ポートフォリオ構成を詳細に見ます。物流、住宅、オフィス、商業といったセクターごとに需要動向が異なるため、直近の入居率推移と賃料改定率を確認しましょう。例えば、総務省の人口移動報告では2024年の都心回帰が再加速しており、住宅系REITは空室率が平均1%台に低下しています。逆にサブリース比率の高い商業施設では、テナント交渉力が弱い場合があるので注意が必要です。
第三段階として、運用会社の実績とガバナンスを比較します。運用報告書のIR活動頻度や、物件売却益の再投資方針に目を通すと、長期視点か短期視点かが透けて見えます。実は、ガバナンスの質は株価の変動性にも影響します。金融庁の研究では、外部評価機関によるESGスコア上位のREITは、指数全体より価格下落局面での下げ幅が平均15%小さいと示されています。
最後に、投資タイミングを決定します。チャートを見て直近高値からの調整幅や出来高を確認し、利回りが過去3年平均より0.5ポイント程度上回った局面を狙うのがセオリーです。日銀が段階的にETF買い入れを縮小している影響で、2025年に入ってREIT市場は月末に売りが出やすい傾向があります。この周期を利用すれば、年2〜3回は割安水準でエントリーできるチャンスが巡ってきます。
2025年度の市場環境と注目セクター
まず押さえておきたいのは、インフレ率上昇が賃料に及ぼすプラス効果です。総務省の消費者物価指数は2025年7月まで23か月連続で前年同月比2%を超えており、特に物流賃料は2024年比で3.2%上昇しました。また、EC拡大と半導体工場の国内回帰で全国物流空室率は過去最低の1.9%となり、物流系REITの増配傾向は続くと見込まれます。
一方で、オフィス系は二極化が進んでいます。東京都心5区のAクラスビル空室率は2.4%まで改善したものの、B・Cクラスは依然5%台です。高品質物件に集中するREITか、リニューアル投資で付加価値を高める戦略をとるREITが有利になります。また、2025年度はホテル需要がコロナ禍からの完全回復で再拡大し、インバウンド客数は日本政府観光局の推計で3,400万人に達する見込みです。ホテル系REITはADR(平均客室単価)がコロナ前比15%高い水準を維持しており、分配金の上振れ余地があります。
税制面では2025年度の新NISAを活用した長期保有が引き続き有効です。成長投資枠と積立投資枠の合計で年間360万円、非課税保有限度額1,800万円の範囲内なら、分配金と譲渡益が非課税となります。分配金利回り3.5%のREITを非課税で20年運用すれば、課税口座に比べ実質利回りで約0.7ポイント上乗せできる計算です。初心者こそ制度を組み合わせた運用を検討しましょう。
まとめ
ここまで、REITを選ぶときの具体的な比較ステップと、2025年度の市場環境を解説しました。利回り、LTV、物件分散、運用会社の質という四つの軸で絞り込み、割安局面を狙う手順を踏めば、初心者でも銘柄選定の迷いは大幅に減ります。さらに、物流とホテルを中心に需要が伸びる現状を踏まえつつ、新NISAなどの制度を活用すれば、税負担を抑えた長期安定運用が可能です。次にチャートとIR資料を開き、自分の条件に合う2〜3銘柄を比較する行動から始めてみてください。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) J-REIT指数月報 – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 貸出平均金利推移 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 統計局 人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 日本政府観光局(JNTO) 訪日外客統計 – https://www.jnto.go.jp

