不動産投資は安定収益を得られる資産運用として人気ですが、「本当にリスクは少ないのか」と不安に感じる人も多いはずです。特に初心者は、利回りや節税メリットばかりに目が向き、見落としがちなデメリットに後から気付くケースが少なくありません。本記事では「不動産投資 デメリット 何を」知っておくべきかを中心に、2025年9月時点の最新情報を踏まえて解説します。読了後には、自分に合ったリスク許容度を判断し、具体的な対策を立てられるようになります。
不動産投資の魅力の裏にあるリスク
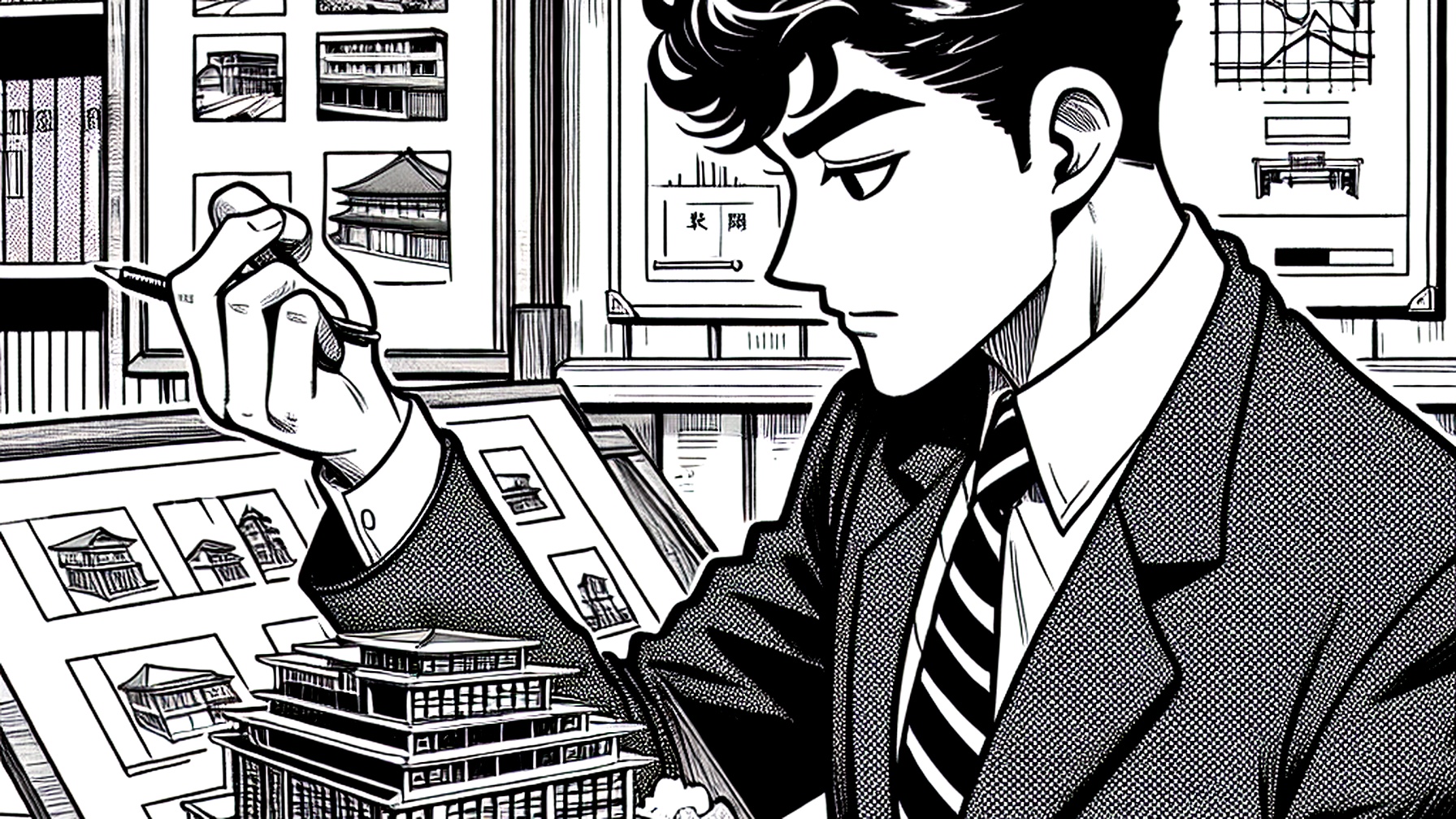
まず押さえておきたいのは、収益性と安全性のバランスです。不動産は現物資産のため価値がゼロになる可能性は低い一方、長期保有が前提となり流動性が低くなります。
国土交通省の「不動産価格指数(2025年7月速報)」では、住宅価格は全国平均で前年比3.2%上昇しました。しかし都心部と地方の差は拡大しており、エリア選定を誤ると値下がりリスクが高まります。また、投資用ローンの金利は足元で上昇傾向にあり、日本銀行の政策見通し次第では返済負担が増える懸念があります。
加えて、契約後に簡単には売却できない点も見逃せません。不動産流通推進センターの統計によると、2024年の中古マンション平均売却期間は約4.3か月でした。値引き交渉を含めると半年以上かかるケースもあり、その間のローン返済や管理費は負担し続ける必要があります。つまり、高い利回りだけで判断せず、出口戦略まで含めた総合的な計画が不可欠です。
空室リスクと家賃下落への備え方
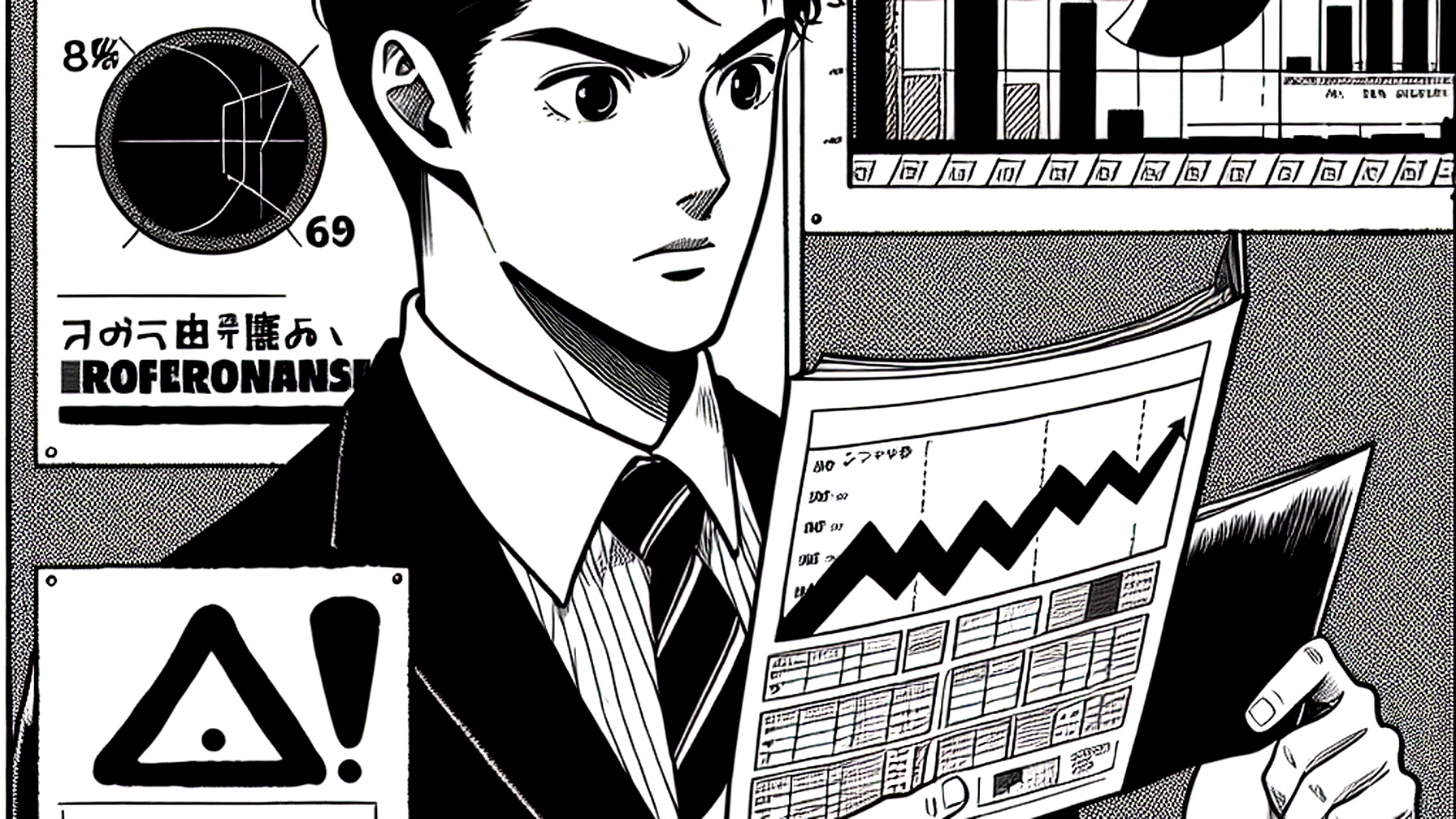
重要なのは、空室率を現実的に見積もることです。総務省「住宅・土地統計調査2023」によると、全国の空き家率は13.8%と過去最高を更新しました。空室が続くと家賃収入が途絶え、収支は一気に悪化します。
特に単身者向け物件は供給が過多になりやすく、築年数が10年を超えると家賃が平均8〜12%下落するデータもあります。また、一度下げた家賃を元に戻すのは難しく、設備のグレードアップや広告費の増加が必要になる点も覚えておきましょう。
対策として、立地選定に加え「入居者ターゲットの多様化」が有効です。ファミリー層や高齢者向けに間取りを変更したり、ペット可物件へ転換したりすることで競合を避けられます。さらに、サブリース契約(家賃保証)の利用は収入を平準化できますが、手数料や家賃見直し条項を十分に確認することが大切です。
修繕費・大規模修繕が資金繰りを左右する
ポイントは、想定外の支出をどこまで織り込めるかです。外壁塗装や屋上防水などの大規模修繕は、マンションなら12〜15年ごとに発生し、一戸あたり100万〜150万円が目安となります。
国土交通省「マンション大規模修繕工事費用実態調査(2024年版)」では、工事費がここ10年で約18%上昇したと報告されています。人件費と資材費の高騰が主因で、今後も高止まりする見通しです。修繕積立金だけでは不足するケースが増え、一時金徴収や追加ローンが必要になることもあります。
戸建て投資の場合でも、給排水管や屋根の全交換には数百万円単位が必要です。したがって、毎月のキャッシュフローの20〜30%を「修繕準備金」として留保するのが実務的な目安といえます。予防保全として点検を年1回実施すれば、中長期的にコストを抑えられる点も覚えておきましょう。
税制と融資ルールの変化が与える影響
実は、税制度の変更が収益に直結します。2025年度税制では、所得税の累進構造は現行維持となった一方、損益通算の厳格化が議論されています。現時点では、賃貸損失と給与所得の通算は制限なく認められていますが、将来の改正余地を常に念頭に置く必要があります。
固定資産税については、2025年度評価替え後も住宅用地の特例(1/6軽減)は継続中です。ただし、家屋の経年による評価額下落が緩やかになる傾向があり、税負担が想定より下がらないケースが見受けられます。また、相続税対策としての賃貸経営は引き続き有効とされるものの、路線価上昇エリアでは圧縮効果が縮小している点に注意が必要です。
融資面では、金融庁が2024年に公表した「不動産融資に関するモニタリング方針」により、自己資金10〜20%を求める銀行が増えました。さらに、賃料収入の7割を返済原資とみなす審査基準が普及し、フルローンは例外的な扱いになっています。借入比率が高い場合、金利上昇局面でキャッシュフローが急激に悪化するため、長期固定金利への借り換えを含めたリスク管理が欠かせません。
デメリットを最小化する実践的な対策
まず押さえておきたいのは、デメリットを「見える化」することです。物件選定時に5年・10年・15年後のシナリオを作り、空室率や修繕費を複数の前提で試算します。保守的な数字でも手元資金が枯渇しない計画であれば、心理的負担も軽減されます。
次に、物件管理の外注と自主管理を組み合わせる方法があります。入居者募集は専門会社に任せつつ、清掃や簡易点検を自分で行えば、管理手数料を年10〜20万円程度削減できます。また、IT重説やオンライン内見を活用すると空室期間短縮に役立ちます。
情報収集力の強化も欠かせません。自治体が公表する都市計画や再開発情報は、将来の賃料推移を予測する重要な手がかりになります。さらに、2025年度に創設された「住宅省エネ2025補助金」は、賃貸物件の断熱改修にも上限100万円の補助が適用されるため、長期入居と光熱費削減の両面でメリットがあります。最新制度を的確に活用することで、デメリットをチャンスに変えられるのです。
まとめ
本記事では、不動産投資の代表的なデメリットとして価格変動リスク、空室・家賃下落、修繕費、税制・融資の変化を取り上げました。これらは避けられないものの、事前のシミュレーションと制度活用、そして情報収集によって大幅に軽減できます。結論として、リスクを正しく理解し、自分の資金力と目的に合った投資戦略を選ぶことが成功への近道です。今日からできる第一歩として、気になる物件の収支表を保守的な条件で再計算し、どの程度の余裕資金が必要かを確認してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 マンション大規模修繕工事費用実態調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産流通推進センター 不動産取引統計月報2024 – https://www.retpc.jp
- 金融庁 不動産融資に関するモニタリング方針2024 – https://www.fsa.go.jp

