相続税の負担を少しでも軽くしたいものの、何から手を付ければ良いのか分からない――そんな悩みを抱える方は多いです。特に金融資産が中心の場合、評価額がそのまま課税対象になるため節税の余地はほとんどありません。一方で不動産、とりわけ中古マンションへの投資は、評価額を時価より低く抑えつつ安定収益も期待できる点が魅力です。本記事では「マンション投資 相続対策 中古」という視点から、評価の仕組み、物件選び、制度活用、家族への引き継ぎ方まで体系的に解説します。読み終えたとき、具体的な次の一歩が見えるはずです。
相続税評価とマンションの関係を理解する

重要なのは、相続税の課税評価額が市場価格と必ずしも一致しない点です。国税庁の財産評価基本通達では、区分マンションの評価は「路線価×持分面積」に基づく土地評価と「固定資産税評価額」による建物評価を合算して求めます。その結果、東京23区で時価7,000万円前後の中古区分でも、評価額が5,000万円を下回るケースが珍しくありません。つまり現金で7,000万円を持つより、中古マンションに置き換えたほうが2,000万円超の課税ベース削減が見込めるわけです。
さらに、相続人が複数いる場合は区分ごとに持ち分を分けることも容易です。物理的に分筆が難しい一棟物件に比べ、区分マンションは取得者をあらかじめ指定しやすく、遺産分割協議のトラブルも減らせます。このように評価減と分割の柔軟性が、中古マンション投資を相続対策に適した手段へ押し上げています。
中古マンション投資が相続対策に向く理由
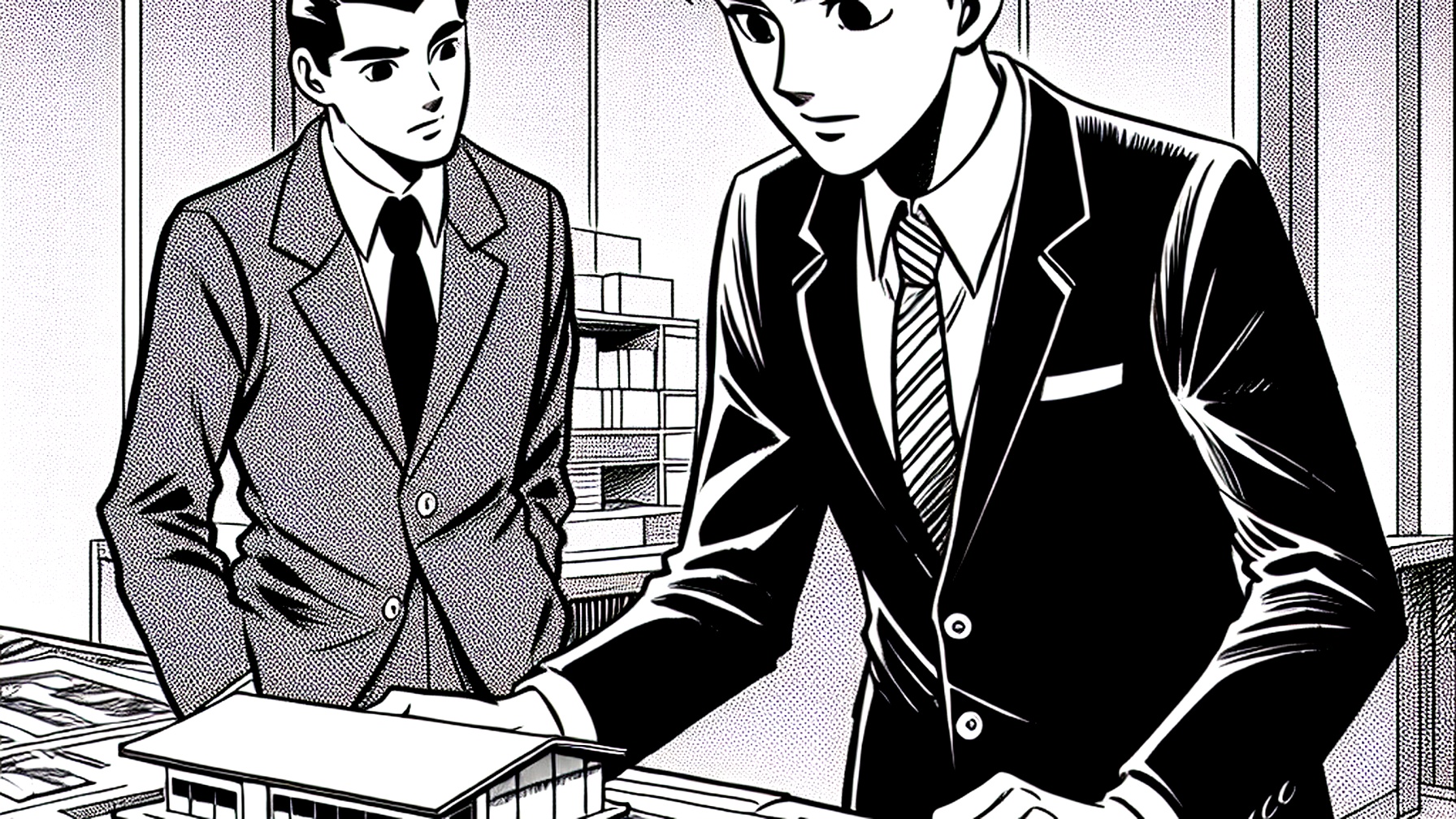
まず押さえておきたいのは、築年数が進んだ物件ほど建物評価額が下がり、相対的に土地評価のウェイトが高まる点です。土地は減価しないため、長期保有しても帳簿上の価値が大きく減ることはありません。また、建物部分が大幅に償却済みの中古は賃料利回りが高く、手残りが出やすいのも利点です。
実は国土交通省の住宅市場動向調査によると、築20年以上の都心区分マンションは平均表面利回り5.2%と、新築の3.6%に比べ1.6ポイント高い結果が出ています。相続発生までの期間に家賃収入でローン元本を圧縮できれば、相続人の負担も軽くなります。加えて、2025年時点で住宅ローン金利は1%台前半を維持しており、レバレッジ効果を保ちながらキャッシュフローを確保しやすい環境です。
一方で中古特有の修繕リスクは無視できません。しかし、管理組合の修繕積立金の残高推移を確認し、長期修繕計画に沿った工事が実施されているかを点検すれば、大半のリスクは事前に把握できます。築古だから危険という先入観を捨て、管理状況という“ソフト面”を評価する視点が欠かせません。
失敗しない物件選びのポイント
ポイントは「立地」「管理」「価格」の三位一体で判断することです。立地は将来的な賃貸需要を左右します。総務省の人口推計では、都心5区の単身世帯は2035年まで微増が見込まれていますが、郊外では減少傾向が続きます。このデータを踏まえると、駅徒歩7分以内かつ転勤族や学生が多いエリアが、有利な空室リスク低減策となります。
次に管理面ですが、重要なのは大規模修繕の履歴と積立金残高のバランスです。国交省「マンション総合調査」では、積立金不足を訴える管理組合は38.1%に達しています。不足していれば、相続後に追加一時金を請求される可能性もありますから、購入前の精査が不可欠です。
最後に価格。中古区分は過去成約事例が豊富ですから、レインズ市場データの平米単価と比較し、10%以上割高なものは避けるのが無難です。割安購入はそのまま評価額の低減と利回り向上に直結します。つまり立地と管理をクリアした物件を適正価格よりやや低く買えれば、相続対策としても投資としても二重のメリットが得られます。
2025年度制度を活用した法的・税務対策
実は制度を組み合わせると、節税余地はさらに広がります。2025年度も継続する「小規模宅地等の特例」を使えば、被相続人が居住していた区分マンションを取得し、一定要件を満たす相続人が住み続けた場合、土地評価額を80%減額できます。投資用区分には原則適用されませんが、将来的に自宅として使う可能性があるなら選択肢に入れて損はありません。
また、生前に子や孫へ贈与しておく「相続時精算課税制度」も活用しやすいです。2,500万円までの贈与を非課税で移転でき、相続時にまとめて精算する仕組みですが、将来値上がりが見込まれる都心中古マンションを早めに移しておくと、有利に評価減の効果を享受できます。
融資面では、2025年度に実施中の住宅金融支援機構「フラット35リノベ」が選択肢になります。耐震・省エネリフォームを伴う中古購入に対し、借入当初5年間の金利を年0.3%引き下げる制度で、同機構が定める適合証明を取得すれば利用可能です。金利優遇は返済総額の圧縮だけでなく、家賃収入の余剰キャッシュを増やし、相続発生時に納税資金を確保するうえでも役立ちます。
キャッシュフロー管理と家族への引き継ぎ方
まず、相続対策として中古マンションを持つ以上、年間キャッシュフローを黒字で回す仕組みが前提になります。家賃収入からローン返済、管理費、修繕積立金、固定資産税を差し引き、手残りが月1万円でも残れば納税原資の蓄積が可能です。不動産経済研究所が公表する家賃指数では、築15年以降の賃料下落幅は年間0.5%前後で安定しています。大幅な収入減の懸念は限定的といえます。
家族への引き継ぎは、「遺言書」と「管理マニュアル」のセットが効果的です。遺言書で誰がどの区分を取得するか明確にし、管理マニュアルで賃貸借契約書や保険証券、管理組合連絡先を一覧化しておくと、相続人は運営をスムーズに引き継げます。さらに、生命保険を活用して相続税納税資金を用意しておけば、物件を売却せずに済む可能性が高まります。
最後に、相続人自身が賃貸経営に興味を持つかどうかを話し合っておくことも重要です。もし運営が難しい場合は、管理会社に運営を一括委託する「サブリース契約」を検討するとよいでしょう。ただし、家賃保証額の見直し条項や解除条件をよく確認し、柔軟に出口戦略を取れるよう備えることが欠かせません。
まとめ
本記事では、現金より評価額を抑えられる相続税評価の仕組み、中古マンション特有の高利回りと管理リスク、2025年度も有効な制度の活用法、そして家族へのスムーズな引き継ぎ方までを解説しました。マンション投資 相続対策 中古という組み合わせは、節税と安定収益を同時に狙える実践的な手法です。まずは気になるエリアの相場を調べ、管理状況の良い物件を適正価格で探すことから始めましょう。そして専門家と連携しながら、遺言書や資金計画を整えれば、家族に安心を残す投資が現実のものとなります。
参考文献・出典
- 国税庁 財産評価基本通達 – https://www.nta.go.jp/
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp/
- 不動産経済研究所 首都圏新築・中古マンション価格データ – https://www.fudosankeizai.co.jp/
- 総務省統計局 人口推計2025年版 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省 マンション総合調査2024 – https://www.mlit.go.jp/
- 住宅金融支援機構 フラット35リノベ制度概要 – https://www.jhf.go.jp/
- 全国賃貸住宅新聞 家賃指数2025 – https://www.zenchin.com/

