親から突然受け継いだ空き家やマンションをどうすべきか、悩んでいる方は多いものです。売却して現金化する選択肢もありますが、上手に賃貸運用すれば毎月の安定収入を得られる可能性があります。本記事では「不動産投資 始め方 相続物件」をキーワードに、相続登記から資金計画、リフォーム戦略まで初心者がつまずきやすいポイントを網羅的に解説します。読み終えれば、相続物件を活用した投資の全体像と、2025年度時点で活用できる制度の概要がつかめるでしょう。
相続物件を投資に活用するメリットと注意点
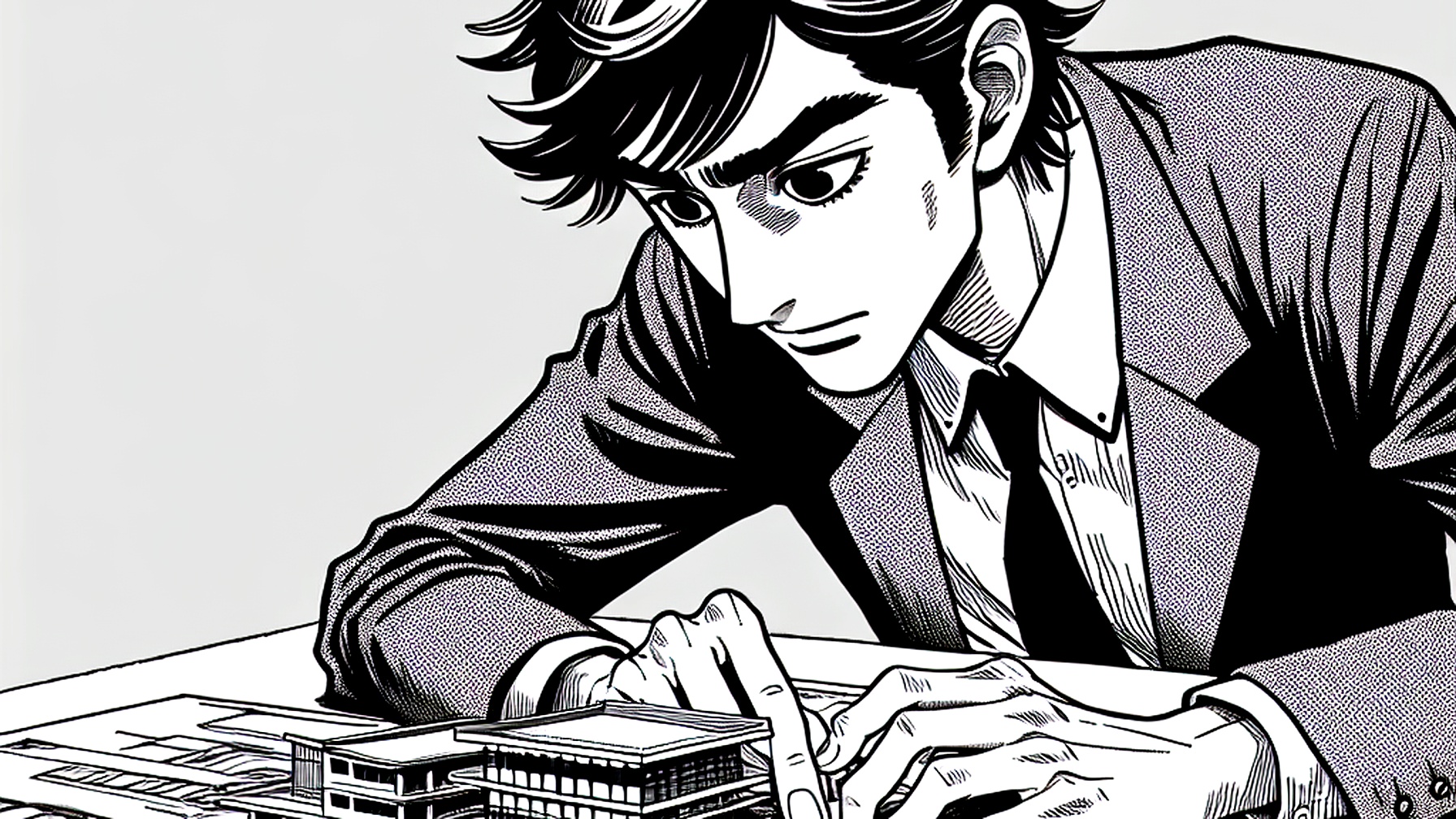
重要なのは、相続物件には新規購入とは異なる強みとリスクが混在している点を理解することです。固定資産税評価額が低ければ初年度からキャッシュフローが改善しやすい一方、築年数が古く修繕費がかさむケースも少なくありません。
まずメリットとして、購入費用がゼロに近い点が挙げられます。国土交通省の住宅市場動向調査によると、投資用物件の初期費用は平均で物件価格の16〜18%が諸費用に消えます。しかし相続物件なら登録免許税と司法書士費用程度で済み、手元資金をリフォームや広告費に回せるのです。
一方で、相続時の空室期間が長い物件は周辺相場より賃料を下げても入居が決まりにくいケースがあります。総務省の住宅・土地統計調査(2023年速報値)では、空き家期間が3年以上になると成約までの平均期間が約1.7倍に延びるとの結果が出ています。つまり取得コストが低いからといって収益化が容易とは限らず、現状把握が欠かせません。
また感情面のハードルも見逃せません。思い出が詰まった実家を賃貸に出すことに家族が抵抗を示す場合があります。その際は、将来的な維持費や固定資産税を数字で示し、賃貸運用がいかに家計を安定させるかを共有すると合意形成が進みやすいでしょう。
まず押さえておきたい相続登記と税金の基礎
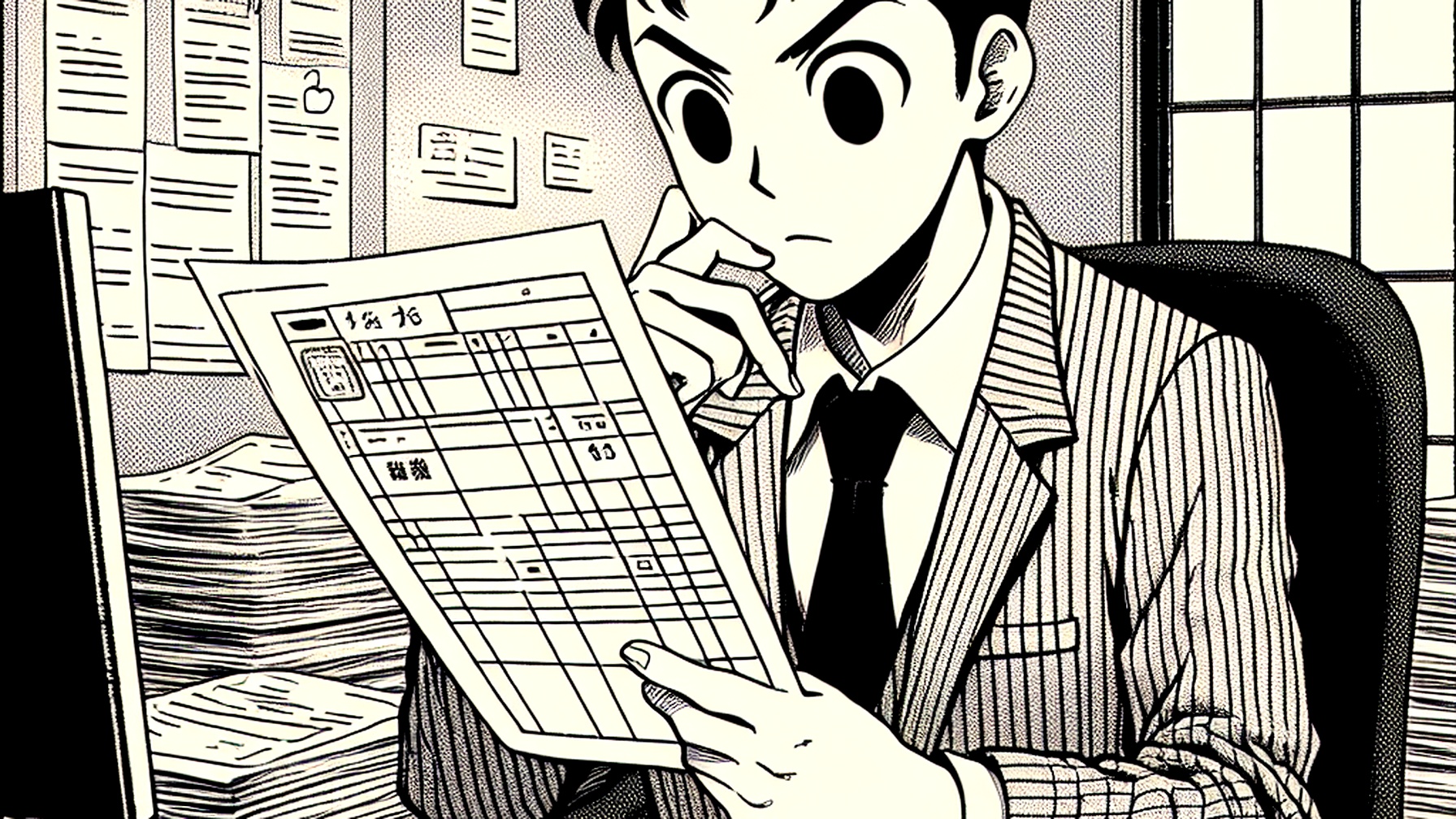
ポイントは、法律面の手続きを先送りにしないことです。2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は法務局への申請で完結しますが、遺産分割協議書や戸籍一式の収集に時間がかかるため、早めに着手することが大切です。司法書士へ依頼すると10万〜15万円程度が相場ですが、登記を済ませていないと金融機関の融資審査すら受けられません。
次に税金の話です。相続時点で評価額が基礎控除内に収まれば相続税はゼロですが、賃貸運用を始めると不動産所得として確定申告が必須になります。国税庁の申告事績(2024年分)によれば、不動産所得者の約25%が経費計上の漏れで追徴を受けています。青色申告特別控除65万円を確実に受けるため、専用帳簿と複式簿記の導入をおすすめします。
さらに2025年度も継続される登録免許税の軽減措置を利用すると、建物の所有権移転登記税率を0.3%から0.1%へ抑えられます。期限は2026年3月31日登記分までの予定なので、リフォーム完了後の名義変更を検討している場合はスケジュールに注意しましょう。
収支シミュレーションとキャッシュフロー管理
まず押さえておきたいのは、相続物件こそ「見えないコスト」を洗い出す姿勢です。毎月の家賃収入からローン返済と管理費を差し引くだけでは不十分で、長期修繕費や退去時の原状回復費も取り込んだシミュレーションが欠かせません。
たとえば木造築30年の戸建てを賃料8万円で貸し出すケースを考えます。住宅金融支援機構の賃貸住宅融資(2025年7月金利1.55%固定)で800万円のリフォームローンを15年返済すると、年間返済額は約66万円です。固定資産税8万円、火災保険4万円、管理委託料家賃の5%で年4.8万円を加えると、年間支出は82.8万円となります。
ここに空室率10%を見込み、その他突発修繕を年10万円と想定すると、年間純収益は約2万円しか残りません。つまり利回りは0.2%にとどまり、投資としては危険水域です。この試算で問題なのは、賃料設定とリフォーム予算のミスマッチです。家賃を5000円上げられる立地か、リフォーム費を600万円以下に抑えられるかを複数パターンで検証することで、投資判断の精度が高まります。
キャッシュフロー表は最低でも15年分を年次で作成し、金利上昇2%、空室率20%という厳しい条件でも赤字にならないラインを確かめましょう。また毎月の家賃収入から固定費の15%を別口座に積み立てれば、大規模修繕のタイミングで慌てずに済みます。
成功するリフォーム戦略と入居促進策
実は、相続物件の収益化で最も差がつくのがリフォーム方針です。新築同然に戻せば安心感は高まりますが、回収に時間がかかり、投資効率が落ちる恐れがあります。
リフォーム前にはターゲットを明確に設定しましょう。単身向けエリアなら浴室乾燥機とインターネット無料を優先し、家族向けなら宅配ボックスと駐車場整備が成約率を左右します。SUUMO賃貸トレンド調査(2024年版)では、上記設備が賃料+3000円の上乗せ効果を持つと報告されています。
工事費を圧縮するコツは、既存の間取りや設備を活かすことです。たとえばキッチンを最新モデルに総入れ替えする代わりに、扉交換と水栓のみ交換すればコストは3分の1に下がります。さらにインスペクション(建物状況調査)を実施すると、構造的な欠陥を把握でき、将来の高額修繕リスクを早期に潰せます。
入居促進策としては、募集開始時期を年度替わりの2カ月前に設定し、写真と360度VR内見を用意することが有効です。国交省賃貸市場データ(2025年1月)では、VR掲載物件の問い合わせ数は静止画のみの1.6倍という結果が示されています。つまり質の高い情報提供が早期満室への近道となります。
2025年度の活用できる支援制度と融資の最新動向
ポイントは、利用可能な公的支援を漏れなくチェックすることです。2025年度も継続予定の「住宅省エネ改修促進事業」は、賃貸物件の断熱改修や高効率給湯器導入に対し、上限120万円の補助を受けられます。申請期限は2026年3月末で、交付決定前の着工は対象外となるためスケジューリングが重要です。
融資面では、政策金融公庫の生活衛生貸付が空き家活用事業向けに拡充され、最長20年・金利1%台が組める枠が設定されています。審査では地域貢献性が重視されるため、地域の空き家対策計画に合致した企画書を添えると可決率が上がります。
金融機関選びでは、地元信用金庫の空き家対策ローンも見逃せません。固定金利2.0%前後で500万円まで無担保という商品が増えており、小規模リフォームに適しています。複数銀行に同時申し込みを行う「資金調達マッチングサイト」を使えば、手間をかけずに最安金利を比較できます。
さらに地方自治体独自の「空き家リフォーム補助」も活用価値があります。たとえば愛知県豊橋市では、住宅用途への改修費の3分の1(上限90万円)を補助し、賃貸活用も対象に含めています。制度ごとに対象区域や入居者条件が異なるため、市区町村のホームページで最新情報を確認しましょう。
まとめ
相続物件を使った不動産投資は、取得コストの低さという大きなメリットがある一方、古さゆえの修繕費や家族間の合意形成といった課題も抱えています。相続登記と税務処理を早期に済ませ、長期キャッシュフローを保守的に試算し、ターゲットに合ったリフォームを行うことで収益化の道が開けます。さらに2025年度の補助金や低利融資を上手に組み合わせれば、自己資金を抑えつつ資産価値を高めることが可能です。記事で紹介したチェックリストに沿って一歩ずつ行動し、相続物件をあなたの新しい収入源へと育ててください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 2023年速報 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 相続税の申告事績 2024年分 – https://www.nta.go.jp
- 法務省 相続登記の申請義務化に関する情報 – https://www.moj.go.jp
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 フラット35賃貸住宅融資情報 – https://www.jhf.go.jp
- SUUMO 賃貸トレンド調査 2024 – https://suumo.jp
- 国土交通省 賃貸市場データ集 2025年1月 – https://www.mlit.go.jp

