不動産価格が上がり続けるいま、投資を始める時期に迷う人は多いはずです。特に中古マンションは価格も利回りも千差万別で、「買い時」が見えにくいと感じるでしょう。本記事では「マンション投資 いつ 中古」をテーマに、相場の流れや金利、税制優遇を総合的に整理します。読了後には、自分に合った購入タイミングを判断できるようになるはずです。
今なぜ中古マンションに注目が集まるのか
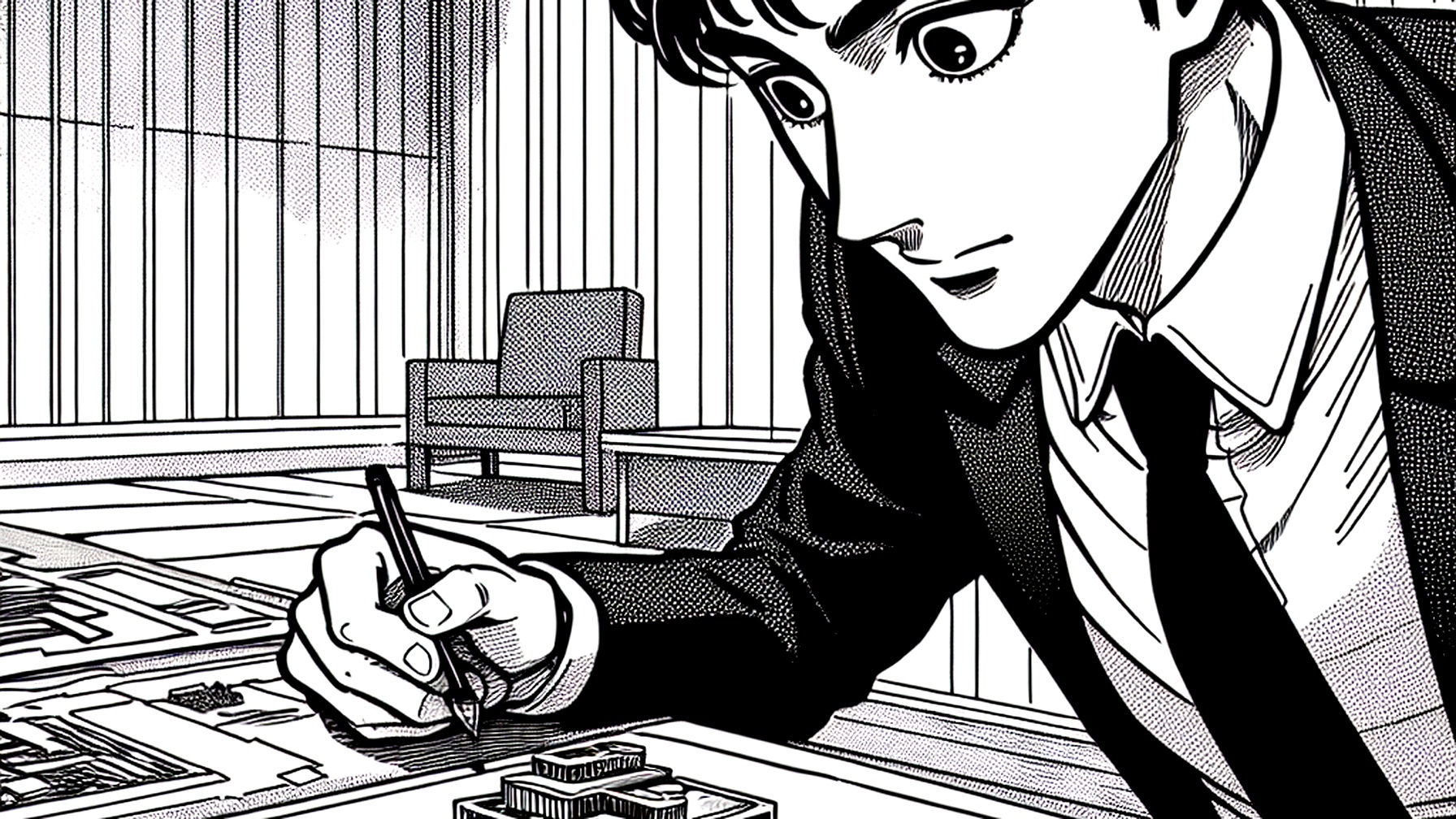
まず押さえておきたいのは、新築価格の高騰が投資家の視線を中古へ向けている点です。不動産経済研究所によると、2025年9月時点の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円で、前年より3.2%上昇しました。この水準では表面利回りが3%台にとどまり、融資金利を差し引くと手残りがわずかになります。
一方で、築20年前後の中古物件なら価格は新築の6割程度に下がり、同じエリアでも利回りが5〜6%に届くことがあります。つまり、家賃水準が大きく変わらないのに取得費だけ抑えられるため、キャッシュフロー改善に直結します。
さらに、中古市場は物件数が豊富で選択肢が多い点も魅力です。築年数と立地の組み合わせ次第でリスクを分散できるので、初心者でもポートフォリオを組みやすいといえます。ただし、物件の管理状況や修繕積立金の残高を見落とすと、想定外の支出を招くため注意が必要です。
購入タイミングを見極める三つの視点
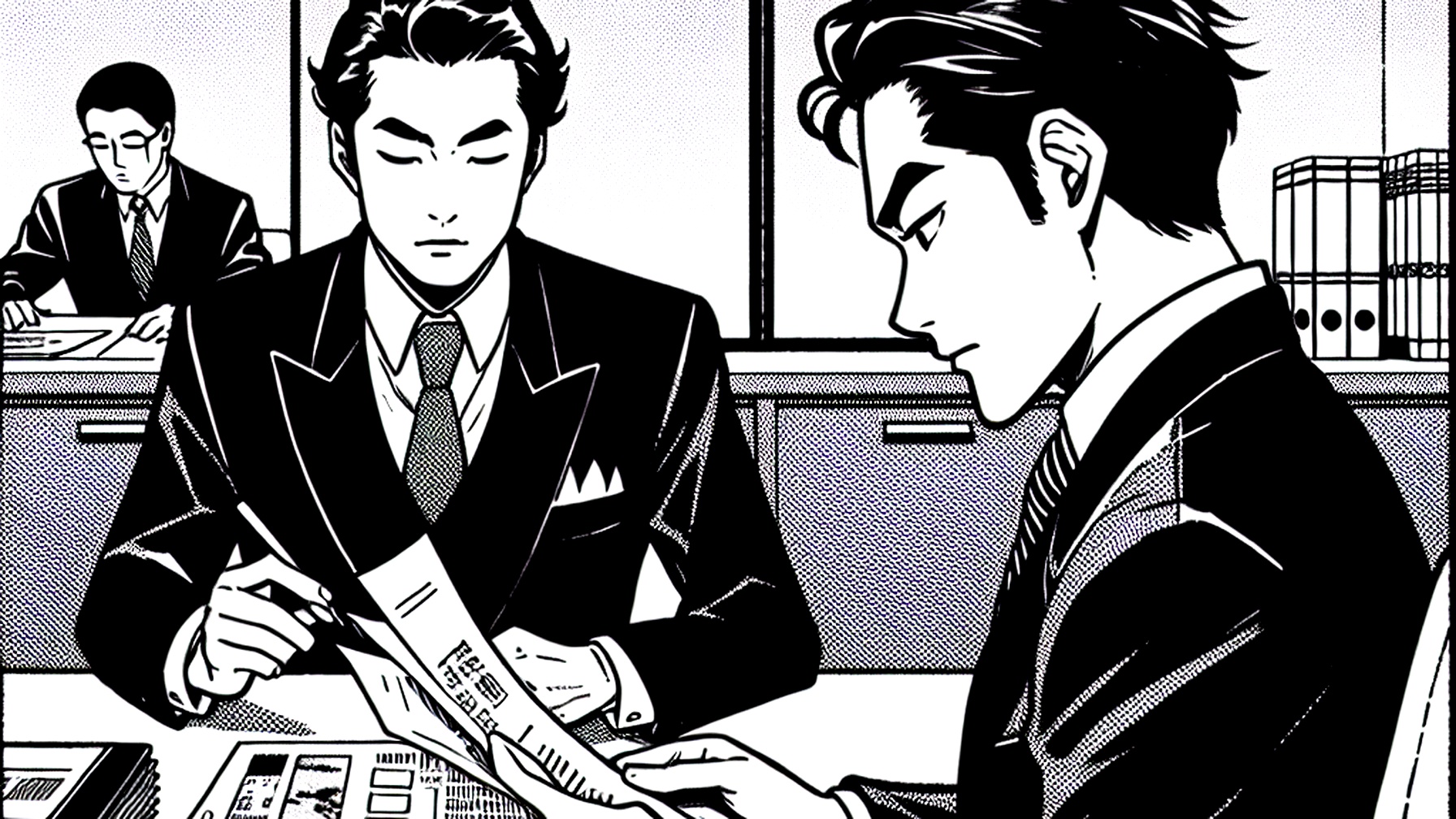
ポイントは「物件価格」「金利」「ライフプラン」の三点を同時に考えることです。価格が下がっても金利が上がれば収支は悪化し、家計に余力がなければチャンスを逃します。
まず価格については、国土交通省の不動産価格指数を確認しましょう。2025年初頭から首都圏中古マンション指数は横ばいで推移しており、短期的な高騰リスクは限定的です。逆に、地方中核都市ではリモートワーク定着に伴う需要増で指数が2%ほど上昇しています。
次に金利です。日本銀行の住宅ローン平均金利は、2025年9月で変動型が0.45%、固定20年が1.50%前後となっています。過去10年で見ると依然として低水準ですが、日銀の金融正常化議論が活発化しており、固定金利を早めに確定する意義が高まっています。
最後はライフプランとの整合性です。自己資金が貯まるまで待つか、低金利を優先して早く購入するかで判断は変わります。将来の転勤や家族構成の変化を踏まえ、家賃収入が生活費の何割をカバーするか試算してみると、決断の軸がぶれにくくなります。
価格サイクルと金利動向の読み方
実は不動産市場には平均8〜10年のサイクルがあるとされます。2008年のリーマン・ショック後に底を打ち、2020年のコロナ禍でも大幅調整は起きませんでした。背景には超低金利と都心への人口集中が重なったことが挙げられます。
しかし、2023年以降は建築コスト高で新築供給が減り、既存ストックに需要が向かった結果、中古価格もじわりと上昇しました。今後は金利上昇プレッシャーが強まるため、価格が横ばいのうちに固定条件で借り入れる戦略が有効です。言い換えると、金利が動く前が「買い時」になりやすいのです。
金利が1%上がると、3,000万円を35年返済した場合の総返済額は約600万円増える計算です。これに対し、中古物件価格の下落は短期では5%前後が一般的で、300万円程度の下げにとどまるケースが多いとされています。つまり、金利上昇リスクの方が収益に与える影響が大きいことがわかります。
市場サイクルの谷を正確に当てるのは難しいものの、金利見通しなら経済指標である程度推測できます。長期金利が0.75%を超えたら固定型の繰上げ返済や借り換えを検討するなど、事前にシナリオを用意しておけば慌てずに対応できます。
税制優遇と2025年度ローン控除を活用する
重要なのは、制度の恩恵を受けることで実質利回りを底上げできる点です。2025年度の住宅ローン控除は、投資用区分マンションには適用されませんが、個人事業主としての青色申告特別控除や、減価償却費の活用で課税所得を圧縮できます。
たとえば、鉄筋コンクリート造(RC)の法定耐用年数は47年ですが、中古購入後でも残存耐用年数に基づき加速度償却が可能です。築30年の物件なら残存17年が目安となり、年間180万円前後の減価償却費を計上できるケースもあります。これにより所得税・住民税が合わせて20%軽減されれば、実質手取りが36万円増える計算です。
加えて、2025年度の固定資産税減額特例は耐震基準適合証明を取得した中古住宅に対し、課税標準が1年間半額になる措置が続いています。取得後に耐震補強を行い、証明書を提出すれば翌年度税負担を抑えられます。
制度は申請期限や要件が細かく変わるため、国税庁や自治体の公式サイトで最新情報を確認することが欠かせません。専門家に相談しながら必要書類を準備することで、取りこぼしを防げます。
失敗しない物件選びと運用のコツ
まず、エリアの人口動態と賃貸需要を把握することが肝心です。総務省の住民基本台帳によれば、東京都心5区の人口は2025年も微増傾向にありますが、郊外では横ばいから微減に転じる地域が目立ちます。人口が安定している駅徒歩10分圏内を狙うだけで空室リスクは大幅に下がります。
物件選定では、管理組合の財務状態を必ず確認しましょう。修繕積立金が不足しがちなマンションでは、将来的に一時金が発生しキャッシュフローを圧迫します。管理規約や長期修繕計画をチェックし、外壁補修の実施履歴を確認することがポイントです。
運用面では、賃料設定を適切に見直すことで収益を最大化できます。家賃を据え置きにすると、インフレ局面で実質利回りが目減りします。年一度は周辺相場と比較し、リフォームや家具付きプランなど付加価値を加える提案を管理会社と協議すると良いでしょう。
最後に、出口戦略を早めに描くことが肝要です。築40年を超えると流通性が落ち、売却期間が長引く傾向があります。15年後に残債が減った時点で一度査定を受け、含み益が確保できるなら売却を検討するなど、複数のシナリオを用意しておくと安心です。
まとめ
本記事では、中古マンション投資の優位性と購入タイミングを、価格・金利・制度の三方向から整理しました。新築価格が歴史的高値を更新する一方で、中古は選択肢が多く利回りも見込めます。低金利のうちに固定条件を確保し、税制優遇を最大限活用することで実質利益を高められる点が最大の魅力です。まずは自分のライフプランと資金計画を照らし合わせ、市場動向をウォッチしながら具体的な物件探しを始めてみてください。行動を先延ばしにするほど機会コストは膨らみます。今日から一歩を踏み出し、将来の安定収入への道を切り開きましょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 長期プライムレート等統計 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳に基づく人口動態 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 不動産所得の必要経費 – https://www.nta.go.jp

