不動産投資を始めたいけれど、数字が苦手で踏み出せない人は少なくありません。物件価格や家賃収入だけに目を向けると、後から思わぬ出費に悩まされることもあります。本記事では「収支計算 進め方」を軸に、初心者でも自分でキャッシュフローを組める方法を解説します。読むことで、物件選びの判断基準が明確になり、融資交渉や長期経営の戦略立案に活かせるはずです。
収支計算を始める前に押さえる基本概念
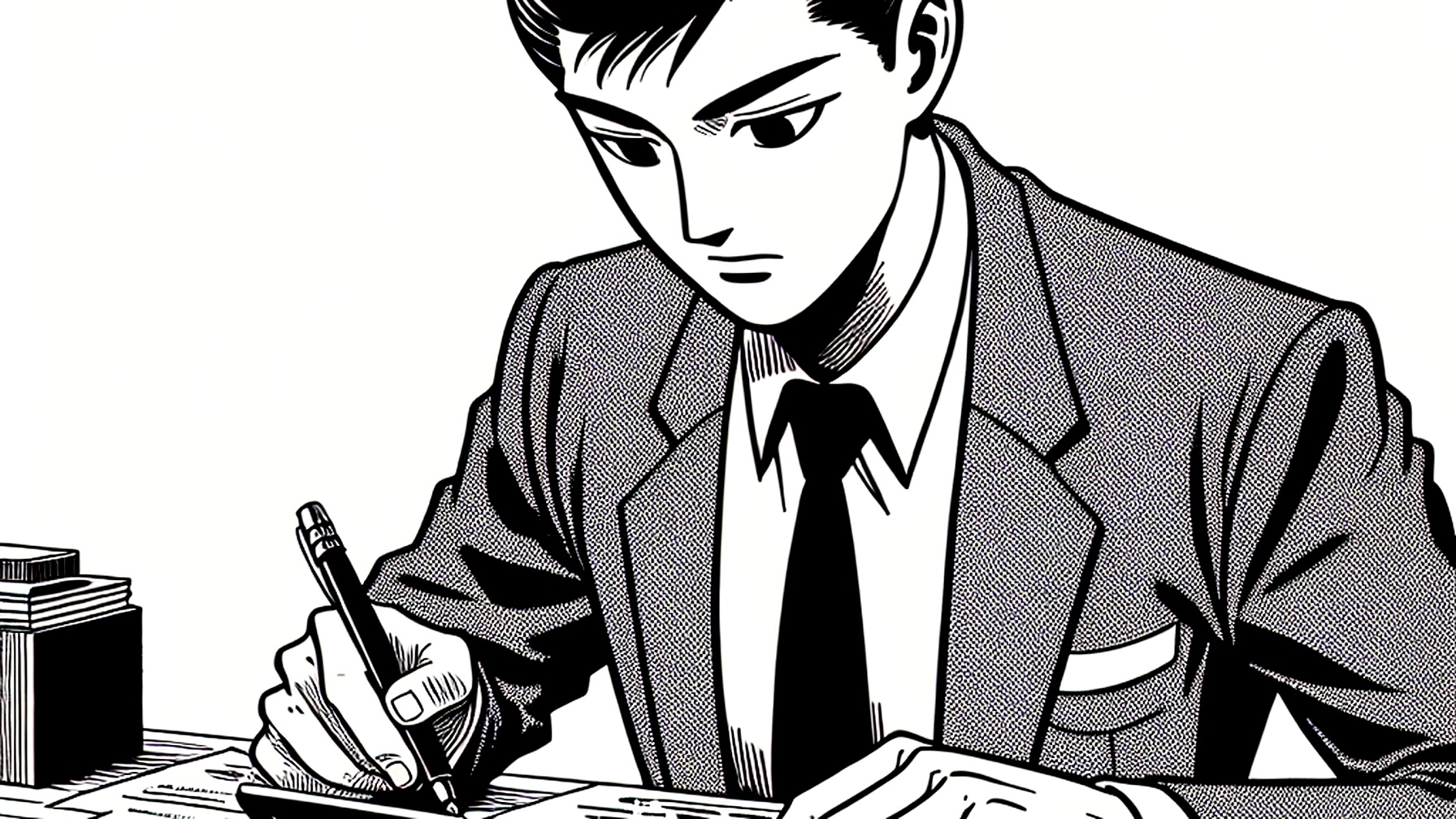
まず押さえておきたいのは、収支計算が単なる足し算引き算ではない点です。国土交通省の「2025年版不動産投資市場調査」によると、長期で黒字を維持しているオーナーほど、購入前に複数シナリオを作成しています。つまり、表面利回りだけを見ても実態はつかめません。
そこで重要なのは「キャッシュフロー」と「損益」の違いです。キャッシュフローは手元現金の動き、損益は会計上の利益を示します。減価償却費は損益には影響しますが、実際に現金が出るわけではありません。この差を理解しないと、帳簿上は黒字なのに資金ショートする事態を招きます。
次に覚えておくべき用語が「実質利回り」です。実質利回りは、家賃収入から空室損や運営費を差し引いた後の利回りを指します。日本賃貸住宅管理協会の2025年データでは、首都圏ワンルームマンションの運営費率はおおむね25%前後です。諸費用を加味し、楽観的な数字に流されないことが第一歩となります。
キャッシュフロー表の作り方と実例
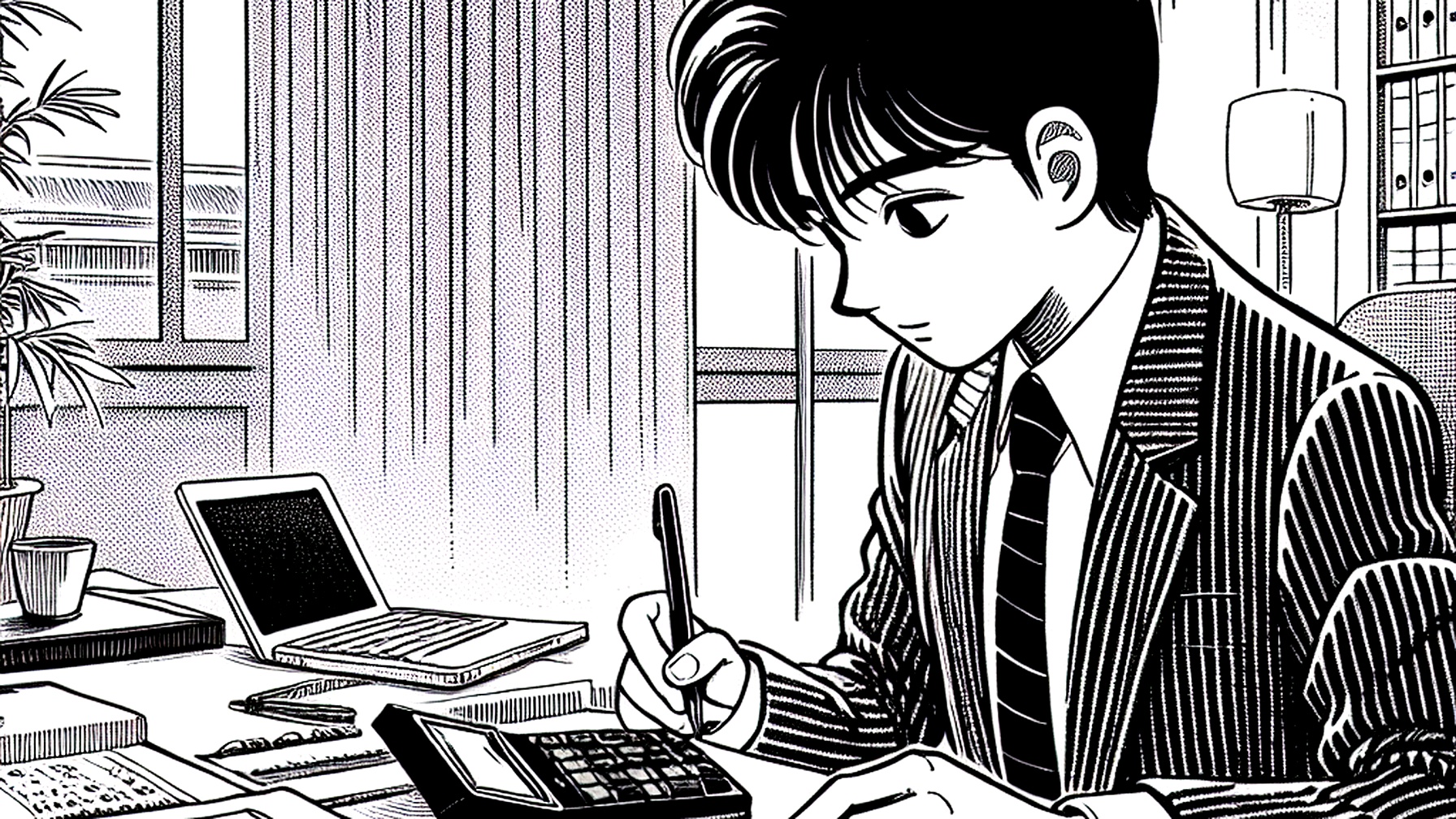
ポイントは、月次と年次の二つの時間軸でキャッシュの流れを把握することです。月次表では家賃の入金タイミングとローン返済日のずれを把握し、年次表では固定資産税など年払い費用を計上します。こうすることで一時的な赤字月を見落とさず、資金繰りを安定化できます。
具体的には、まず家賃収入から管理委託料と修繕積立金を引きます。次にローン返済額、保険料、共用部電気代などを差し引き、最終的に手元に残る金額を算出します。住宅金融支援機構の「2025年度フラット35利用者データ」によれば、35年返済で金利1.3%の場合、毎月の返済額は借入1000万円あたり約3万円です。この数字を基準に、自分の借入額で置き換えるとキャッシュフローが具体化します。
実例として、購入価格2500万円、表面利回り6%の区分マンションを想定しましょう。家賃年間150万円から運営費30万円を差し引くと実質収入は120万円です。ローン返済が年間108万円だとすると、年間キャッシュフローは12万円になります。この段階でプラスでも、修繕が発生すると即座に赤字化するため、別途年間10万円以上の予備費を確保する必要があります。
想定外に備えるシミュレーション設定
実は、想定外に備えるかどうかで投資の成否が大きく分かれます。総務省統計局の「住宅・土地統計調査」では、全国平均の空室率は2023年時点で13.8%ですが、地方では20%を超える市区も存在します。したがって、計算時は空室率15%程度を最低ラインに設定することが望ましいです。
さらに、金利上昇シナリオを組み込むことも欠かせません。日銀は2024年から段階的に金融緩和を修正し、固定金利もわずかに上がり始めました。日本政策金融公庫のデータでは、投資用ローン金利が1%上昇すると、35年返済で総返済額は約17%増えます。金利1%アップを前提にシミュレーションすることで、余剰資金の必要額が見えてきます。
ここで一度、最低限押さえるチェックポイントを整理します。
- 空室率15%
- 金利+1%
- 修繕費倍増
上記を同時に適用し、それでも年間キャッシュフローが5万円以上残るか検証しましょう。たとえ試算上は厳しくても、改善策を考えるきっかけになります。逆に、楽観シナリオしか作らないと、実際の経営で赤字転落した場合に軌道修正が困難になります。
税金と補助制度を織り込むコツ
基本的に、税金はキャッシュアウトとして扱います。固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税され、都市計画税と合わせて評価額の1.4%前後です。納付時期が4分割されるため、資金繰りの山を平準化しやすい反面、うっかり支払い忘れると延滞金が発生します。
また、2025年度は「住宅省エネ改修促進税制」が継続中です。一定の断熱性能向上工事を行うと、所得税から最大25万円が控除されます。この制度は2026年末工事完了分まで有効と発表されています。賃貸物件に適用できれば、改修費の回収期間を短縮できるため、収支計算に反映しておくと有利です。
一方、消費税の還付を狙った新築一棟投資には注意が必要です。国税庁は2024年に還付要件を厳格化し、形式的なスキームは認めない方針を示しました。つまり、税務調査で否認されるリスクまでシミュレーションに入れる必要があります。専門家へ相談料を計上しても、将来の税務リスクを軽減できるなら長期的にはプラスです。
収支計算を経営に活かすチェックポイント
重要なのは、収支計算を一度作ったら終わりにしない姿勢です。物件取得後は、少なくとも年に一度は実績値と試算値を比較し、差異があれば原因を分析します。たとえば管理費の上昇が原因なら、管理会社に見直しを交渉するか、別会社に切り替える選択肢も検討できます。
また、修繕積立の進捗を確認し、予定よりコストが膨らみそうなら追加積立や資金調達を前倒しで考えます。東京都都市整備局の「マンション修繕積立金ガイドライン2024」では、築20年時点の修繕積立金は平均月額250円/㎡と示されています。この数字より低い場合、将来の大規模修繕で一時金徴収が必要になるかもしれません。
最後に、複数物件を保有する場合はポートフォリオ全体で収支を管理します。高利回りでもリスクの高い地方物件と、利回りは低いが安定した都心物件を組み合わせることで、全体のキャッシュフローを平準化できます。こうした視点で定期的にシミュレーションを更新することが、長期安定経営への近道となります。
まとめ
この記事では「収支計算 進め方」を中心に、キャッシュフロー表の作成からシミュレーションの要点、税制や補助制度の織り込み方まで解説しました。大切なのは、楽観と悲観の両方のシナリオを作り、数字を定期的に見直す習慣を持つことです。自分で計算できるようになれば、物件選びや融資交渉で有利に立てます。今日から試算表を作成し、数字に強い投資家への第一歩を踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本賃貸住宅管理協会 2025年業界統計 – https://www.jpm.jp/
- 住宅金融支援機構 フラット35利用者データ2025年度 – https://www.jhf.go.jp/
- 日本政策金融公庫 2025年度中小企業金融資料 – https://www.jfc.go.jp/
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp/
- 東京都都市整備局 マンション修繕積立金ガイドライン2024 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 国税庁 消費税還付制度の見直し2024 – https://www.nta.go.jp/

