空室が続いたら返済は大丈夫か、管理費が上がったら赤字になるのではないか──マンション投資を考え始めたとき、多くの人がこうした不安を抱きます。特に「マンション投資 実質利回り どこで」と検索する方は、表面利回りでは判断できないリアルな手取り額を知りたいはずです。本記事では、実質利回りの計算方法からエリア別の目安、融資や税金まで、2025年9月時点の最新データを交えながら解説します。読めば、数字の裏側にあるリスクとチャンスを自分で読み解けるようになります。
実質利回りが示す本当の収益力
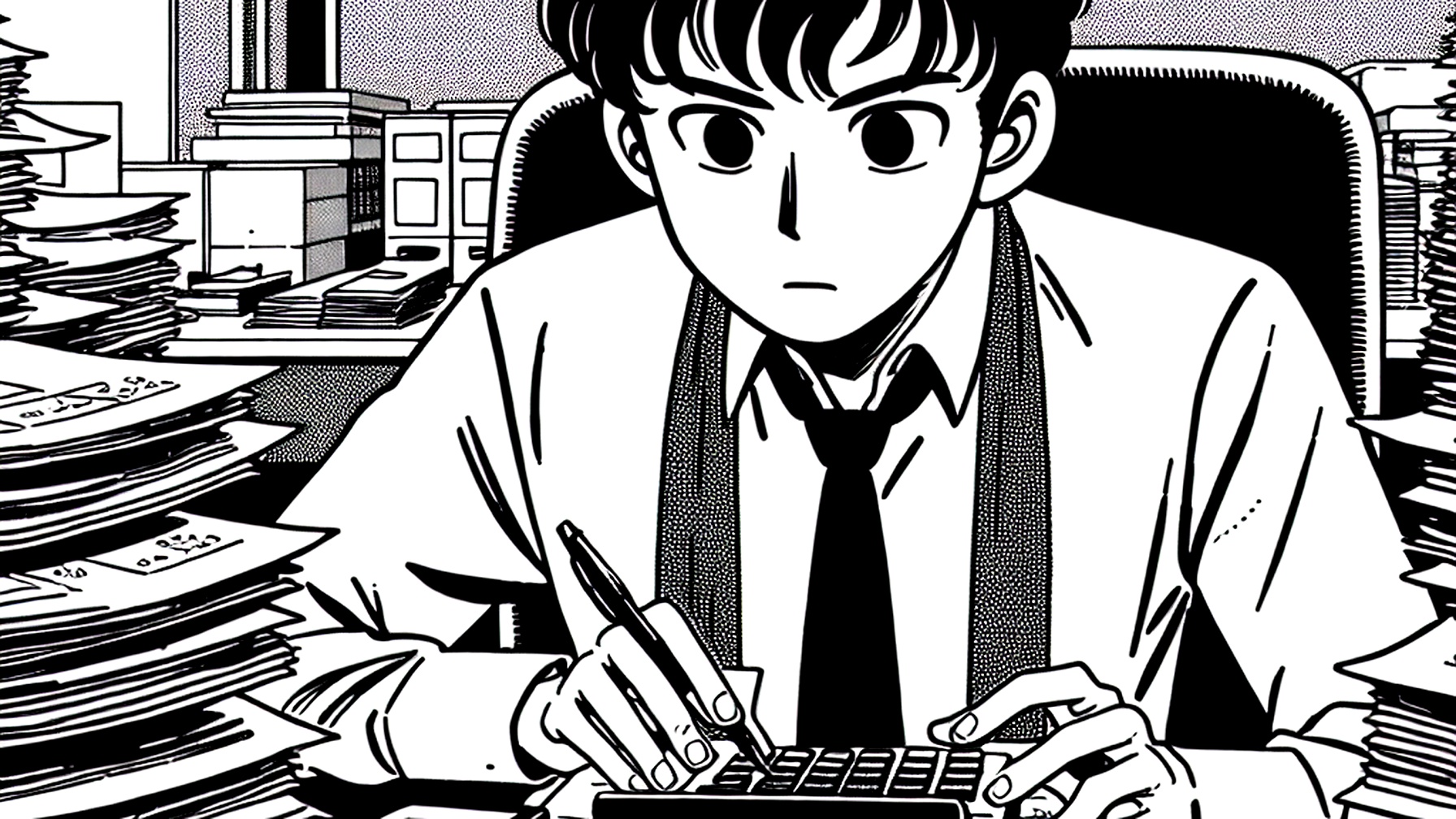
重要なのは、表面利回りと実質利回りの差を正確につかむことです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標ですが、実質利回りは管理費・修繕積立金・固定資産税などを差し引いた後の手取り額で計算します。
まず、都心ワンルームの例を見てみましょう。東京23区内で価格2,500万円、年家賃収入105万円の物件は、表面利回り4.2%となります。しかし管理費と積立金が月1.5万円、固定資産税が年10万円、入退去に伴う原状回復費を年平均4万円と仮定すると年間支出は32万円です。差し引き家賃手取りは73万円となり、実質利回りはおよそ2.9%に下がります。
この差は小さく見えても、30年間で約390万円の手取り差を生みます。また、家賃下落や空室が重なるとさらに利回りは縮小します。つまり実質利回りを正しく把握しないと、キャッシュフローが赤字になるリスクを見落としてしまうのです。
一方で、実質利回りが低くても長期的に資産価値が上がる物件なら選択肢になります。実質利回りはあくまでフローの指標であり、ストック価値とのバランスで判断する視点が欠かせません。
エリア選定の基本は人口動態と賃料水準
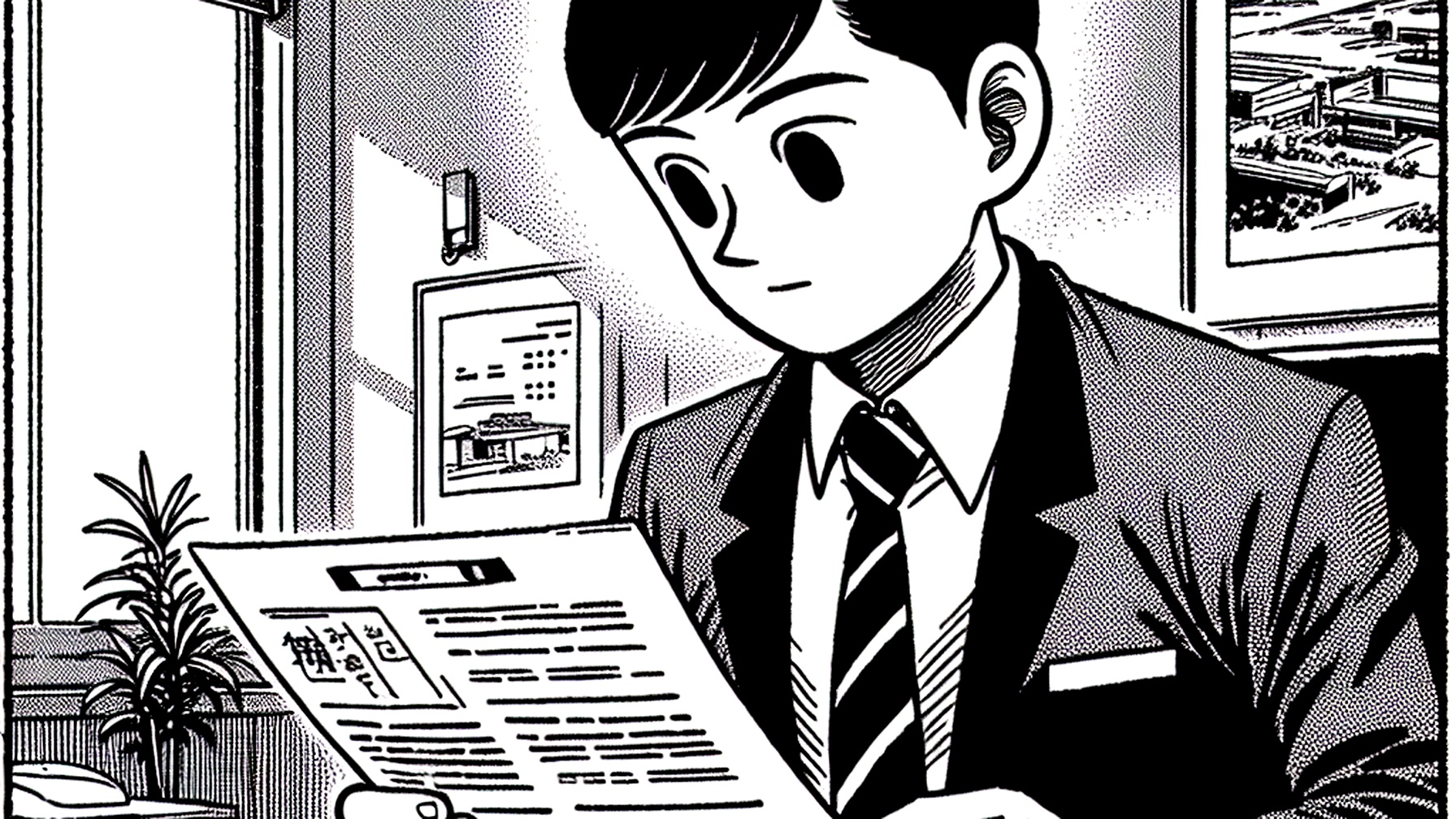
まず押さえておきたいのは、利回りの源泉が「賃料水準×稼働率」であることです。総務省の住民基本台帳によると、2024年から2025年にかけて東京23区の人口は微増を維持していますが、県全体で見ると埼玉や千葉の一部エリアは横ばいに転じています。この小さな変化が将来の稼働率を左右します。
たとえば東京23区の単身世帯比率は約52%で、ワンルーム需要が底堅いことが分かります。一方、郊外の駅徒歩20分圏では家賃2万円台の競合物件が増え、新築でも家賃を上げにくい状況です。つまり人口動態が安定し、賃料が高水準で推移しているエリアほど実質利回りが読みやすくなります。
実は自治体の都市計画も重要な手掛かりです。再開発エリアは一時的に供給が増え表面利回りが下がる傾向がありますが、完成後は地価上昇とともに賃料が改善するケースが多いです。東京都心の湾岸部が典型例で、2020年の大型再開発から5年で平均賃料が約12%伸びました。
ただし、利回りだけを追うと地方の高利回り物件に目を奪われがちです。日本不動産研究所の2025年調査では、札幌中心部のワンルーム平均表面利回りは5.6%と東京を上回ります。しかし空室期間が長いと実質利回りは一気に低下します。エリア選定では家賃水準と稼働率の安定度をセットで検証することが欠かせません。
物件タイプ別に変わる利回りの落とし穴
ポイントは、同じエリアでも物件タイプが違えば実質利回りが大きく変わる点にあります。ワンルーム、ファミリータイプ、アパートでは、取得価格と支出の構造が異なるからです。
ワンルームは価格が抑えやすく流動性も高い一方、管理費と積立金の割合が大きく、実質利回りが目減りしやすい特徴があります。東京23区での平均表面利回り4.2%に対し、実質利回りは2.5%前後に落ち着くケースが多いです。
ファミリータイプは表面利回りが3.8%と低めですが、入退去回数が少ないため原状回復費を抑えやすいメリットがあります。さらに家賃減額交渉を受けにくく、長期入居が前提になりやすいことから、実質利回りは3%台を保ちやすいです。ただし価格帯が高い分、自己資金と融資枠の確保が課題になります。
アパートは木造2階建てが中心で表面利回り5.1%と高水準ですが、修繕費と減価償却費が大きい点に注意が必要です。屋根や外壁の改修で一度に数百万円の費用が発生するため、実質利回りが2%台に下がるケースも珍しくありません。また耐用年数が短いため、金融機関が融資期間を抑える傾向があり、返済比率が上がりやすいデメリットがあります。
これらの違いを踏まえると、投資初心者はワンルームで始めてファミリータイプへ広げる、あるいはアパートを選ぶなら長期修繕計画を詳細に立てるなど、タイプごとに戦略を変えることが現実的です。
融資条件と税金が左右するキャッシュフロー
実は、実質利回りを確定させる最終要因は融資と税金です。金融機関の金利が0.3%変わるだけで手取りが年間10万円以上動く場合もあります。現在、都市銀行の投資用住宅ローンは変動0.95%前後、地方銀行は1.3%前後が目安です。固定金利はやや高く1.7%程度ですが、長期の金利上昇リスクをヘッジできます。
また2025年度まで継続が決定している「住宅貸付事業用減価償却特例」は、築22年以上の木造アパートを取得した場合、耐用年数を短縮して償却できる制度です。これにより購入初年度の課税所得を圧縮し、実質利回りを高める効果が期待できます。ただし適用期限が2026年3月と明記されているため、投資スケジュールを逆算する必要があります。
一方で、固定資産税は築年数によって評価額が下がるため、築古物件では税負担が軽くなる傾向があります。しかし耐用年数を過ぎて融資期間が短いと、返済圧力が大きく実質利回りを圧迫します。つまり、税メリットと融資条件のバランスを取ることがキャッシュフロー改善のカギです。
さらに、管理会社への支払手数料や保険料など、経費として計上できる項目を漏れなく把握することで実質利回りを底上げできます。経費計上の基準は国税庁の通達が年々細かくなる傾向にあるため、税理士と連携して最新の扱いを確認することが不可欠です。
まとめ
ここまで、実質利回りを高めるための視点をエリア、物件タイプ、融資・税制の三つに分けて見てきました。数字を読むうえで最も大切なのは、表面利回りでは見えない支出を具体的に洗い出し、将来シミュレーションを保守的に組むことです。そして人口動態や賃料水準が安定したエリアで、自分の資金計画に合った物件タイプを選択し、融資と税制を組み合わせてキャッシュフローを最適化する。この手順を踏めば、初心者でも実質利回り3%以上の安定運用は十分に狙えます。まずは試算表を作成し、今日紹介したポイントを一つずつ当てはめてみてください。行動を起こすことで、不確実だった投資の輪郭がはっきりと見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp/
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得 – https://www.nta.go.jp/
- 国土交通省 都市計画現況調査 – https://www.mlit.go.jp/

