親から受け継いだマンションやアパートをどう守り、次世代へ円滑に渡せるか。税負担を抑えつつ資産価値を維持したいという悩みは、多くのオーナーに共通します。本記事では、中古物件を活用した相続対策の考え方と実践ステップを、2025年9月時点の税制と市場データに基づいて解説します。読み終える頃には、自分に合った戦略を見極め、すぐに行動へ移せる具体的なヒントが得られるはずです。
相続対策で中古物件が選ばれる背景
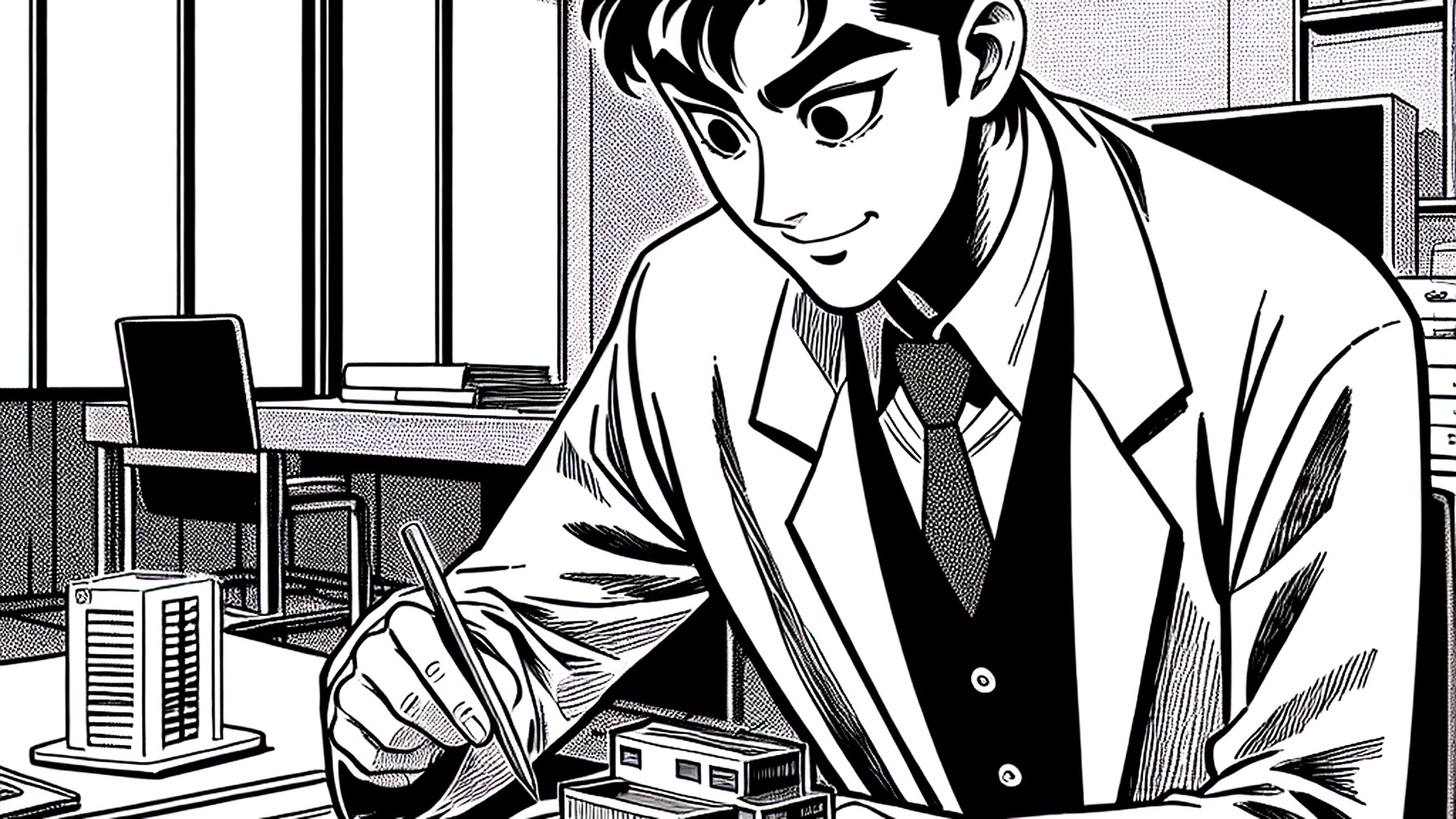
重要なのは、中古物件が「評価額を抑えつつ収益を得られる資産」として機能する点です。新築より安価に取得できるだけでなく、相続税評価額も低くなる傾向があるため、節税と収益確保を同時に狙えます。
まず、国税庁の路線価は実勢価格の八割程度が目安とされています。実勢価格が抑えられる中古住宅は、その分だけ相続税評価も低くなりやすいのです。さらに、賃貸に出せば家賃収入が得られるため、納税資金を物件自体で生み出せるメリットがあります。一方で、築年数が古くなるほど修繕費が増えるため、キャッシュフローとのバランスを見極める必要があります。
次に、2025年現在の中古市場は空き家対策や環境配慮の流れを受け、リノベーション需要が高まっています。国土交通省のデータでも、中古住宅成約件数は直近五年間で一五%増加しました。需要が底堅いことで出口リスクが抑えられ、相続後に売却や他の用途へ転用しやすい点も魅力です。
つまり、中古物件は節税効果と運用柔軟性を兼ね備えた選択肢となります。ただし、立地や建物状態によっては空室リスクが高まるため、収益計画を保守的に立てることが欠かせません。
相続税評価額とキャッシュフローの仕組み
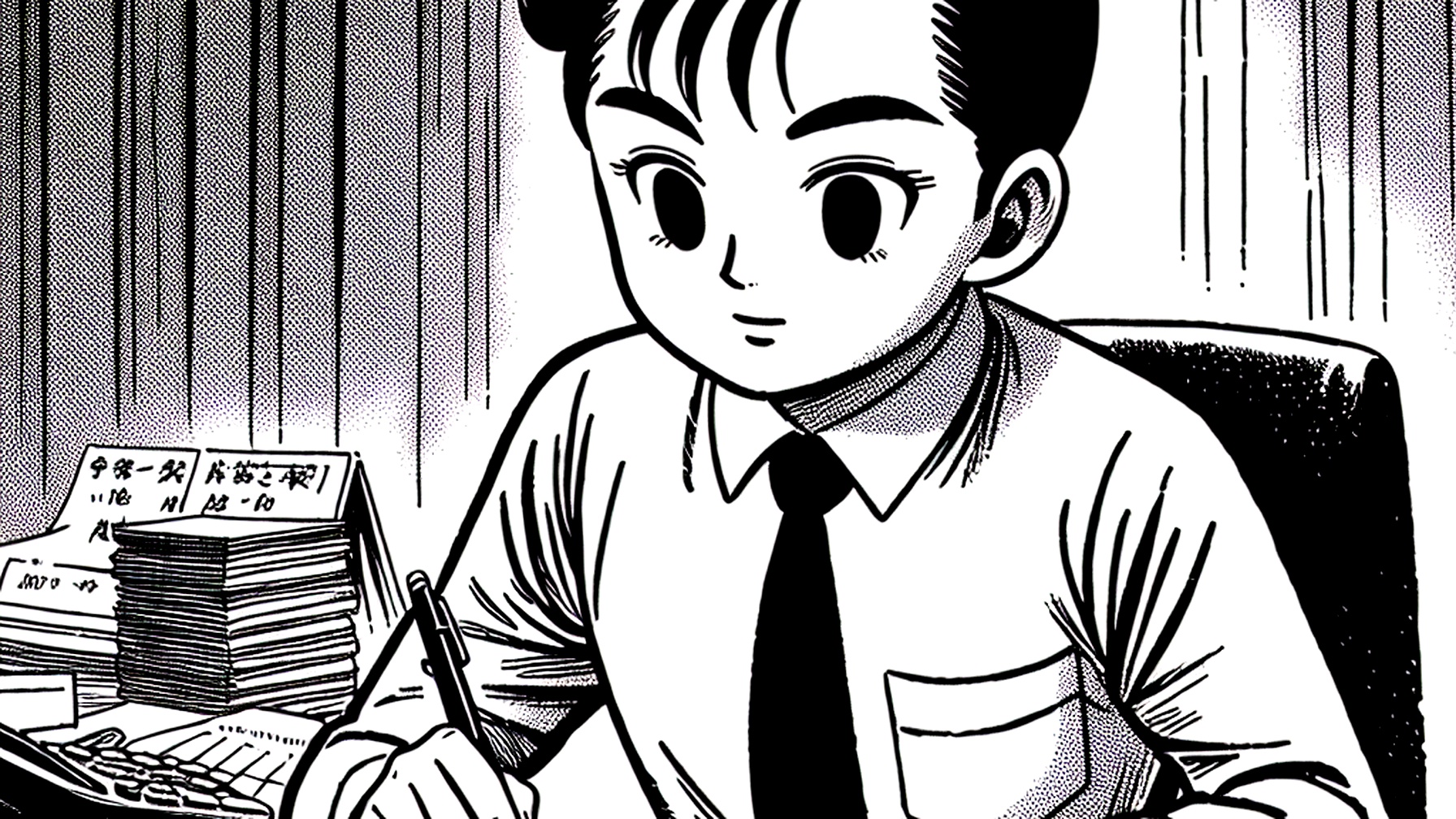
まず押さえておきたいのは「相続税評価額を下げ、同時に現金収入を生む」という二面作戦です。土地と建物は評価方法が異なるため、それぞれの仕組みを理解することが第一歩になります。
土地の評価は路線価方式が基本で、市場価格より低く算定される傾向があります。さらに、賃貸中の土地は「貸宅地」として借地権割合を控除でき、評価額が二〜四割下がるケースも珍しくありません。建物は固定資産税評価額を基準とし、築年数が経過するほど減価償却が進むため、新築より評価額が小さくなります。中古 相続対策で収益物件を取得する際は、この減価効果を最大限に活用できます。
一方、キャッシュフローは家賃収入からローン返済と運営費を差し引いて算出します。重要なのは、表面利回りではなく実質利回りで検討することです。たとえば年間家賃300万円、運営費が三割、ローン返済が年間120万円の場合、手取りは約90万円です。相続税の納税資金を十年で貯めるには、手取りが年間100万円程度欲しいため、利回り改善や自己資金投入の調整が必要になります。
また、金融機関は収益還元法で融資額を判断します。家賃下落や空室率上昇を見越し、金利上昇二%、空室率二〇%でも資金繰りが破綻しないかシミュレーションすることが安全策です。こうした保守的な計画が、相続後のトラブル回避につながります。
物件選びとリフォーム戦略のポイント
実は、物件選びの時点で相続後の出口戦略が八割決まります。築古だからこそリフォームで価値を高める視点が欠かせません。
まず立地です。総務省の将来人口推計によれば、2025年以降も都市部への人口集中は続くと予測されています。駅徒歩十分圏や大学、病院などの需要源に近いエリアは、築二五年以上でも入居需要が安定しています。一方で郊外のバス便エリアでは人口減少が進み、空室期間が長期化しやすいので注意が必要です。
次に建物状態です。構造躯体に問題がなければ、内装と設備を刷新するだけで家賃を一〜二割上げられる場合があります。2025年度の国土交通省「長期優良住宅リフォーム推進事業」は、耐震補強や断熱改修を行うと最大100万円の補助を受けられます(予算上限に達し次第終了)。補助金を活用すれば、自己資金を抑えながら競争力を高められるのです。
さらに、リフォーム内容は節税にも直結します。工事費のうち資本的支出は減価償却となり、毎年の所得税を圧縮できます。修繕費として一括計上できるか、資本的支出として複数年で償却するかは税理士と相談し、キャッシュフローを最適化しましょう。
2025年度の税制優遇をどう活用するか
ポイントは、現行制度をフル活用して税負担を軽減しつつ、家族への承継をスムーズに行うことです。主な制度と活用法を整理します。
2025年度も「小規模宅地等の特例」は継続しており、賃貸経営を行う土地は面積200㎡までの部分について最大50%評価減を受けられます。この特例は賃貸経営を継続することが条件なので、空室が続くと適用が難しくなります。物件取得前から長期運営計画を立てることが欠かせません。
また、2023年改正で拡充された「相続時精算課税制度」の110万円基礎控除は2025年も有効です。これを利用して親から子への資金移動を進め、早期に中古物件を購入して運営実績を積む方法もあります。早く始めるほど、収益と減価償却による節税効果を長く享受できます。
住宅ローン控除は原則自宅取得向けですが、相続対策としては「親子リレーローン」が活用できます。子が返済を引き継ぐ前提であれば、親の存命中から資産を共有し、贈与税の負担を抑えながら運用ノウハウを伝授できるのが利点です。もっとも、共有名義はトラブルのもとになりやすいため、遺言や家族会議で取り決めを明確にしておくと安心です。
家族信託と法人化を組み合わせる実践例
まず押さえておきたいのは、家族信託と不動産管理法人を併用すると、管理の手間と税負担を大幅に軽減できる点です。認知機能の低下などによる資産凍結リスクも避けられます。
家族信託とは、財産の名義を受託者に移し、受益権によって利益を受け取る仕組みです。親を受益者、子を受託者とすれば、親が判断能力を失っても賃貸経営は継続できます。2025年現在、信託契約そのものに特別な税制優遇はありませんが、贈与税や登録免許税が非課税になる場面があるため、司法書士と連携して設計する価値があります。
次に管理法人ですが、所得税率が高い個人より法人税率の方が低い層が多いことがポイントです。たとえば個人の最高税率45%に対し、資本金1億円以下の法人は実効税率約23%で済みます。法人で資産管理を行い、株式を贈与する形で承継すれば、将来の相続税評価額を分散させられるメリットも得られます。
さらに、家族信託で受益権を法人に帰属させるスキームを組めば、賃料収入が法人に集まり、親族への給与分配によって所得を分散できます。もっとも、制度設計を誤ると二重課税や実務負担が増えるため、税理士・司法書士・不動産会社の三者で打ち合わせを重ねることが成功への近道です。
まとめ
この記事では、中古物件を活用した相続対策の考え方と実践手順を整理しました。中古物件は取得価格と相続税評価額を同時に抑えられ、賃料収入で納税資金を確保できる点が最大の強みです。土地評価の仕組みや減価償却を理解し、リフォームと税制優遇を組み合わせれば、キャッシュフローと節税を両立できます。家族信託や法人化も視野に入れ、専門家の力を借りながら、自分と家族に合ったプランを早めに構築しましょう。行動を先延ばしにせず、今日から情報収集と物件見学を始めることで、将来の安心と家族の笑顔が手に入ります。
参考文献・出典
- 国税庁「路線価図・評価倍率表」 – https://www.rosenka.nta.go.jp
- 国土交通省「不動産市場動向調査」2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省「日本の地域別将来人口推計」2024年公表 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「長期優良住宅リフォーム推進事業」2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 財務省「2025年度税制改正の大綱」 – https://www.mof.go.jp/tax_policy
- 法務省「家族信託に関するガイドライン」2025年版 – https://www.moj.go.jp

