アパート経営に興味はあるものの、「本業が忙しくて空室対策まで手が回るだろうか」と不安に感じるサラリーマンは少なくありません。実際、国土交通省の住宅統計によれば2025年7月時点の全国アパート空室率は21.2%と依然高水準です。しかし適切な戦略を取れば、安定収入を得ながら本業との両立も十分に可能です。本記事では、サラリーマンが限られた時間で効率良く実践できる空室対策を中心に、物件選びから管理会社との連携、最新の支援制度までを詳しく解説します。最後まで読めば、忙しい日常の中でもアパート経営を成功に導く具体的なステップが見えてくるはずです。
サラリーマンがアパート経営に向く理由
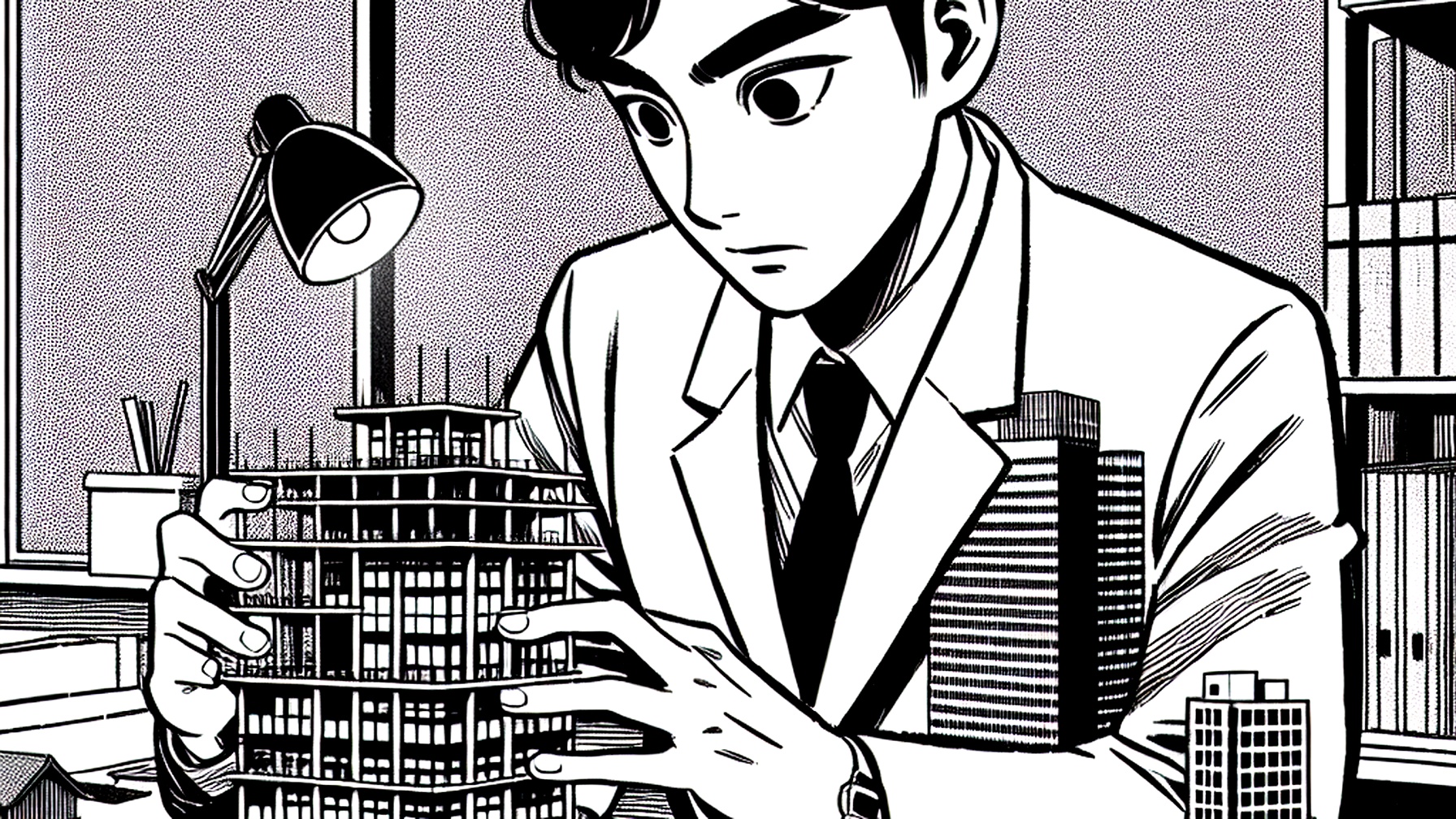
まず押さえておきたいのは、安定した給与所得が融資審査で大きな強みになる点です。金融機関は返済能力の証拠として継続的な収入を重視します。また給与天引きで住宅ローンを組む経験がある人なら、返済スケジュールや金利の考え方にも慣れているため投資判断がスムーズです。
続いて、サラリーマンは社会保険が充実しており、急な収入減にも一定のセーフティネットが働きます。これにより、多少の空室期間が生じても生活基盤が揺らぎにくいというメリットがあります。加えて、勤務先の福利厚生で提携ローンが優遇されるケースもあるため、金利差が長期収益に与える影響を抑えられる可能性があります。
一方で時間的な制約は大きな課題です。しかし近年はクラウド型管理システムの普及により、入居者対応や家賃確認をスマホで完結させる仕組みが整っています。つまり本業への影響を最小限にしつつ、データをもとに迅速な空室対策が取れる環境が整ってきたと言えるでしょう。
重要なのは、自分が「時間をかける業務」と「外部に委託する業務」を明確に線引きすることです。例えば物件選定やリフォーム方針など収益に直結する判断は自身で行い、日常のクレーム対応は管理会社に任せるといった分業が理にかないます。このように強みを生かし弱点を補う体制が、サラリーマン投資家の成功を後押しします。
空室を生まない物件選びの視点
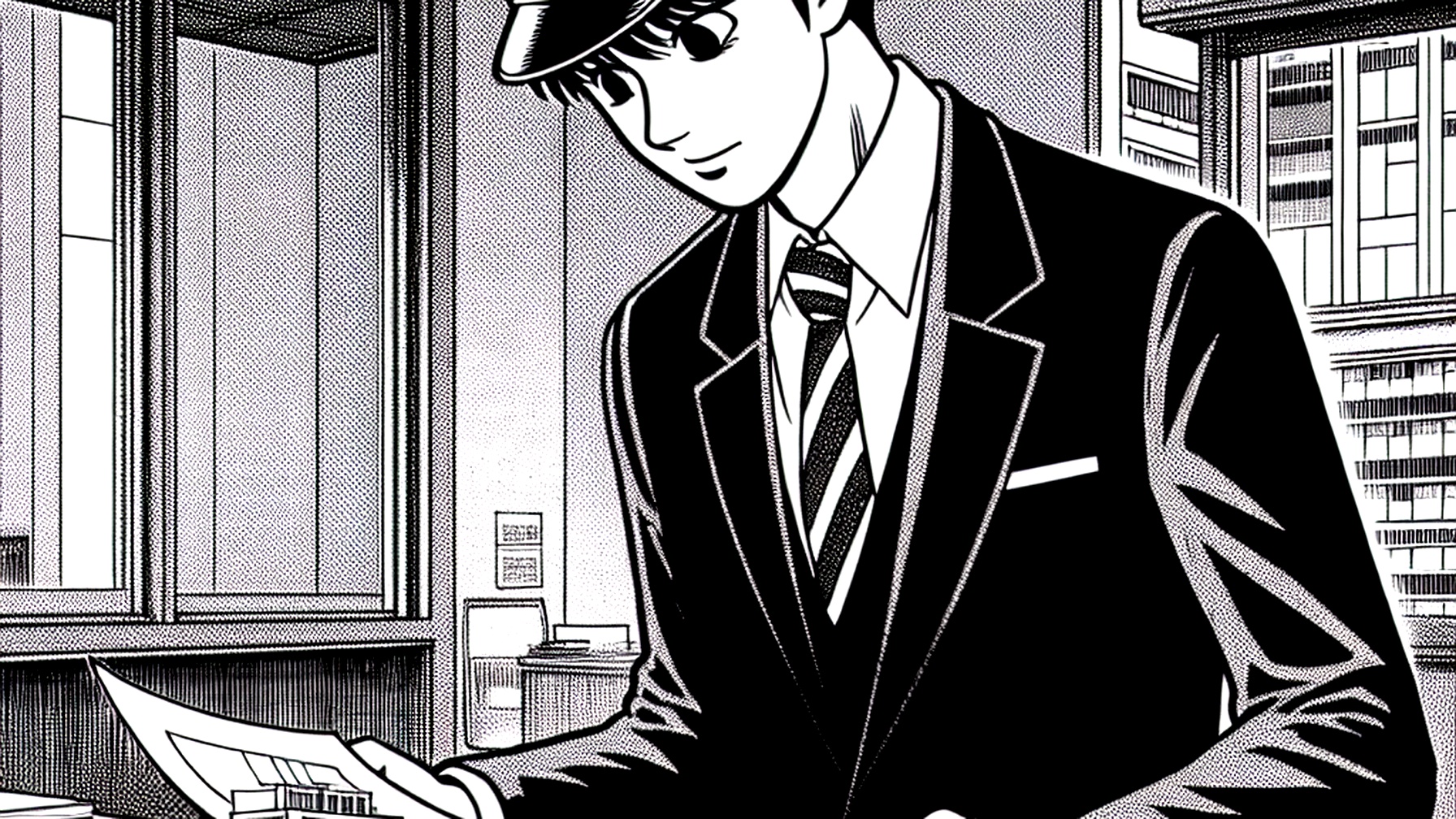
ポイントは、将来の需要を数値で確かめながら購入エリアを絞り込むことです。通勤利便性や周辺施設のみならず、自治体の人口推移や開発計画まで総合的に見る姿勢が欠かせません。
まず人口動態を確認する際は、国立社会保障・人口問題研究所が公開する「日本の地域別将来推計人口」が役立ちます。ここで2035年時点まで世代別の人口推移を把握し、若年層が維持される市区町村に的を絞れば、単身向けアパートの安定需要が見込めます。また、駅から徒歩10分圏内という従来の鉄則にとらわれ過ぎず、自転車利用前提で15分圏内まで許容すると、割安な土地でも競争力を保てるケースがあります。
次に、築年数とリノベーション費用のバランスを考える必要があります。新築は空室リスクが低い反面、表面利回りが5%台にとどまる例も多いです。築25年でも構造がしっかりした物件を500万円かけて再生し、家賃を相場より10%下げる戦略なら、実質利回り8%超が狙えることがあります。つまり取得価格とリフォーム費用の総額で戦略を組む視点が重要です。
さらに、競合先の空室率チェックも欠かせません。物件半径500m以内のアパートを実地で見学し、夕方にバルコニーの洗濯物の有無を確認すると居住率を肌感覚でつかめます。ウェブ掲載数と現地の実態がかけ離れている場合、管理会社の募集姿勢に問題がある可能性も浮かび上がります。こうしたフィールドワークは休日にまとめて行い、短時間で効率的に情報を集めると、本業と両立しやすくなります。
入居者が長く住む賃料設定とサービス
実は、家賃をただ下げるだけでは空室対策になりません。相場より5000円下げても長期入居につながらなければ収益は悪化します。大切なのは「総支払額の納得感」を高めることです。
まず賃料査定は、SUUMOやLIFULL HOME’Sの募集データを使い、築年数や階数が近い5件の平均を出す方法が簡便です。その平均から1000円高い設定でも、Wi-Fi無料やスマートロック導入など付加価値を付ければ選ばれる余地があります。特に20代単身者は月2000円程度の通信費が浮くメリットを重視するため、無料インターネットは入居促進効果が高い施策です。
また、初期費用のハードルを下げる工夫も有効です。敷金ゼロ・礼金ゼロは競合が増えたものの、クリーニング費を定額精算にする、火災保険を自社指定で安く抑えるといった微調整で差別化できます。国土交通省の調査では、礼金ゼロ物件の平均入居期間は1.8年長い傾向があると示されています。つまりオーナーが一次的に負担を増やしても、中長期的な空室削減効果で回収できる図式です。
加えて、入居後の快適性を高める小規模リフォームも検討しましょう。たとえば、築30年の和室を6畳分フローリング化する費用は約15万円ですが、視覚的な古さを払拭できるため退去率を低減します。さらにLED照明と人感センサーを共用部に設置すると、電気代の削減と防犯性向上を同時に実現でき、入居者の満足度を引き上げます。
最後に、口コミ対策として入居者アンケートを実施し、対応要望を月内に処理する仕組みを整えると満足度が定量化されます。ポジティブなコメントはSNSやポータルサイトの「オーナーからのメッセージ」で公開し、物件イメージを底上げしましょう。こうした一連のサービス強化が、家賃の安易な値下げに頼らない持続的な空室対策となります。
賃貸管理会社との協働で差をつける
基本的に、サラリーマン投資家は管理会社の力量で成果が左右されると言っても過言ではありません。選定の際は、管理戸数より「1人当たり担当戸数」に注目すると、担当者が物件にかける時間を推測できます。
まず面談時に、空室が出た場合の広告媒体と反響件数の平均を確認しましょう。SUUMO掲載後1週間で問い合わせ5件以上が目安です。加えて、AI価格査定ツールを導入している会社は、募集家賃の調整にスピード感があります。忙しいオーナーほど、このようなデータドリブンな企業と組むことで時間を節約できるのです。
一方で、運営コストも見逃せません。管理手数料は5%が相場ですが、家賃保証付きプランでは10%を超える場合があります。保証料が高くても空室期間ゼロを確保できるなら、長期で見ると手取りは安定します。ここでも自分のリスク許容度を基準に選択することが肝要です。
協働効果を高めるには、物件の魅力をオーナー自ら発信する姿勢も重要です。例えば、周辺の飲食店情報をまとめたリーフレットを作成し、内見時に配布してもらうと入居率が3%向上した事例があります。担当者は営業トークに利用でき、物件の内覧時間が延びるため成約率を底上げする効果があります。
最後に、月次レポートのフォーマットをこちらから提示し、家賃滞納率やクレーム件数を共有してもらいましょう。数字で成果を確認することで改善点が明確になり、次の空室対策を迅速に打てます。このPDCAサイクルを管理会社と共有することが、限られた時間でも最大の成果を生むカギとなります。
2025年度に活用できる支援制度と節税策
重要なのは、実際に利用できる制度を確実に押さえておくことです。2025年度にアパート経営者が活用可能な代表的制度は「住宅省エネ改修補助金(中小賃貸オーナー型)」と「小規模宅地等の特例」による相続税評価減です。
まず住宅省エネ改修補助金は、賃貸アパートでも外壁断熱や高効率給湯器の導入費用のうち最大200万円が助成対象となります。受付は2025年4月から2026年2月までですが、予算枠に達し次第終了するため早めの申請が必要です。断熱性能を上げると光熱費が下がり、物件広告でも「光熱費が抑えられる」と訴求できるため空室対策と直結します。
次に、サラリーマン投資家が見落としがちな制度が「小規模宅地等の特例」です。被相続人が所有する賃貸用不動産は条件を満たせば土地評価額が50%減額されます。将来的な相続を見据えて法人化を検討する場合でも、この特例の適用条件を踏まえた役員報酬設定や持株比率を事前に設計すると節税効果を最大化できます。
さらに、所得税対策として2025年度も継続する「損益通算制度」は健在です。減価償却費を活用して不動産所得を赤字にし、給与所得と相殺することで税負担を軽減できます。ただし過大な赤字計上は税務調査のリスクを高めるため、耐用年数短縮や一括償却資産の計上は税理士と相談しながら慎重に進める必要があります。
最後に、地方自治体が実施するリフォーム補助を併用すると、自己負担をさらに減らせます。例えば、東京都多摩市では2025年度も「空き家・空室対策リノベ補助」が継続し、上限50万円の補助が受けられます。自治体独自の補助は募集開始が春先に集中するため、年始に情報収集してスケジュールに組み込むと資金計画が立てやすくなります。
まとめ
空室リスクが高止まりする今でも、サラリーマンの強みを生かせばアパート経営は十分に成立します。ポイントは需要のあるエリア選定、付加価値による家賃戦略、管理会社との協働体制、そして2025年度に実際に使える補助金や税制を的確に活用することです。まずは休日に物件周辺を歩き、管理会社と面談する行動から始めてみてください。本業に支障をきたさずとも一歩を踏み出せば、安定収入と資産形成の両立が見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報版 – https://www.mlit.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 – https://www.ipss.go.jp
- 環境省 住宅省エネ改修補助金2025年度概要 – https://www.env.go.jp
- 総務省「土地・住宅税制のあらまし 2025」 – https://www.soumu.go.jp
- 東京都多摩市 空き家・空室対策リノベ補助 – https://www.city.tama.lg.jp

