投資先としてアパート経営が気になりつつも、「収益性が低い」「やめとけ」と耳にして二の足を踏んでいませんか。確かに利回りの計算だけで飛び込むと、空室や修繕費で想定外の赤字になるケースは珍しくありません。しかし一方で、データを基にリスクを把握し、物件と融資を丁寧に選べば堅実に利益を上げているオーナーもいます。本記事では「なぜ失敗が語られやすいのか」という背景から、収益性の決まり方、2025年度の最新制度までを分かりやすく解説します。読み終えるころには、自分に向いているかどうかを判断できる軸が手に入るはずです。
アパート経営が「やめとけ」と言われる背景
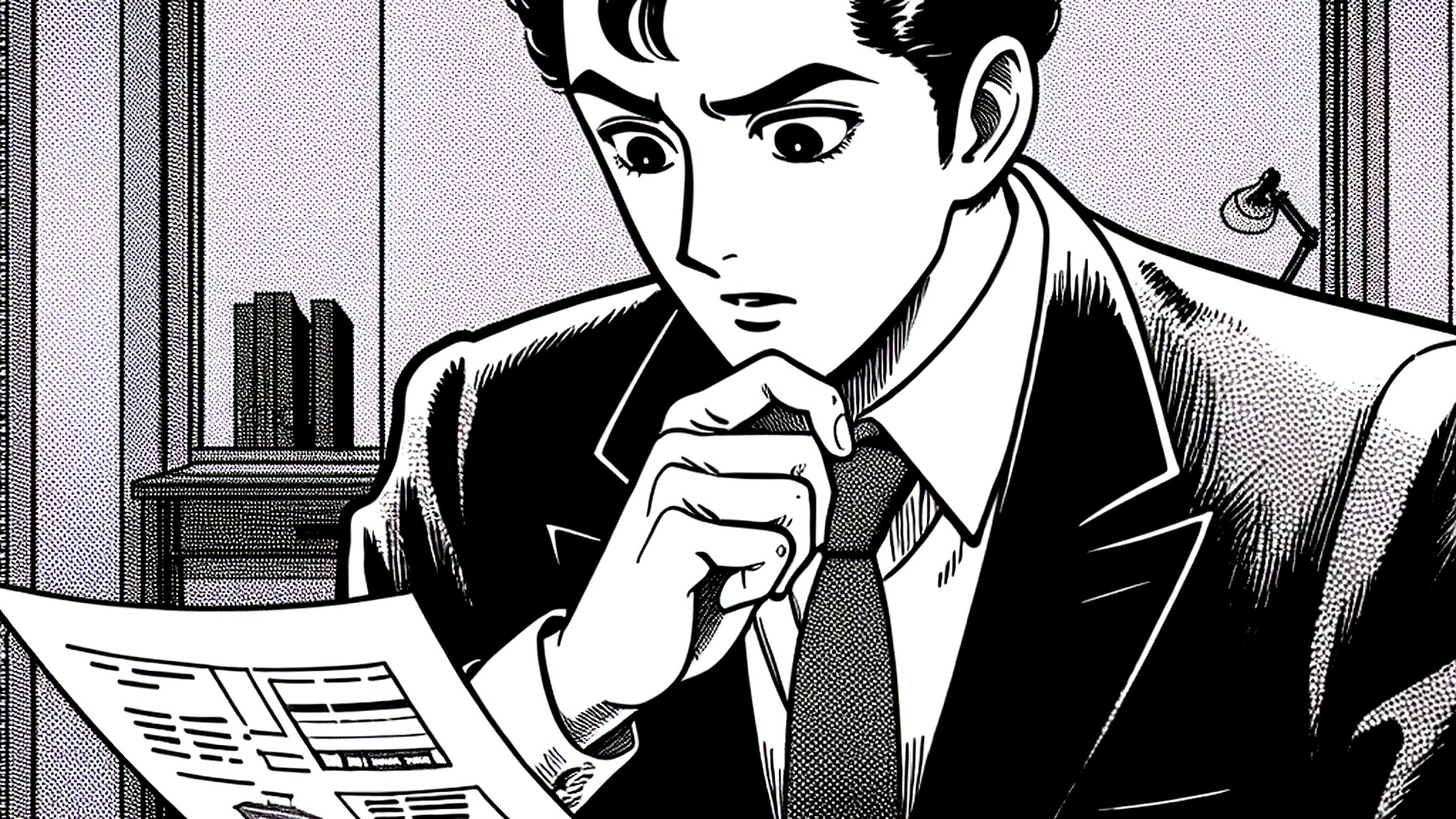
重要なのは、ネガティブな声の多くが事実と誇張の両方を含んでいる点です。国土交通省の住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で、確かに高水準が続いています。また、築20年以上の木造アパートでは修繕費が年間家賃収入の15%前後に達する例もあります。こうした数字だけを見ると、「儲からない」と結論づけたくなるでしょう。
しかし視点を変えると、空室率が下がりつつある地域や、修繕費を抑えられる鉄骨造の新築案件も存在します。つまり平均値はあくまで全国の“ざっくりした”リスクであり、個別物件に落とし込むと上下の振れ幅が大きいのです。加えて、情報発信の多くが失敗談に偏りやすいという構造もあります。人は成功より失敗を共有したくなるため、ネット検索では悲観的な記事が上位に並びやすいのです。まずはこのフィルターを意識し、「やめとけ」の背景を立体的に捉える必要があります。
収益性を左右する5つの要素
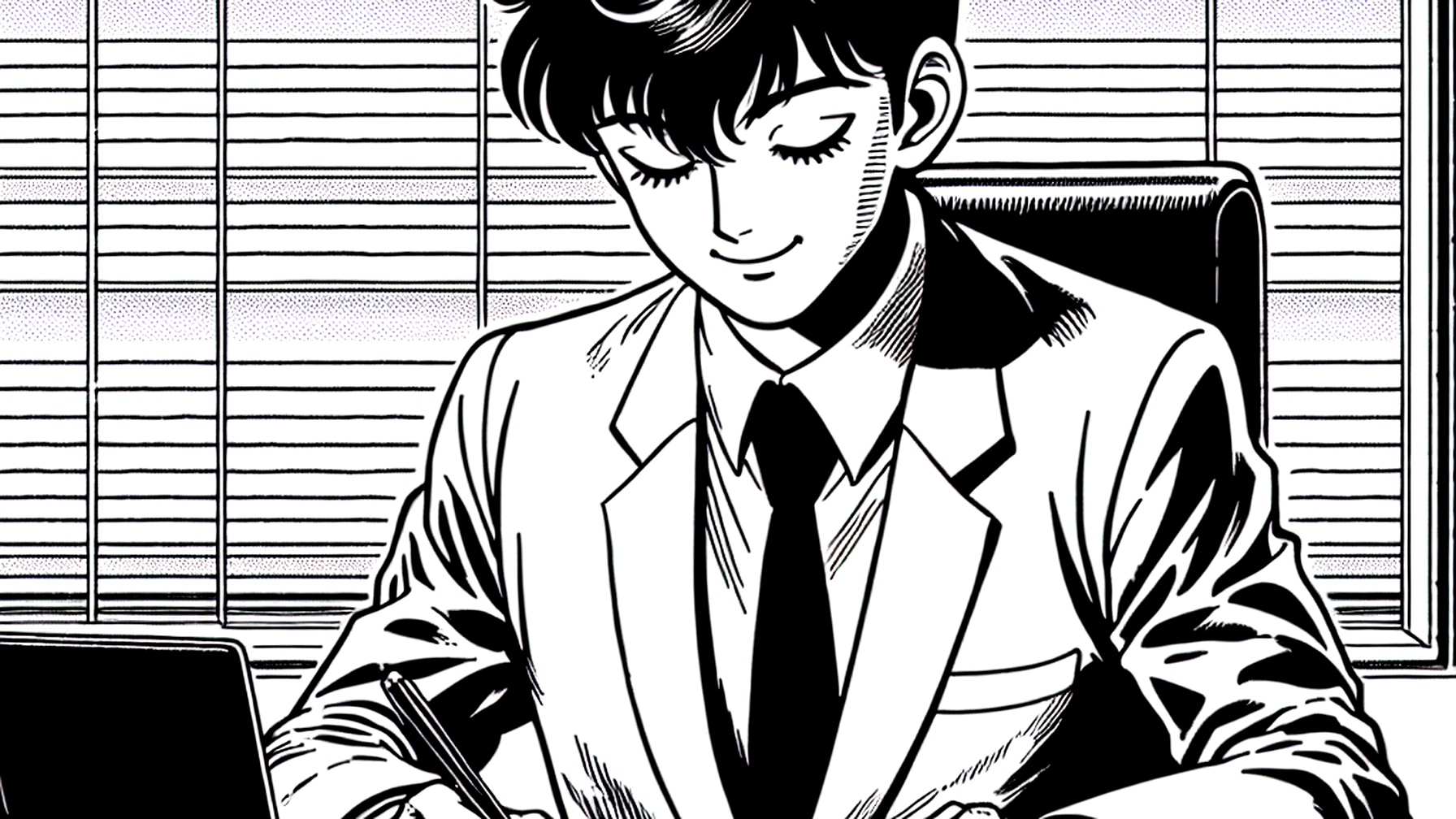
ポイントは、家賃収入だけではなく支出と税引後キャッシュフローまで把握することです。収益性を決める主な要素は①家賃水準、②空室率、③運営コスト、④金利、⑤税金の五つに集約されます。
家賃水準は立地と築年数でほぼ決まりますが、最近は省エネ性能や通信環境も影響を与えます。テレワーク需要の増加でネット無料設備を導入した物件は、同じ築年でも月3000円程度高く貸せた事例があるため、設備投資の回収シミュレーションが不可欠です。空室率は自治体の人口動態を調べれば一定の予測が可能で、東京都心のワンルーム平均稼働率は90%以上、地方郊外では70%台と差が開きます。
運営コストには管理委託料、設備更新、固定資産税が含まれます。特に修繕費は築年で跳ね上がり、築30年以降は外壁塗装や給排水管更新で一度に200万円超の出費が発生しがちです。金利は日本銀行の統計で2025年7月時点のアパートローン変動金利平均が2.3%となっており、1%上昇すれば年間返済額は2000万円借入で約20万円増える点を押さえてください。税金面では所得税と住民税のほか、法人化すれば税率を抑えられますが設立費用と事務負担が増えるため、損益分岐点を明確にすることが大切です。
実際のキャッシュフローを数字でイメージする
まず押さえておきたいのは、表面利回りと手残りが大きく異なる現実です。例として、首都圏郊外にある価格6000万円、表面利回り8%の木造アパート(満室想定家賃年480万円)を見てみましょう。空室率15%を見込むと実収入は約408万円に減少します。ここから管理委託料5%、修繕費10%、固定資産税35万円を差し引くと運営純収益(NOI)は約306万円となります。
次に、自己資金1200万円・借入4800万円(金利2.3%、期間25年)の返済額は年約249万円です。この時点で税引前キャッシュフローは57万円しか残りません。さらに所得税・住民税を合わせて20%課税されると、手元には45万円程度しか残らず、表面利回り8%のつもりが実質利回り0.7%まで縮小します。逆に、購入価格を5500万円に下げ、ネット無料設備で家賃を月2000円アップさせれば、同じ条件で税引後キャッシュフローは年100万円近くに改善する試算も可能です。数字を通じて「購入価格の1割交渉がどれほど大きいか」を肌感覚で理解しておくことが、失敗を遠ざける第一歩になります。
2025年度の融資・税制は味方になるか
実は、2025年度の制度を上手に活用すると収益性を底上げできます。まず融資面では、金融庁の指導によりフルローンが難しくなった一方、自己資金2割以上なら金利を0.3%下げる地銀の特約が増えています。金利0.3%の差は25年ローンで総返済額が約180万円変わるため、自己資金比率を高めて借入条件を引き出す戦略は有効です。
税制では、賃貸住宅の省エネ改修に対する「住宅ローン控除(投資用部分)」が2025年度も継続しています。適用条件は建物の省エネ基準適合証明を取得し、改修後6か月以内に貸し出すことです。控除額は最大65万円ですが、キャッシュフロー改善よりも改修費の早期回収に繋がる点でメリットがあります。また、小規模住宅用地の固定資産税減額措置(200㎡以下部分を1/6評価)は2025年度も延長されており、土地値が高い都市部ほどインパクトが大きいです。
一方、節税目的で注目されがちな「加速度償却スキーム」は国税庁が監視を強化しており、2025年4月の通達改正で中古木造の耐用年数見直しが厳格化されました。安易に短期償却を見込むと想定通りの節税ができず、逆に追徴課税リスクを抱える恐れがあります。制度を味方にするには、税理士と連携して適切な会計処理を行うことが欠かせません。
リスクを抑えて挑戦するためのチェックリスト
ポイントは、購入前に「想定外」を極力潰しておく姿勢に尽きます。まず、エリアの人口と世帯数を過去10年分さかのぼり、減少傾向なら別の地域を検討しましょう。次に、建物診断(インスペクション)で配管と躯体の状態を確認します。ここで発見された瑕疵は価格交渉の材料になるだけでなく、将来の修繕費を精度高く見積もる基礎にもなります。
融資交渉では2行以上に同時申込を行い、条件を比較することが金利低減の鉄則です。近年はネットバンク系が金利面で優位ですが、地方銀行はエリア限定で保証料を抑えるプランを用意することがあります。さらに、管理会社選定は「管理戸数」より「担当者一人当たりの担当戸数」に注目してください。担当物件が多すぎると、空室対策の提案が後手に回るリスクが高まります。
最後に、購入後1年目は手元資金を家賃収入の6か月分残すのが目安です。国交省調べで平均空室期間が2.8か月というデータがあるものの、退去が重なると5か月以上無収入になる例もあります。余剰資金をバッファーとして確保しておけば、急な修繕が発生しても「やめとけ」の声に振り回されず、計画通りの運営を貫けるでしょう。
まとめ
本記事では、アパート経営が「やめとけ」と言われる理由を空室率、修繕費、金利など五つの要素から整理し、実際のキャッシュフロー計算で数字のギャップを可視化しました。さらに、2025年度の融資優遇や固定資産税の減額制度を活用すれば、収益性は十分に高められることも確認しました。大切なのは平均値ではなく、自分が購入する物件の個別データと制度の活用余地を見極める視点です。この記事で紹介したチェックリストを用い、物件選びから資金計画まで一つずつ検証していけば、悲観論に惑わされず堅実なアパート経営への道が開けるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年7月速報) – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 令和7年住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行「貸出約定平均金利の推移」2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 財務省「法人税関係法令集2025年度版」 – https://www.mof.go.jp
- 東京都住宅政策本部「民間賃貸住宅市場レポート2025」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp

