都心の不動産価格が上昇を続ける一方、手取りが伸びにくい会社員は資産形成の選択肢に迷いがちです。新築マンションは魅力的でも価格が高く、融資負担を考えるとなかなか踏み出せません。そこで注目したいのが、中古物件を活用したマンション投資です。中古なら購入価格を抑えつつ家賃水準を確保しやすく、会社員の安定した給与と組み合わせることで資金計画が立てやすくなります。本記事では「マンション投資 中古 会社員」をキーワードに、物件選びから融資、リスク管理まで2025年9月時点の最新情報を交えて解説します。
会社員が中古マンション投資を選ぶ理由
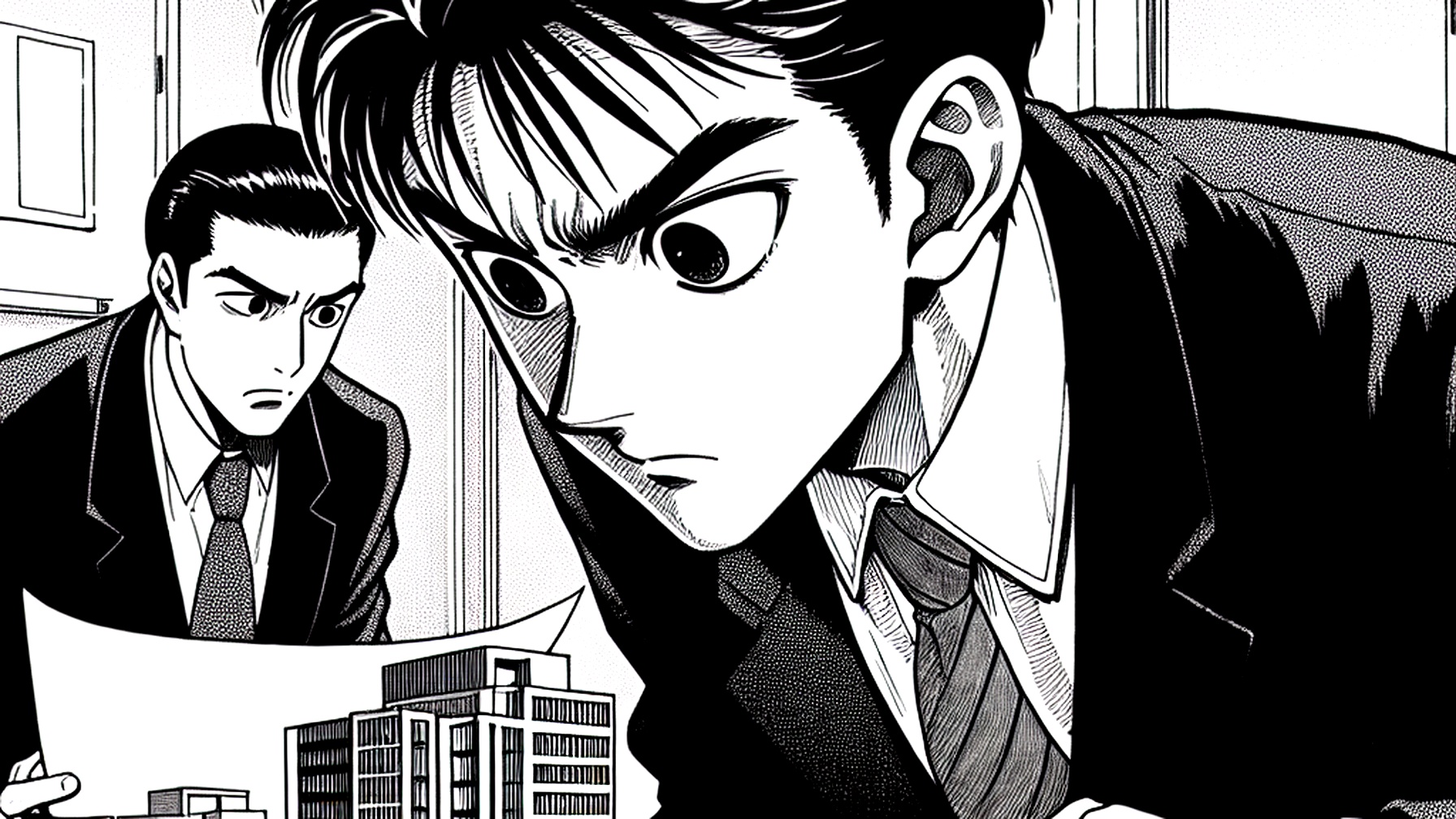
まず押さえておきたいのは、中古マンションが会社員に向いている根拠です。新築と比べて取得コストが低く、貸し出す家賃との差が利回りに直結します。
中古物件は築年数に応じて価格が下がる一方、都心の賃料は緩やかにしか下がりません。不動産経済研究所のデータでも、東京23区の新築平均価格は7,580万円ですが、築20年前後のワンルームなら2,500万円前後で見つかります。これは自己資金二割を入れても500万円程度で済む計算になり、会社員でも準備しやすい額です。
さらに、減価償却費を経費計上できる点が中古ならではのメリットです。木造アパートに比べ耐用年数が長い鉄筋コンクリート造(RC)のマンションでも、築古であれば残存耐用年数が短くなり、年間の経費計上額が増えます。給与所得と損益通算することで所得税と住民税が軽減され、手取り増につながるケースもあります。
一方で、建物の管理状態や修繕履歴を確認しなければ思わぬ出費が生じる恐れがあります。重要なのは、管理組合の長期修繕計画が機能しているか、修繕積立金が不足していないかを購入前に調べることです。これらを踏まえれば、中古マンションは会社員にとってリスクとリターンのバランスが取れた投資対象になります。
収益計算の基本とキャッシュフロー
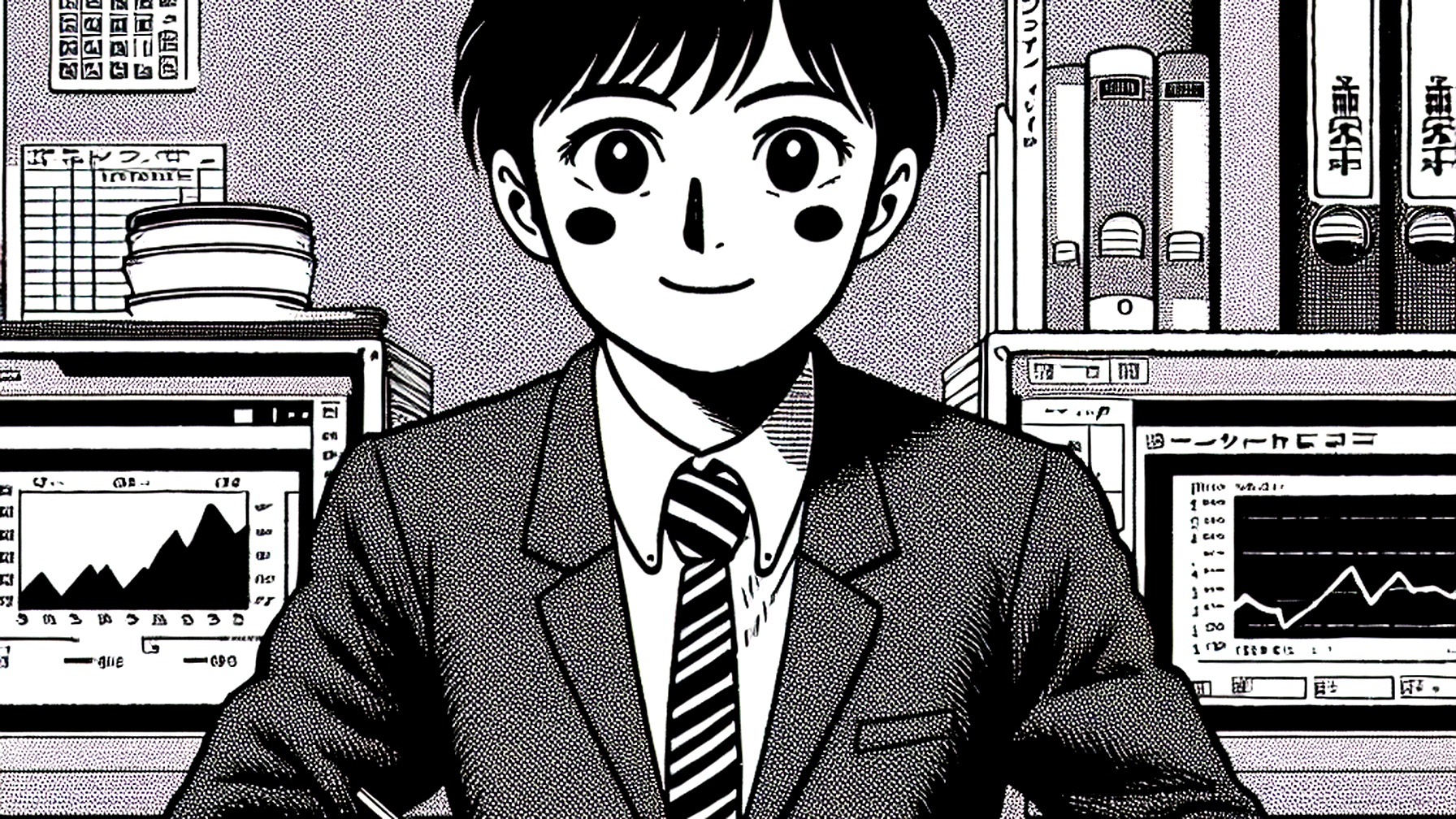
ポイントは、家賃から経費と返済を差し引いた後に残るキャッシュフローを正しく把握することです。表面利回りだけでは実質的な収益を判断できません。
家賃収入から管理費、修繕積立金、管理会社への手数料、固定資産税を差し引いたものが営業純利益(NOI)です。次に、金融機関への元利返済額を差し引き、手元に残る資金がキャッシュフローになります。この数値が月数万円でも黒字で回れば、長期で見たときに大きな差を生みます。
例えば、購入価格2,500万円、家賃9万円、返済期間25年、金利1.5%とします。年間家賃収入108万円から諸費用を差し引き、年間返済額が約100万円であれば現金収支はほぼトントンです。しかし、減価償却による節税効果と元本返済による資産形成を合わせると、実質的なリターンは年4〜5%程度に達します。
また、空室期間を組み込んだシミュレーションを行うことが欠かせません。国交省「住宅市場動向調査」では、都心ワンルームの平均空室率は約5%ですが、保守的に10%で計算しても黒字を維持できるか確認しましょう。このように複数シナリオで検証すれば、想定外の事態にも耐えられる計画を作れます。
物件選びで押さえるべき指標
実は、立地と建物スペックのバランスを見極めると失敗確率を大幅に下げられます。重要なのは駅距離だけでなく、賃貸需要を生む生活利便性です。
まず、駅から徒歩10分以内かつ最寄り駅の乗降客数が3万人以上あるエリアは、単身者需要が安定しています。周辺にスーパーやコンビニ、クリニックが揃っているかも確認しましょう。これらは長期入居の鍵になるため、実際に歩いて生活動線を確かめることが大切です。
築年数だけに注目せず、2000年以降に新築された「新耐震基準適合物件」を優先すると、金融機関の評価が上がり、融資条件が有利になります。また、総戸数30戸以上の中規模以上のマンションは修繕積立金が安定しやすく、長期的な維持コストが読みやすい特徴があります。
利回りを上げたいあまりに郊外の高利回り物件へ傾きがちですが、出口戦略も考えましょう。将来売却する際、人口減少が進むエリアでは買い手が限定され、価格が大きく下がるリスクがあります。つまり、多少利回りが低くても、資産価値が下がりにくい場所を選ぶことが長期的に見て合理的です。
2025年度の融資環境と税制のポイント
基本的に、会社員は安定収入が評価され、融資を受けやすい立場です。2025年度は日銀の緩やかな金利正常化が進みつつも、住宅ローン金利は1%台後半で推移しており、投資用ローンは2%前後が目安です。複数行を比較し、事前審査で提示される金利と融資割合を必ずチェックしましょう。
2025年度の所得税法では、減価償却の計算方法や損益通算のルールに大きな変更はありません。建物部分の取得価格を把握し、耐用年数に基づく定額法で毎年経費計上できます。また、住宅取得等資金の贈与非課税特例は居住用のみ対象なので、投資用には適用できない点に注意が必要です。
固定資産税に関しては、総務省の通達で2025年度も住宅用地の軽減措置が継続します。敷地200平方メートル以下の部分は課税標準が6分の1になるため、土地持分がある区分マンションでも恩恵を受けられます。購入前に登記簿を確認し、自室の土地持分面積を把握しておくと節税額を試算しやすくなります。
金融庁が公表する「金融モニタリングレポート2025」では、投資用ローンの審査が物件収益性よりも返済負担率に重点を置く傾向が示されています。したがって、自己資金を物件価格の20%程度用意し、返済比率を年収の30%以内に抑えると審査通過率が高まります。
リスク管理と長期戦略
ポイントは、短期的な家賃収入に一喜一憂せず、10年以上の視点で損益を管理することです。特に修繕リスクと金利上昇リスクを同時に考える姿勢が欠かせません。
修繕リスクについては、国土交通省「マンション大規模修繕工事実態調査」によると、築25年時点で一戸あたり平均120万円の負担が発生しています。購入時に修繕積立金が潤沢でも、将来の不足分を想定し、毎月のキャッシュフローから積み立てを行うと安心です。
金利上昇リスクに備えるには、返済額軽減型の元金均等返済や固定金利期間選択型を組み合わせる方法があります。さらに、繰り上げ返済用のプール資金を100万円程度確保しておくことで、市場金利が急上昇した際の負担を軽減できます。
最後に出口戦略です。築30年前後になると買い手の多くは自己居住かリノベ投資家になります。この層が重視するのは立地と管理状態です。したがって、日頃から入居者マナー向上や総会への参加を通じて管理水準を保ち、将来的な売却価値を高める努力を続けましょう。
まとめ
本記事では「マンション投資 中古 会社員」という切り口で、購入理由、収益計算、物件選び、2025年度の制度、リスク管理までを整理しました。価格が抑えられた中古マンションは、会社員の安定収入と相性が良く、節税効果も期待できます。大切なのは、キャッシュフローを保守的に見積もり、管理状態と立地を重視する姿勢です。将来の金利や修繕負担も計画に組み込めば、長期的な資産形成の軸として機能します。まずは自己資金の準備と融資相談から一歩を踏み出し、自分に合った中古マンションを探してみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 マンション大規模修繕工事実態調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 固定資産税に関する資料 – https://www.soumu.go.jp
- 金融庁 金融モニタリングレポート2025 – https://www.fsa.go.jp

