相続税の負担が気になり、現金をそのまま残すよりも賃貸物件を活用したい――近年こうした相談が増えています。しかし初めてのアパート経営となると、空室リスクや修繕費の見込みが漠然として不安が尽きません。本記事では、相続対策としてのアパート経営の仕組みから、修繕費を税務上どのように活かせるかまでを整理します。最新の空室率データと2025年度の制度動向を交えつつ、初心者でも読み進めやすい流れで解説しますので、自分の資産計画にどう組み込むか具体的なヒントが得られるはずです。
アパート経営が相続対策になる理由
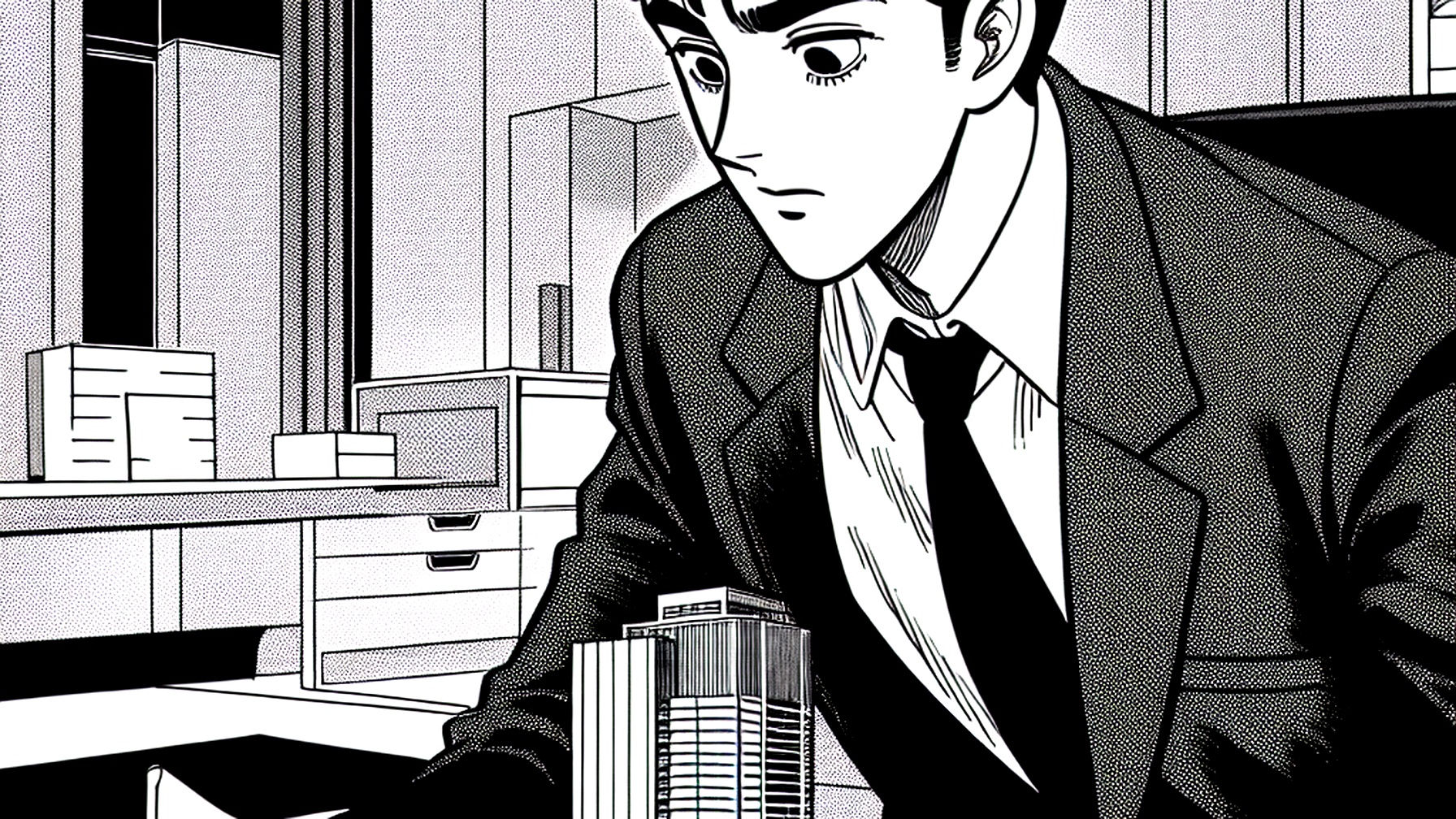
重要なのは、賃貸用不動産が評価額を圧縮しやすい点です。国税庁の財産評価基本通達では、貸家は自用の土地建物よりも評価が下がり、相続税の課税対象額が自動的に減少します。現金一億円を持っている場合と、同額で建てたアパートを所有している場合では、課税対象額が三割近く異なる試算も珍しくありません。
さらに、賃貸収入が毎月入ることで、相続人の生活費を助ける効果も期待できます。たとえば年間家賃収入一千万円、諸経費四百万円の物件なら、六百万円が手元に残り、相続発生後も家族のキャッシュフローを安定させます。ただし、人口減少の地域では空室が増え評価額だけでなく収入も落ちるため、立地選びが要です。
2025年七月の全国アパート空室率は二一・二%で、前年より〇・三ポイント改善しました。都心部は一五%前後にとどまる一方、地方は三〇%を超えるエリアもあります。つまり相続対策と言えども、賃料収入の裏付けがない物件では本末転倒になります。適正な家賃設定と需給バランスを常に確認する姿勢が欠かせません。
修繕費の基礎知識と税務メリット

まず押さえておきたいのは、修繕費が必要経費として全額損金算入できる点です。屋上防水や外壁塗装などの大規模修繕は金額が大きくても、支出した年度の所得から控除できるため、所得税と住民税の軽減効果が高まります。相続開始前に計画的に修繕を行うことで、被相続人の所得税を圧縮し、現金残高を減らして評価額を下げる二重の効果が生まれます。
一方で、資本的支出に該当する場合は減価償却でしか落とせない点に注意が必要です。エレベーターの全面入替や間取り変更を伴う大規模改装は耐用年数に応じて分割費用計上となります。国税庁の通達では、修繕費と資本的支出の判定基準が具体例とともに示されていますので、税理士と連携して判定するのが安全策です。
実は、法人名義で物件を保有している場合と個人名義では処理の柔軟性が異なります。法人は決算期を選べるため、修繕費を期末に集中させることで節税効果を高める戦略も可能です。また金融機関との融資契約では、修繕積立の計画提出を求められる事例が増えており、税務と金融の両面から修繕を位置づける必要があります。
キャッシュフローと長期修繕計画の立て方
ポイントは、年次キャッシュフロー表と長期修繕計画表を重ねて作成することです。家賃、ローン返済、固定資産税、保険料、修繕費を列記し、二〇三五年、二〇四五年といった将来時点で現金残高がマイナスにならないか確認します。空室率を二〇%、金利上昇一%といった厳しめのシナリオで試すと、リスクに強い計画かどうかがはっきりします。
長期修繕計画は十二年周期で外壁、十五年周期で屋上防水というように設備ごとに並べると具体的です。たとえば外壁塗装三百万円、屋上防水二百万円、給排水管更新四百万円という数字を入れ、各年の予算配分を可視化します。計画を作るときは建築士による劣化診断報告書があると根拠が明確になり、金融機関や税務調査でも説明しやすくなります。
なお、修繕費の資金を内部留保のみでまかなうと手元資金が枯渇する恐れがあります。最近は修繕専用ローンを取り扱う地方銀行が増え、金利は年二〜三%台が一般的です。金利負担を考慮しても、税務メリットと入居者の満足度向上による賃料維持効果を合わせれば、借入れによる修繕が合理的なケースは多いです。
2025年度の制度と金融機関の最新動向
実は、2025年度は省エネ性能向上を目的とした「民間賃貸住宅省エネ改修支援事業」が継続しており、外壁断熱や高効率給湯器の導入で最大費用の三分の一が補助対象になります。申請期限は2026年三月末までと公表されており、申請時期を修繕計画に組み込むと費用負担を抑えられます。
また、耐震性向上を図る「賃貸住宅耐震化促進事業」も2025年度も存続し、1981年以前の旧耐震基準物件を改修する場合は設計費と工事費の一部が補助されます。耐震補強は資本的支出に該当しやすいものの、補助金を活用すれば初期負担が減り資金繰りに余裕が出るため、相続開始前に安全性を高める好機と言えます。
金融機関の姿勢も変化しています。地銀や信金はESG評価を重視し、省エネ改修や太陽光パネル設置を含む修繕計画に対して金利優遇を提示するケースが増えました。たとえば某地方銀行では、長期修繕計画を提出し、一定の省エネ基準を満たすと融資金利が〇・二%下がるメニューを導入しています。これらを組み合わせると、修繕費を単なるコストではなく資産価値向上と実質負担削減につなげられます。
失敗を避けるためのチェックポイント
まず、相続対策 アパート経営 修繕費の三つを切り分けずに一括で考える癖を付けましょう。現金をアパートに変えるだけでは不十分で、継続的に入る賃料と計画的な修繕があってこそ、節税と資産保全が両立します。購入時は利回りだけでなく、築後十年、二十年時点の修繕履歴と見積もりを必ず確認し、オーナー引継ぎ後の手持ち資金を把握することが重要です。
次に、税務申告の精度が将来の調査リスクを左右します。修繕費の判断を自己流で行うと、五年後に資本的支出として否認され追徴課税となる例があります。税理士と建築士のダブルチェック体制を整え、写真と領収書をセットで保存しておけば、調査が来ても慌てずに済みます。
最後に、家族への情報共有を怠らないようにしてください。オーナーが急逝した際、相続人がローン残高や修繕積立額を把握していないと、適切な運営判断が遅れます。定期的に収支表を家族会議で説明し、公正証書遺言や家族信託を検討すると、争続リスクを抑えながら経営方針を継続できます。
まとめ
本稿では、アパート経営を活用した相続対策の基本と、修繕費を節税と資産価値維持にどう結び付けるかを解説しました。評価圧縮効果、修繕費の即時損金化、長期修繕計画と補助金の併用という三本柱を押さえれば、将来の税負担と空室リスクに備えながら家族のキャッシュフローを守れます。結論として、制度や金利が変動しても、自ら数字を確認し専門家と協働する姿勢が成功の鍵です。今日から収支表と修繕計画の作成に着手し、後悔のない資産承継を進めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「住宅市場動向調査2025」 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁「財産評価基本通達」 – https://www.nta.go.jp
- 環境省「民間賃貸住宅省エネ改修支援事業 2025年度概要」 – https://www.env.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅耐震化促進事業 2025年度公募要領」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行「金融システムレポート2025年6月」 – https://www.boj.or.jp

