家賃収入で生活を安定させたい。でも「高利回り」と聞くと、難しそうで一歩を踏み出せない。そんな悩みを抱える人は多いでしょう。私も当初は同じでしたが、実際に物件を購入し、年間表面利回り10%超を維持してきた結果、会社員の給与を上回るキャッシュフローを得ています。本記事では、その体験を具体例として紹介しつつ、高利回りを実現するための物件選び、運営の工夫、2025年度時点で利用できる融資や税制の最新情報まで整理します。読み進めれば、数字の裏付けと失敗談の両面から、初心者でも再現しやすい戦略が見えてくるはずです。
高利回り物件とは何かを理解する
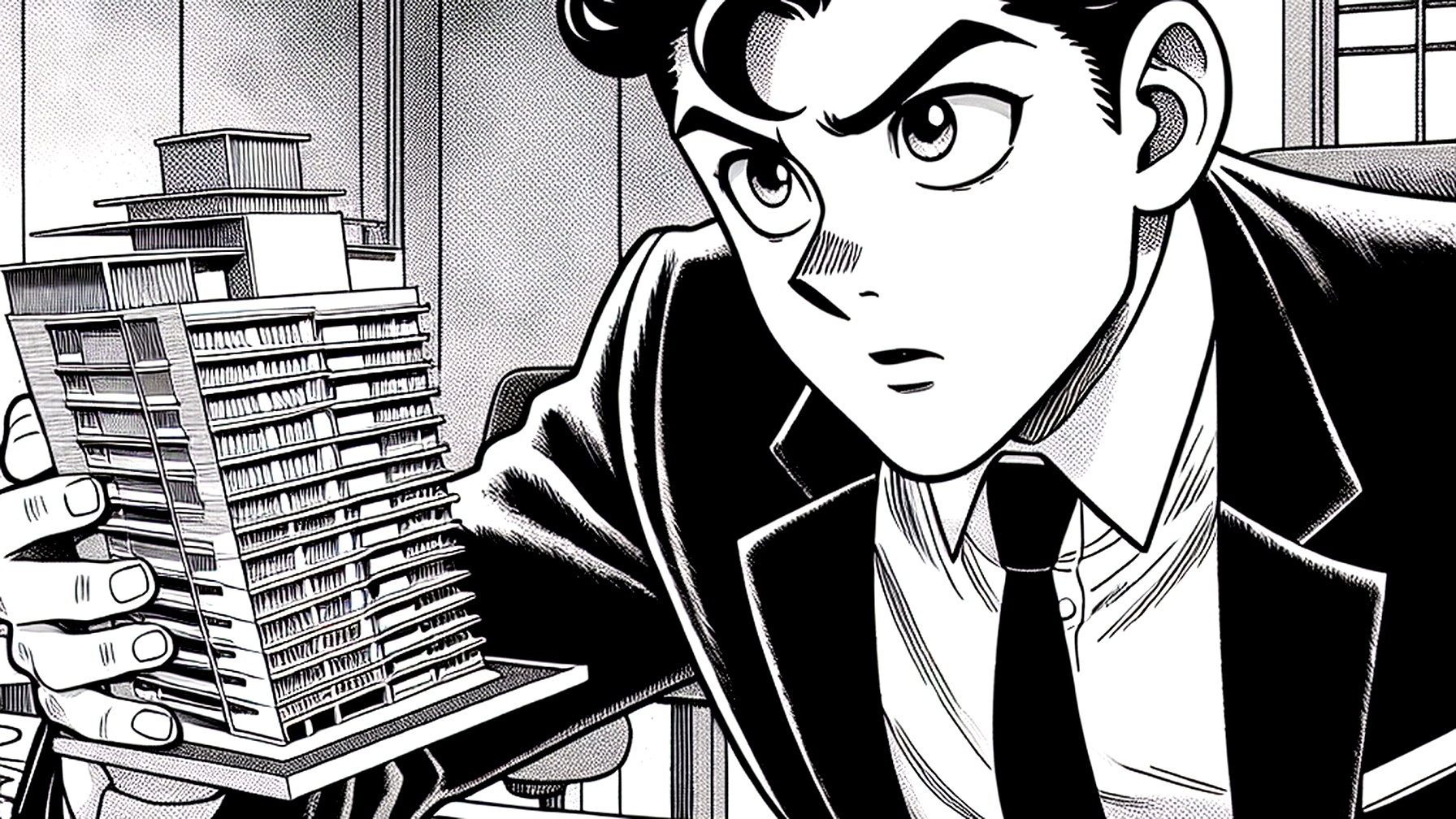
まず押さえておきたいのは、高利回りの定義と背景です。不動産投資で利回りと言えば、年間家賃収入を物件価格で割った「表面利回り」が指標になります。日本不動産研究所の2025年9月データでは、東京23区ワンルームの平均利回りが4.2%、アパートは5.1%でした。この数字と比べ、7〜8%を超える物件が市場では「高利回り」と呼ばれます。ただし利回りが高いほど良いとは限りません。修繕費や空室リスクが大きければ、手取りは低下します。つまり、見かけの数字だけでなく、運営コストと将来の資産価値を同時に見る視点が必要です。
次に、地域ごとの賃貸需要を調べる重要性を理解しましょう。例えば私が取得した埼玉県川口市の木造一棟アパートは、最寄り駅から徒歩7分で大学のキャンパスに近接していました。家賃相場は都内より安いものの、学生需要が底堅く、空室期間は平均二週間です。結果として購入価格3,600万円に対し年間家賃収入は420万円、表面利回り11.6%を達成しました。立地と賃貸ターゲットの整合が高利回りの原動力になります。
私の高利回り 体験談:購入から運営まで
ポイントは、情報収集から融資交渉、運営改善まで一気通貫で行ったことです。物件探しはレインズ公開前の未公開情報を持つ地場仲介に依頼しました。その際、希望利回りとエリアを具体的に伝え、週に一度は事務所へ顔を出し信頼関係を築きました。結果、築22年のアパートを市場価格より300万円安く購入できたのです。
融資面では地方銀行を活用しました。私は会社員として勤続10年だったため、年収の1.5倍を自己資金として提示し、返済比率を抑える提案を実施。2025年9月時点で同銀行の投資用住宅ローン固定金利は2.1%ですが、返済比率30%以下を条件に1.8%まで引き下げられました。この0.3%差で、30年総返済額が約180万円削減できています。
運営では小さな改善を積み重ねました。入居者募集にはSNS広告を併用し、1戸あたり平均3万円だった原状回復費をDIYで2万円に圧縮。さらに、Wi-Fi無料設備を導入した結果、家賃を月2,000円アップできました。こうして実質利回りは購入時の9.2%から現在は10.4%へ向上しています。
高利回りを実現する物件選びの視点
重要なのは「需要が読めるエリア」を最優先することです。人口動態を見ると、総務省「住民基本台帳人口移動報告」では2024年から25年にかけ、東京都隣接の埼玉・千葉・神奈川で転入超過が続いています。都心より価格が抑えられる上、賃貸需要が安定しているため、高利回り物件が比較的見つけやすいのです。
次に築年数の許容範囲を広げると、選択肢が増えます。木造なら築25年、RC(鉄筋コンクリート)なら築35年程度でも、構造躯体が健全なら融資期間を20年以上確保できます。私が行うチェックは、耐震基準適合証明の取得可否、屋上防水と給排水管の更新履歴、外壁クラックの有無です。これらを確認すると、将来の大規模修繕費を予測でき、物件価格交渉にも使えます。
加えて、利回り向上余地があるかを見極めます。現行家賃が相場より低い、空室が放置されている、共用部が荒れている物件は、改善余地が大きいサインです。例えば私が川口で取得したアパートは、クリーニング不足で満室時想定家賃の70%しか回収できていませんでした。そこで入居者退去に合わせて照明と床材を刷新し家賃を引き上げたところ、購入翌年には年間収入が60万円増加しました。つまり、購入後の施策込みで利回りを組み立てる発想が欠かせません。
収益を守る運営とリスク管理
実は、高利回りを維持するうえで最大の敵は「突発的な支出」です。空室期間の伸長、退去時の修繕、家賃滞納が代表例ですが、事前に備えることで影響を最小化できます。私は家賃保証会社(サブリースではなく滞納保証)を活用し、毎月家賃の5%を保証料として支払う代わりに、滞納リスクを事実上ゼロにしています。保証料を差し引いても高利回りを維持できるかが判断基準です。
修繕費に関しては、毎月家賃の10%を「修繕積立口座」に移しておきます。国土交通省の「賃貸住宅修繕積立ガイドライン」では、木造アパートの長期平均修繕費は年間家賃収入の8〜12%と示されています。この範囲で積み立てておけば、大規模修繕時も追加借り入れを回避できます。
空室対策では、ターゲット層に合わせた設備投資が効果的です。学生向けならWi-Fi導入、ファミリー向けなら宅配ボックスが好評でした。導入費は一戸あたり2万円程度ですが、空室期間が一か月短縮されれば元が取れる計算です。また、写真と動画を高画質で用意し、ポータルサイトだけでなくSNSにも掲載すると、問い合わせ件数が3割増えた経験があります。こうした小さな手間が、利回りを長期的に支えます。
2025年度に活用できる制度と融資環境
まず、2025年度も継続している「住宅ローン控除(投資用は対象外)」と混同しないよう注意が必要です。不動産投資家が利用できるのは「減価償却費による損益通算」と「固定資産税の経費化」が中心となります。しかし、自治体によっては空き家対策を目的に、賃貸住宅の耐震改修に補助金を出しています。例えば東京都の「既存住宅エコリフォーム補助」は2025年度も継続予定で、賃貸物件でも上限120万円まで補助されます。期限は2026年3月申請分までです。
融資面では、日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」が賃貸住宅の改修にも適用され、上限7,200万円、金利1.6%前後で利用可能です。私は2024年に外壁塗装の改修費800万円を同制度で借り入れ、返済期間10年、金利1.55%を適用してもらいました。商業ローンより低金利なので、キャッシュフロー改善に直結しました。
さらに、環境性能の高い賃貸住宅には「ZEH-M支援事業(2025年度版)」が使えます。新築共同住宅を対象に1戸あたり最大40万円の補助があり、長期的にみると空室対策にもつながるため、共同事業での活用を検討する価値があります。ただし、申請枠は毎年6月頃に締め切られるので、スケジュール管理が重要です。
まとめ
高利回りを目指すうえで、数字だけを追うと落とし穴にはまります。私の体験談が示す通り、賃貸需要を読み、融資条件を最適化し、運営改善を続けることで初めて手取りが増えます。まずは需要のあるエリアで、改善余地の大きい中古物件を探し、必要な修繕費を把握することから始めてください。そして、2025年度も利用できる補助金や低利融資を組み合わせれば、初期投資を抑えながら収益性を高められます。この記事が、あなたの最初の一歩を後押しし、安定した家賃収入への道標となれば幸いです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅修繕積立ガイドライン – https://www.mlit.go.jp
- 東京都 既存住宅エコリフォーム補助 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 日本政策金融公庫 生活衛生貸付 – https://www.jfc.go.jp

