突然の相続税負担に不安を抱きつつ、資産形成も同時に進めたい──そんな悩みを持つ方は少なくありません。現金をそのまま残すと評価額がそのまま課税対象になりますが、収益マンションに転換すれば評価額を抑えつつ家賃収入も得られます。本記事では「マンション投資 相続対策」をキーワードに、仕組みの基本、2025年度の制度、物件選びの視点、家族への引き継ぎ方法、そしてリスク管理まで体系的に解説します。初めての方でも読み進めるだけで具体的な行動ステップが見えてくるはずです。
相続対策としてマンション投資が注目される理由
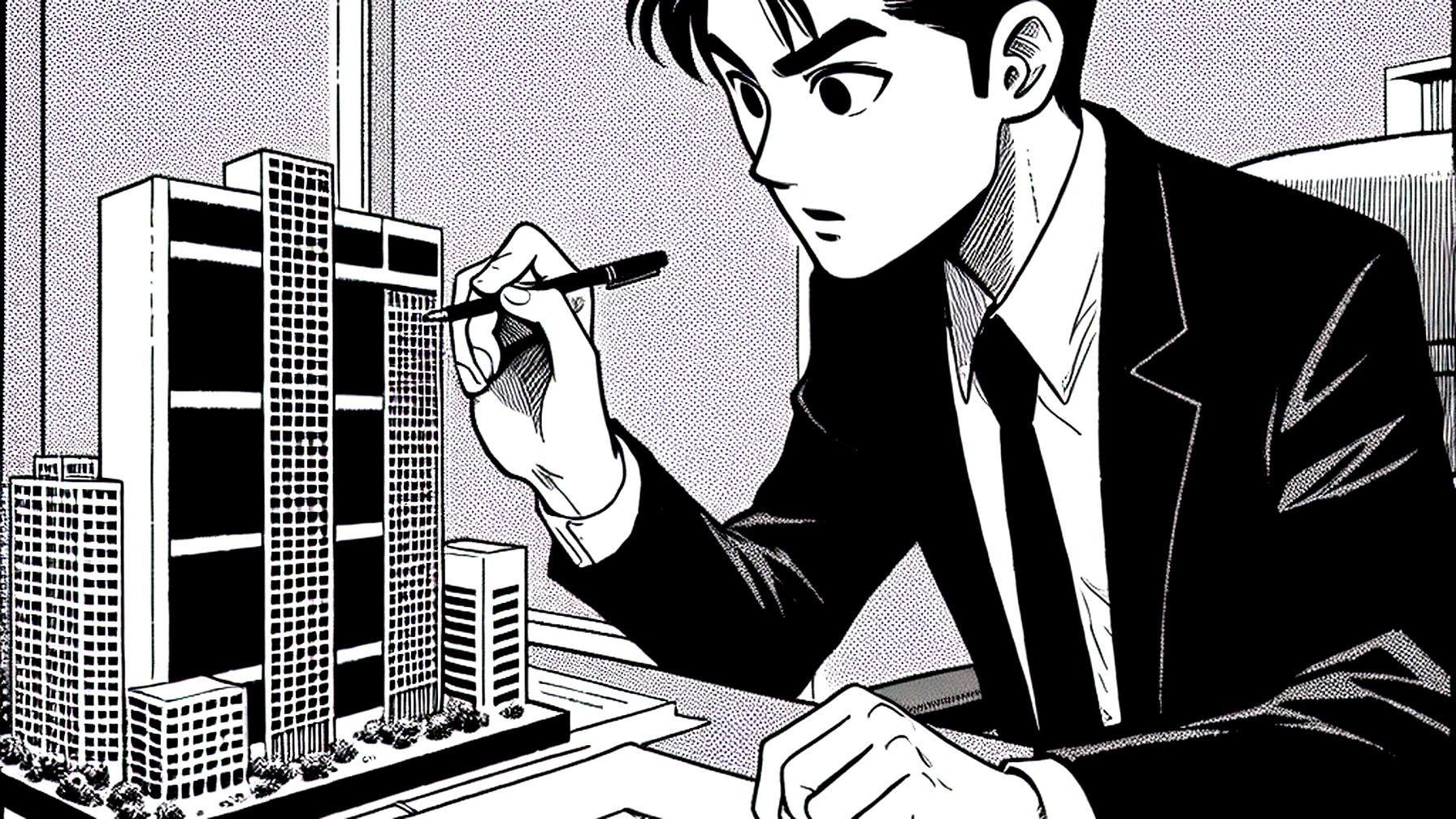
重要なのは、マンションに置き換えることで相続財産の評価額を圧縮できる点です。国税庁の路線価は実勢価格のおおむね80%前後に設定されるため、現金よりも相続税評価額が低く算定されます。さらに、賃貸に出している部屋は「貸家建付地」として20%程度の減額補正が加わり、総合的な圧縮効果が高まります。
もう一つの魅力は、生前のキャッシュフローを確保できることです。2025年9月時点の東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円ですが、同程度の中古物件を利回り4%で取得すると、年約300万円の家賃が期待できます。つまり、相続財産を減らしながら生活費やローン返済にも充当できる「攻守両立」の資産運用になります。
また、物件を共有名義にしておけば、相続人間の持分調整も比較的スムーズに行えます。換金処分しやすい都心マンションなら分割協議が長期化しにくく、遺産分割によるトラブルを防ぎやすい点も見逃せません。一方で、空室リスクや修繕コストを過小評価すると収支が崩れるため、後述のリスク管理が不可欠です。
最後に、投資用マンションは金融機関の評価も安定しているため、相続時における納税資金の調達がしやすいという利点があります。生命保険付きローンを組めば、債務が相続開始と同時に消滅し、実質的に無借金の不動産を残せる仕組みも活用可能です。
税負担を抑える仕組みと2025年度の制度
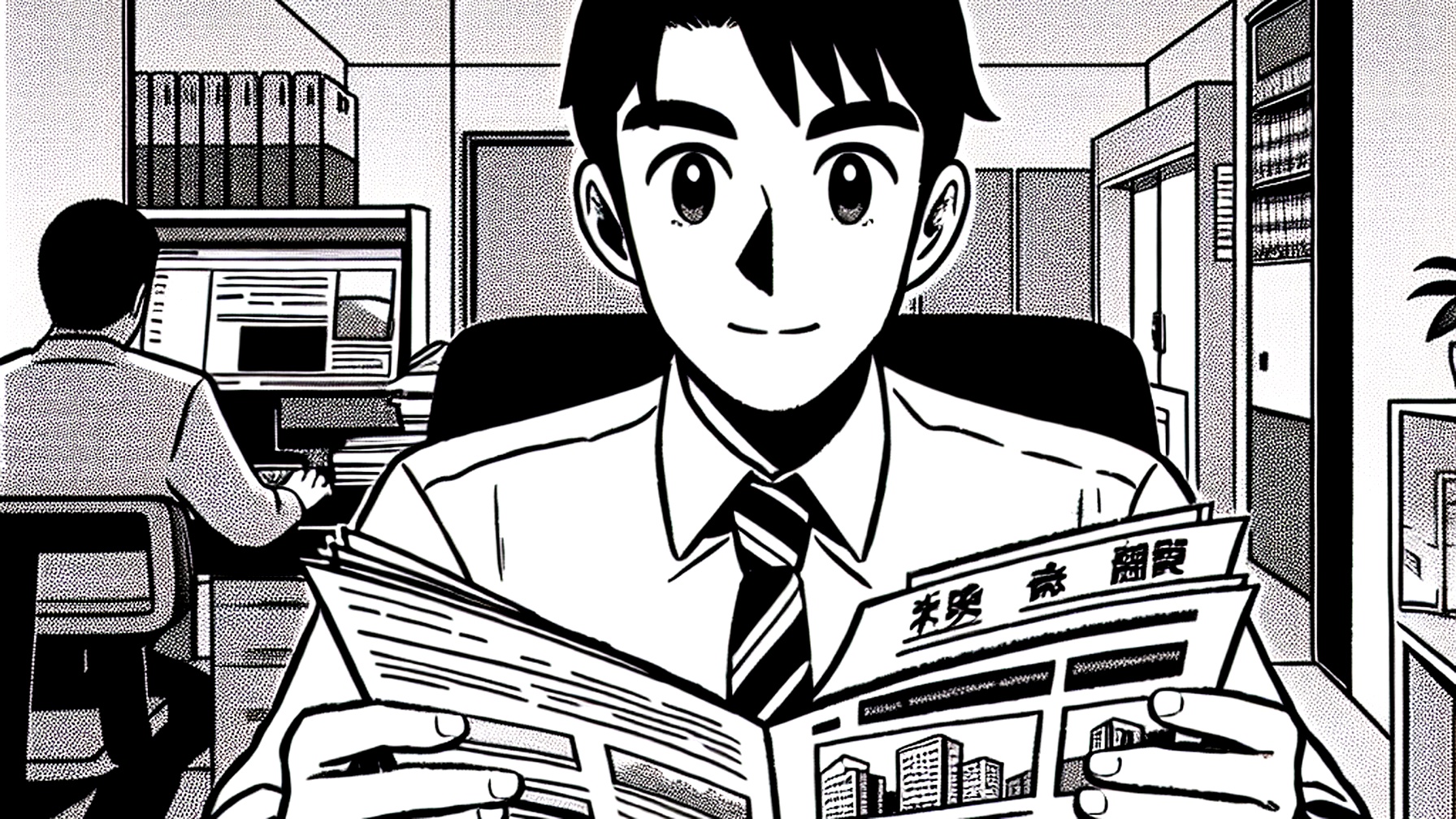
まず押さえておきたいのは「小規模宅地等の特例」です。賃貸用マンションの敷地なら、面積上限200㎡まで土地評価額を50%減額できるため、都市部では数千万円単位の節税効果が見込めます。ただし取得から3年以内に売却すると適用が取り消されるため、長期保有が大前提になります。
2025年度も引き続き利用できるのが「相続時精算課税制度」です。生前に子や孫へマンションを贈与する際、2,500万円まで贈与税が非課税になり、将来の相続財産から控除されます。昨年の税制改正で持戻し期間が従来の3年から7年へ延長されたものの、賃貸マンションで評価額を抑えつつ早期に賃料収入を移転できるメリットは大きいままです。
さらに、住宅取得等資金の非課税枠(2025年度上限1,000万円)も健在です。子が自宅用マンションを取得する場合、この枠を併用して古い区分マンションを購入し、自分は新築を賃貸に回す「世代間クロス投資」も検討できます。ただし自宅用途要件や合計所得金額の制限があるため、税理士に確認のうえ計画を立てましょう。
一方で、暦年贈与の基礎控除は110万円で据え置かれています。毎年コツコツと区分持分を贈与し、7年間で最大770万円を非課税移転できるため、複数の制度を組み合わせると柔軟な節税設計が可能です。つまり制度の理解と順序立てた贈与計画が、長期的な相続税対策の鍵になります。
物件選びで押さえたい三つの視点
ポイントは、立地・築年数・管理状況のバランスです。まず立地ですが、東京23区や主要政令市の駅近は空室率が低く、相続後に売却する場合でも高値で成立しやすい傾向があります。国土交通省の2025年土地白書によると、都心5区の賃貸住宅平均空室率は3.5%で全国平均の約半分でした。
築年数については、表面利回りだけで判断しない姿勢が重要です。築20年を過ぎると価格の下落カーブが緩やかになり、減価償却メリットも得られますが、大規模修繕積立金が不足している物件だと将来的に一時金徴収の恐れがあります。管理組合の長期修繕計画や滞納率を確認し、数字が整っているか見極めましょう。
管理状況は、建物の寿命と資産価値を左右します。エントランスやゴミ置き場の清潔感は入居者の満足度を映し出す鏡です。日本賃貸住宅管理協会の調査では、共用部の美観が良い物件は退去率が年間9%低下するという結果が出ています。つまり、管理が行き届いたマンションは収益安定性が高く、相続財産としても評価されやすいのです。
最後に、金融機関の評価目線を忘れてはいけません。築浅・駅近・総戸数50戸以上の区分マンションは担保評価が安定し、ローン金利の優遇を受けやすくなります。借入金利が0.3%下がるだけで、7,000万円借入・期間30年の場合の総返済額は約370万円減少します。資金計画と物件スペックをセットで検討する姿勢が求められます。
家族信託と管理体制で引き継ぎを円滑に
実は、節税だけでなく運用の継続性も相続対策の核心です。家族信託を活用すれば、認知症などで判断能力が低下しても受託者が賃料管理や売却を遂行でき、資産凍結を防げます。2025年9月時点で家族信託そのものに税制優遇はありませんが、後見制度より柔軟に管理権限を移譲できるのが強みです。
家族への情報共有は書面化が基本です。レントロール(家賃明細)や修繕履歴、入居者との連絡記録をクラウドで共有しておくと、相続開始後に誰が何をすべきか迷いません。総務省のデジタル利用実態調査によると、クラウドストレージ利用率は50%を超え、家族間のデータ共有に抵抗感が薄れてきています。
管理会社の選定も引き継ぎの成否を左右します。管理委託契約は自動更新条項が付いていることが多く、切り替えのタイミングを逃すと割高な手数料が継続します。年間管理料が家賃の1%違うだけで、家賃収入300万円のケースでは30,000円が毎年コスト増となる計算です。複数社から定期的に見積もりを取り、家族でも比較できる体制を整えましょう。
さらに、生命保険付き団体信用生命保険(団信)の見直しも欠かせません。ローン残高に応じた保障があると、万が一の際に借金ゼロのマンションが相続財産となります。近年はガン・三大疾病・就業不能までカバーする特約付き団信が増えており、保険料上乗せ幅は金利+0.2%前後が主流です。保障と返済負担のバランスを見ながら選択しましょう。
リスク管理と長期運用のコツ
まず、空室リスクを数値で把握することが出発点です。シミュレーションでは平均入居率95%が一般的ですが、都心好立地でも将来の供給過剰は否定できません。保守的に90%前提で試算し、ローン返済比率(家賃に対する元利返済割合)を60%以下に抑えると、賃料下落にも耐えやすくなります。
次に、修繕コストの予備費を準備します。国土交通省のマンション長寿命化ガイドラインでは、築30年までに専有部も含め1㎡あたり累計1.2万円の修繕費が推奨されています。専有面積60㎡なら72万円です。これを家賃収入の5%を毎月積み立てれば、およそ12年間で目標額に到達します。計画的な積立がキャッシュフローの安定につながります。
金利上昇リスクには固定と変動のハイブリッド型ローンが有効です。借入額の50%を固定金利、残りを変動金利に設定すると、金利上昇局面での返済額上昇を約半分に抑えられます。日本銀行の2025年9月マクロ経済レポートでも、政策金利は段階的な引き上げが示唆されているため、低金利のうちに金利固定比率を高める戦略が現実的です。
最後に、不測の事態に備える出口戦略を用意しましょう。価格上昇局面で売却する「キャピタルゲイン型」だけでなく、相続後に自己居住へ転用する選択肢も利便性が高いです。住宅ローン控除を活用できる可能性が出てくるため、将来的なライフプランと税制を複合的に検討することが、マンション投資 相続対策を成功へ導きます。
まとめ
ここまで、現金よりも評価額を圧縮できる仕組み、生前贈与や小規模宅地等の特例といった2025年度の制度、立地・築年数・管理状況のチェックポイント、家族信託を含む引き継ぎ体制、そして空室・金利・修繕の三大リスクへの備え方を解説しました。
マンション投資 相続対策は、節税と資産形成を同時に実現できる強力な手段です。まずは家族と資産状況を共有し、税理士や不動産会社に相談しながらシミュレーションを作成しましょう。早めに動けば動くほど選択肢は広がり、将来の安心につながります。
参考文献・出典
- 国税庁「令和6年分 相続税の申告のしかた」 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省「土地白書2025」 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産経済研究所「首都圏新築マンション市場動向2025年9月」 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅市場データブック2025」 – https://www.jpm.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合・経済見通し2025年9月」 – https://www.boj.or.jp

