不動産投資ローンを選ぶとき、「固定金利にすべきか変動金利にすべきか」で悩む人は多いはずです。金利水準がわずかに違うだけで、30年後の総返済額は数百万円単位で変わります。そこで本記事では、2025年9月時点の最新金利と市場動向を踏まえつつ、固定金利の特徴や選び方を分かりやすく解説します。初心者が陥りやすい落とし穴と、その回避策まで丁寧に解説するので、読み終える頃には自分に合ったローンタイプを判断できるようになります。
ローン金利タイプを正しく理解する
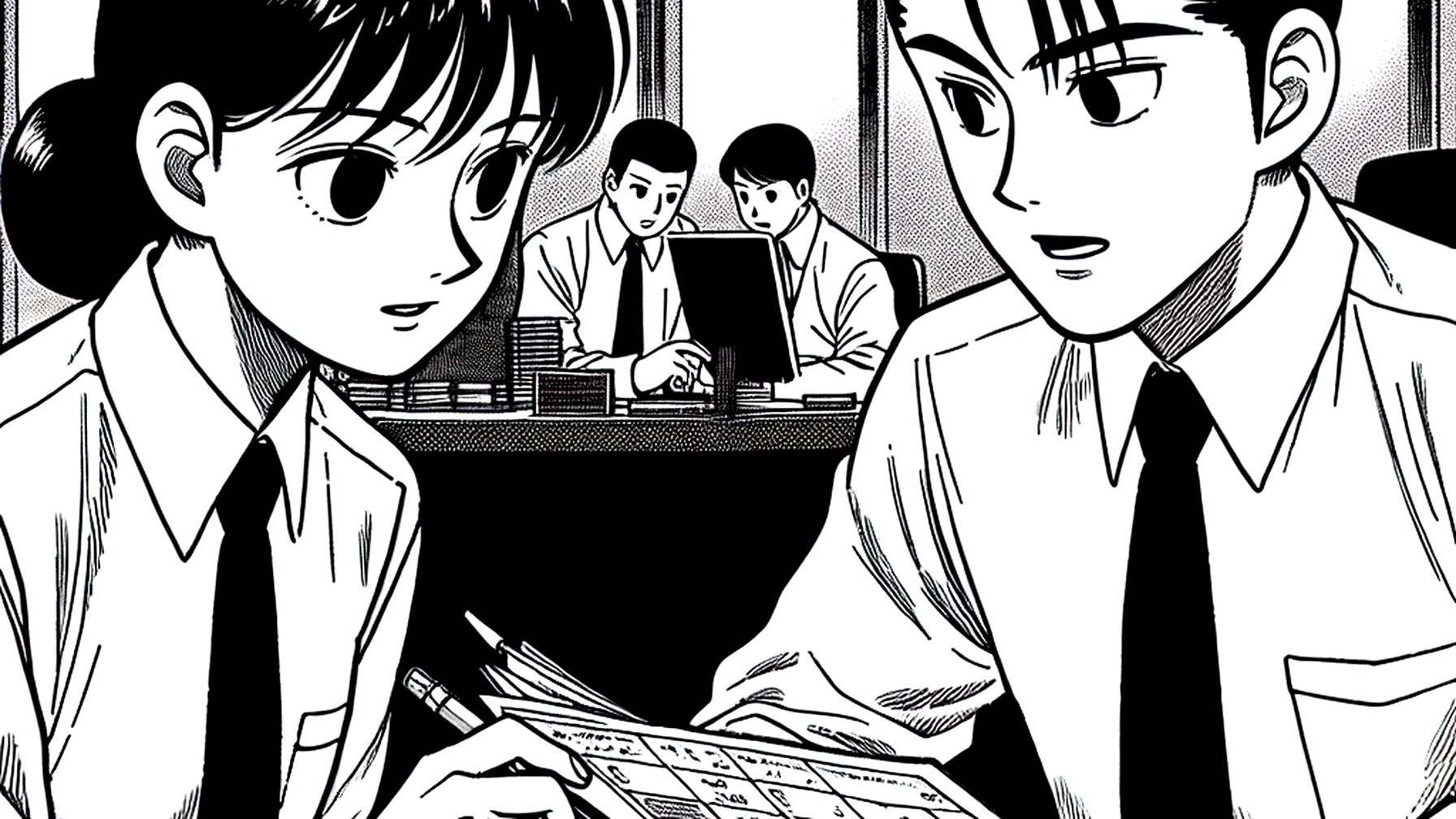
まず押さえておきたいのは、住宅ローンと異なり投資用ローンでは「金利タイプの違い」が収益性に直結する点です。一般に変動金利は2025年9月時点で年1.5〜2.0%、固定金利(全期間固定)は年2.5〜3.0%というのが全国銀行協会の統計値です。金利差だけを見ると変動が有利に見えますが、賃料下落や空室が続いてキャッシュフローが細ると、金利上昇の影響をもろに被ります。
つまり、固定金利は表面利回りが同じ物件でも収支のブレを抑えやすいのが特徴です。変動金利は市場の下振れ局面では有利ですが、海外金利の上昇が国内市場に波及するリスクを考えると、長期保有を前提にする投資家ほど固定金利の検討価値が高まります。また、金融機関によっては投資用ローンを固定で組む場合、自己資金を2〜3割求めるケースがあるので、資金計画とセットで考えることが大切です。
固定金利を選ぶメリットと注意点
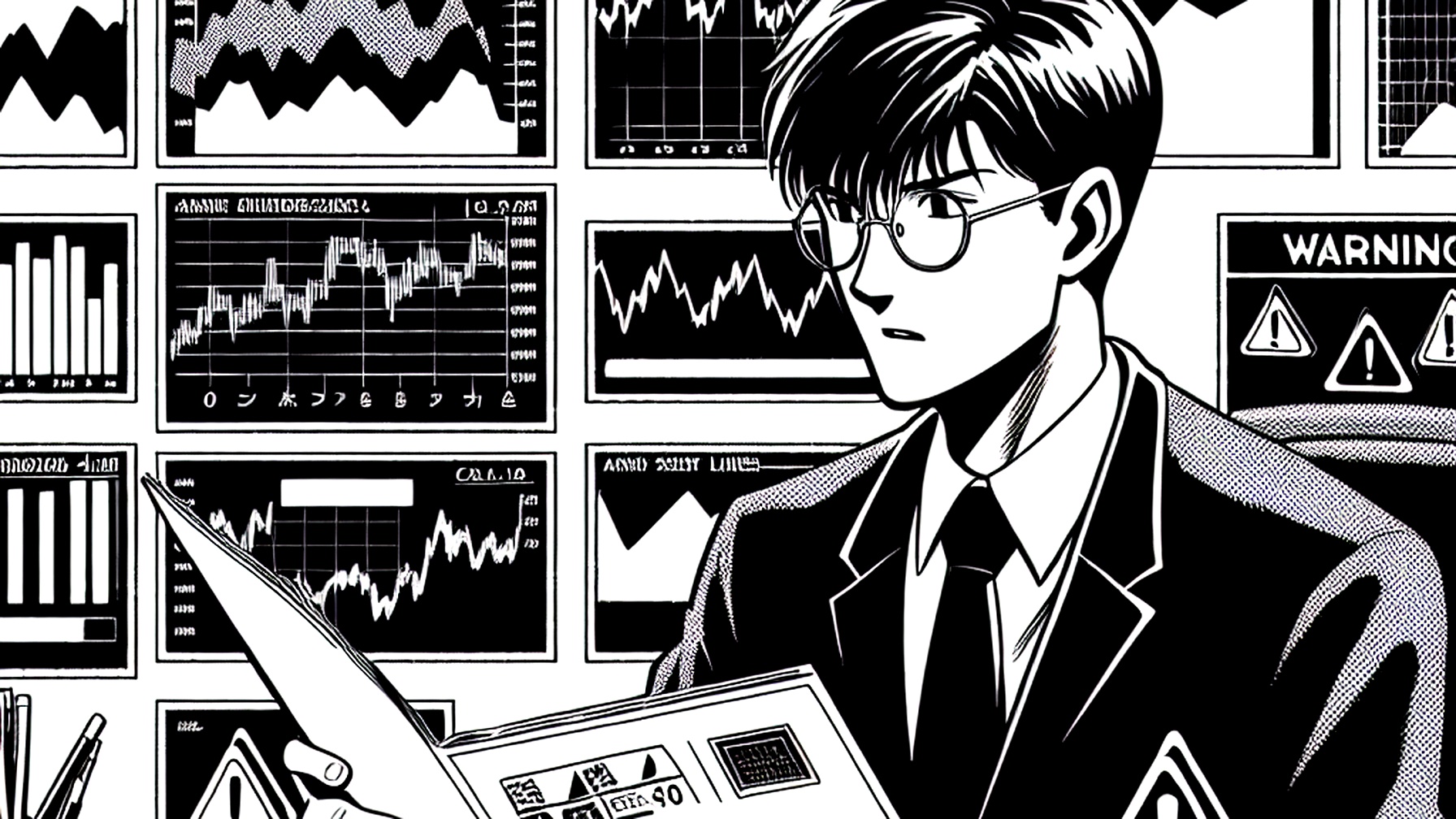
ポイントは、固定金利がもたらす「返済額の確定」という安心感です。賃料収入が一定であれば、返済額も一定となるためキャッシュフロー計画を立てやすくなります。さらに、2025年度も続くインフレ傾向が強まれば、実質的には借入債務の目減り効果が期待できます。
一方で、固定金利には初期コストが高いという弱点があります。金利が変動より1%高い場合、借入額1億円で期間30年なら総支払額は約1700万円増える試算です。この差額を「安心料」と割り切れるかが判断基準になります。加えて、固定期間中に一括繰り上げ返済を行うと、繰上げ手数料や違約金が発生する場合もあるため、投資戦略と返済計画を整合させることが必要です。
実は、固定金利を選ぶ際に「長期固定か期間固定か」で迷う人も多くいます。期間固定は5年や10年など一定期間だけ金利を固定する方法ですが、再設定時に大幅に金利が上がるリスクがあります。長期固定は金利変動リスクを最後まで排除できますが、代わりに初期金利がやや高くなります。資産形成のステージや出口戦略を意識し、どの程度の金利上昇に耐えられるかをシミュレーションしておくことが欠かせません。
固定期間別シミュレーションの読み方
重要なのは、数字を単に比べるのではなく「投資期間と金利リスク」をセットで見る視点です。以下は借入1億円、返済期間30年、元利均等返済の場合の一例です(諸費用は除く)。
- 変動金利1.7%:月返済額34.6万円、総返済額1億2460万円
- 固定10年2.7%→以後3.5%:月返済額38.8万円、総返済額1億3970万円
- 全期間固定2.8%:月返済額40.9万円、総返済額1億4700万円
シミュレーションで見るべきは、空室率や家賃下落を織り込んだキャッシュフローが30年間持続可能かどうかです。家賃収入を月50万円と仮定し、維持費・管理費で15%を差し引くと手残りは42.5万円です。全期間固定の場合、空室が1ヶ月続くだけでキャッシュフローは赤字になる可能性があります。逆に変動金利で金利が1%上昇すると、月返済額は約3.6万円増えます。どちらのリスクが自身の許容範囲か、数字で比較する作業が欠かせません。
また、期間固定を選ぶ場合は「固定終了後に売却する」「再度借り換え交渉を行う」など、次の一手を事前に決めておくとリスクをコントロールしやすくなります。金融機関は返済実績が良好な顧客に対して金利優遇を提案してくることもあるため、複数のシナリオを持つことが有効です。
金利上昇局面での資金計画
実は、固定金利を選んだとしても資金余力がなければ長期投資は難しくなります。総務省家計調査によると、2025年の平均貯蓄率は上昇傾向にありますが、突発的な修繕や空室でキャッシュアウトが生じるのは避けられません。そこで、ローン返済とは別に「空室リスク備蓄」として家賃3〜6ヶ月分の運転資金を確保することが推奨されます。
さらに、金利上昇局面では複数物件を保有していると、融資ポートフォリオ全体の返済負担が高まります。固定金利にしても融資枠は限られるため、次の投資機会を逃さないよう自己資金の比率を高めておく戦略が有効です。具体的には、家賃収入から20%以上を繰り上げ返済または内部留保に回すなど、余剰資金を厚くする習慣がリスクヘッジにつながります。
また、金融機関の審査では「キャッシュフローの安定性」と「自己資金の厚み」が重視される傾向が強まっています。2025年度以降も不動産投資ローンへの規制強化が続く可能性があるため、返済比率(年間返済額÷年収)を35%以内に抑えることが望ましいとされています。固定金利を選択すれば返済額が読めるので、審査時に説明しやすいメリットも生まれます。
金融機関と商品の比較ポイント
まず押さえておきたいのは、投資用固定金利の商品性は銀行ごとに大きく異なる点です。都市銀行は長期固定を取り扱う一方、地方銀行や信用金庫は期間固定中心の商品をそろえています。また、ネット系銀行は団体信用生命保険を自由設計できるなど独自の特色を打ち出しています。金利だけでなく、融資上限や繰上げ返済手数料も比較対象に入れることが重要です。
都市銀行で固定金利を選ぶ場合、自己資金2割を条件に金利が2.6%まで下げられるケースがあります。一方、地方銀行は立地や管理状況に独自の評価基準を持つため、同じ物件でも金利が0.3%前後変わることがあります。つまり、物件の稼働実績や周辺賃料の相場データを提示できれば、優遇金利を引き出しやすくなるのです。
比較のプロセスを段階的に示すと、①自己資金比率を決める、②返済比率が許容範囲か確認、③シミュレーションを複数パターン用意、④複数行に同条件で見積もりを依頼、という流れになります。特に④では、同じ返済期間・借入額で提示金利をそろえるよう要求しないと、手数料や保証料込みの総コストが比較できません。また、提案書には「総返済額」「繰上げ返済手数料」「違約金条項」が明記されているかを必ずチェックしてください。
最後に、固定金利を選ぶ際は「借り換え余地」と「出口戦略」の両面から判断することが肝心です。金利が想定よりも大幅に下がれば借り換えで固定金利を下げるチャンスがありますし、物件価値が上がれば売却益で残債を清算する選択肢も生まれます。これらを踏まえてこそ、固定金利の安心感が最大限に活きるのです。
まとめ
記事では、不動産投資ローンを固定金利で組む際の考え方を解説しました。固定金利は返済額を確定できる安心感がある一方で、初期コストが高く、途中解約時の負担も無視できません。そのため、投資期間・空室リスク・自己資金比率を総合的にシミュレーションすることが欠かせません。まずは複数の金融機関から同条件で見積もりを取り、自分が許容できる金利上昇幅を数字で把握しましょう。適切な金利タイプを選べば、長期にわたって安定したキャッシュフローを確保でき、不動産投資をより堅実に進められます。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 日本銀行「金融システムレポート」 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局「家計調査年報2025」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「不動産価格指数」 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁「金融モニタリングレポート2025」 – https://www.fsa.go.jp

