家賃収入で資産形成を目指したいものの、「表面利回りは分かるけれど、実質利回りが低いと失敗するらしい」と不安に感じている方は少なくありません。本記事では実質利回りの基本から計算方法、2025年の市場動向までを丁寧に解説します。読み終えるころには、数字の読み方と改善策が具体的にイメージでき、マンション投資を一歩前に進める自信が得られるはずです。
実質利回りとは何か
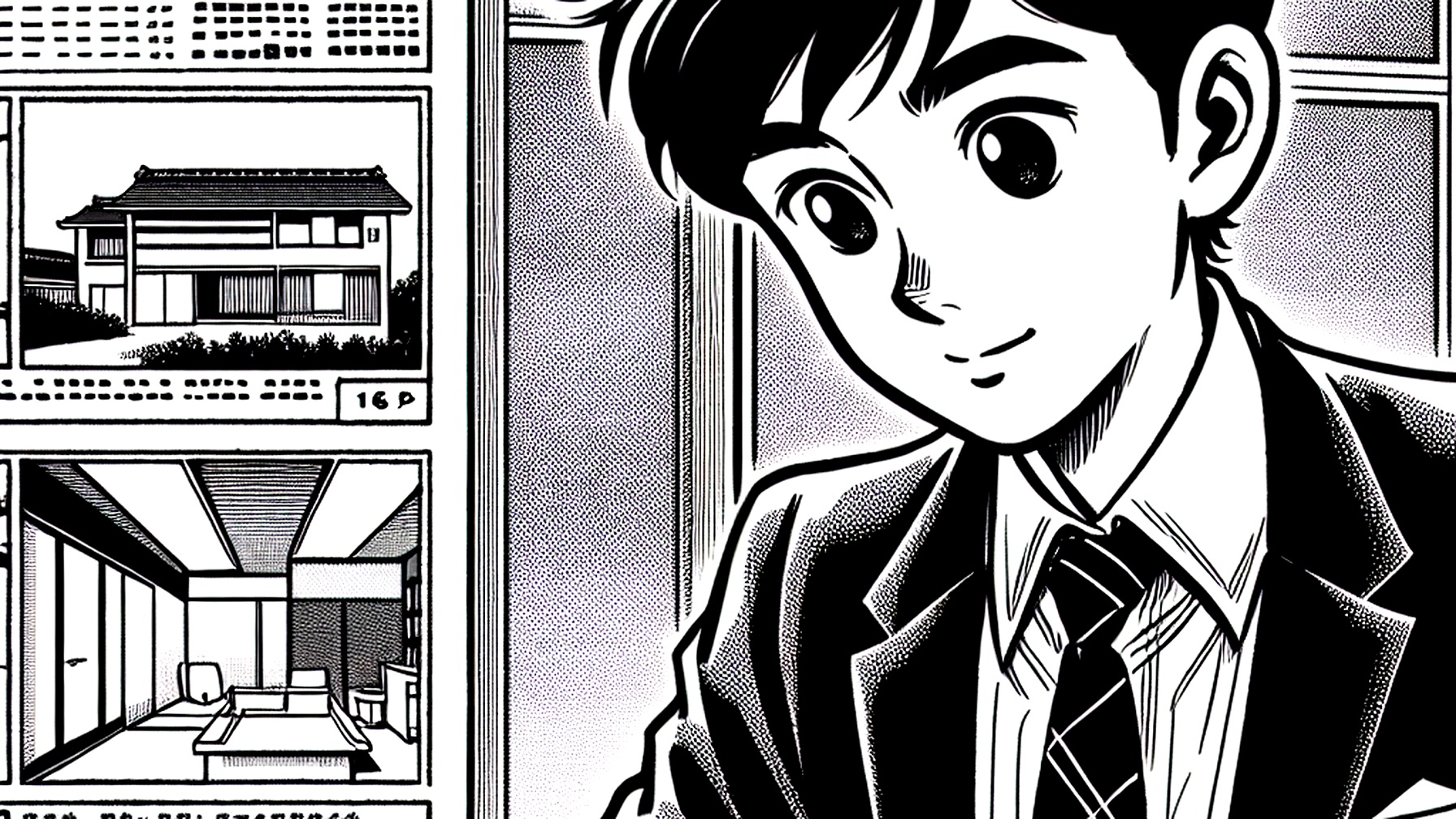
重要なのは、表面利回りと実質利回りの違いを正確に理解することです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標ですが、経費や空室リスクを考慮していません。一方、実質利回りは諸経費を差し引いた後の手取り収入を基に算出するため、投資の採算性をより正確に示します。
まず東京23区のワンルームでは、2025年9月時点の平均表面利回りが4.2%と報告されています(日本不動産研究所)。しかし管理費や修繕積立金などを差し引くと、実質利回りは平均で2.5%前後に下がるケースが多いのが現実です。つまり、表面利回りだけで購入を決めると、期待したほどキャッシュフローが残らない可能性があります。
また、実質利回りはローンの有無で変わります。金利1.7%の融資を受けた場合、手取り額がさらに減少し、自己資金比率が低いほど利回りも圧縮されます。それでも実質利回りがプラスで安定していれば、長期的な資産拡大につながるため、数字の裏側を読む力が欠かせません。
実質利回りを左右する経費の正体
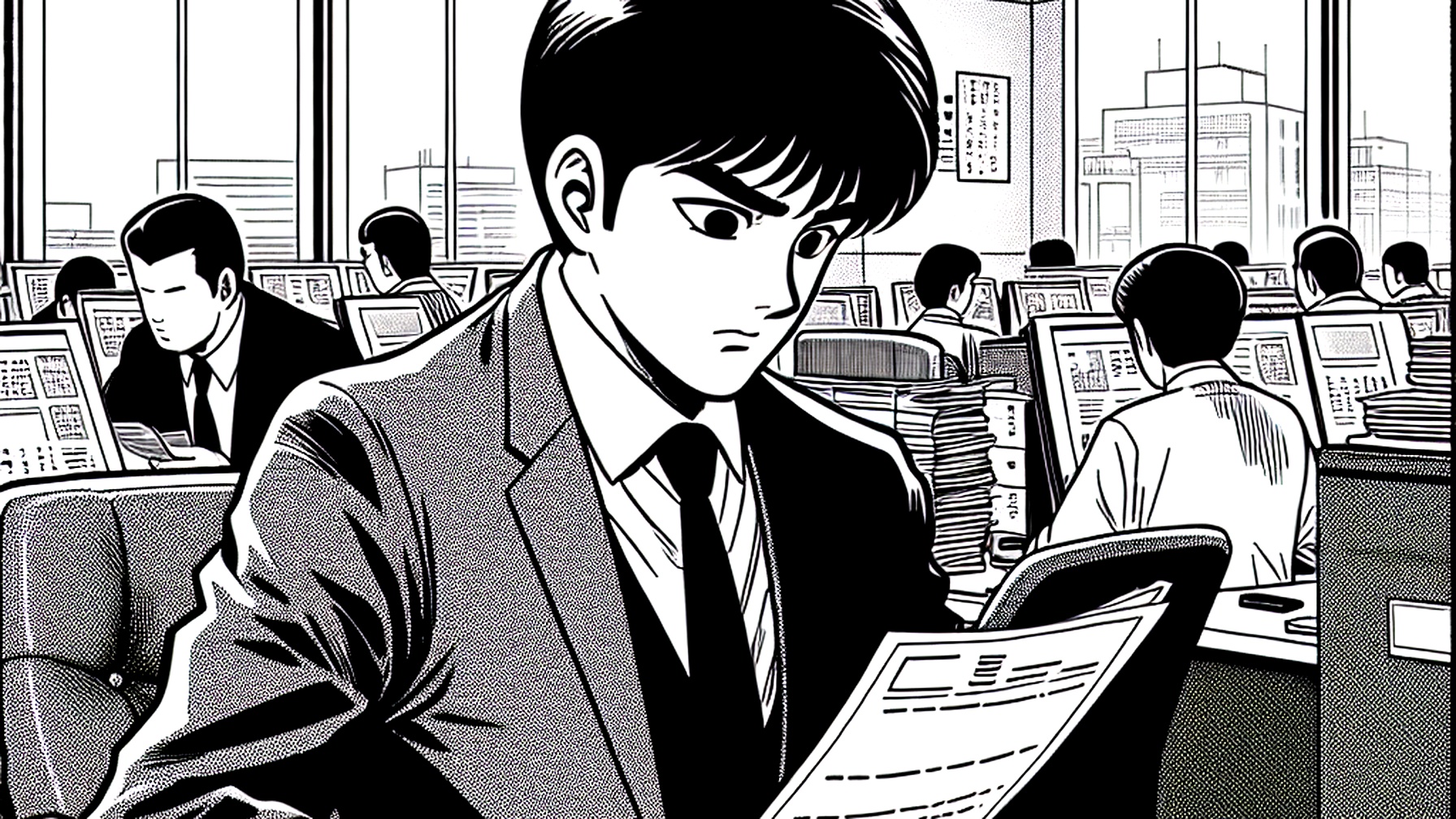
ポイントは、経費の内訳を細かく把握し、固定費と変動費を切り分けることです。固定費には管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税が含まれ、支出額をほぼ事前に把握できます。変動費は入退去時の原状回復費や空室損、広告料などで、想定外の出費を招く要因となります。
中でも修繕積立金は築年数とともに上昇する点に注意が必要です。築15年で月額1万円だった区分マンションが、築30年には月額2万円を超える例も珍しくありません。長期的に見れば、実質利回りを食い潰す最大の敵になり得るのです。
さらに、火災保険と地震保険も忘れがちなコストです。最近は自然災害リスクの高まりにより、保険料が年率2〜3%で上昇している地域もあります。保険の見直しは経費削減の余地が大きいものの、補償内容を削り過ぎると損失リスクが跳ね上がるため、バランスが肝心です。
最後に空室損があります。総務省「家計調査」によると、単身世帯の平均転居頻度は4年に1回程度です。退去後1カ月でも空室が続けば、年間手取りは数十万円単位で減ることになります。実質利回りの計算には、平均空室率5〜10%を見込んでおく方が安全です。
具体的な計算ステップ
まず押さえておきたいのは、計算式そのものはシンプルだという事実です。年間家賃収入から年間経費を差し引き、さらにローン返済を除いた手取り額を物件価格+購入時諸費用で割れば実質利回りが求められます。以下に数値例を示しながら手順を追います。
例として、物件価格2,800万円のワンルームを想定します。年間家賃収入は120万円、管理費と修繕積立金の合計が18万円、固定資産税・保険料が5万円、平均空室損を8万円とします。年間経費合計は31万円となり、手取り家賃は89万円です。
次にローン条件を年利1.7%、返済期間30年、借入80%とします。年間返済額は約96万円になり、年間のキャッシュフローはマイナス7万円です。購入時には諸費用として約170万円(物件価格の6%相当)が発生するため、総投資額は2,970万円となります。
ここでローン返済前の実質利回りを計算すると、89万円÷2,970万円=2.99%です。しかし返済後のキャッシュフローはマイナスなので、投資としては再検討が必要になります。自己資金を増やす、家賃を上げる、金利を下げるといった改善策の効果を同じ式に当てはめ、複数パターンで検証すると意思決定が格段に精度アップします。
利回り改善の戦略
実は、実質利回りは小さな工夫の積み重ねで1%近く改善できることがあります。家賃設定を相場より2,000円上げるだけで年間2.4万円の増収になり、先ほどの例では利回りが3.07%へ上昇します。家賃アップには、無料Wi-Fi導入や宅配ボックスの設置など、入居者の満足度を高める投資が効果的です。
一方で経費削減も見逃せません。管理委託手数料を月額1,000円下げれば年間1.2万円の節約になります。建物管理会社は複数社を比較し、交渉する姿勢が重要です。また、火災保険は代理店経由ではなくネット型を選ぶことで、同等の補償内容でも数千円安くなるケースがあります。
長期修繕計画を自分でチェックすることも利回り向上策の一つです。大規模修繕を前倒しにするか、共用部分の仕様を見直すかで費用総額が変わるため、管理組合の議事録を確認し適切なタイミングで意見を出しましょう。投資家が主体的に関わることで、修繕コストが数十万円単位で抑えられた実例も報告されています。
最後にローンの借り換えです。2025年現在、都市銀行の投資用ローンは変動金利1.4〜2.0%が中心ですが、地銀や信用金庫には1%前半の商品も登場しています。借り換えにかかる事務手数料や抵当権設定費用を含めても、金利が0.5%下がれば総返済額は数百万円縮小し、実質利回りを大幅に押し上げます。
2025年の市場動向と戦い方
まず押さえておきたいのは、物件価格の上昇が利回りを圧迫している点です。不動産経済研究所によると、東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%増となりました。価格が上がる一方で家賃は横ばい傾向にあるため、表面利回りはじわじわ低下しています。
しかし、実質利回りで見ると必ずしも悲観する必要はありません。日本不動産研究所のデータでは、同時期のアパート平均表面利回りが5.1%であるのに対し、入居者属性が安定しているファミリーマンションは3.8%ながら空室率が低いという結果が出ています。安定稼働によって実質利回りが良好に保たれる可能性が高いのです。
今後は金利動向にも目を配る必要があります。日銀の金融政策が段階的に正常化へ向かうと想定され、長期金利は緩やかに上昇する局面が予想されます。金利が1%上がると返済額は約15%増えるため、繰上返済や固定金利への切り替えを検討し、実質利回りの低下をあらかじめ抑える対策が求められます。
また、2025年度の住宅省エネ改修補助金は区分マンションにも拡大適用されています。対象工事には高断熱窓の交換や高効率給湯器の導入が含まれ、上限45万円の補助が受けられます。これを活用して設備更新すれば、入居者満足度を高めつつ自己負担を抑えられ、結果的に家賃維持と利回り改善につながります。制度には年度上限額があり、申請は早い者勝ちとなる点を覚えておきましょう。
まとめ
本記事では実質利回りの定義、計算手順、経費の内訳、改善策、そして2025年の市場動向を解説しました。表面利回りだけでは見えないコストを把握し、家賃収入の最大化と経費最適化を同時に進めることが成功の鍵です。まずは購入候補物件の実質利回りを複数シナリオで試算し、改善余地を洗い出してください。行動を積み重ねることで、安定したキャッシュフローと将来の資産形成が現実のものとなるでしょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 家計調査 – https://www.stat.go.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

