不動産価格が高止まりする一方、預貯金の利回りはほぼゼロに近い状況が続いています。資産を守りながら将来の相続リスクにも備えたい──そう考える方にとって「マンション投資 中古 相続対策」は魅力的なキーワードです。本記事では、中古マンション投資が相続対策として有効な理由を解説し、2025年度の税制や市場データを踏まえつつ、物件選びから出口戦略までの流れを丁寧に紹介します。読み終えたとき、あなたはご家族の将来を具体的にイメージしながら投資プランを組み立てる第一歩を踏み出せるはずです。
中古マンション投資が相続対策に向く理由
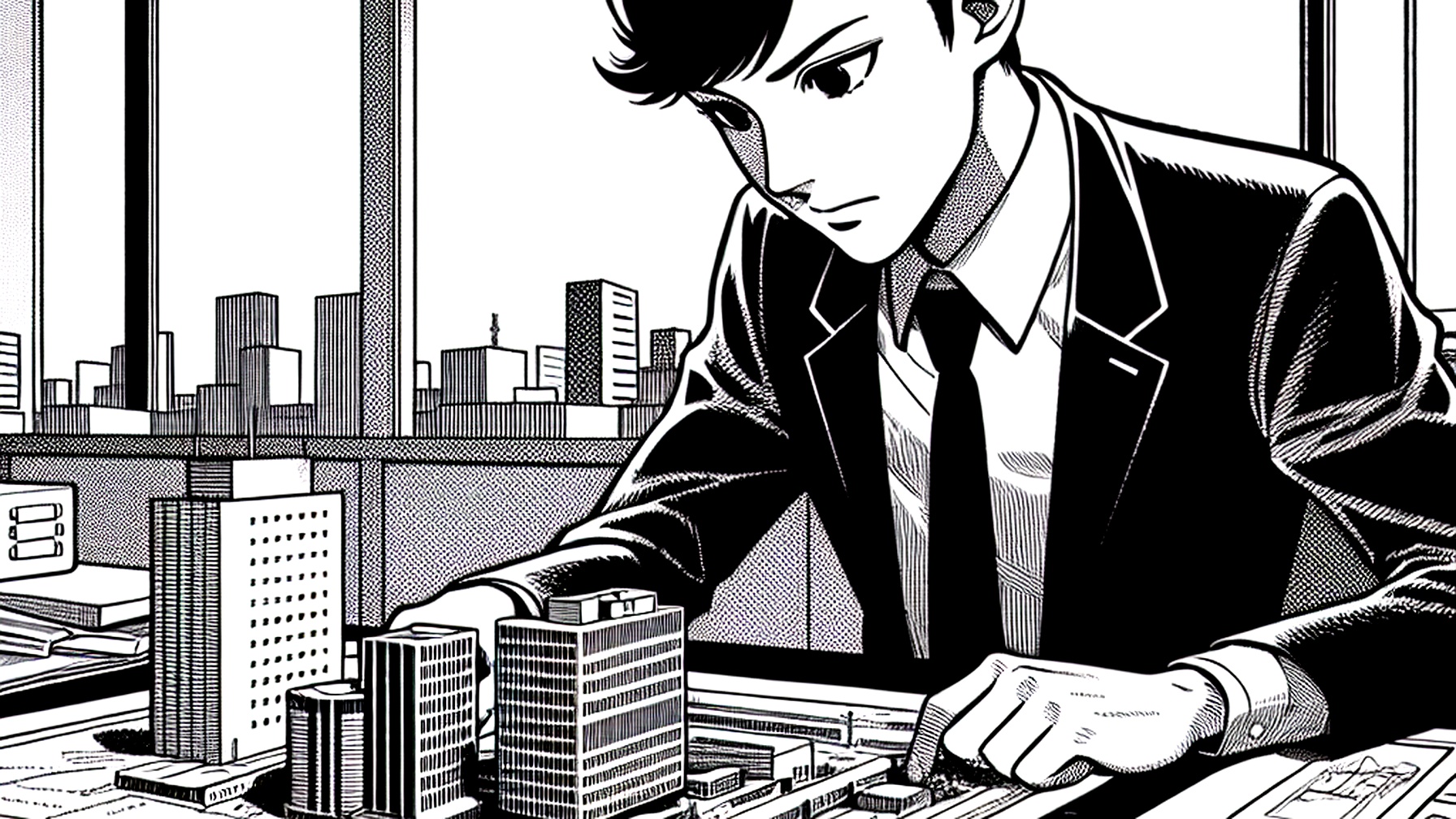
重要なのは、中古マンションが「評価額の圧縮効果」と「安定収益」の両方を兼ね備えている点です。相続税では土地や建物は路線価や固定資産税評価額で算定されるため、現金よりも評価が下がりやすく、税負担を抑えやすいといえます。さらに築年数を経た物件は新築に比べて価格がこなれており、利回りも相対的に高くなる傾向があります。つまり、限られた資金で節税と収益確保を同時に狙えるのが中古マンションの強みです。
一方で、相続対策として機能するかどうかはキャッシュフローの安定度に左右されます。築20年を超える区分マンションでも東京都心では空室率が5%前後と低水準で推移していますが(総務省住宅・土地統計調査2023)、地方では二桁になるエリアも少なくありません。立地次第で節税とリスクは表裏一体になるため、賃貸需要を客観的に検証するプロセスが欠かせません。
また、中古マンションは購入後すぐに家賃収入が見込める点も相続対策向きです。長期運用を前提とするため、毎年の相続時精算課税の活用や生命保険料控除と合わせてキャッシュフローを最適化しやすくなります。加えて、被相続人が高齢の場合でも、賃料収入が介護費用や医療費の足しになるという副次的なメリットもあります。
実務上は、物件取得費や減価償却費を経費計上できるので所得税の圧縮にもつながります。ただし、築古物件の耐用年数は短く、新耐震基準を満たさない場合は融資条件が厳しくなるため、金融機関との事前調整が必須です。このように、中古マンション投資は多面的な効果を発揮する一方、物件選びと資金計画を誤ると想定外のリスクを抱え込む点を忘れてはいけません。
2025年度の税制を踏まえた現金と不動産の比較
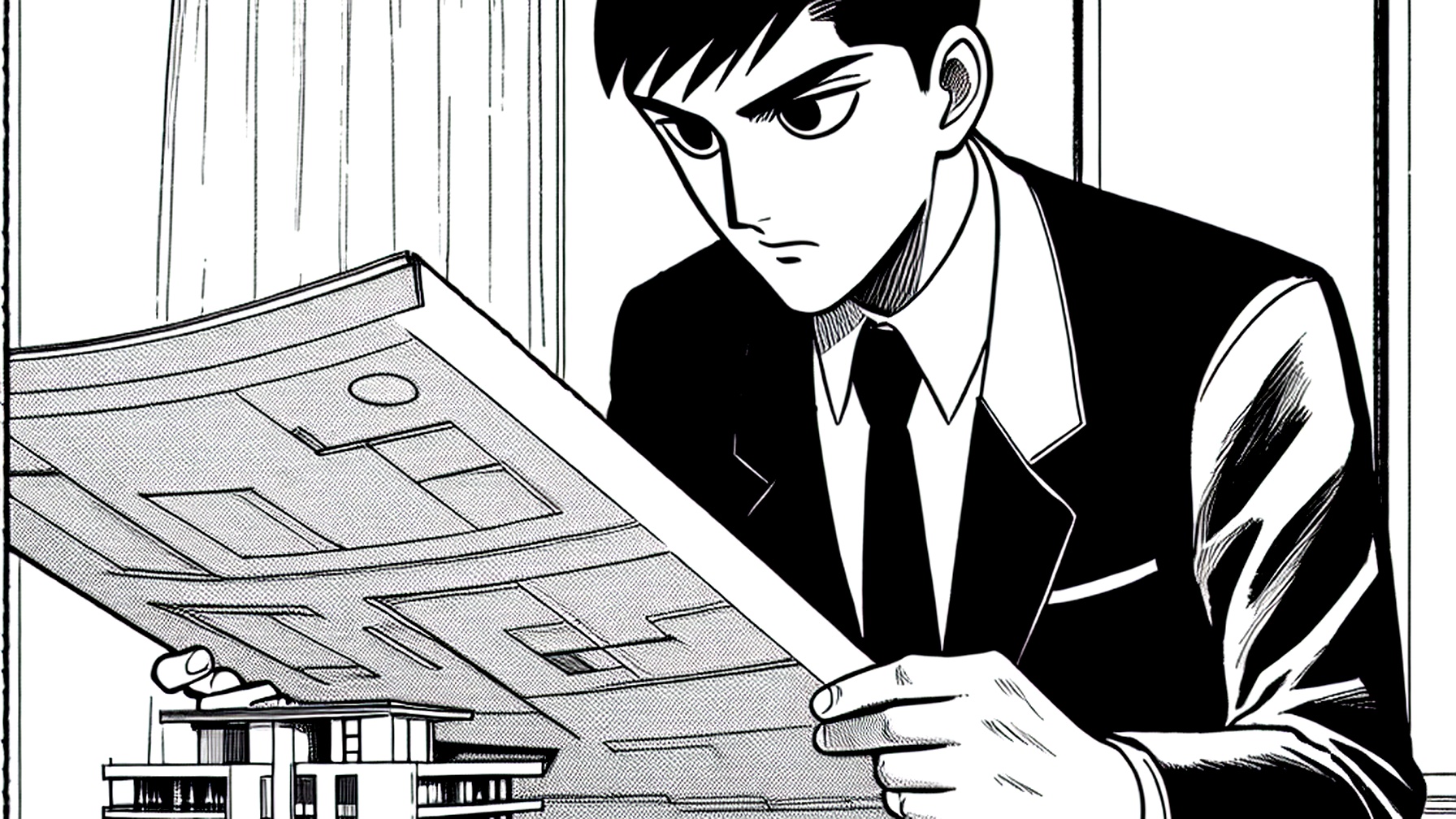
まず押さえておきたいのは、相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で据え置かれている点です。たとえば子ども二人の場合、基礎控除額は4,200万円にとどまります。財産の大半が現金の場合、この枠を超えた分がそのまま課税対象となるため、評価圧縮効果のある不動産保有がより重要になります。
2025年度も「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」が継続され、子や孫への贈与は最大1,000万円まで非課税(省エネ性能が一定基準以上の住宅は1,500万円)です。しかし、この制度は2026年3月までの時限措置であり、今後の延長は未定とされています。一方、相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円まで贈与時に非課税で将来的に相続財産に加算されます。中古マンション購入資金を一括贈与するケースでも、贈与時に課税されないメリットがあります。
現金と不動産を比較すると、固定資産税や管理費などのランニングコストが発生する点で不動産は不利に見えます。けれども、現金はインフレ局面で実質価値が目減りするリスクを抱えます。日本銀行が公表する消費者物価指数は2024年度に前年比2.1%上昇し、2025年度も2%前後の見通しです。インフレに強い実物資産を組み込むことは、資産の実質的な価値を守るうえで合理的といえます。
税制面では、小規模宅地等の特例が賃貸用マンションにも適用可能です。被相続人が所有する賃貸用宅地については200㎡まで50%の評価減を受けられるため、区分所有でも敷地持分がある場合には恩恵を受けられます。なお、この特例は「貸付事業用宅地等」に該当することが条件で、空室率が高いと認定されない事例もあります。したがって、空室を長期間放置しない体制づくりが節税効果を左右します。
物件選びで損をしないためのチェックポイント
ポイントは、相続対策と運用効率の両立を図ることです。まず立地に関しては賃貸需要が読みやすい駅徒歩10分圏内が基本ですが、近年はリモートワーク普及の影響で駅距離よりも生活利便性が重視される傾向があります。スーパーや病院、保育施設が徒歩圏にそろうエリアはファミリー層の定着率が高く、空室リスクを抑えやすくなります。
築年数は構造と規模で判断する必要があります。鉄筋コンクリート造(RC)は法定耐用年数47年ですが、実態として60年以上使用されるケースが多く、長期保有に適しています。ただし、昭和56年以前の旧耐震基準物件は金融機関の評価が低くなるため、耐震診断結果や補強工事の有無を必ず確認してください。
間取りや専有面積も収益性を大きく左右します。ワンルームは利回りが高い反面、賃料下落局面で競合が激しくなります。ファミリータイプは賃料の伸びが限定的ですが、入居期間が長い傾向があり、結果として修繕回数を減らせます。投資目的が相続対策なら、長期的な賃貸需要の安定を優先する戦略が有効です。
売買契約時は登記簿だけでなく、管理組合の長期修繕計画書を確認してください。修繕積立金が滞納されている物件では、将来的に一時金を徴収される恐れがあります。また、賃貸中の物件は「賃貸借契約書」を入手し、敷金や更新料の扱いを明らかにしておくことがトラブル防止につながります。これらの書面を精査することで、予期せぬコストを早期に把握できるため、実質利回りを正確に算出できます。
投資スキームと家族信託の活用法
実は、中古マンション投資と家族信託を組み合わせることで、認知症リスクや争族(そうぞく)リスクを同時に低減できます。家族信託とは、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に託す仕組みで、成年後見制度と異なり運用の自由度が高いのが特徴です。たとえば、物件の名義だけを信託へ移し、賃料収入を委託者である親が受け取り続ける形にすれば、生活資金を確保しつつ管理を子世代に移行できます。
金融機関によっては、信託口口座での家賃受け取りに対応していない場合があります。しかし、2025年9月時点で三井住友信託銀行や三菱UFJ信託銀行は個人向け家族信託サポートを提供しており、区分マンションでも組成実績があります。信託契約で受託者の権限を明確にすることで、売却や再投資の判断をスムーズに行えるため、相続発生時に財産分割が停滞するリスクを避けられます。
さらに、生命保険を組み合わせた「返済原資の確保」も有効です。団体信用生命保険(団信)付きローンを利用すれば、借入残高は被相続人の死亡時に弁済され、家族には無借金の物件と賃料収入が残ります。相続財産の評価はローン残債控除後の価格で計上されるため、節税効果も持続します。
ただし、借入金利が上昇局面に入った場合、長期固定金利を選択すると返済総額が増え、利回りが低下する懸念があります。固定か変動かを選ぶ際は、日本政策金融公庫の長期金利動向や日銀の金融政策決定会合議事要旨を参考にし、ストレスシナリオでシミュレーションを行いましょう。
管理と出口戦略でトラブルを回避する
まず、長期保有を前提とする中古マンション投資では、管理会社の選定がパフォーマンスに直結します。賃貸管理手数料は家賃の3〜5%が一般的ですが、24時間コールセンターや原状回復工事の手配などサービス内容は千差万別です。委託契約前に、入居者クレーム対応や滞納保証の範囲を確認しておくことが、将来的な家族の負担軽減につながります。
出口戦略としては、相続前に売却する「生前整理」と、相続発生後に売却する「死亡後売却」があります。生前整理は税制面で贈与税がかかる可能性がありますが、被相続人自身が判断できるうちに市場動向を見極められる利点があります。死亡後売却では相続税の申告期限(10か月以内)までに売却を完了しなくても、申告後3年以内なら更正の請求で税額を調整できる場合があります。
売却時の譲渡所得税率は保有期間5年超で20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)に軽減されます。相続を経た物件は前所有者の取得日を引き継ぐため、築古物件ならほとんどが長期譲渡扱いになります。ただし、令和5年度より導入されたインボイス制度で、仲介手数料の消費税処理が煩雑化しています。適格請求書発行事業者でない仲介会社に依頼すると、仕入税額控除ができない点に注意してください。
最後に、災害リスクも忘れてはなりません。気象庁によると2024年の台風発生数は平年比120%と高水準で推移しており、浸水リスクの高い地域では火災保険料が年々上昇しています。ハザードマップを確認してから購入を判断し、保険加入時は水災補償の有無を必ずチェックしましょう。これらの備えが、ご家族の将来を守る安全網となります。
まとめ
本記事では、マンション投資 中古 相続対策という視点から、評価額の圧縮効果、2025年度税制との相性、物件選びの勘所、家族信託や団信を活用したスキーム構築、そして管理と出口戦略までを一気通貫で解説しました。現金だけを保有するよりも、不動産を組み込むことで節税とインフレヘッジを同時に実現できる点が大きな魅力です。まずは家族で資産状況と将来のライフプランを共有し、金融機関や専門家に相談しながら、具体的なシミュレーションを作成してみてください。行動を先延ばしにしなければ、ご家族の安心と資産形成を同時にかなえる道筋が見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 不動産経済研究所「マンション市況レポート2025」 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本銀行「消費者物価指数と物価見通し」 – https://www.boj.or.jp
- 三井住友信託銀行「家族信託サービスのご案内」 – https://www.smtb.jp
- 国土交通省「令和6年度税制改正概要」 – https://www.mlit.go.jp
- 気象庁「台風統計資料」 – https://www.jma.go.jp

