親族が亡くなったあとに高額な相続税が発生し、慌てて土地を手放したという話は珍しくありません。アパート経営であれば評価額を下げつつ賃料収入も得られると聞いても、空室リスクや借入への不安が先立ち、最初の一歩を踏み出せない人も多いでしょう。私は十五年以上にわたり、オーナーの悩みを現場で見てきました。その経験から言えるのは、実例を知るほど判断材料が増え、最適な相続対策へ近づけるという事実です。本記事では「アパート経営 体験談 相続対策」を軸に、制度・数字・生の声を交えて具体的な行動指針を示します。
アパート経営が相続対策になる理由
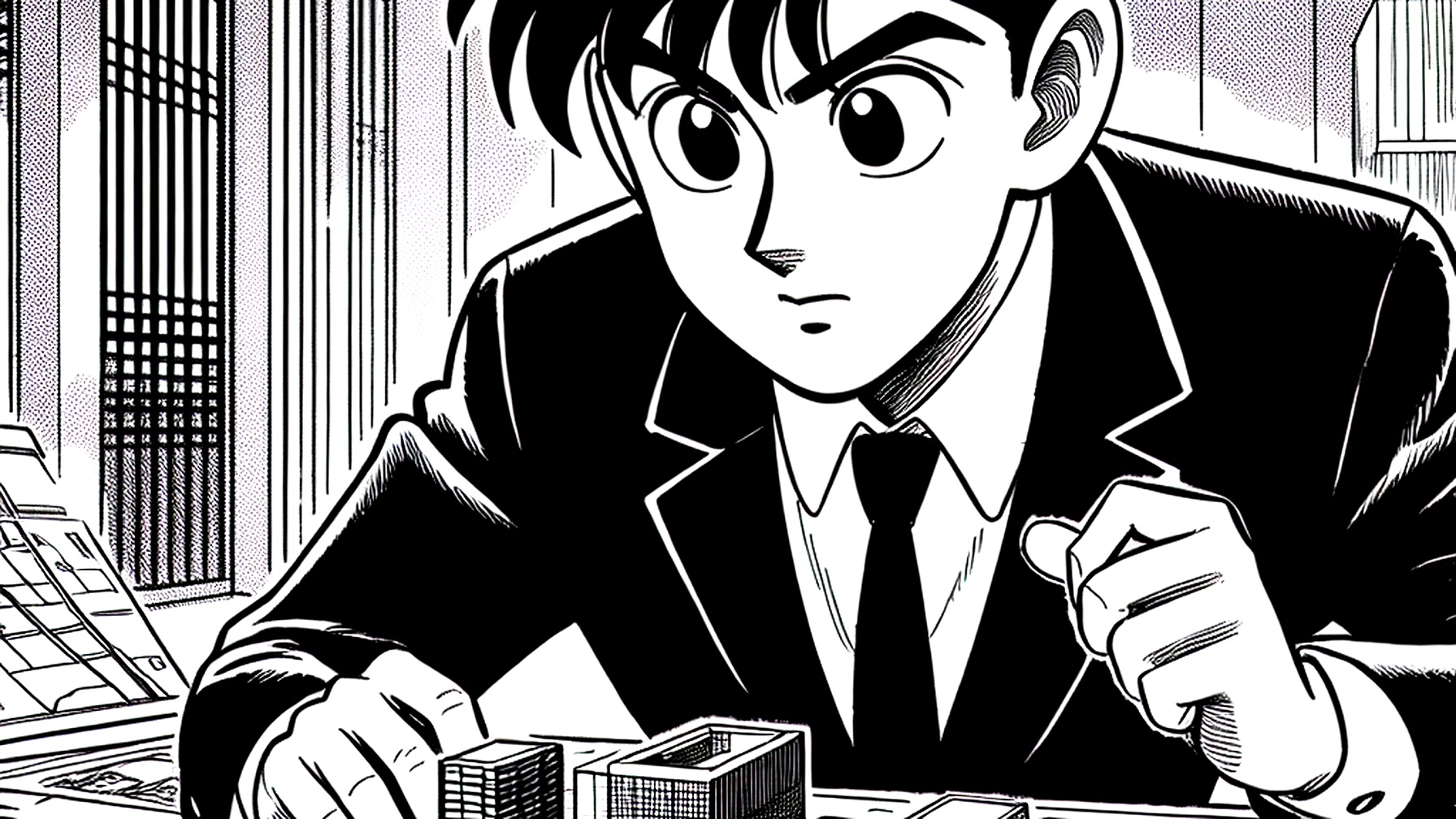
まず押さえておきたいのは、賃貸用不動産が相続財産の評価額を圧縮できる点です。国税庁の財産評価基本通達では、貸家建付地や貸家は自用地より低い評価となり、相続税の負担を抑えられます。つまり、現金のまま置いておくよりアパートに組み替えるほうが課税対象額を減らせる仕組みです。
さらに、小規模宅地等の特例が適用されると、330平方メートルまでの貸付事業用宅地は最大50%の減額評価が可能です。2025年度もこの特例は継続しており、適用条件を満たせば大幅な税負担の軽減が見込めます。制度は毎年見直しがありますが、現時点で廃止の動きは出ていません。
ただし、評価減を狙うだけでは不十分です。賃料収入が赤字になれば、借入返済で生活資金を圧迫し、本末転倒となります。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善したものの、依然として高い水準です。長期の視点でキャッシュフローを確保しつつ、相続時の評価減を両立させる設計が要となります。
失敗と成功を分けた体験談から学ぶポイント
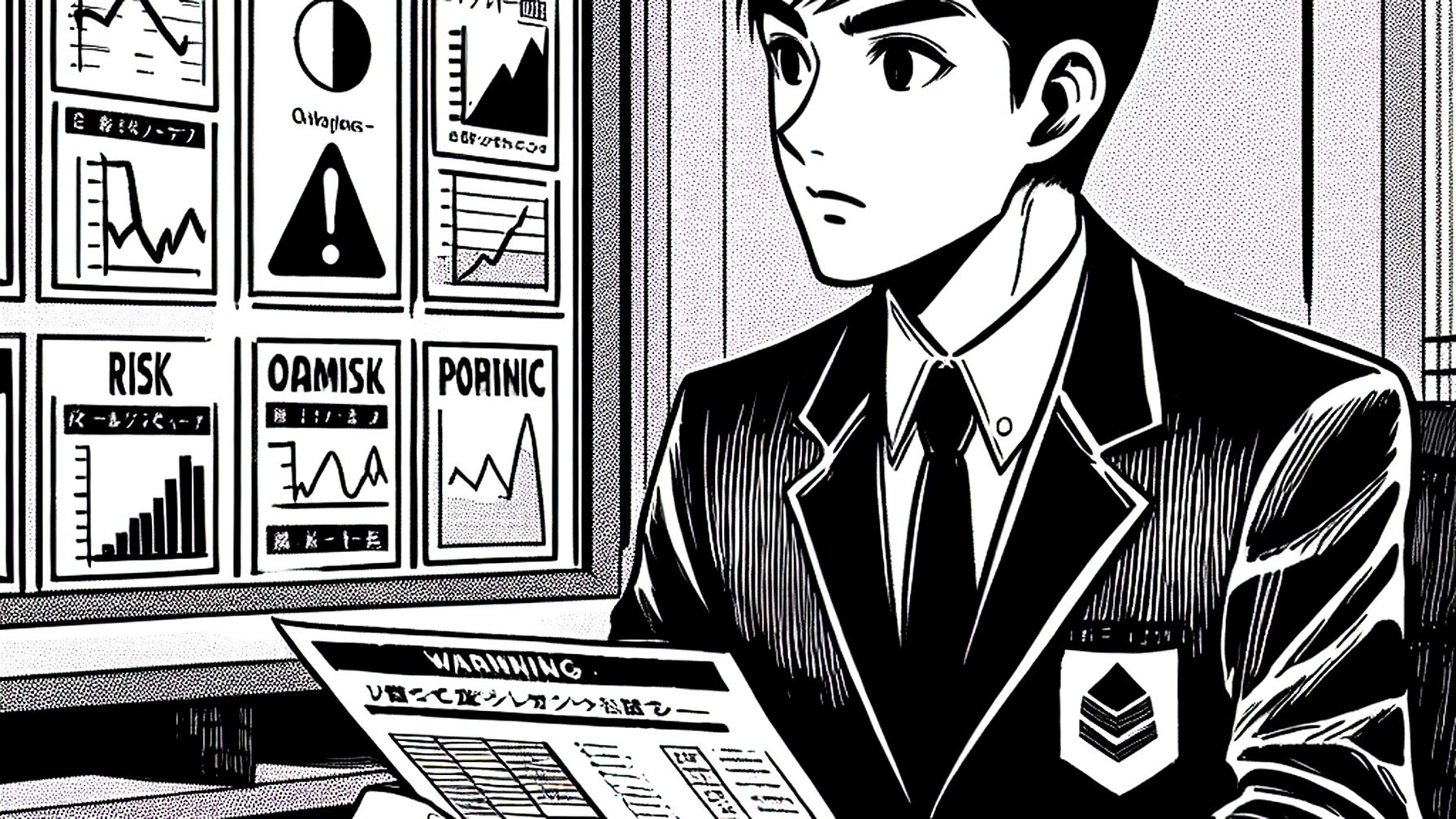
重要なのは、数字だけでなくオーナーの体験談を通じて判断材料を増やすことです。ここでは、私が伴走した二つの事例を紹介し、分岐点を整理します。
鈴木さん(60代)は、駅徒歩20分の郊外地で木造8戸のアパートを新築しました。建築費は1億2,000万円で、自己資金は1割。完成当初は満室でしたが、築5年で空室が3戸に増え、家賃を1割下げても決まらず、年間キャッシュフローはマイナスに転落しました。原因は、賃貸需要の読み違いと修繕費の過小見積もりでした。結果として相続評価は下がったものの、借入返済のために子どもが自宅を担保に追加提供する事態になりました。
一方で、田中さん(50代)は既存の更地を利用し、RC造15戸を1億8,000万円で建築しました。自己資金3割を投入し、完成後の家賃は市場平均より5%高く設定しました。要因は、単身世帯の増加が見込める大学近接エリアを選び、インターネット無料やIoT鍵など付加価値を付けた点にあります。築7年を迎えた現在も平均入居期間は4.1年で、空室は月平均1戸未満。年間キャッシュフローは400万円を維持し、評価減と収益確保を両立しています。
両者の差は、賃貸需要のデータ分析と長期修繕計画の有無に集約できます。空室率や家賃推移を精査せず楽観的に判断すると、相続対策どころか家計の負担増となるリスクが高いとわかります。
2025年度の税制と補助の現状を押さえる
ポイントは、最新の制度を活用しながら過度な期待を抱かないことです。2025年度の相続税基本控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」のまま据え置きで、大幅な見直し予定はありません。小規模宅地等の特例も継続していますが、親の生前に賃貸事業を行っていること、相続後も事業を継続することなど要件が明確化されつつあります。専門家と確認し、形式だけの賃貸経営にならないよう注意が必要です。
加えて、環境性能を高めた賃貸住宅への補助が追い風になっています。国土交通省と環境省が連携する「賃貸住宅省エネ化推進事業(2025年度)」では、断熱強化や高効率給湯器の導入に対して最大1,200万円の補助が受けられます。期限は2026年3月交付申請分までです。省エネ仕様は入居者ニーズの高まりとともに空室圧縮にも寄与するため、補助活用で建築費増を抑えつつ競争力を高める効果があります。
一方で、家賃支援給付金のようなコロナ時代の緊急制度はすでに終了しています。過去の補助実績だけで試算を組むと、予定収支が大きく狂うので注意しましょう。制度の有無は毎年チェックする姿勢が、長期の相続対策を成功させる鍵となります。
長期視点でキャッシュフローを守る方法
実は、アパート経営の成否は借入期間と金利条件に左右される面が大きいです。2025年9月時点でメガバンクの投資用ローン変動金利は年2.3〜3.2%、地方銀行は年2.8〜3.5%が主流です。金利が1%上昇すると年間返済額が数十万円単位で増えるため、初期段階で複数行を比較し、固定と変動の組み合わせを検討するとリスク分散になります。
また、維持費を過小評価しないことが重要です。管理委託費、固定資産税、修繕費を合計すると、家賃収入の20〜25%が目安となります。築10年以降は外壁塗装や給水管交換が重なりやすく、一時的に年間家賃の15%程度の出費が発生します。田中さんが成功したのは、竣工時から修繕積立口座を設け、月次キャッシュフローの15%を自動振替した点にあります。
さらに、入居者満足度を高める小さな施策も効果的です。無料Wi-Fiや宅配ボックスは一戸あたり月千円程度のコストで導入できますが、平均入居期間を半年延ばすだけで空室損失の削減効果が上回るケースが多いです。安定収益が続けば、相続発生時に追加借入をせずに納税資金を確保しやすくなり、家族の負担を軽減できます。
相続を見据えた出口戦略の立て方
まず、誰が事業を継ぐのかを早期に決め、遺言や家族信託で権利関係を整理することが欠かせません。事業承継計画が曖昧なまま相続が起こると、賃貸経営の意思決定が遅れ、空室や修繕の対応が後手に回ります。遺言作成は公証役場で10万円前後、家族信託は司法書士報酬を含めても50万〜100万円程度が相場で、将来のトラブル回避コストとしては高くありません。
次に、売却や組換えの可能性を定期的に検証しましょう。築20年を超えると修繕費は増加し、銀行の評価も下がりやすくなります。10年ごとに不動産会社へ査定を依頼し、売却益と保有益を比較することで、最適な時期を逃さずに済みます。税負担を抑えるためには、長期譲渡所得になる5年超の保有や、相続後3年以内の売却特例なども視野に入れると効果的です。
最後に、納税資金の確保策として生命保険を組み合わせる手段があります。被相続人を契約者兼被保険者、子を受取人とする終身保険を活用すると、500万円×法定相続人の非課税枠を使いつつ、死亡時に現金を確保できます。保険料を経費計上できない点は留意しつつも、アパート収入だけでは賄いきれない場合の安全弁となります。
まとめ
本記事では、アパート経営を相続対策として活用する仕組みと、体験談から得た成功・失敗の分岐点を解説しました。要は、節税効果だけでなく、空室率や修繕費を踏まえた実質収益を確保できるかどうかが勝負を分けます。制度の改正や補助金の有無は毎年変わるため、2025年度の情報を基にしても、継続的なアップデートが欠かせません。今できる行動として、①需要分析を伴う立地選定②長期修繕計画の策定③家族間での事業承継方針の共有を進めてください。そうすれば、資産を守りながら次世代へ円滑に引き継ぐ土台が整うはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 財産評価基本通達 – https://www.nta.go.jp
- 国税庁 相続税の申告のしかた 2025年版 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ化推進事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/sustainable
- 日本銀行 金融機関貸出金利推移 2025年8月 – https://www.boj.or.jp

