多くの投資家が「想定利回りは良いのに、手元に残るお金が少ない」と感じています。実質利回りを正しく把握できていないと、空室や修繕費が増えるたびに計画が狂い、不安が募るばかりです。本記事では「マンション投資 実質利回り いつ」をテーマに、測定のタイミングと算出方法をやさしく解説します。読み終えるころには、数字に振り回されず自分で判断できる基準が身につき、次の行動に自信を持てるようになります。
実質利回りとは何かを理解する
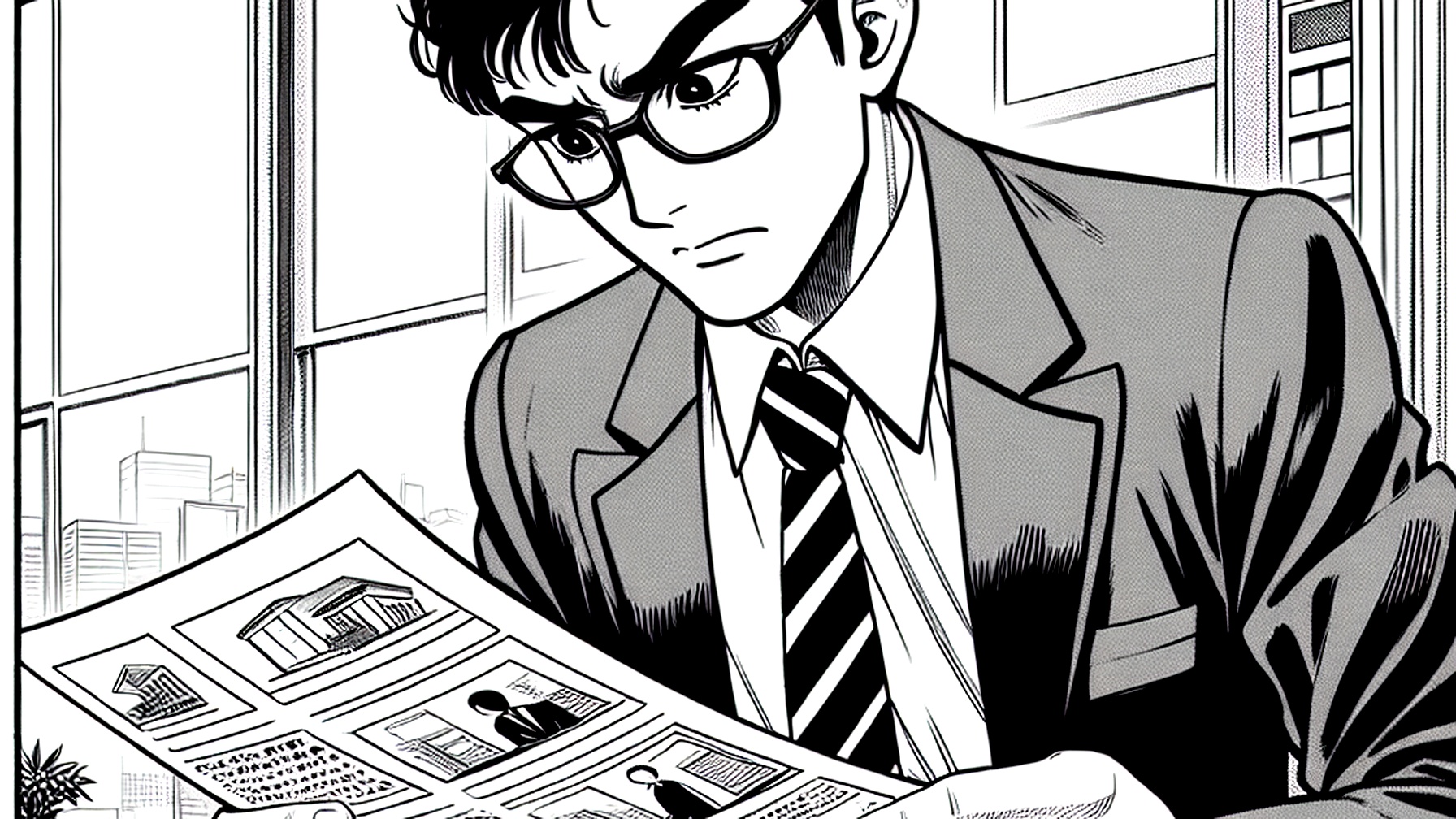
重要なのは、表面利回りと実質利回りの違いを区別することです。実質利回りとは、賃料収入から管理費や修繕費、税金などの諸経費を差し引き、自己資金を含む総投資額で割った指標を指します。
まず表面利回りは家賃収入を物件価格で割った単純な割合です。計算が楽なので広告に多用されますが、運用コストを無視しているため、実際のキャッシュフローを正確に示しません。一方で実質利回りは細かな費用を加味するため、物件ごとの収益性を比較しやすいメリットがあります。
たとえば東京都心のワンルームで、年間家賃が120万円、物件価格が3000万円の場合、表面利回りは4%です。しかし年間経費を30万円、取得時諸費用を200万円と仮定すると、実質利回りは(120万−30万)÷3200万で2.8%に低下します。つまり購入前に「経費をどこまで入れるか」を明確にしておくことが、現実的なシミュレーションにつながります。
実質利回りを測る最適なタイミング
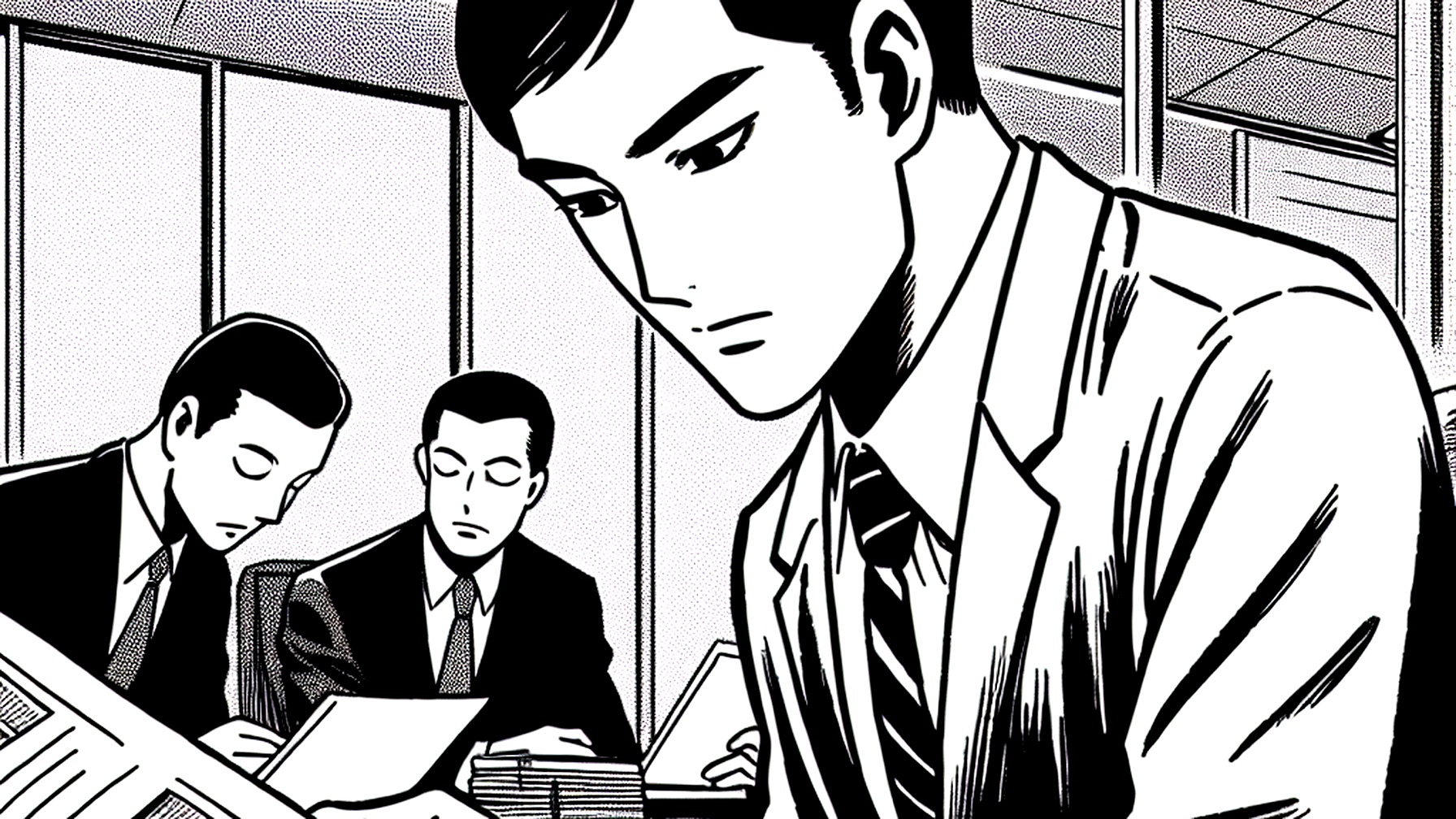
ポイントは、購入前と購入後で「いつ」計測するかを分けて考えることです。購入前は精度を高めるために複数のシナリオを準備し、購入後は定期的に実績を更新していきます。
購入前の試算では、金融機関から提示された金利、管理会社の見積もり、固定資産税評価額など、入手可能な資料をすべて盛り込みます。東京23区の平均空室率は2025年6月時点で5.4%(東京都都市整備局)ですが、自身の物件が築古か築浅かで差が生じるため、保守的に10%前後で計算するのが無難です。
購入後は決算期ごと、少なくとも年1回のタイミングで実質利回りを更新しましょう。修繕積立金の改定や金利の見直しなど、コスト構造は年々変化します。特に築10年を過ぎると大規模修繕の積立額が上がるケースが多いため、その時点で見直すと前倒しの対策が可能です。
実は空室が続いた月に慌てて再計算するより、定期的なモニタリングの中に空室期間を織り込む方が、長期的な収益管理には有効です。数値のブレを平均化することで、感情に左右されない判断ができます。
資金計画と税金が利回りに与える影響
まず押さえておきたいのは、自己資金と借入割合によって実質利回りの見え方が大きく変わる点です。自己資金を増やすと毎月の返済額が減りキャッシュフローは改善しますが、分母である投資総額が下がり過ぎると利回りが見かけ上高くなるため注意が必要です。
税金面では、所得税・住民税の節税効果を期待して減価償却を利用するケースが多く見られます。たとえば木造アパートなら最短4年、新築RCマンションなら47年と、耐用年数が違うだけで年間の経費計上額が大きく変わります。減価償却が切れた後も利回りが維持できるかどうかを、購入前にシミュレーションすることが大切です。
2025年度の税制では、住宅ローン控除は自己居住用に限られるため投資用物件には適用されません。ただし損益通算によって、給与所得と合算することで所得税が軽減される可能性があります。実質利回りを語る際には、税引き後の手取りベースで評価する習慣を身につけましょう。
さらに、繰上返済を検討するときはキャッシュフローと金利水準のバランスが鍵になります。金利が1%未満で固定されている場合、運用利回りがそれを上回る限り繰上返済は急がない方が得策です。つまり資金計画と税戦略が、実質利回りの持続性を左右する重要な要素となります。
データで読み解く今後の利回り動向
実は、平均利回りだけを見ても個別物件の判断材料には不足しますが、市場の方向性をつかむ手がかりにはなります。日本不動産研究所によると、2025年9月の東京23区ワンルーム表面利回りは4.2%で、前年同期比0.1ポイント低下しました。価格上昇と賃料横ばいが同時に進んでいるため、実質利回りはじわりと圧縮されています。
一方、同じデータでアパートの表面利回りは5.1%と相対的に高い水準を維持しています。しかし木造アパートは修繕周期が短く、実質利回りが大きく削られる傾向があります。つまり表面利回りが高いからといって安易に飛びつくと、想定外の出費でキャッシュフローが悪化するリスクがあるのです。
不動産経済研究所の調査では、新築マンションの平均価格が2025年9月時点で7580万円、前年より3.2%上昇しました。価格が上がり続ける局面では出口戦略としての売却益が期待できますが、賃料上昇が追いつかないと実質利回りはさらに下がります。そのため、今後は「購入後何年で修繕費が増え、家賃がいくら上がるか」という長期的な視点が欠かせません。
加えて、国内金利は2025年4月の政策修正で長期金利が1%台前半に乗ったまま推移しています。金利上昇局面では借入コストが上がり、実質利回りを圧迫します。固定金利か変動金利かを選ぶ段階で、金利上昇シナリオを織り込む必要があるでしょう。
実質利回りを高める運用術
まず空室期間を短縮する工夫が、最も直接的に利回りを押し上げます。具体的には、内見時の第一印象を高めるために壁紙や照明を部分的にリニューアルし、初期費用を抑えつつ賃料は維持する手法が効果的です。コストは1室あたり10万円前後で済むことが多く、1か月空室を埋めるだけで回収できるケースも珍しくありません。
また管理会社との契約形態を見直すことも有効です。サブリース(家賃保証)は空室リスクを低減できますが、保証賃料が相場の90%前後に設定されるため実質利回りが目減りします。エリアや築年によっては、集金代行方式に切り替えた方がトータルの収益が向上する場合があります。
さらに、家賃以外の収入源を確保すると実質利回りが底上げされます。代表例はインターネット使用料の共益費化や太陽光パネルの売電収入です。共用部電力を賄える程度でも、電気料金が下がれば維持コストの削減につながり、実質利回りの改善に寄与します。
最後に、運用データをクラウドで一元管理し、毎月の入出金を可視化することが欠かせません。視覚的に推移を把握できれば、予兆段階で収益悪化に気付けます。つまり、日常の小さな改善を積み重ねることでしか、実質利回りは上がらないというのが長年の経験で得た結論です。
まとめ
実質利回りは、取得前のシミュレーションと取得後の定期モニタリングを通じて磨かれます。購入時に経費を漏れなく見積もり、年1回の決算で数値を更新すれば、突然の空室や金利上昇にも慌てずに済むでしょう。今日得た知識を基に、まず手持ち物件の利回りを再計算してみてください。数字の本当の姿が見えれば、次に取るべき行動は自然と浮かび上がります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 東京都都市整備局「住宅市場動向調査」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「土地総合情報システム」 – https://www.land.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計」 – https://www.stat.go.jp

