家賃収入で生活の安定を図りたい、けれど「本当に高利回りは実現できるのだろうか」と不安を抱く人は多いものです。筆者も同じ悩みを経て、いまでは年間家賃収入3,000万円を超えるまでに成長しました。本記事では、初心者がつまずきやすいポイントを具体的な体験談とともに解説し、高利回りを狙ううえでの現実的な戦略を提示します。読み終えたとき、利回りだけに惑わされず、確かな収益物件を選び抜く力が身につくはずです。
なぜ高利回りだけを追いかけてはいけないのか
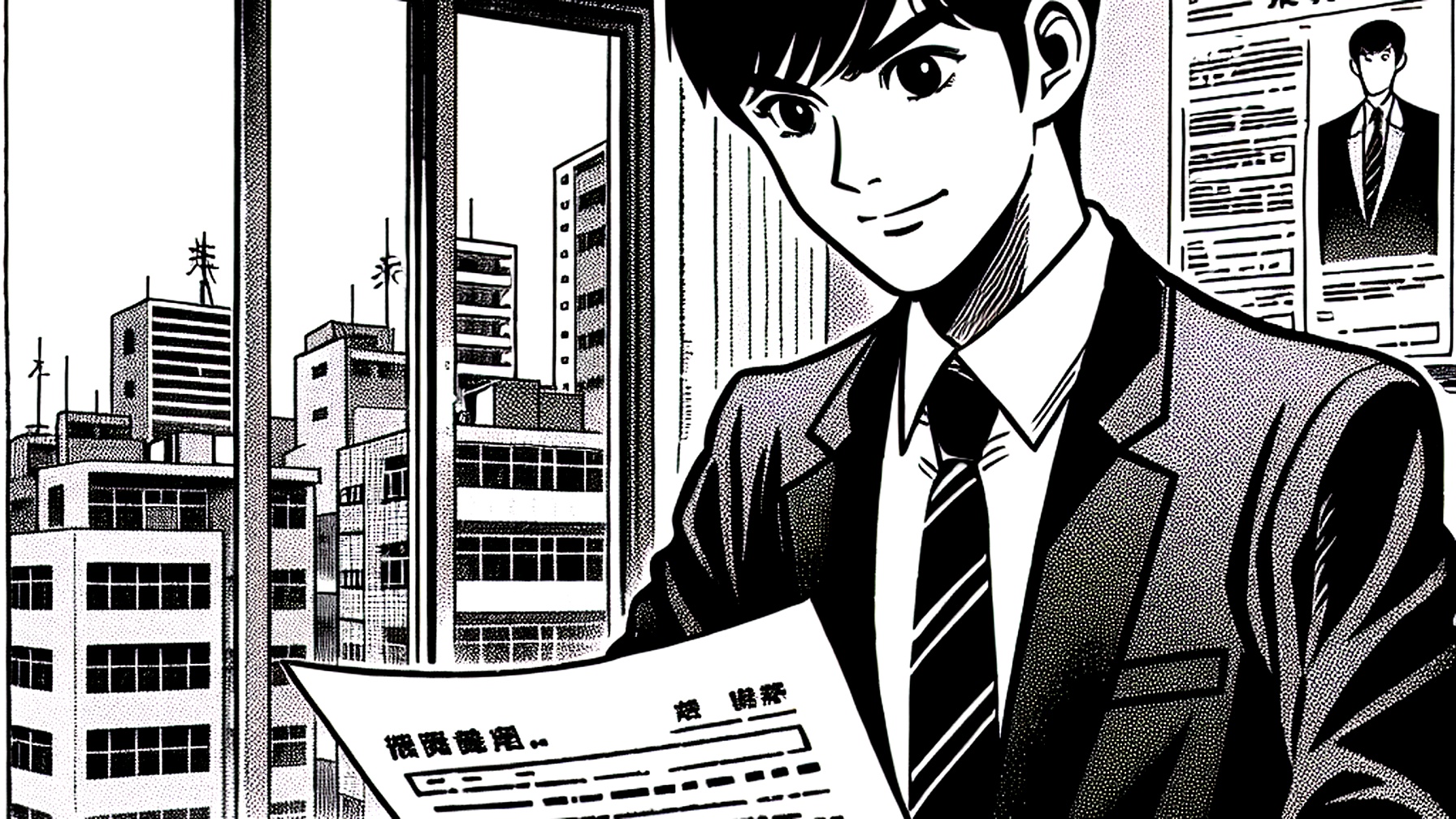
重要なのは、表面利回りの数字が高いほど実質収益も高いとは限らない点を理解することです。日本不動産研究所が公表した2025年9月時点の平均表面利回りは、東京23区のワンルームで4.2%、アパートは5.1%と報告されています。地方で12%をうたう物件を見つけると魅力的に感じますが、運営コストや空室リスクを加味すると必ずしも得とは言えません。
私が初めて購入した郊外アパートは表面利回り12%でした。ところが購入後すぐに入居者が半分退去し、空室募集にかかった広告料が年間家賃の1.5か月分に達しました。さらに築25年のため給排水管の更新が必要となり、突発的な修繕費で利回りは実質6%まで低下しました。この経験で、利回りの裏側に潜む支出を見抜く視点が欠かせないと痛感しました。
つまり、想定収支を作成するときは管理費・固定資産税・修繕積立・広告料を厳しめに見積もる姿勢が大切です。保守的に計算し、それでもネット利回り(実質利回り)が地区平均を上回るなら投資判断に値します。
実際の体験談が教える買い付けの決め手
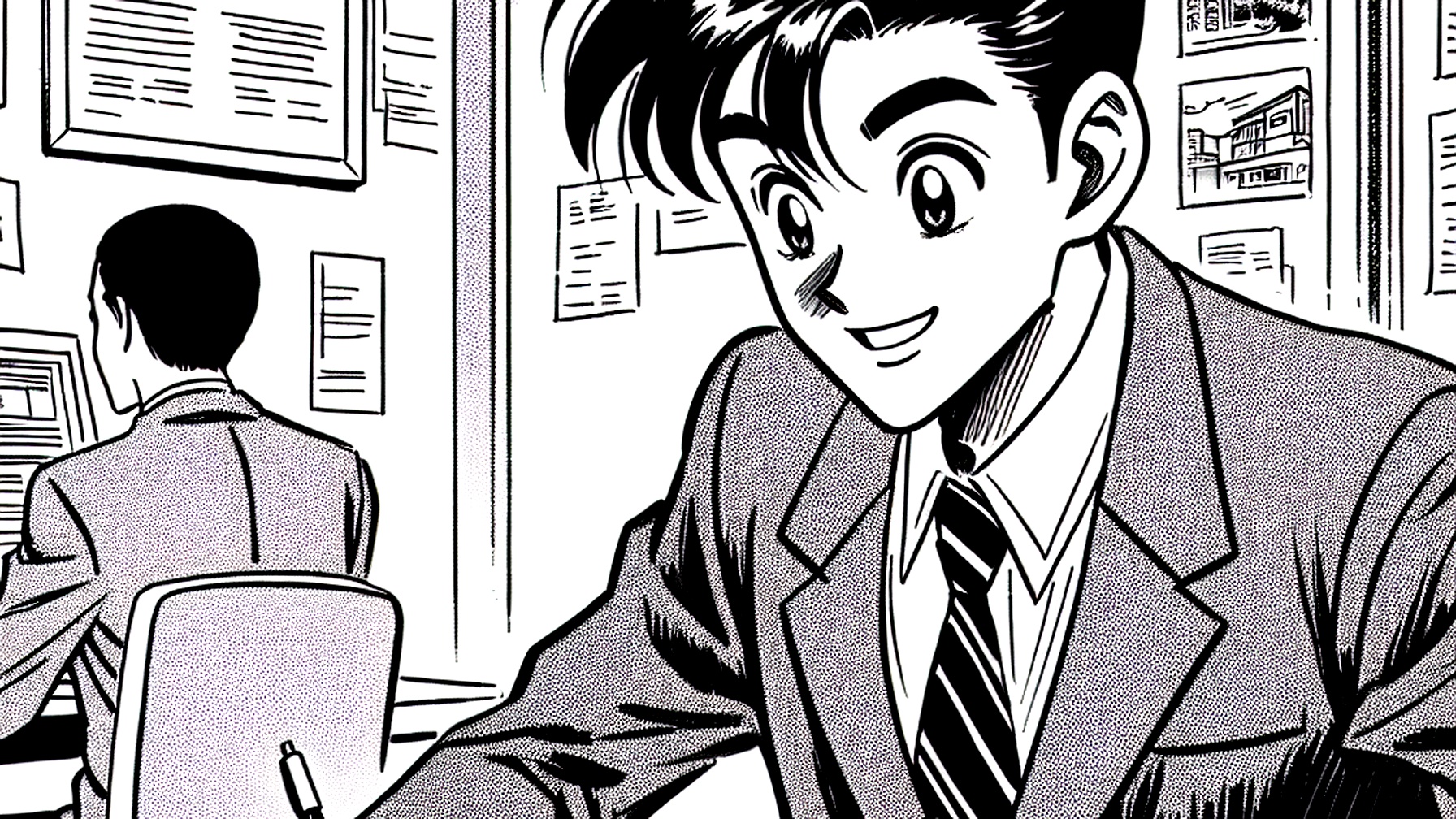
まず押さえておきたいのは、情報の質が高いほど高利回り物件に出会う確率が上がるという点です。筆者が利回り8.5%の築浅アパートを取得できたのは、地元仲介会社との関係構築に半年を費やしたからでした。メールではなく毎週足を運び、近隣で売却予定のオーナー情報を共有してもらえたのです。
買い付け時に意識したのは三つの指標だけでした。第一に実質利回りが7%以上確保できること、第二に最寄り駅から徒歩10分以内で人口減少率が低いエリアであること、第三に建物検査(インスペクション)で致命的な瑕疵がないことです。表面利回りが多少低くても、空室期間が短い立地ならキャッシュフローが安定します。
交渉では、売り急ぎの理由を探り出し、価格以外の条件—たとえば決済スピード—で貢献する姿勢を示しました。実は、売主の資金繰りが切迫していたため、通常1か月かかる決済を2週間で完了させる代わりに300万円の値引きを勝ち取れました。こうした柔軟な提案が高利回りに直結します。
高利回りを実現する運営改善術
ポイントは、購入後の運営で利回りをさらに底上げできるかどうかです。私が行ったのは、インターネット無料化と宅配ボックス設置による賃料アップ、そして省エネ改修での支出削減でした。インターネット無料化は一戸あたり月額1,800円のコストで、平均3,000円の賃料増を実現できました。
さらに、2025年度も継続中の国交省「賃貸住宅省エネ改修促進事業」を利用し、断熱サッシ交換に対し1戸あたり上限50万円の補助金を受給しています。これにより自己負担が抑えられ、光熱費の削減をアピールして入居率を97%から99%に向上させました。空室損失の低減は数字以上の効果をもたらします。
運営データを毎月集計し、管理会社と面談する習慣も欠かせません。空室期間が30日を超えたら家賃設定・広告方法・内装を即見直すルールを徹底しています。こうした小さな改善の積み重ねこそ、ネット利回り10%超えを維持するカギになります。
2025年度の融資環境と補助制度の使い方
実は、高利回り物件ほど融資条件が厳しくなる傾向があります。2025年9月時点で、都市銀行の賃貸向け融資金利は1.3%〜2.0%が目安ですが、築古・地方物件では金利が0.5ポイントほど上乗せされるケースが一般的です。そこで筆者は地方銀行と政策金融公庫の併用を選びました。公庫は耐震・省エネ性能が一定基準を満たす場合、最大20年の固定金利が利用できるからです。
さらに、購入後の改修費に対しては自治体の「空き家再生支援補助金(2025年度)」を活用しました。東京都世田谷区では上限200万円、対象経費の3分の2が補助されるため、長期優良住宅化リフォームを行ったうえで家賃を10%引き上げることに成功しています。補助申請には事前審査が必要なため、購入前からスケジュールに組み込むとスムーズです。
融資と補助金を組み合わせることで自己資金を温存でき、その分を次の投資に回せます。資金調達フェーズでどれだけ情報収集を徹底するかが、ポートフォリオ拡大スピードを左右します。
リスク管理と出口戦略をどう描くか
まず、リスクは「発生率×損失額」で考えると整理しやすくなります。自然災害リスクに備え、火災保険に地震補償特約を付けると年間保険料は3万円上がりますが、震度6強の被害で全損した場合の損害1,500万円をカバーできます。費用対効果を数値化すると保険料の意義が明確です。
また、金利上昇リスクには「返済比率25%ルール」を設定しました。家賃収入に対する元利返済額を25%以内に抑え、金利が2%上昇しても35%を超えないように計画しています。実際に2024年の一時的な金利上昇局面ではストレステストが機能し、キャッシュフローに大きな影響はありませんでした。
出口戦略としては、保有10年目に区分売却で利益確定し、収益を次の大型物件へロールオーバーする計画を描いています。2025年の税制では、長期譲渡(5年超)に適用される20.315%の譲渡税率が据え置かれているため、早期売却より手残りが増える計算です。購入時点で想定売却価格と想定修繕費をシミュレーションしておくと、出口が近づいた際に迷わず実行できます。
まとめ
本記事では、表面利回りに惑わされない物件選び、体験談に基づく交渉術、運営改善、資金調達、そしてリスク管理まで、収益物件で高利回りを得るための具体策を紹介しました。高利回りは一朝一夕で実現するものではなく、購入前の調査から購入後の改善まで一貫したプロセスが求められます。まずは保守的な収支計画を立て、信頼できるパートナーを見つけ、補助制度を積極的に活用することが第一歩です。行動を重ねるほど知見は蓄積し、やがてあなた自身の体験談が次の投資家を勇気づけることでしょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ改修促進事業 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都世田谷区 空き家再生支援補助金 – https://www.city.setagaya.lg.jp
- 日本政策金融公庫 住宅関連融資 – https://www.jfc.go.jp
- 気象庁 地震被害想定データ – https://www.jma.go.jp

