投資初心者の多くは、「築浅の物件は価格が高くて利回りが低いのでは」と悩みます。実は適切に選べば、高利回りと長期安定を同時に得ることが可能です。本記事では築浅 収益物件 高利回りという三つの条件を満たす物件を見つけるための考え方から、2025年度時点で使える資金調達の最新情報までを網羅します。読み終えた頃には、物件選定からリスク管理まで一連の流れが具体的にイメージできるはずです。
築浅物件が人気を集める背景
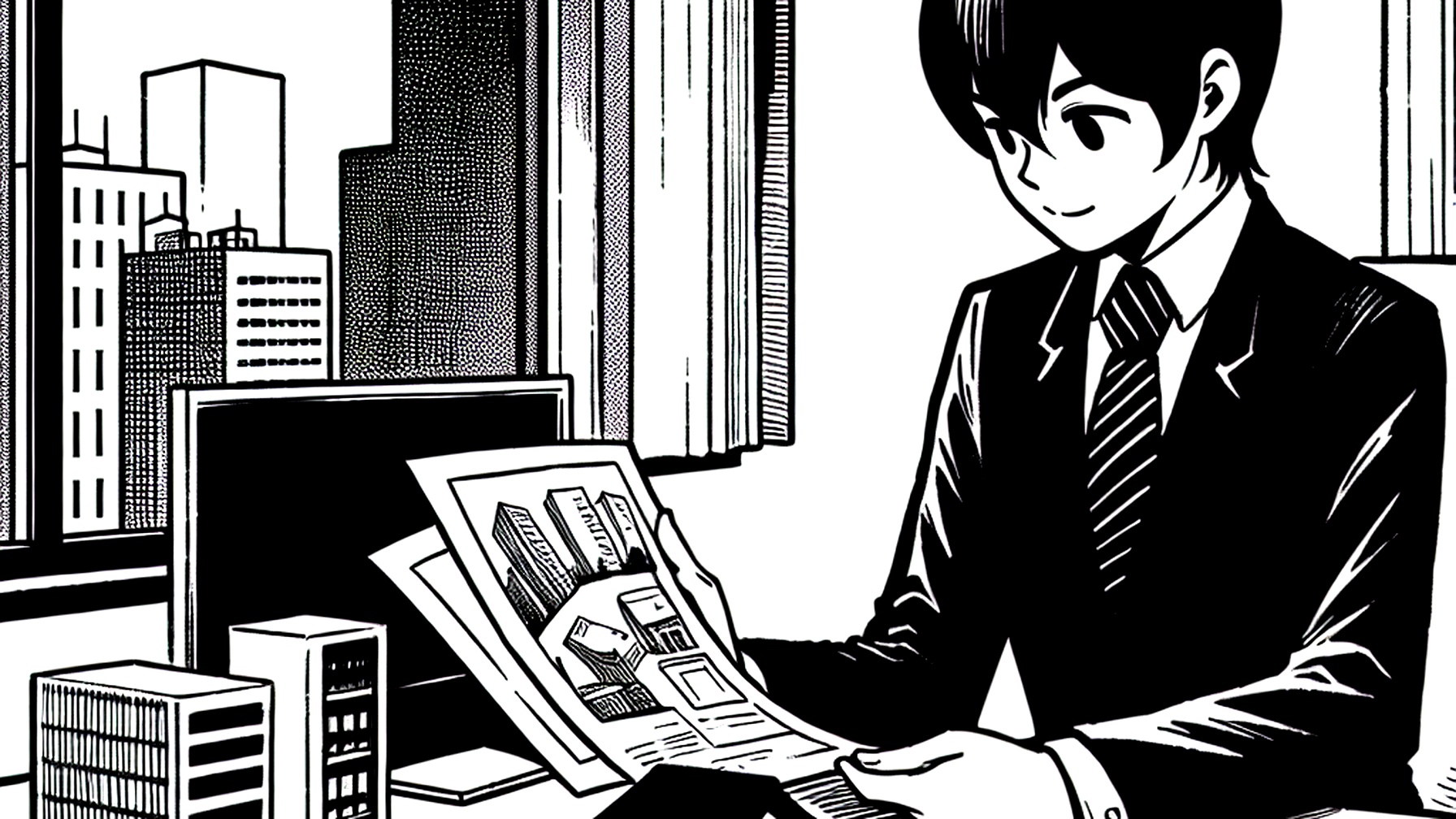
まず押さえておきたいのは、築浅物件が市場で評価される理由です。築5年以内のマンションは外壁や設備の劣化が少なく、当面の大規模修繕費を抑えられます。これによりキャッシュフローの不確実性が低くなり、金融機関の評価も高まります。
東京都心のデータを確認すると、日本不動産研究所による2025年9月時点の平均表面利回りはワンルームで4.2%です。しかし築浅で駅近の一部物件では5%超の事例も散見されます。家賃下落が緩やかなことに加え、大規模修繕準備金の積立が十分である点が高評価につながっています。
一方で購入価格が築古より高いのは事実です。したがって投資家は長期保有を前提に、家賃下落と修繕費の発生時期をシミュレーションする必要があります。築浅だからこそ得られる「初期10年間の安定」を収益計画に組み込むことが、成功への近道になります。
収益物件の利回りを正しく計算する
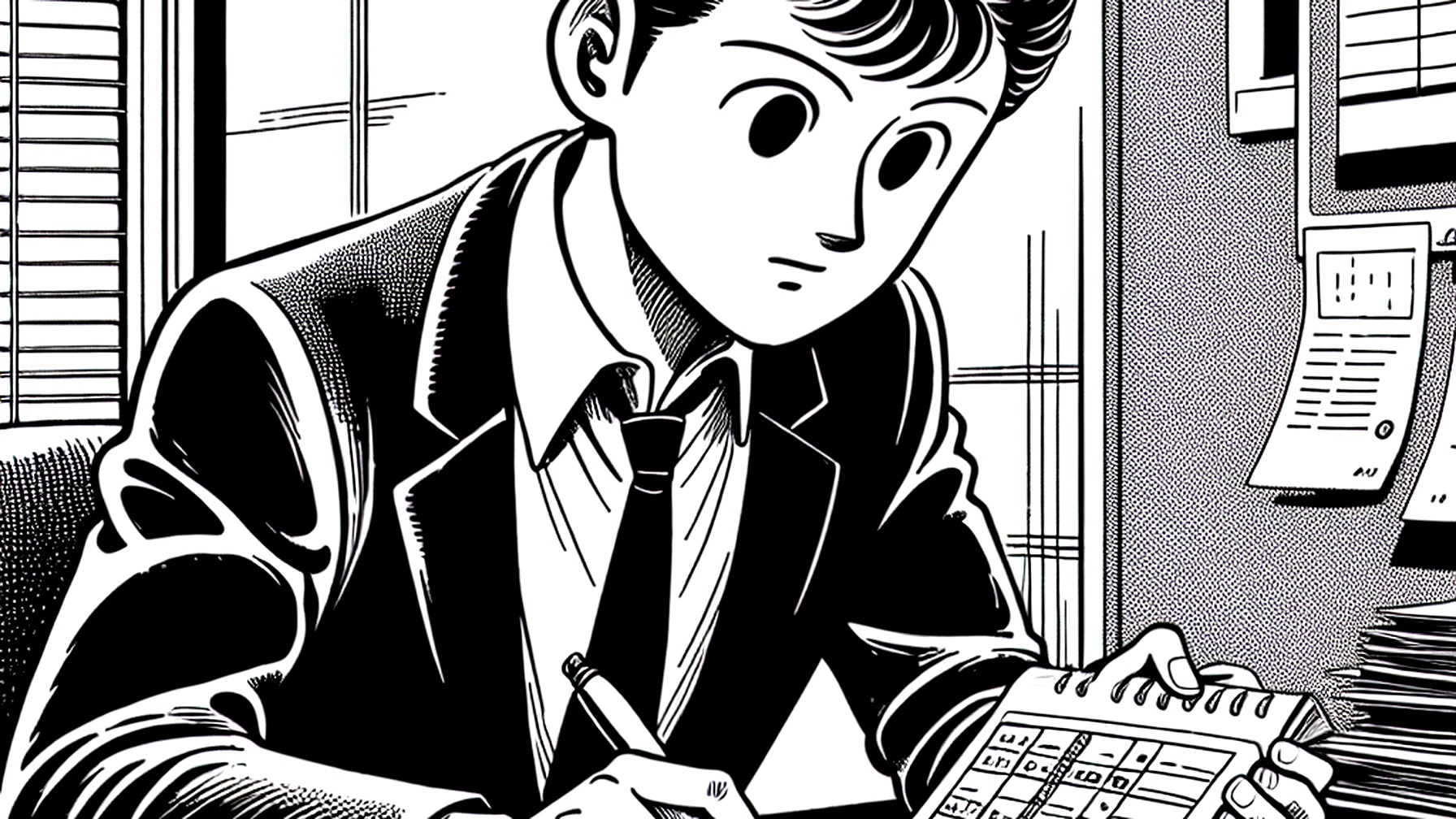
ポイントは、表面利回りと実質利回りを明確に区別することです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純指標で、市場比較に便利ですが経費を無視します。実質利回りは管理費や固定資産税などを差し引くため、キャッシュフローを測る上で欠かせません。
例えば価格3000万円、年間家賃180万円の区分マンションを想定します。表面利回りは6%ですが、管理費と修繕積立金で年間24万円、固定資産税10万円を差し引くと、実質利回りは4.6%に下がります。築浅であってもこの差は必ず発生します。
さらにローンを利用する場合、金利1.5%、返済期間30年とすると年間返済額は約125万円です。この数字を差し引いた後の手取りは21万円となり、手取り利回りは0.7%にとどまります。つまり借入条件が利回りを大きく左右するため、金利交渉と自己資金比率の調整が不可欠です。
高利回りを実現する立地と間取りの条件
重要なのは、築浅という条件だけでなく「稼ぐ力」を持つ立地と間取りを見極めることです。都心では駅徒歩5分以内のワンルームが安定的な需要を維持します。また大学やオフィスが集中するエリアでは1K〜1DKが強い一方、郊外のファミリー層向けでは2LDK以上が好まれます。
2024年に公表された総務省の転入出超過データによると、23区でも千代田区・港区・中央区が引き続き人口増でした。これらの区で築浅ワンルームを購入し、家具付き賃貸にすると平均5.5%程度の利回りを確保できた実例があります。家具付きは初期コストが増えますが、賃料を8〜10%上乗せできるため収益性が高まります。
一方で地方都市でも利回り8%超の築浅アパートが見つかる場合があります。しかし将来的な転出超過リスクや家賃下落幅が大きい点を見逃せません。人口動態に加え、再開発計画や企業誘致の動向を自治体の公開資料から確認し、実質利回りが将来も維持できるかを判断してください。
2025年度の資金調達と公的支援の最新事情
まず、金利環境は歴史的低水準が続いています。2025年9月時点で大手銀行の投資用不動産ローンは固定1.3%前後、地方銀行では1.7%〜2.0%が中心です。借入額が物件価格の80%以内なら、低金利のプロパーローンを引き出しやすくなります。
公的支援としては「不動産取得税の軽減措置(2025年度末まで継続予定)」が挙げられます。新築または築20年以内の優良住宅に該当する場合、課税標準から1200万円が控除され、取得後3〜6か月で還付される仕組みです。高額な築浅物件ほど恩恵が大きいため、物件探しの段階で適用要件を確認しましょう。
さらに東京都では「賃貸住宅省エネ改修助成(2025年度)」を実施しています。賃貸人が断熱改修を行うと、工事費の1/3(上限150万円)が補助されます。築浅物件でも省エネ性能を高めることで、入居付けを有利にしつつ実質利回りを押し上げることが可能です。
リスク管理で投資パフォーマンスを守る
実は、高利回り戦略ほどリスク管理の巧拙が結果を左右します。空室リスクに備えて家賃保証会社の利用を検討し、保証料を経費に組み込んでおくと安定感が増します。また火災保険と地震保険を長期契約にすることで、保険料の値上がりを抑えられます。
修繕リスクについては、築浅でも10年目以降に給排水管や外壁補修が発生します。国土交通省のガイドラインでは、30㎡程度のワンルームで給湯器交換費用は約20万円、外壁タイル補修は共用部分で戸当たり40万円とされています。毎月のキャッシュフローから1〜2万円を修繕積立として確保し、将来の大規模支出に備えるべきです。
売却リスクも軽視できません。人口減少エリアでは出口戦略が難しくなるため、購入時点で周辺の成約事例を必ずチェックします。築浅・駅近・需要の厚いエリアを選ぶことで、万一の売却でも損失を最小限に抑えられます。
まとめ
築浅 収益物件 高利回りを同時に実現するには、立地と間取りの需要分析、実質利回りの精密計算、そして低金利を生かした資金調達が鍵になります。さらに2025年度の不動産取得税軽減や省エネ改修助成を活用すれば、手取り収益を一段押し上げられます。空室・修繕・売却の三つのリスクを数値で管理し、キャッシュフローに余裕を持たせることが長期的な成功につながります。今日から自治体データと金融機関の条件を調べ、具体的な物件シミュレーションを始めてみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅における省エネ改修支援事業」 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都住宅政策本部「賃貸住宅省エネ改修助成」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 東京都主税局「不動産取得税のあらまし(2025年度版)」 – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp

