サラリーマンとして働きながら「給与だけでは将来が不安」と感じていませんか。私の相談者にも、家計のゆとりや老後資金の確保を目的に副収入を求める方が増えています。本記事では、実際に本業を続けながら月10万円以上の家賃収入を確立した成功事例を交え、初心者でも理解しやすい不動産投資のステップを解説します。読むことで、資金計画の立て方から物件選び、2025年度の支援制度までを一気に把握でき、自分に合った投資戦略を描けるようになります。
サラリーマンこそ不動産投資に向く理由
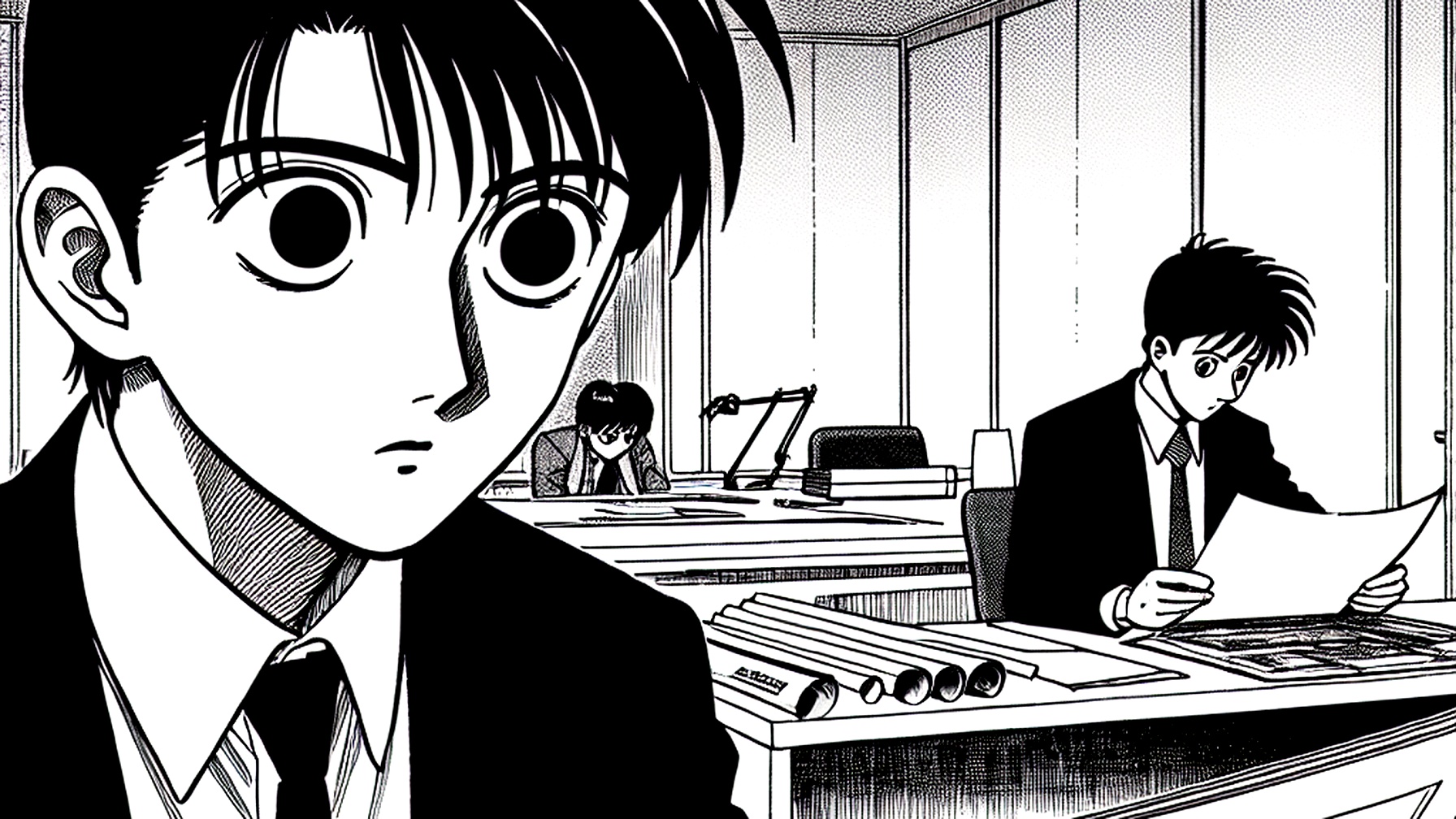
重要なのは、安定した給与収入が金融機関の信用力を高める点です。毎月の給料があることで、融資審査で評価されやすく、より好条件のローンを引き出しやすくなります。金融庁の2024年度「個人向け融資実態調査」でも、会社員は自営業者より平均で0.3%低い金利が提示されたと報告されています。
まず、定期的なキャッシュインがあることは返済比率のコントロールを容易にします。返済比率とは年間返済額を年収で割った値で、一般に35%以下が安全圏とされます。給与が安定していれば、この割合を保ちやすく、追加の物件取得も計画的に進められます。
また、会社員は社会的信用だけでなく、労働時間が読める点でも有利です。時間をブロックして物件の調査や管理会社との打合せにあてやすいため、無理のない範囲で投資を継続できます。つまり、本業の安定が投資リスクの緩衝材となり、長期で着実に資産を増やせるのです。
キャッシュフローを生む仕組みを理解する
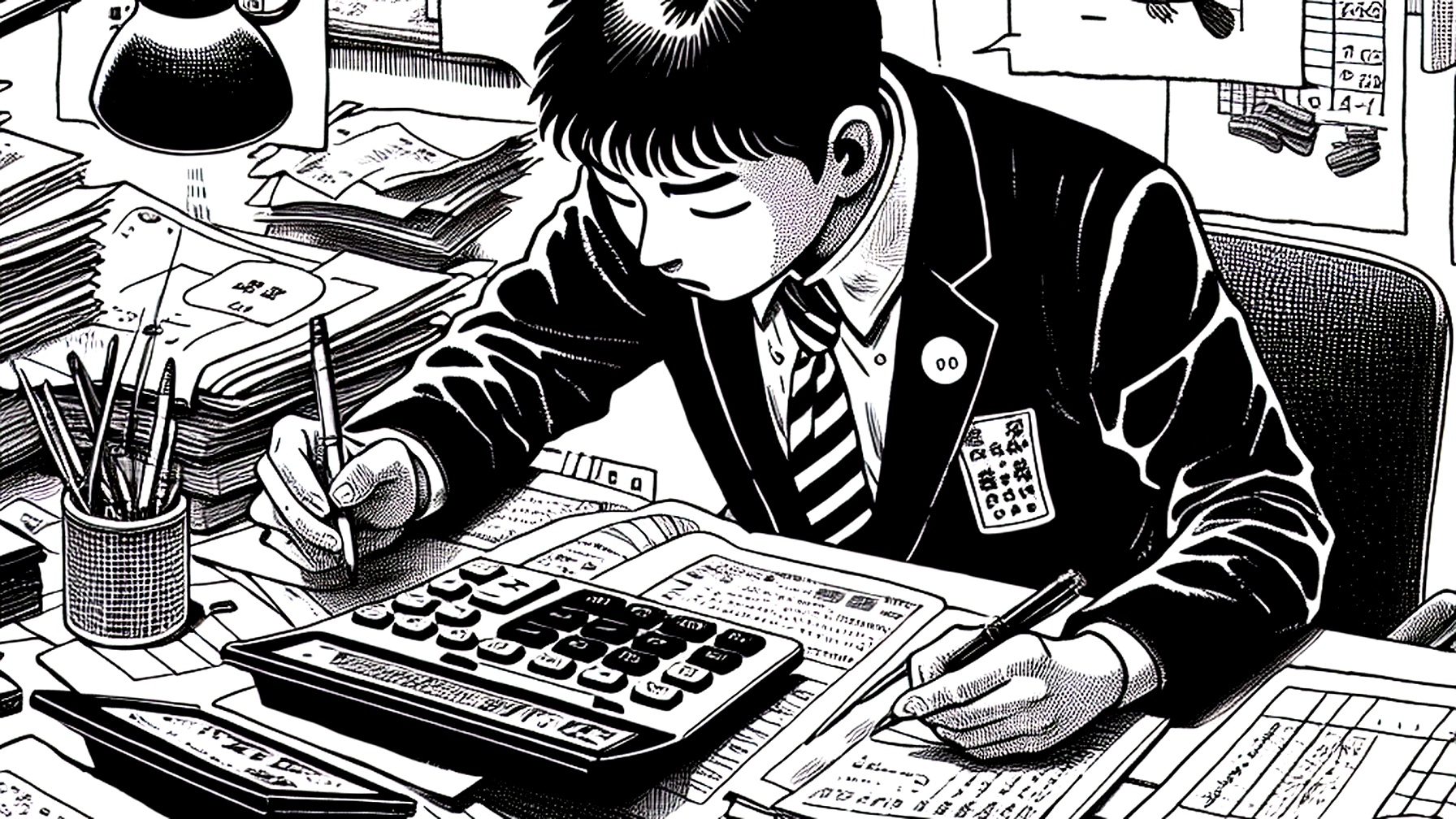
ポイントは、家賃収入から諸経費とローン返済を差し引いた「手残り」を最大化することにあります。国土交通省の賃貸住宅市場統計(2025年3月公表)では、都内ワンルームの平均利回りは4.2%、地方中核市の中古アパートは7.8%でした。数字だけを追うのではなく、空室率や修繕費まで含めた実質利回りで判断する姿勢が欠かせません。
たとえば、家賃6万円のワンルームを1戸保有した場合、管理費・修繕積立金で月8千円、ローン返済で3万5千円が出ていきます。さらに固定資産税を月割り換算すると約4千円です。残るのは月1万3千円ですが、退去による空室リスクを見込んで手残りの30%を内部留保すると、手取りは約9千円となります。この計算を基に複数戸を組み合わせ、毎月10万円のキャッシュフローを目指していきます。
実は、金利上昇に備えたシミュレーションも大切です。日本銀行は2025年4月にマイナス金利を解除しましたが、短期プライムレートは0.85%で推移しています。仮に金利が1%上昇しても手残りが黒字でいられるよう、借入期間や自己資金比率を調整することが安全運転につながります。
成功事例① 都内ワンルーム投資で本業+月3万円
まず押さえておきたいのは、人口集中エリアの空室リスクの低さです。都内勤務のAさん(32歳、IT企業)は、2023年に築15年のワンルームを2,100万円で購入しました。自己資金は300万円、残りは金利1.4%、35年ローンです。
Aさんは職場に近い物件を選び、自ら内覧して回遊動線や日当たりを確認しました。その結果、賃料相場より2千円高い6万5千円で入居者を確保できました。管理は24時間対応の代行会社に委託し、月2千円の管理料でストレスなく運用しています。購入初年度の年間手残りは約36万円、当初目標だった「通信費と保険料を家賃で払う」を達成しました。
さらに、2年目には家賃保証会社の見直しで年間コストを1万円削減し、手残りが月3万円台に上昇しています。本業への影響がほとんどない点が精神的にも大きなメリットだとAさんは語ります。この事例は、小規模でも着実にキャッシュフローを積み上げる好例と言えるでしょう。
成功事例② 地方中古アパート再生で月7万円
一方で、高利回りを求めるなら地方の中古アパート再生が選択肢になります。Bさん(40歳、メーカー勤務)は、地方中核市で築28年の木造アパート4戸を1,600万円で取得しました。金融機関からは金利2.2%、期間25年の融資を受け、自己資金を450万円投入しています。
購入後すぐに空室が2戸ありましたが、Bさんはリフォームに60万円を投じ、デジタルロックと無料Wi-Fiを設置しました。国土交通省補助事業「既存住宅省エネ改修補助金(2025年度)」を利用し、断熱窓改修費の1/3にあたる12万円の補助を受けたことで、初期コストを抑えられました。結果として家賃を1戸あたり5.5万円に設定でき、年間収入は264万円に達しています。
維持費と返済を差し引いた後の手残りは月約7万円で、5年目には投下自己資金を回収できる計算です。Bさんは「地方でも需要を見極め、付加価値を与えれば家賃を下げずに勝負できる」と語り、実際に管理会社から追加仕入れの提案が来るほど信頼を築いています。
2025年度の支援制度と融資環境をチェック
まず、2025年度も継続している制度として「住宅ローン控除(投資用は対象外)」や「不動産取得税の軽減措置」があります。投資家が直接利用できる制度は限られますが、省エネ改修やバリアフリー化に関する国の補助金は賃貸物件でも活用可能です。特に、前述の既存住宅省エネ改修補助金は、断熱工事や高効率給湯器の導入費用の最大1/3を補助します(申請期間は2026年3月まで)。
また、地方銀行や信用金庫は「地域創生融資枠」を設け、空室率改善に寄与する事業計画に対して金利優遇を行っています。金融機関のサイトで公表される最新金利をチェックし、複数行に同時打診することが肝要です。さらに、日本政策金融公庫の「中小企業事業資金」では、サラリーマン名義でも副業としての賃貸事業に融資が下りるケースが増えており、自己資金1割で調達できた例もあります。
大切なのは、制度を「使えそうだから使う」のではなく、長期的なキャッシュフローにどう影響するかを検証したうえで活用することです。補助金は確かに魅力的ですが、申請や報告の手間と比較してリターンが見合うか冷静に判断しましょう。
リスク管理と出口戦略で未来を描く
結論として、成功事例に共通するのは「出口から逆算した計画」です。物件を保有し続ける場合でも、最終的に売却する場合でも、収益性が下がる前に手を打つ準備が欠かせません。
まず、空室リスクは需給バランスの変化で顕在化します。定期的に人口動態と賃貸需要のデータを確認し、賃料改定や設備更新を前向きに検討しましょう。一方で、自然災害リスクは地震保険と火災保険でヘッジできます。地震保険料率は2024年10月改定で平均4.5%上がりましたが、補償額を見直してもトータルコストは月数百円の差しかありません。
さらに、ローン残高と物件価値の差である「エクイティ」を定期的に把握することが重要です。不動産仲介大手の調査によれば、築20年を超える木造アパートでも、リフォームと運営成績次第で購入時価格の90%で売却できた例があります。保有か売却かを判断するために、年1回は査定を取り、出口の選択肢を持ち続けましょう。
最後に、複数物件を所有する場合はキャッシュフローを束ね、ローンの一本化や繰上返済も選択肢となります。金利交渉は残債1,000万円以上で効果が出やすく、実例では0.3%の引き下げで年間返済額が15万円減少したケースが報告されています。
まとめ
本記事では、サラリーマンが不動産投資で月10万円の純収入を得るまでの道筋を、都内ワンルームと地方アパートの成功事例を交えて解説しました。安定した給与を信用力に変え、キャッシュフローを精緻に計算し、2025年度の制度や融資を賢く使うことが鍵となります。まずは生活防衛資金を確保したうえで、小さく始めて学びながら拡大する戦略を取りましょう。今日からできる第一歩として、通勤ルートの賃貸需要を調べ、物件情報を毎日1件確認する習慣をつけてみてください。行動の積み重ねが、将来の安定と自由につながります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局賃貸市場統計 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 個人向け融資実態調査 2024 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 短期プライムレート推移 2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省 既存住宅省エネ改修補助金 2025年度要領 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 不動産経済研究所 不動産価格指数レポート 2025年上期 – https://www.fudousankeizai.co.jp

