アパート経営を始めると、物件の管理をどうするかで悩む人が多いものです。自分で全部こなすべきか、管理会社に任せるか、それともサブリースを利用すべきか――どの方法にも長所と短所があります。本記事では「アパート経営 管理方法 比較」をテーマに、初心者でも理解できるよう各方式の特徴と費用感、最新トレンドを整理します。読了後には、自分に合った管理スタイルを選ぶための判断軸が見えてくるはずです。
管理方式にはどんな選択肢があるのか
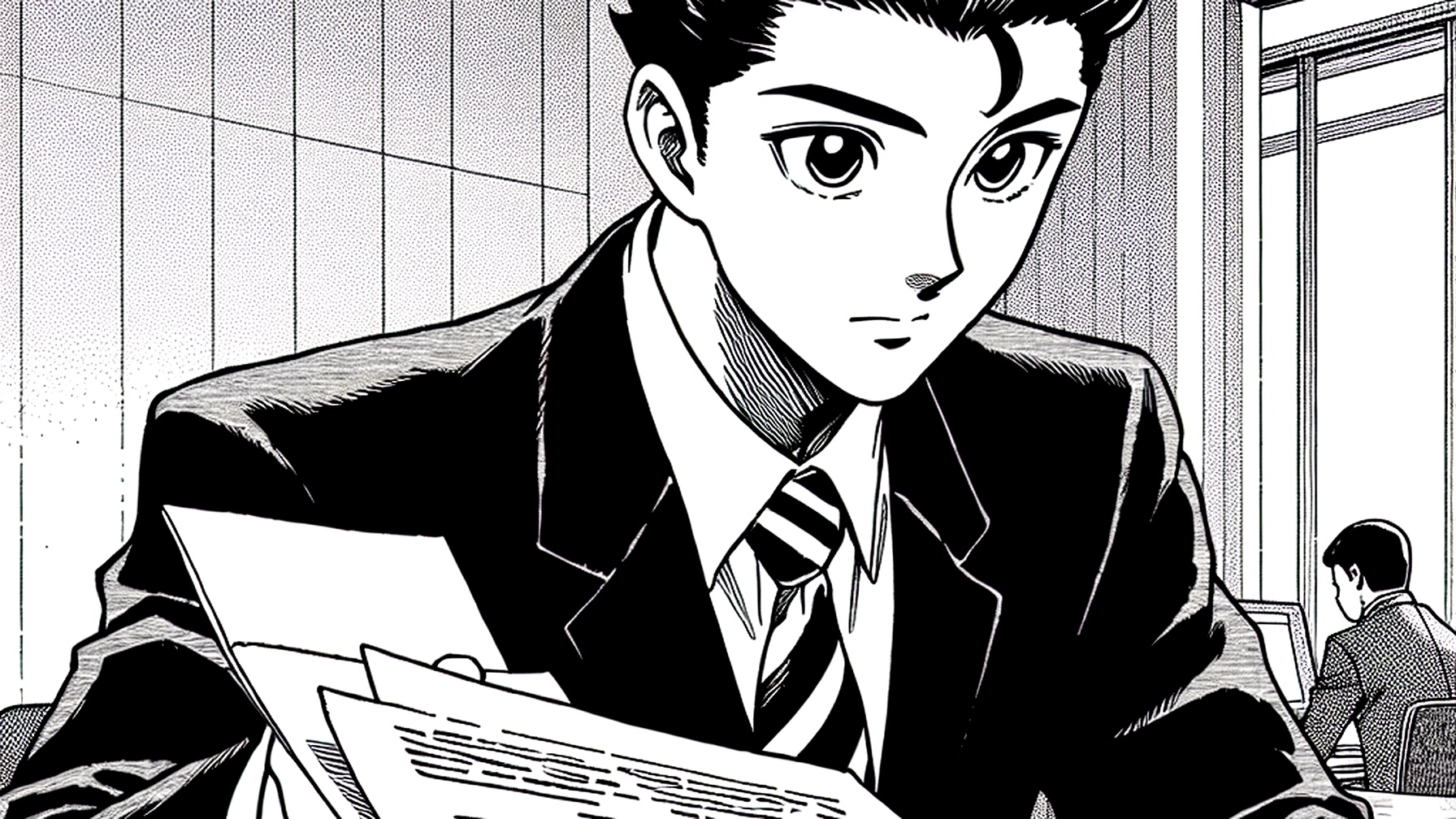
まず押さえておきたいのは、アパート管理には大きく分けて自主管理、管理委託、サブリースの三つがある点です。2025年現在、全国のアパートオーナーの約65%が管理委託を利用し、20%がサブリース契約、残り15%が自主管理という構成になっています(国土交通省「賃貸住宅実態調査2024」)。それぞれの方式は業務範囲と責任分担が異なり、収益構造に直結します。
自主管理は家賃の入金確認からクレーム対応、修繕発注までオーナーが自ら行います。管理委託は入居募集や契約業務を含むほぼ全工程を管理会社に任せ、手数料として家賃の3%〜8%程度を支払います。サブリースは管理会社が賃借人となり、一括で家賃を保証する仕組みです。つまり、管理の手間をどこまで削減したいかが方式選択の最初のポイントになります。
自主管理のメリットとリスク
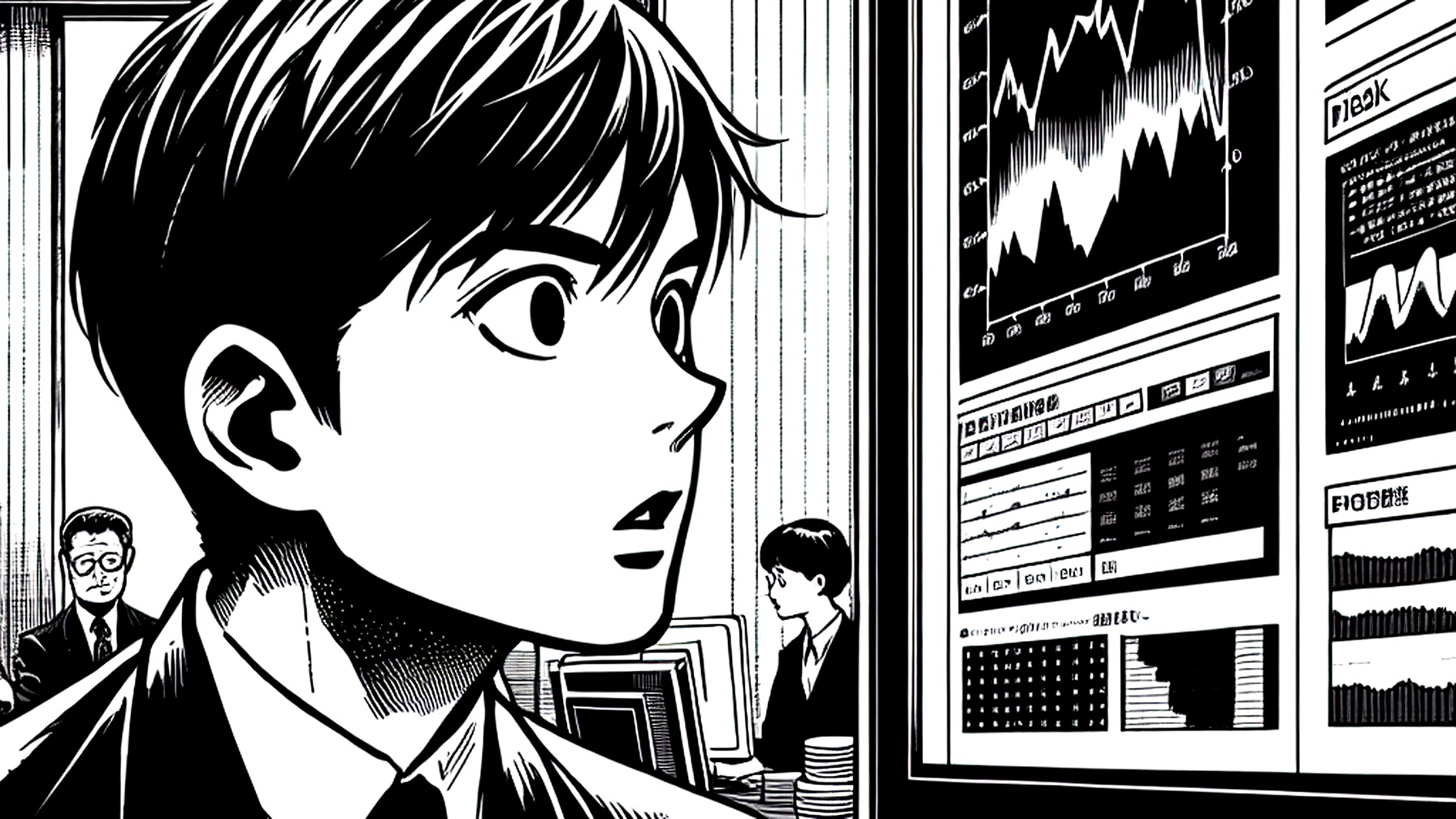
重要なのは、手間を惜しまないオーナーにとって自主管理が高い収益性をもたらす可能性がある点です。管理手数料が不要なため表面利回りを最大化しやすく、入居者との直接コミュニケーションで長期入居を促せる場合もあります。加えて、修繕業者を自分で選べるため、費用を細かくコントロールできる点も魅力です。
一方でリスクも無視できません。夜間や休日の設備トラブルは即時対応が求められ、対応が遅れればクレームや退去につながります。また、建築基準法や民法、賃貸住宅管理業法など関連法令の改正に常に目を配る必要があります。2021年に完全施行された賃貸住宅管理業法では、一定戸数以上の管理業を行う場合に国土交通大臣への登録が義務化されました。自主管理であっても、管理戸数が200戸を超えると登録対象になることを覚えておきましょう。
さらに、全国平均空室率が21.2%(2025年7月時点、前年比-0.3%)と依然高水準である中、入居募集を個人で完結させる難度は上昇しています。広告掲載のノウハウや家賃設定のデータにアクセスできないと、空室期間が長引き収益が目減りしかねません。
管理委託の選び方と費用相場
ポイントは、費用だけでなく業務範囲の詳細を比較することです。管理委託契約は「集金代行型」と「運営代行型」に大別され、前者は家賃回収や更新手続きを担当し、入居募集や修繕発注は別途費用というケースが多いです。後者は募集から退去精算までワンストップで対応し、手数料は家賃の5%〜8%が目安となります。
2025年度の不動産健全化推進事業のガイドラインによると、管理会社を選ぶ際は「管理受託方式」「損害保険加入状況」「24時間対応体制」の三項目を必ず比較するよう推奨されています。特に24時間対応は入居者満足度だけでなく、設備トラブルの早期発見につながり大規模修繕費の抑制にも寄与します。
費用面では、家賃10万円の部屋を10戸保有している場合、手数料5%なら月額5万円、年間60万円の経費となります。自主管理との単純比較では利回りが下がりますが、空室改善やクレーム対応の迅速化によって実質収益が上がる例も珍しくありません。つまり、数字上の削減額だけでなく、時間価値やストレス低減といった非金銭的リターンも総合的に見極める姿勢が求められます。
サブリースの実態と注意点
実は、サブリースは「家賃保証」という安心感が強調される一方で、契約内容の確認不足によるトラブルが後を絶ちません。国民生活センターの相談件数は2024年度で前年比12%増となり、賃料減額や中途解約を巡るケースが目立ちます。サブリース契約は通常30年など長期で締結されますが、家賃保証額は2年ごとに見直しが入る条項が一般的です。この点を把握せずに契約すると、想定より早く収支が悪化するリスクがあります。
2020年12月の賃貸住宅管理業法改正で、サブリース業者は重要事項説明書の交付と契約前の書面説明が義務化されました。2025年時点でもこの規定は有効で、減額条件や中途解約時の違約金が記載されていない場合は是正を求めることができます。また、原状回復義務の範囲や修繕負担をどちらが担うかも細かく確認し、曖昧な場合は特約で明文化しておくと安心です。
サブリースの手取り家賃は、相場家賃の80%前後が目安となります。例として、月額家賃8万円の部屋が10戸ある場合、オーナーの受取額は月64万円、年間約768万円です。ただし、築年数が進むと85%→75%→70%と段階的に減額されるプランが多く、長期収支シミュレーションが不可欠です。
2025年の最新トレンドと賢い比較術
まず押さえておきたいのは、テクノロジーの進化が管理方式の垣根を低くしている事実です。クラウド型管理ツールは、家賃の自動集金やオンライン内見予約、AIによるリフォーム提案まで対応し、自主管理でも管理会社並みの効率を実現可能にしました。一方、大手管理会社はIoTセンサーを導入し、水漏れや火災リスクをリアルタイムで検知するサービスを拡充しています。これにより、空室期間を1か月短縮できれば家賃×戸数分の増収が見込めるため、導入費用を数年で回収できる試算もあります。
また、環境性能を高めたアパートへの補助制度も見逃せません。2025年度の「住宅省エネ2025キャンペーン」は、外壁断熱改修や高効率給湯器の導入に対し最大120万円の補助を継続しています。管理方式にかかわらず、オーナー自ら申請し、工事後は管理会社と連携して入居者募集に活用する事例が増えています。省エネ性能を高めることで光熱費負担が減り、空室対策と同時にESG投資の観点から資産価値向上も期待できます。
比較検討の流れとしては、①収支シミュレーションを複数方式で作成、②時間コストと精神的負担を数値化、③テクノロジー活用や補助金活用で差額を再計算、という三段階が効果的です。最適解は物件規模やライフスタイルによって異なるため、定期的に方式を見直す柔軟性も成功への鍵となります。
まとめ
アパート経営の管理方法は、自主管理、管理委託、サブリースの三つが主流で、それぞれ手間と収益性のバランスが異なります。自主管理は高利回りが魅力ですが、法令対応やクレーム処理に時間を取られる点が課題です。管理委託は手数料がかかるものの、専門ノウハウで空室リスクを抑えられます。サブリースは安定収入が得られる代わりに長期的な家賃減額のリスクがあるため、契約内容の細部確認が必須です。テクノロジーや2025年度の省エネ補助金を活用しつつ、自身の目標と時間価値を基軸に比較すれば、最適な管理戦略が見えてきます。まずはシミュレーションを作成し、数字と感覚の両面で納得できる選択を進めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅実態調査2024 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 国民生活センター 相談事例集2024 – https://www.kokusen.go.jp
- 賃貸住宅管理業法(2020年改正条文) – https://elaws.e-gov.go.jp
- 住宅省エネ2025キャンペーン 公式サイト – https://jutaku-shoene.go.jp/2025
- 不動産健全化推進事業 ガイドライン2025 – https://www.re-fair.jp/guideline

