不動産投資に興味はあるけれど、いきなり物件を買うのはハードルが高いと感じる方は多いはずです。実は、東京証券取引所に上場するREIT(リート)なら数万円から始められ、分配金を受け取りながら不動産市場に参加できます。ただ「REIT どこで おすすめ」と検索すると、証券会社やスマホ証券がずらりと並び、選択肢が多すぎて迷うのも事実です。本記事では2025年9月時点の最新情報を用い、初心者でも失敗しにくいREITの選び方と買い方を分かりやすく解説します。読後には、自分に合った口座を判断し、税制優遇を最大限に活かす具体的なステップが見えてくるでしょう。
REITとは何か、そして株式との違い
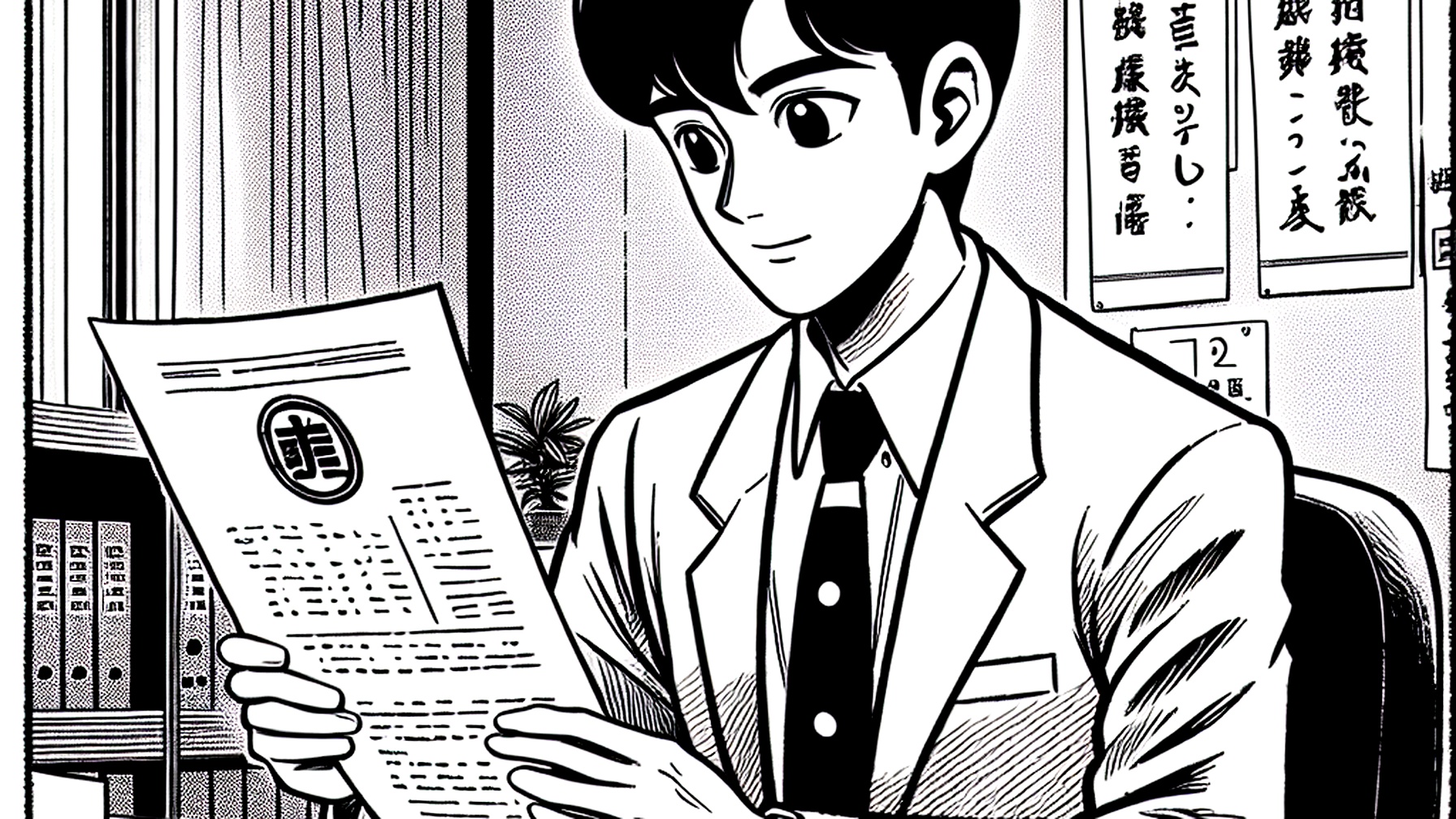
まず押さえておきたいのは、REITが複数の収益不動産をまとめて運用する投資信託である点です。投資家は一口あたり数万円で多数の物件を間接保有でき、賃料収入や物件売却益の九割超が分配金として戻ります。株式と異なるのは、利益の大半を分配することで実質的な法人税が軽減され、インカムゲインが安定しやすい仕組みにあります。
この特徴により、分配利回りは東証プライム上場株の平均配当利回りを一〜二ポイント上回る傾向があります。金融庁の2025年6月データでは、J-REIT平均分配利回りは年4.1%、プライム市場平均配当利回りは年2.5%でした。つまり、インフレ局面でも実物資産からのキャッシュフローを得られる点が魅力です。
一方で、物件取得競争が激化すると利回り低下リスクがあり、地震や風水害により物件価値が毀損するリスクも無視できません。株式より価格変動が小さいと言われるものの、リーマン・ショック時には東証REIT指数が半年で五割下落した過去もあります。したがって、REITは「安定配当が期待できるが、元本保証ではない金融商品」と理解することが出発点になります。
購入前に押さえておきたい3つの確認ポイント
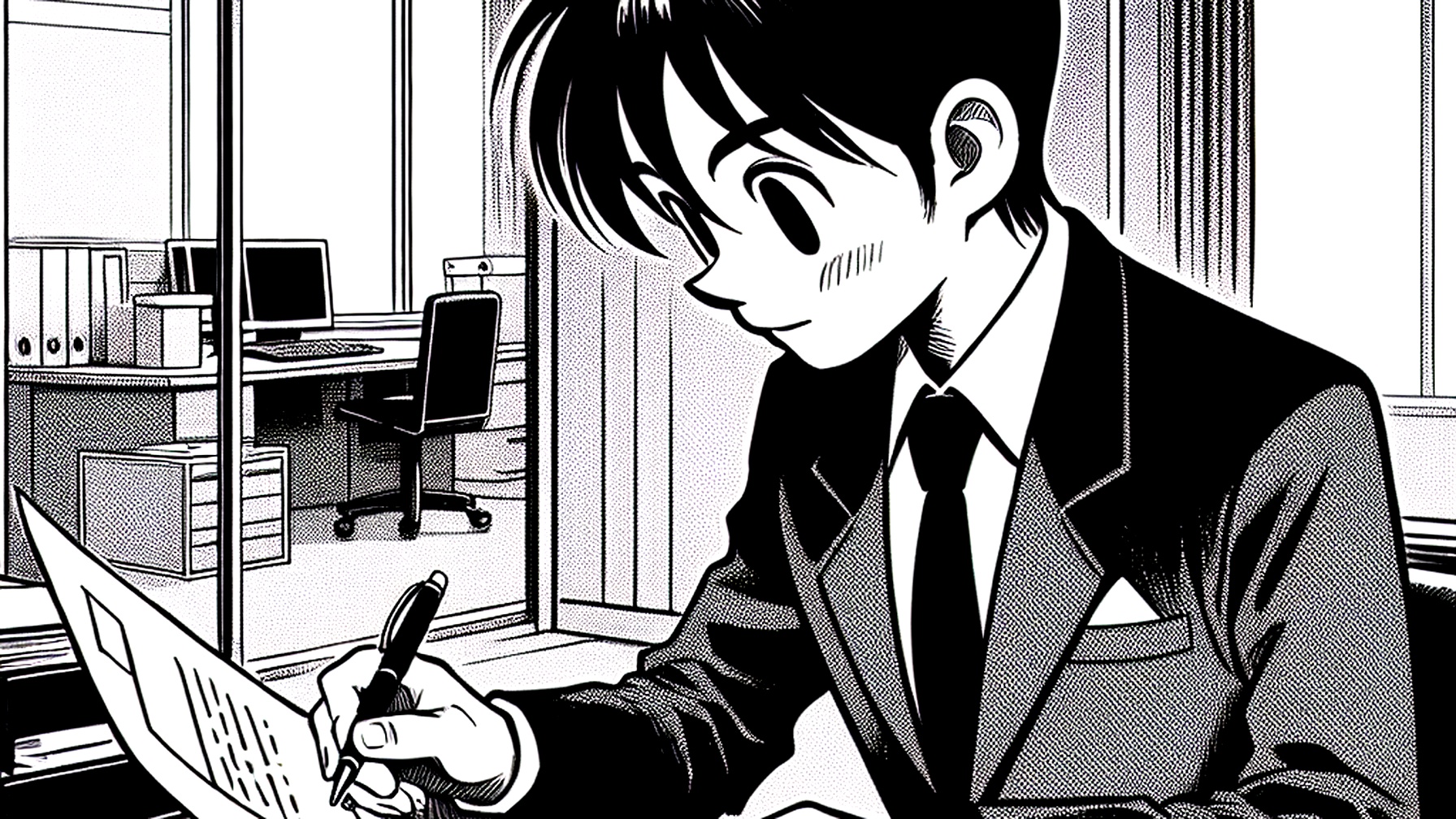
重要なのは、口座を開設する前に「商品性」「コスト」「流動性」の三点を確認することです。まず商品性では、自分が投資したいアセットタイプ(オフィス、住宅、物流施設など)を明確にし、ポートフォリオの分散度合いを調べます。総戸数が多くテナント分散が進んでいる住宅系REITは、景気変動に強いとされる一方、オフィス特化型は景気敏感ですが賃料上昇局面でリターンが伸びやすい特徴があります。
次にコストですが、REIT自体の運用報酬(信託報酬)は年0.3%前後で横並びです。むしろ証券会社の取引手数料や為替手数料(海外REITの場合)が長期的なリターンを左右します。2025年9月現在、大手ネット証券の現物株式売買手数料は「ゼロ円化」が進みましたが、一部の店舗型証券では約定代金の0.5%程度が発生します。手数料差が複利効果を削ぐことを忘れてはいけません。
三点目の流動性は、売買したいときに約定できるかどうかに直結します。東証の月間売買代金ランキング上位REITは一日50億円以上の出来高がありますが、地方物件中心の小型REITだと数千万円にとどまる場合もあります。出来高が少ない銘柄は値幅制限一杯まで下落しても買い手が付かないケースがあるため、初心者はまず流動性の高い銘柄から始めると安心です。
REIT どこで おすすめと聞かれたら?証券会社別比較
ポイントは、投資スタイルにより最適な証券口座が変わることです。売買頻度が低く、分配金を積み上げる長期保有派なら、取引手数料無料で夜間取引も可能なネット証券が有力です。例えばSBI証券と楽天証券は2025年4月に「現物株式・ETF・REITの国内取引手数料完全無料化」を実現し、分配金も自動でNISA口座に入金されます。
一方で、スマホ一つで完結したい若年層からはLINE証券やPayPay証券が人気です。これらは一口単位(数千円)でREITを買える「ミニ投資」に対応し、就業中に細かく成行注文を出すユーザーが増えています。ただし、スプレッド方式の売買で実質手数料が0.5%前後になることもあるため、購入前に提示価格を必ず確認しましょう。
対面サポートを重視する場合は、野村證券や大和証券が提供する「REITレポート」が役立ちます。専門アナリストによる賃料市場予測や物件取得パイプラインの分析を受け取れる反面、取引手数料はネット証券より高水準です。つまり、「自分で調べる時間がない人が、情報コストとして手数料を払う」形になります。
加えて、海外REITに興味がある方はマネックス証券やIG証券が選択肢になります。米国リートETFは経費率が年0.1%台と低く、分配利回りも4%前後です。円安局面のドル建て配当は魅力的ですが、為替変動リスクを意識し、円転タイミングを分散させることが肝心です。
2025年の税制優遇を活かす買い方
まず押さえておきたいのは、2024年に制度改正された新NISAが2025年も有効で、年間投資枠は成長投資枠240万円とつみたて投資枠120万円、合計360万円です。このうち成長投資枠で国内外REITが購入でき、売却益・分配金が非課税になります。金融庁の試算では、分配利回り4%のREITを年間240万円分購入し20年間保持すると、課税口座との差額は約70万円になります。
また、企業型DCを導入していない会社員や自営業者は、個人型確定拠出年金(iDeCo)で海外REITファンドを購入する選択肢があります。iDeCo拠出額は全額所得控除となり、掛金上限(月額2万3000円〜6万8000円)に対する節税効果は年収500万円の会社員で約8万円です。ただし、60歳まで原則引き出せないため、短期資金と混同しないことが重要です。
さらに、相続税対策として子や孫名義のジュニアNISAは2023年度で終了しましたが、代替策として「贈与税非課税枠110万円」を使い、毎年REITを現物贈与する方法があります。親が分配金を生活費にしている場合、将来の相続財産を減らしつつ家計を助ける効果が期待できます。
リスク管理と長期運用のコツ
実は、高配当だけを追い求めるとポートフォリオがオフィスやホテルに偏り、景気後退期にダメージを受けやすくなります。ポイントは、アセットタイプの分散と余裕資金による長期保有を両立させることです。住宅系40%、物流系30%、オフィス系20%、その他10%のように構成すると、テナント撤退や賃料下落の影響を抑えられます。
さらに、分配金再投資を徹底することで複利効果が働きます。日本取引所グループの2025年リサーチでは、分配金を再投資したJ-REIT指数は、再投資しない指数に比べ過去10年で約1.8倍のリターンをもたらしました。自動再投資サービスを提供するネット証券を選ぶと、手間をかけずに資産形成が可能です。
地震保険の付帯など、REIT自身がリスクヘッジを行っているかもチェックポイントです。上場各社の有価証券報告書には耐震補強状況や火災保険加入率が記載されており、災害時の修繕負担を投資家が被るリスクを低減します。加えて、借入比率(LTV)が50%を超える高レバレッジREITは金利上昇に弱いので、2025年以降の政策金利動向を見据え、LTV40%前後の銘柄を中心に組むと安定します。
最後に、分散効果を高めるために毎月一定額をドルコスト平均法で投資する方法も有効です。価格変動の影響を平準化しながら口数を積み上げ、長期的なリスクを抑えられます。売却タイミングでは分配金込みのトータルリターンで判断し、目先の価格変動に振り回されない姿勢が大切です。
まとめ
REITは小口で始められ、分配利回りが相対的に高い一方、価格変動や災害リスクを伴う金融商品です。まず商品性・コスト・流動性を確認し、自分に合う証券会社を選ぶことが第一歩になります。そのうえで、新NISAやiDeCoなど2025年度も有効な税制優遇を活用し、分配金再投資とアセット分散を徹底すると、安定収益と資産成長の両立が可能です。今日紹介したポイントを参考に、早めに口座を開き、小額でも行動を開始してみてください。行動こそが、将来のキャッシュフローを生む最大の原動力になります。
参考文献・出典
- 金融庁「NISA特設ウェブサイト」 – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/
- 日本取引所グループ「J-REIT市場データ月報 2025年6月号」 – https://www.jpx.co.jp
- 東証REIT指数データバンク – https://www.jpx.co.jp/markets/jpx-esg/reit-index.html
- 総務省統計局「家計調査報告 2025年版」 – https://www.stat.go.jp
- 財務省「法人企業統計季報 2025年4-6月期」 – https://www.mof.go.jp
- 国土交通省「不動産価格指数 2025年7月公表」 – https://www.mlit.go.jp

