不動産投資を検討するとき、「築浅の収益物件は本当に安全なのか」と迷う方が少なくありません。確かに見た目がきれいで管理も楽に思えますが、購入価格が高めなので利回りが伸びにくいという声も聞かれます。本記事では、築浅物件の特徴を整理し、メリットとリスクの両面を丁寧に解説します。読者のみなさまが「高値づかみ」を回避しつつ、将来にわたり安定した家賃収入を得るためのポイントを具体的にお伝えします。
築浅収益物件とは何か
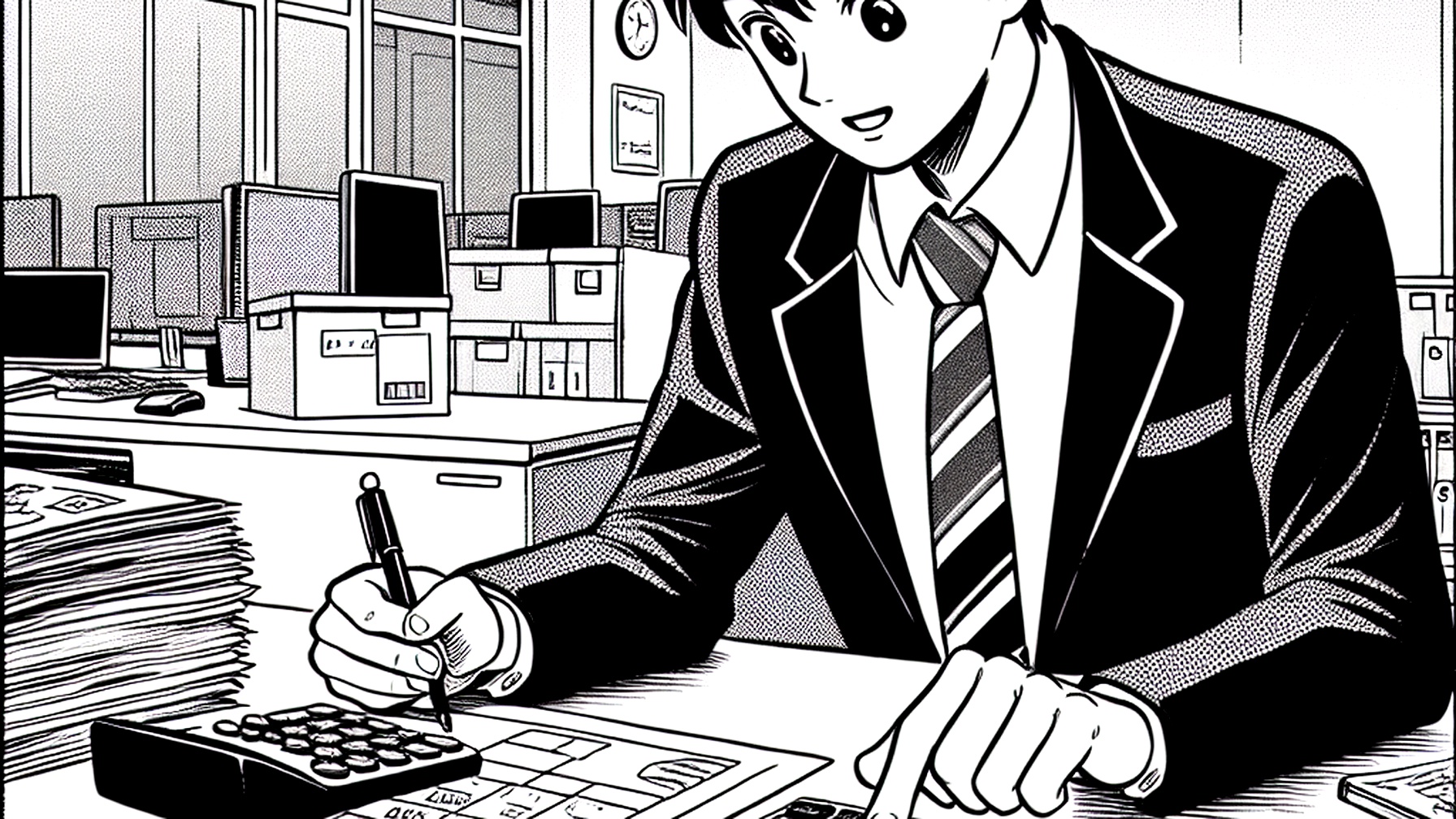
まず押さえておきたいのは「築浅」の定義です。一般に築十年以内の住宅が築浅と呼ばれますが、耐震性や設備仕様が現行基準に近いかどうかが実質的な判断材料になります。国土交通省の建築着工統計によると、二〇一五年以降に完成した賃貸住宅は省エネ性能が向上し、共用部分の設備や通信環境も充実しています。つまり、築浅物件は表面利回りだけでなく将来の競争力まで見込める選択肢なのです。
次に、築浅と新築の違いを意識しましょう。新築は広告効果が高い反面、価格に販売会社の利益が上乗せされるため、実勢価格より一〜二割高くなるケースが多いといわれます。一方で築浅は一度賃借人が付けば実勢価格に近づくため、取得時点での割高感が薄まります。また、固定資産税の評価額が新築よりやや下がるので、税負担を抑えられる点も見逃せません。
なお、金融機関が設定する融資期間は「耐用年数から築年数を引いた残り年数」が目安です。築浅であれば融資期間を長く取りやすく、月々の返済額を下げてキャッシュフローを安定させる効果が期待できます。このように築浅物件は「設備の新しさ」「税負担の軽減」「融資条件の柔軟性」という三つの観点で優位性があります。
築浅を選ぶメリットとデメリット
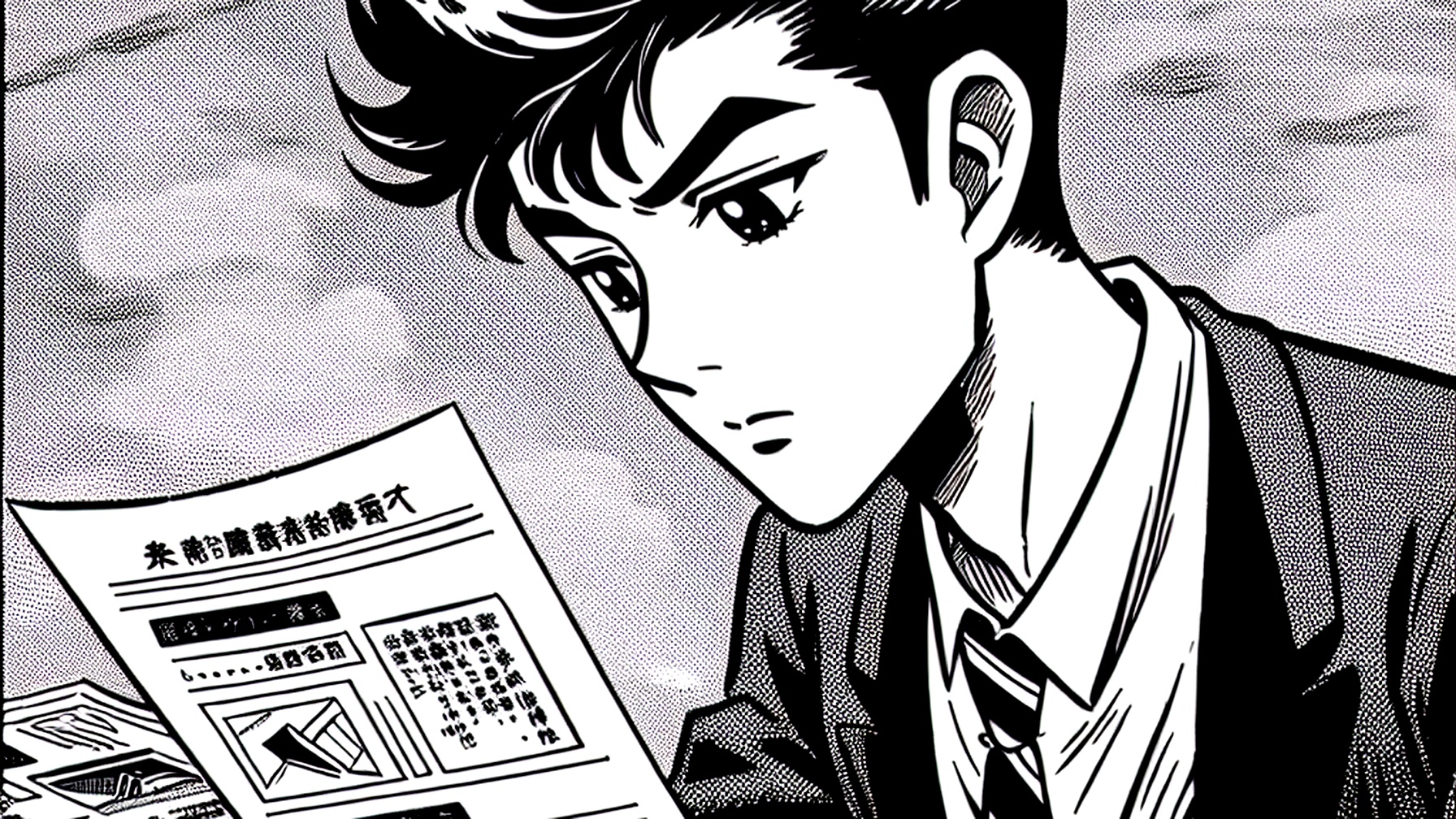
重要なのは、表面的な美しさだけでなく数字で判断することです。築浅の最大の利点は、修繕コストが当面少なく済むという点にあります。日本賃貸住宅管理協会の二〇二四年度調査では、築五年未満の修繕費は年間家賃収入の三%程度にとどまり、築二十年以上の八%前後と比べて大幅に低い水準です。修繕費が低いほど手取りが安定するため、初心者でも資金計画を立てやすくなります。
一方で、取得価格が高いことから表面利回りは平均で四〜五%台に収まりがちです。総務省「住宅・土地統計調査」によると、築二十年以上の木造アパートは七%を超える利回りが珍しくありません。つまり、築浅は安定性を買う代わりに利回りを抑える取引だと言えます。また、減価償却期間が短いため、短期的な節税効果を狙う投資家にとっては魅力が薄くなる点も留意しましょう。
さらに、家賃水準の維持が課題になります。新築プレミアムで募集していた場合、二度目の入居募集では一〇%前後の家賃下落が起こりやすいと指摘されています。対策としては、入居者ニーズを細かく把握し、設備追加やサブスク利用料込みプランなど柔軟な施策で差別化することが欠かせません。メリットとデメリットを冷静に比重づけし、自分の投資方針と照らし合わせる視点が大切です。
立地と築年数のバランスを読むコツ
ポイントは、築年数より先にエリアの将来性を検証することです。人口推計をみると、国立社会保障・人口問題研究所は二〇三五年にかけて三大都市圏の一部で人口微増を予測する一方、地方中核市でも中心部への集中が続くと分析しています。つまり、同じ築浅でもエリアが外れれば空室リスクが高まり、家賃の下落スピードも速くなるのです。
具体的な調査手順としては、役所が公開する都市計画マスタープランと、民間が公表する賃貸空室率データを突き合わせる方法が有効です。たとえば東日本不動産流通機構の成約データによると、二〇二四年時点で東京二三区の空室率は四〜五%程度にとどまりますが、同県郊外では一〇%を超える市もあります。この差は築浅・築古を問わず将来キャッシュフローに直結します。
次に、駅からの距離と周辺施設の質を確認します。最近はオンデマンド交通やフードデリバリーの普及で「駅近」指向が若干緩んでいますが、都心のシングル層は徒歩一〇分以内を依然として重視しています。つまり、築浅であっても駅遠では賃料を維持しにくいので、最寄り駅からの距離と居住属性をセットで検討する必要があります。
最後に、地域ごとの再開発計画をチェックしましょう。二〇二五年度は国土交通省が進める都市再生特別措置法の改正で、中規模再開発にも税制優遇が拡充されています。再開発エリアに近い築浅物件は将来的な資産価値上昇が見込めるため、購入判断において大きなプラス材料になります。
資金計画と融資のポイント
まず押さえておきたいのは、自己資金の比率です。筆者の経験では、物件価格の二五%程度を自己資金として用意すると融資審査が通りやすく、金利や期間も有利な条件を引き出しやすくなります。日本政策金融公庫の二〇二五年度調査では、自己資金が二割を下回る案件は金利が平均〇・四%ほど上乗せされる傾向が確認されています。わずかな差に見えても、三〇年融資では総返済額が三〇〇万円近く変わるケースがあります。
また、金利タイプの選択も重要です。二〇二五年九月時点で大手銀行の投資用変動金利は一・八〜二・五%、固定金利は二・六〜三・三%が目安となっています。日本銀行は長期金利変動幅を〇・五%程度に抑える政策を続けていますが、世界的な金利上昇圧力を考慮すると、変動一本で突き進むのはリスクが高いと言えます。変動と固定を半分ずつ組み合わせる「ミックスローン」は返済計画を柔軟にする有効な手段です。
修繕積立も忘れてはいけません。築浅とはいえ外壁塗装や給排水設備の更新は一五年目以降に一気に発生することがあります。家賃収入の一〇%を毎月積み立てると、二〇年後に想定される大規模修繕費の大部分を自己資金で賄える計算になります。金融機関も修繕計画を評価しますので、購入初期から積立ルールを明示しておくと審査がスムーズになります。
2025年度の制度活用と注意点
実は、二〇二五年度も賃貸経営者向けの直接的な補助金は多くありません。しかし、税制では使える制度がいくつか存在します。代表的なのが「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」です。延べ床面積一二〇平方メートル以下の賃貸住宅については、最初の三年間、固定資産税が二分の一に軽減されます。築浅とはいえ中古購入では対象外になるため、新築後数年以内に売却された物件かどうかを確認することが大切です。
加えて、都市再生特別措置法に基づく民間都市再生事業計画に認定されたエリアでは、不動産取得税の軽減が適用されるケースがあります。二〇二五年度は認定区域が拡大しており、業務地区内で住宅部分が一定割合を占める物件は税率が三%から一・五%に下がります。築浅物件でも該当区域に位置するかどうかで初期費用が大きく変わるため、自治体の発表をこまめに確認してください。
一方で、住宅ローン減税は居住用が前提であり、賃貸用には適用されません。また、環境性能による補助金の多くは自己居住を条件にしているため、誤って申請しないよう注意が必要です。制度を利用するときは、国土交通省や都道府県の公式サイトで条件を必ず再確認し、税理士に相談してから手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
ここまで築浅の収益物件に焦点を当て、その特徴と投資判断のポイントを整理してきました。建物が新しいことで修繕費を抑えやすく、融資期間を長く取れる利点は大きいものの、購入価格が高めで利回りが低くなる傾向があります。立地の将来性を詳細に分析し、自己資金と修繕積立を十分に確保してから購入に踏み切ることが肝心です。結論として、築浅物件は「安定収入を長期で狙う投資家」に適した選択肢であり、制度の軽減税率を賢く活用すればリスクを抑えつつ堅実な運用が可能になります。まずは本記事のチェックポイントを参考に、候補物件のデータを集め、数字と現地確認の両面で検討を進めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 建築着工統計 – https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/statistics.html
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場景況感調査 – https://www.jpm.jp/
- 日本政策金融公庫 生活衛生関係営業の景気動向等調査 – https://www.jfc.go.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口 – https://www.ipss.go.jp/

