不動産投資に興味はあっても、物件を直接購入するのはハードルが高いと感じる方は多いでしょう。そこで注目されるのが「REIT(リート)」と呼ばれる不動産投資信託です。ただ、銘柄数が増えた今、何を基準に選べば良いか迷うのが本音ではないでしょうか。本記事では、人気REITを比較しながら、自分に合った一口を見つけるための視点を解説します。読むことで、利回りだけに頼らない選択基準と、2025年9月時点で押さえるべき最新動向を把握できます。
REITとは何か、そして人気が集まる理由
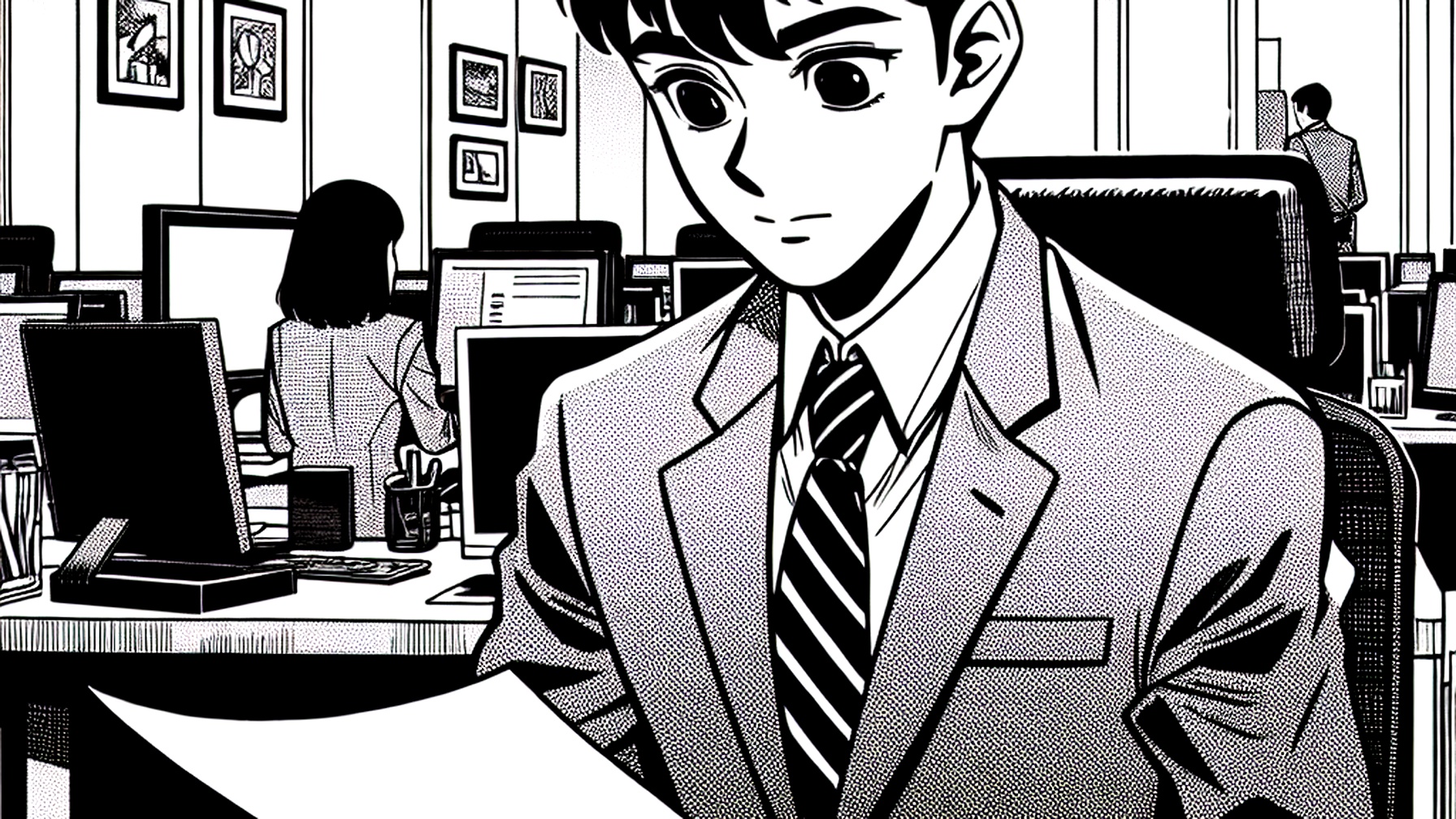
まず押さえておきたいのは、REITが投資家から広く支持される背景です。REITは投資家から集めた資金で複数の不動産を購入し、賃料収入などを投資家に分配する仕組みです。証券取引所に上場しているため、株式と同じように売買でき、少額からでも分散された不動産ポートフォリオに参加できます。
日本では2001年に上場が始まり、2025年8月末時点で60銘柄以上が流通しています。東京証券取引所が公表する東証REIT指数は同月に2190ポイント前後を推移し、2020年比で約15%の上昇を示しました。さらに、上場インフラファンドとの親和性が高まり、配当利回りが平均4.1%と東証一部平均(約2.2%)を上回る状況が続いています。
実は、法的な仕組みに守られている点も人気の理由です。投資法人は利益の90%以上を配当に回すことで法人税が実質的に免除されるため、キャッシュフロー効率が高まります。つまり、株式より配当性向が高い傾向があり、インカムゲイン重視の投資家に適していると言えます。
人気REITをどう比較するか―利回りだけでは判断できない視点
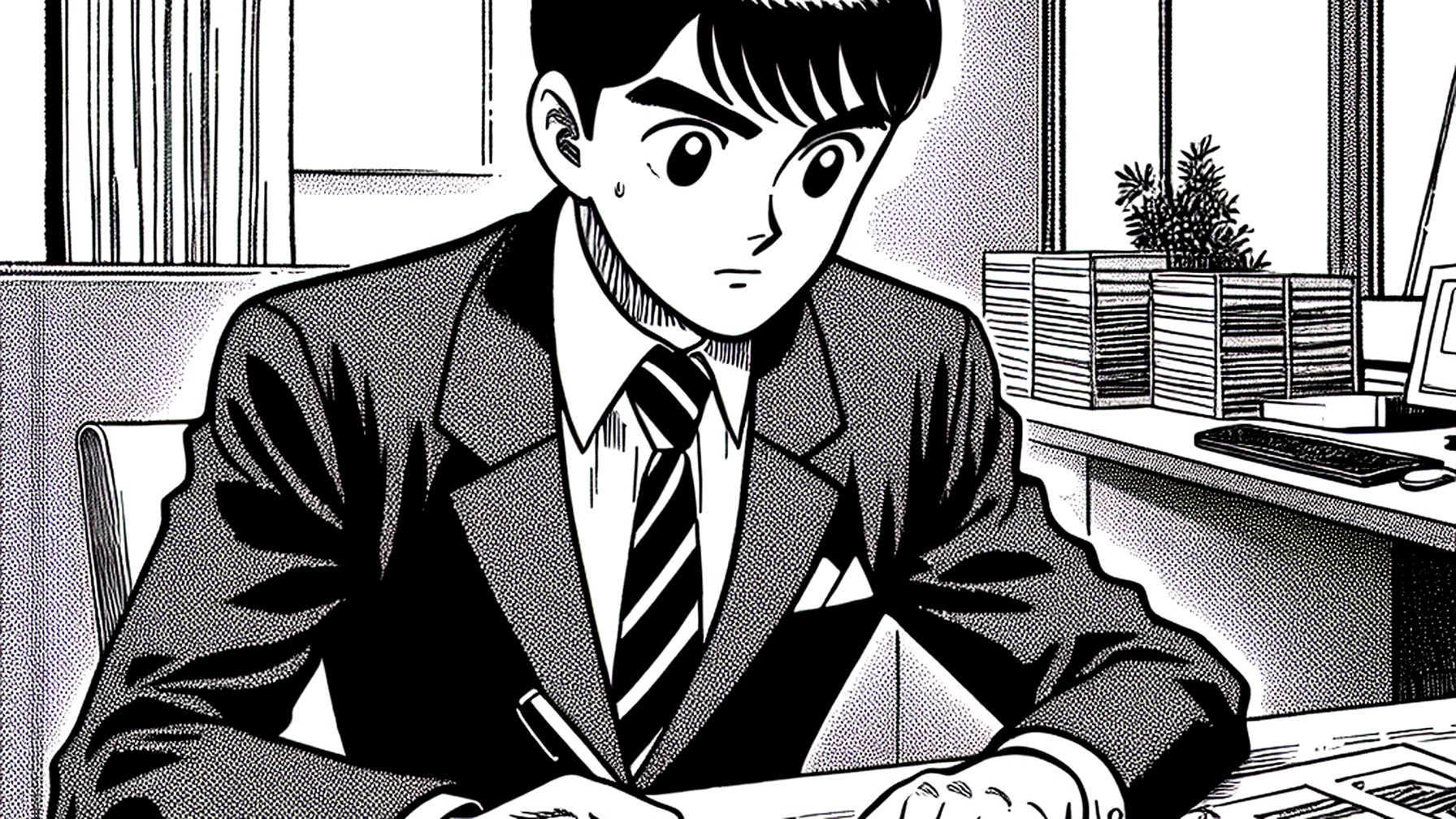
重要なのは、単純な分配金利回りの比較では本質がつかみにくい点です。平均利回りが4%台でも、その背景にある資産規模や運用方針でリスクが大きく異なります。したがって、利回りに加えて資産規模、物件用途、LTV(負債比率)を重ねて見ることが欠かせません。
たとえば、2025年上期のデータを用いて三つの代表的銘柄を比べると次のようになります。
- 日本ビルファンド投資法人:利回り3.5%、資産規模1兆円超、オフィス中心、LTV約44%
- ジャパンリアルエステイト投資法人:利回り3.8%、資産規模1.5兆円、オフィス中心、LTV42%
- 日本リテールファンド投資法人:利回り4.6%、資産規模9600億円、商業施設中心、LTV47%
数値だけを見るとリテール系が高利回りですが、オフィス系は安定度の高いテナント構成と財務余力が評価されます。また、LTVが50%を超えると金利上昇局面でリスクが高まりやすいので、負債水準にも注目しましょう。
さらに、スポンサー企業の信頼度は中長期の成長見通しを左右します。大手デベロッパー系列は物件のパイプラインや資金調達力で優位に立つ一方、地方銀行系は地域特化型として効率的なポートフォリオを構築する傾向があります。つまり、利回りだけでなく、スポンサーと物件ポートフォリオの質を合わせて評価する視点が欠かせません。
市場データが示す2025年のトレンドとリスク要因
ポイントは、マクロ環境とREIT市況が密接に連動する点です。国土交通省の不動産価格指数によれば、都心オフィスは2024年から横ばい傾向に転じています。一方、総務省人口統計では都市部への人口集中が続き、住宅系REITの賃料は緩やかな上昇が続いています。
しかし、金利動向は見逃せません。日本銀行が2025年7月にマイナス金利を解除し、長期金利は1.0%台前半まで上昇しました。これによりREITの分配金利回りと国債利回りの差は縮小し、一部の海外投資マネーが流出する兆しがあります。金融庁のモニタリングレポートでは、金利1%上昇でREIT全体の配当原資が平均5%減少する試算も示されました。
さらに、オフィス需要にはテレワーク定着の影響が残ります。国際的な不動産調査機関JLLの2025年調査では、大手企業のオフィス面積削減率が平均6%にとどまる一方で、フレキシブルオフィス市場が年率10%で拡大していると報告されています。つまり、用途に応じた需給バランスを読み解くことで、銘柄選びの精度が高まります。
初心者がREITを選ぶときの実践的ステップ
まず、投資目的を明確にすることが欠かせません。配当重視であれば利回りと減配リスクを、資産成長重視であれば含み益や内部留保の積み上がりを重視するのが基本です。目的が定まれば、比較すべき指標も自ずと絞り込めます。
次に、3指標を組み合わせて検討します。資産規模5000億円以上、LTV50%未満、FFO(運用キャッシュフロー)成長率3%以上という条件でスクリーニングすると、2025年8月時点で約15銘柄に限定されます。これに用途の分散度合いを加味すれば、ポートフォリオ全体の安定性が高まります。
情報収集の際は、投資法人の決算説明資料を読み、空室率や平均賃料推移に着目しましょう。また、証券会社のレーティングだけに頼らず、不動産証券化協会が提供する月次データを使うことで、市場水準と個別銘柄のギャップを把握できます。つまり、一次情報と統計を組み合わせることで、偏った判断を避けることが可能になります。
最後に、少額投資制度である「iDeCo」や「つみたてNISA」は、2025年度もREITを対象ファンドとして取り扱っています。非課税枠を活用することで、分配金への課税を抑えられるため、長期投資との相性は良好です。
分散投資と出口戦略―リスクを抑えつつリターンを伸ばす
基本的に、REITでも分散投資は有効です。物件用途の違う複数銘柄を組み合わせることで、景気変動や金利上昇の影響を緩和できます。たとえばオフィス1銘柄、住宅1銘柄、物流1銘柄を保有すると、賃料サイクルのピークがずれるため、収入が平準化されやすいです。
出口戦略も事前に決めておくと安心です。分配金利回りが国債利回りと2%未満に縮小した場合や、LTVが急上昇した場合を売却基準に設定する方法があります。これにより、感情に左右されずに利益確定や損切りが行えます。
また、REITを保有し続ける場合でも、年に一度はポートフォリオを見直し、含み益のある銘柄を一部売却し税金をコントロールする「タックスロス・ハーベスティング」を検討すると効率的です。金融庁の2025年度税制改正では、特定口座内の上場投資信託もこの手法が認められており、個人投資家の活用例が増えています。
結論として、分散とルール化された出口戦略を組み合わせることで、REIT投資のリスクを抑えつつ安定的なリターンを目指せます。
まとめ
ここまで、REIT 比較 人気の視点として利回り、資産規模、用途、LTV、スポンサー力の五つを中心に解説しました。2025年は金利上昇という逆風もありますが、住宅や物流を軸に適切に分散すれば、依然として平均4%の安定利回りが期待できます。まずは投資目的を明確にし、月次データを点検しながら少額で始めることが賢明です。今回紹介したステップを実践し、ご自身のポートフォリオをアップデートしてみてください。
参考文献・出典
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 不動産証券化協会 – https://www.ares.or.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 モニタリングレポート2025 – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 人口推計 – https://www.stat.go.jp

