不動産投資に興味はあるものの、失敗例を聞くたびに不安が募る人は多いでしょう。特に「収益物件 危険 購入手順」という言葉で検索する方は、購入の流れを知りつつリスクを最小限に抑えたいはずです。本記事では、2025年9月時点で実践可能な方法だけを取り上げ、物件選びから引き渡し後の管理までを丁寧に解説します。読み進めることで、危険を見抜く目と安全な購入手順が身につき、安心して一歩を踏み出せるようになるでしょう。
収益物件の「危険」を正しく理解する
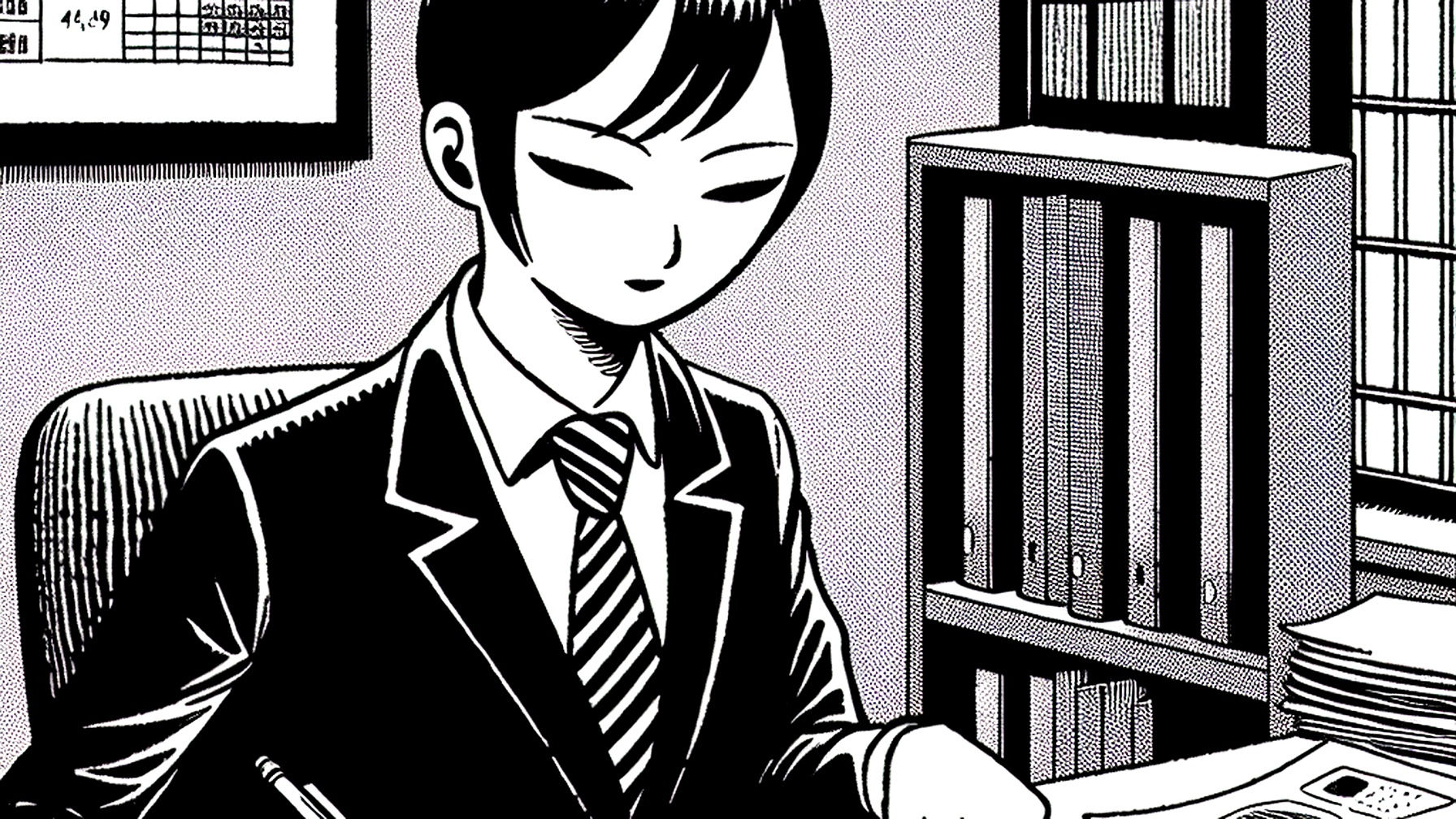
重要なのは、危険を漠然と恐れるのではなく、種類を分けて把握する姿勢です。空室リスク、家賃下落リスク、修繕費の急増リスクなど、収益物件に潜む要素は大きく三つに整理できます。
まず空室リスクは、立地と需要のミスマッチで発生します。国土交通省の住宅着工統計によると、2024年度の新設住宅着工戸数は前年より5%増えました。つまり供給が増える地域では、築年数が浅くても空室が増える可能性があります。また家賃下落リスクは人口動態と密接に関連します。総務省の住民基本台帳人口移動報告では、2025年1月時点で転出超過が続く地方都市が複数確認されており、賃料維持が難しくなるエリアも見受けられます。
一方で修繕費の急増リスクは、物件の築年数だけが原因ではありません。気候変動で集中豪雨が増え、外壁や屋根の劣化が早まる事例も報告されています。国立研究開発法人建築研究所の調査では、過去10年間で雨漏り補修費が平均15%上昇しました。つまり長期保有を前提とするなら、天候によるダメージを想定して資金計画を立てる必要があります。
結論として、危険を具体化して数値で捉えれば、対策の優先順位が定まります。次章からは、実際に危険を避けるための購入手順を順を追って確認していきましょう。
物件選びで見逃しがちなリスクポイント
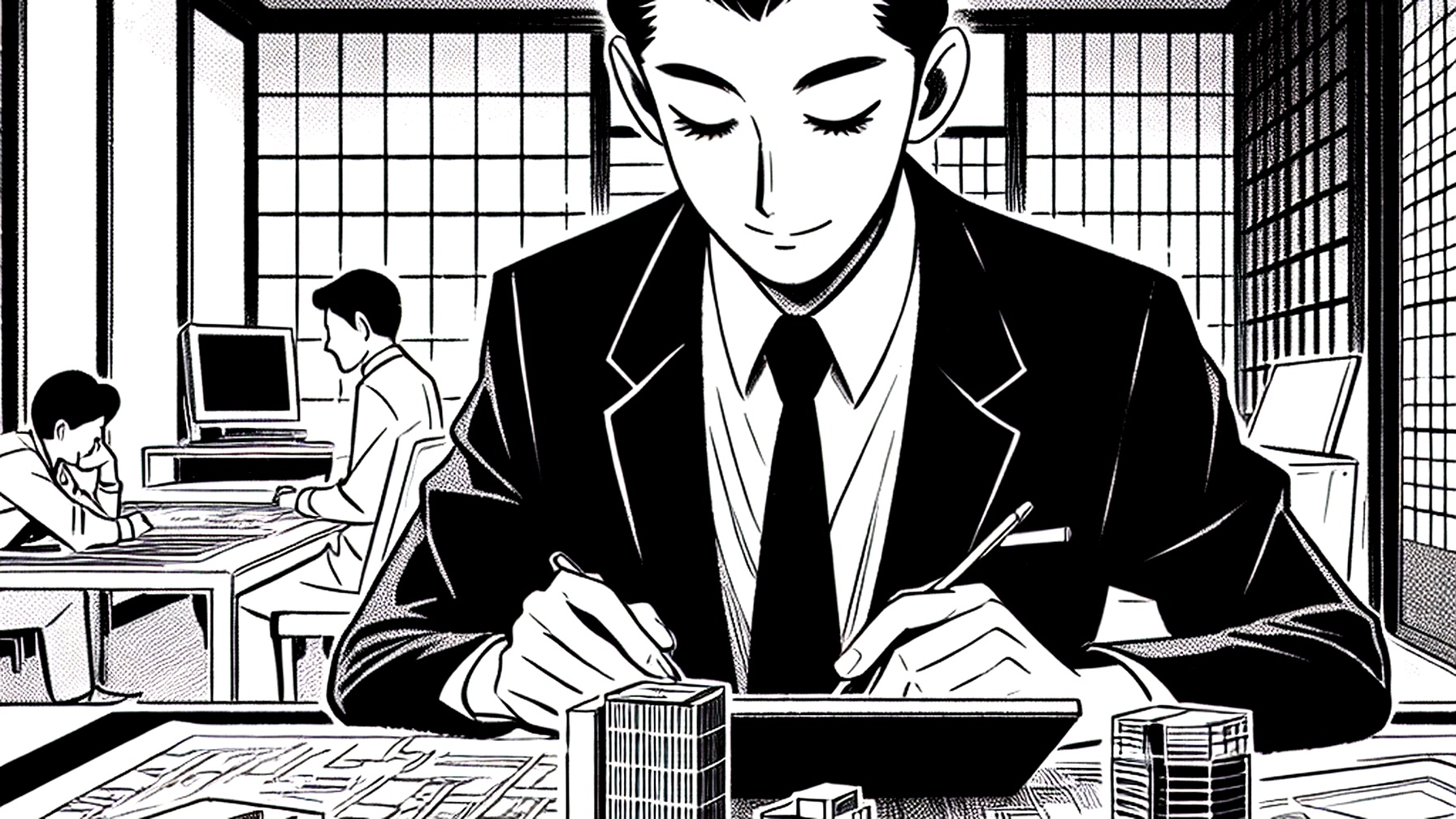
まず押さえておきたいのは、表面利回りだけで判断しない姿勢です。利回りが高い物件は魅力的に見えますが、周辺相場との乖離が大きい場合、将来的に賃料を下げざるを得ないケースがあります。
次に重要なのが、インフラ更新計画の確認です。地方自治体の公表資料には、道路拡幅や上下水道工事の予定が載っています。工事が長期化するとアクセスが悪化し、一時的に入居付けが難しくなる恐れがあります。また、都市計画道路が新設されると接道条件が変わり、再建築不可になる可能性もあるため要注意です。
さらに、洪水や土砂災害リスクを含むハザードマップの精査も欠かせません。国土交通省ハザードマップポータルでは、2025年7月に最新データが公表されました。浸水想定区域に該当すれば、金融機関の融資条件が厳しくなるケースがあります。結果として、自己資金比率が高まり、キャッシュフローに負担がかかります。
実は、管理会社の選定も見落とされがちなリスクポイントです。仲介会社と管理会社が同一の場合、入居募集に偏りが生じるなど利益相反が起きやすいといわれます。したがって複数社から運営シミュレーションを取得し、手数料と入居率のバランスを比較することが重要です。
安全性を高める購入前の調査手順
ポイントは、「自分で調査→専門家で検証→数値で確認」という三段階を踏むことです。ここでは最小限の箇条書きで流れを整理します。
- 自分で調査:現地確認と公的資料の収集
- 専門家で検証:インスペクションと法的チェック
- 数値で確認:資金計画と出口戦略の想定
まず自分で調査する段階では、平日と休日、昼夜の二回は現地を訪れましょう。時間帯による人通りの差や周辺騒音を体感できるからです。加えて、市町村の固定資産税課に出向き、評価額や家屋調査履歴を取得すると、過去の修繕状況も把握できます。
次に専門家で検証するステップでは、建物状況調査(インスペクション)と司法書士の権利関係チェックが欠かせません。2022年の宅建業法改正でインスペクションの説明義務が強化されたものの、実施は任意にとどまっています。日本ホームインスペクターズ協会の統計では、実施率は2024年度で35%に過ぎません。つまり自ら依頼しなければ、隠れた瑕疵を見逃すリスクがあります。
最後に数値で確認する段階では、最悪ケースまで収支を試算します。金融機関の金利が現在1.4%でも、長期固定で組まない限り上昇余地はあります。仮に金利3%・空室率20%でシミュレーションし、なお黒字なら購入に進む判断材料となります。また、出口戦略として「10年後に売却」「20年保有で建替え」など複数シナリオを作り、内部収益率(IRR)を比較するとより実践的です。
契約から引き渡しまでの実務フロー
まず明確にしたいのは、契約書と重要事項説明書(35条書面)の読み込みです。不動産会社は口頭でメリットを強調しがちですが、書面に記載がなければ法的拘束力はありません。そこで専門家に依頼し、特約条項が買主に不利でないかを確認しましょう。
売買契約後は、金融機関の本審査と金銭消費貸借契約(ローン契約)が進みます。2025年度の主要地銀では、耐震診断結果を提出条件に含める例が増えています。耐震基準を満たさない木造アパートは、金利が0.3%上乗せされるケースもあるため注意が必要です。
決済当日は、司法書士立会いのもと残代金を支払い、所有権移転登記を行います。登記費用は固定資産評価額の約2%が目安ですが、郵送依頼にすると1万円程度節約できる場合があります。また、賃貸借契約が継続している場合は、賃料や敷金を日割り計算で清算するため、管理会社と三者間で明細を確認してください。
引き渡し後の初動も大切です。消防設備点検や貯水槽清掃などは、購入後すぐに実施すると入居者の安心感につながります。結果として口コミ評価が上がり、空室期間を短縮できる効果が期待できます。
リスク管理と収支シミュレーションのコツ
実は、購入後に最も差がつくのがランニングコストの管理です。日本賃貸住宅管理協会の2024年度調査では、修繕費と広告費を合わせた運営コスト率は平均25%でした。ここを20%以下に抑えられれば、同じ賃料でも年間収益が大幅に改善します。
まず家賃保証(サブリース)に頼りすぎない戦略を取りましょう。保証料は家賃の10%前後が一般的で、長期的に見ると自己管理より収益が下がります。また保証会社が倒産するリスクもゼロではありません。空室対策としては、IoT設備や無料Wi-Fi導入が費用対効果が高いとされています。総務省「住宅・土地統計調査」では、入居時にネット環境を重視する世帯が2013年比で1.8倍に増加しました。
さらに、修繕積立を毎月確保する仕組みが欠かせません。例えば家賃収入の5%を別口座に振り分けるだけで、10年後に大規模修繕が必要になっても慌てずに済みます。加えて、固定資産税の納税通知書が届く4月から6月にかけて資金が圧迫されるため、事前にキャッシュフローカレンダーを作成しておくと安心です。
そして、年に一度は収支シミュレーションを更新し、利回りと内部収益率を見直しましょう。家賃が下がる局面でも、金利が低いタイミングで借り換えを行えば、収益性を維持できる場合があります。具体的には、残債が物件価格の70%を切った時点で複数行に打診すると、優遇金利の提案を受けやすくなります。
まとめ
本記事では、収益物件の危険を具体的に分類し、それぞれに対処する購入手順を示しました。現地調査から専門家チェック、数値シミュレーションまで段階を踏むことで、リスクは大幅に低減できます。さらに、購入後のランニングコスト管理と定期的な収益見直しを実践すれば、長期にわたって安定したキャッシュフローが期待できます。今日紹介した手順をマスターし、自信を持って次の行動につなげてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/statistics.html
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp/menu/news/s-news/01toukei-07_02000241.html
- 国土交通省 ハザードマップポータル – https://disaportal.gsi.go.jp
- 建築研究所 雨漏り補修費調査報告書 – https://www.kenken.go.jp/japanese/activities/report/leakage2025.html
- 日本ホームインスペクターズ協会 インスペクション実施率統計 – https://www.jshi.org/statistics
- 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場景況調査 – https://www.jpm.jp/research/scenario2024.html

