家賃収入で暮らす未来に憧れても、「収支が合わなかったらどうしよう」と不安に感じる人は多いはずです。特に表面利回りだけで物件を選ぶと、思ったよりお金が残らないケースが後を絶ちません。本記事では、2024年の市場データを基に、収益物件の収支計算をゼロから組み立てる方法を解説します。読み進めることで、購入前に損益を数値で把握し、将来のリスクに備える力が身に付くでしょう。
キャッシュフローを理解する第一歩

重要なのは「手元に現金が残るか」を最初に確認することです。収益物件の魅力は毎月のキャッシュフローにありますが、ローン返済や管理費を差し引くと赤字になる例も少なくありません。
まず、キャッシュフローとは家賃収入からローン元利金、固定資産税、管理委託料などを除いた残額です。国土交通省「賃貸住宅市場景況感調査2024」によると、東京都心の平均管理委託料率は5%前後で推移しています。この数字を家賃に掛け忘れると、年間で数十万円の差が開くため要注意です。
一方、固定資産税は立地と築年数によって大きく変動します。総務省の最新統計では、築20年超の木造アパートでも評価額が底打ちせず、税負担が横ばいの地域が増えました。つまり想定外の経費増を避けるには、自治体の課税明細を事前に取り寄せることが欠かせません。
最後に、ローン返済額は金利と返済期間で大きく左右されます。日本政策金融公庫のデータでは、2025年3月時点の変動金利平均は1.5%台。過去5年で緩やかに上昇しており、返済シミュレーションには2%までの金利上昇を織り込んでおくと安心です。
2024年版収支計算シートの組み立て方
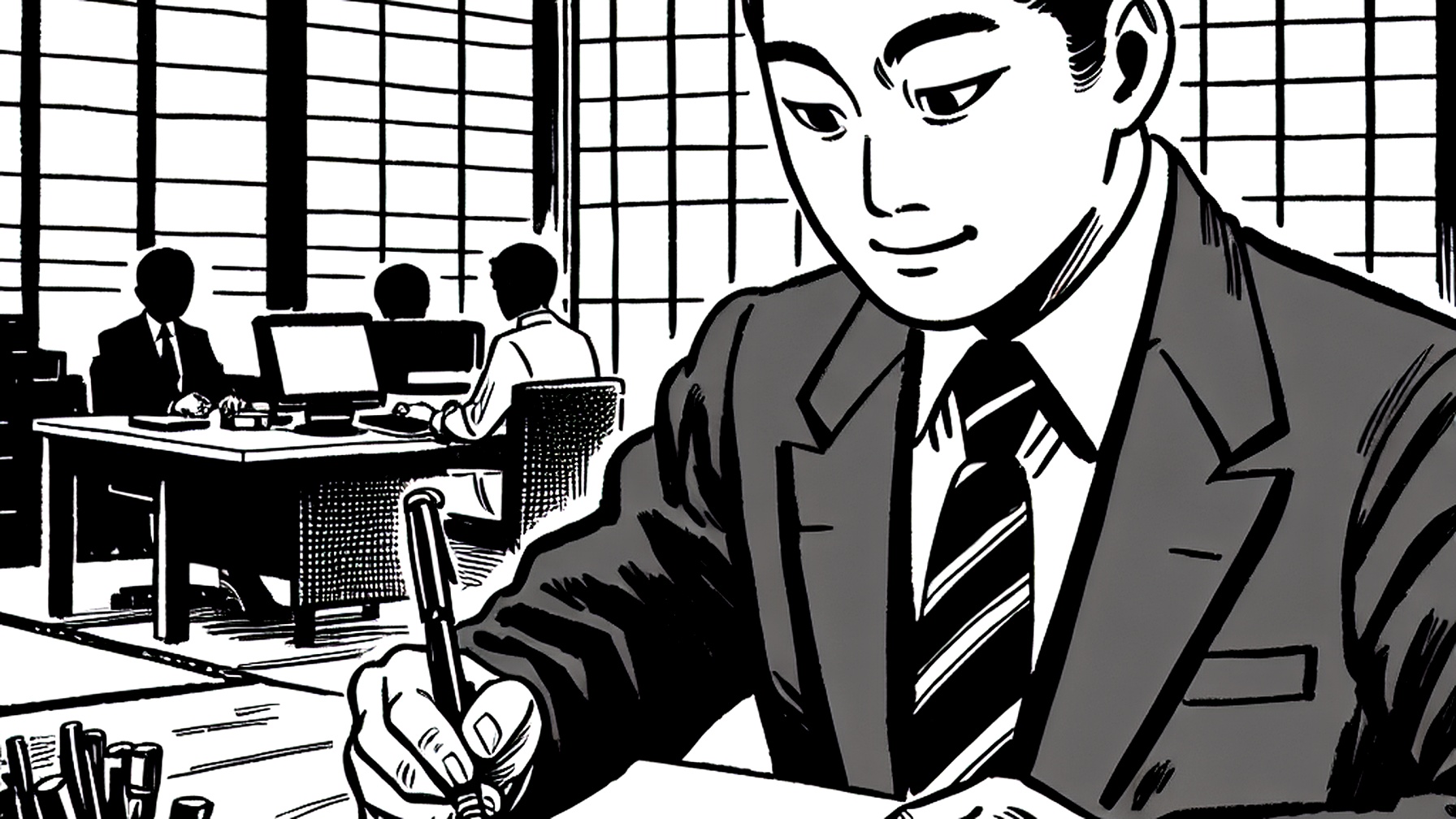
まず押さえておきたいのは、収支シートを「収入」「運営費」「返済」「税金」の四つに分けることです。これだけで計算漏れが激減します。
収入欄には家賃と共益費以外に、駐車場や太陽光売電など副収入を加えます。例えば、埼玉県で月額2万円の駐車場を2台運営すれば、年間48万円の上乗せが可能です。
運営費には修繕費の積立を忘れないようにしましょう。国交省「長期修繕計画ガイドライン」では、屋根防水や外壁塗装を含めた大規模修繕を12年周期で推奨しています。年間家賃収入の10%を目安に積み立てれば、急な出費に慌てずに済みます。
返済欄では、元金と利息を分けて記載すると、借入残高の減少スピードが見えやすくなります。また、繰上返済を実施する年をシミュレーションに加えると、利息軽減効果を具体的に把握できます。
税金欄には所得税と住民税に加え、2025年度も継続している不動産取得税の軽減措置の適用有無を記載します。適用される場合は取得後6か月以内の申請が必要なので、スケジュールに書き込むと抜け漏れが防げます。
空室率と家賃下落をどう織り込むか
ポイントは、楽観シナリオだけでなく「現実的に起こりうる悪化ケース」で試算することです。
家賃下落率について、東京23区の実績値は2024年平均で前年比−1.2%(住宅・不動産統計年報)。小幅とはいえ、築15年を超えると下落ペースが加速する傾向があります。そのため、築浅物件でも15年後には家賃が10%程度下がる前提で計算すると安全圏に入ります。
空室率はエリアによって振れ幅が大きいものの、日本不動産研究所の調査では全国平均7.5%でした。都心ワンルームでも3%は見込んでおくと保守的です。仮に「家賃10%下落+空室率10%」という厳しめシナリオを設定し、なお年間キャッシュフローが黒字なら、リスク耐性は高いと言えます。
さらに、原状回復費用を空室発生時のコストとして計上すると現実味が増します。1世帯あたり平均15万円と見積もり、5年に1回入退去が起こる設定で試算すると、長期のキャッシュフロー曲線が滑らかになります。
融資条件が変わると利回りはこう動く
実は、融資条件を1%改善するだけで利回りが数%上がることがあります。
例えば、3000万円を金利2.2%、期間25年で借りる場合、年間返済額は約158万円です。金利を1.5%に下げられれば年間返済は約144万円となり、表面利回り8%の物件なら実質利回りが0.5ポイント改善します。金融機関比較の重要性が伝わるでしょう。
近年は地銀よりも信用金庫が投資家向け融資に積極的です。2024年下半期、首都圏の信金平均金利は1.3%台まで下がり、事務手数料も低めに設定されています。ただし、融資額の上限やエリア制限があるため、複数行を回り自分の属性に合う先を探すことが大切です。
また、団体信用生命保険(団信)の特約内容にも注目してください。がん特約付き団信は金利に0.2%上乗せされるのが一般的ですが、保険料節約のために別途生命保険で代替する方法もあります。ここまで比較して初めて、正確な収支計算が完成します。
税金と減価償却、2025年度のポイント
基本的に、税金は「払う額」と「戻る額」の両面で考えます。減価償却費が大きいほど所得税は軽くなり、キャッシュフローを押し上げます。
木造アパートの法定耐用年数は22年です。築古物件の場合、残存耐用年数が短いため1年あたりの償却費が大きく、購入初期は税負担が軽減されます。しかし償却が終わると課税所得が急増するので、繰上返済や設備更新をその時期に合わせ、経費をコントロールすると滑らかな納税カーブが描けます。
2025年度税制では、不動産所得に対する青色申告特別控除65万円が継続しています。複式簿記と電子申告が条件ですが、手間に見合うメリットは大きいです。例えば課税所得500万円の投資家なら、65万円控除で住民税も合わせ約14万円の節税が可能になります。
さらに、長期譲渡所得の税率は2025年度も20.315%で据え置かれる見込みです。保有期間5年目以降の売却を視野に入れて出口戦略を計算すると、売却益とキャッシュフローの総合収益が読みやすくなります。
まとめ
本稿では、2024年の市場データを活用した収益物件の収支計算手順を解説しました。キャッシュフローの概念を押さえ、管理費や税金を細部まで盛り込むことで数字のブレは小さくなります。さらに、空室率や家賃下落といったシビアな条件をシミュレーションに入れ、融資条件や税制メリットを最大化すれば、投資判断は一段と精緻になります。今日から試算シートを作り、将来の不安を「確認済みの数字」に変えてみてください。行動を起こすことで、不動産投資の成功確率は確実に高まります。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場景況感調査2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2024 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資動向レポート 2025年3月 – https://www.jfc.go.jp
- 日本不動産研究所 不動産投資市場調査2024 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 長期修繕計画ガイドライン 2024改訂版 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 税制改正大綱2025年度 – https://www.mof.go.jp

