マンション投資を勧められたものの、「自分にはいらないのでは」と迷う声をよく耳にします。確かに投資額は大きく、長期のローンも伴うため、判断を誤ると家計に大きな影響が出ます。本記事では、マンション投資の必要性を客観的に見極めるための視点を整理し、投資以外の選択肢も含めて比較します。読後には、自分にとって本当に必要かどうかを冷静に判断できるはずです。
資産形成の手段は1つではない
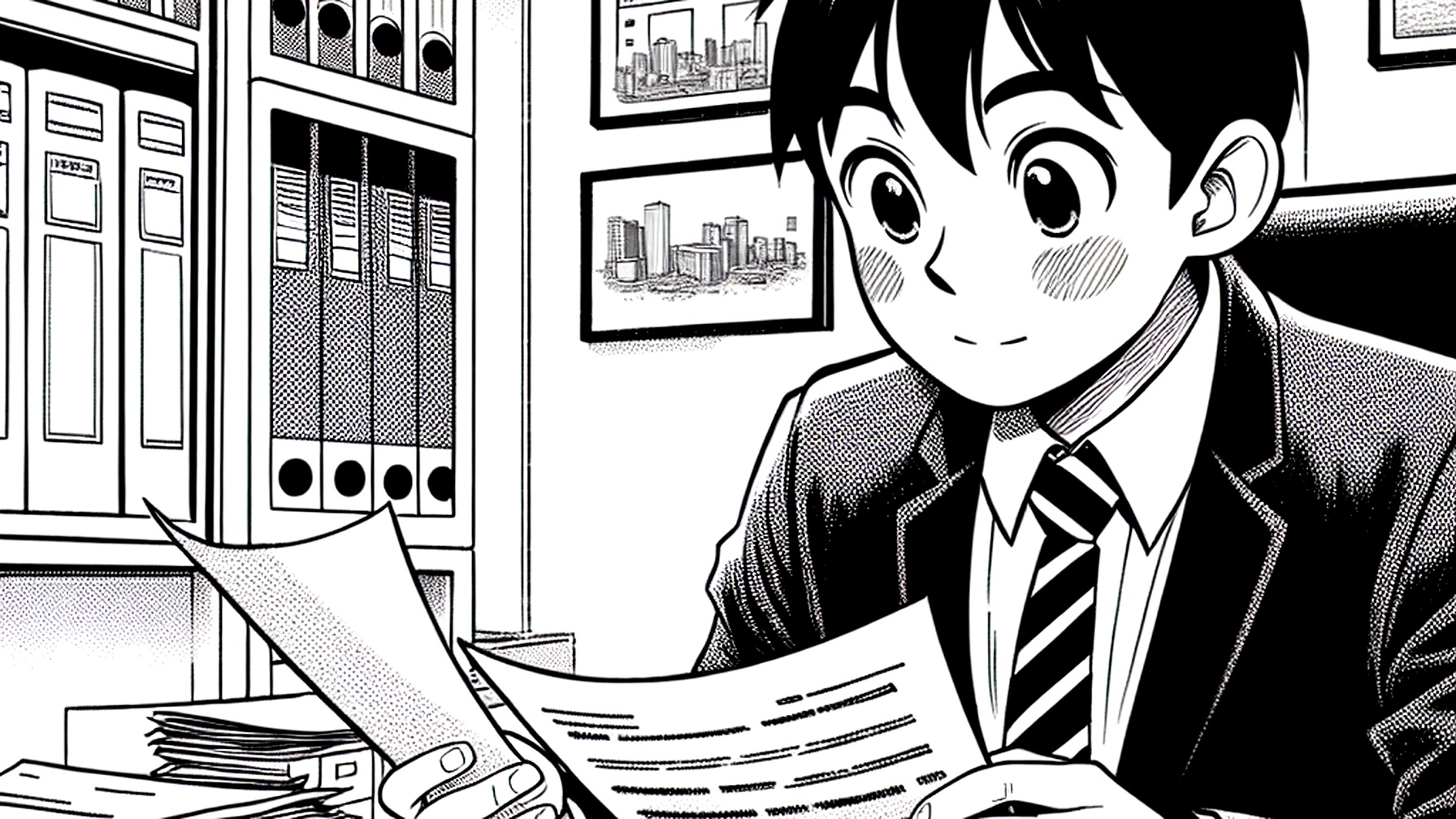
重要なのは、資産形成には複数のルートがあると理解することです。株式や投資信託、iDeCo(個人型確定拠出年金)、さらには副業など、マンション投資以外にも選択肢は多彩です。例えば金融庁の家計調査によると、30代の金融資産保有率は年々上昇しており、2024年時点で平均703万円に達しました。これはNISAやiDeCoの普及が背景にあり、少額から分散投資を行う人が増えている証拠です。また、2025年度も住宅ローン減税は自宅取得向け制度として継続していますが、投資用物件には適用されません。つまり節税メリットを求めるなら、まずはiDeCoなど他制度の活用を検討する価値があります。
キャッシュフローの現実を直視する
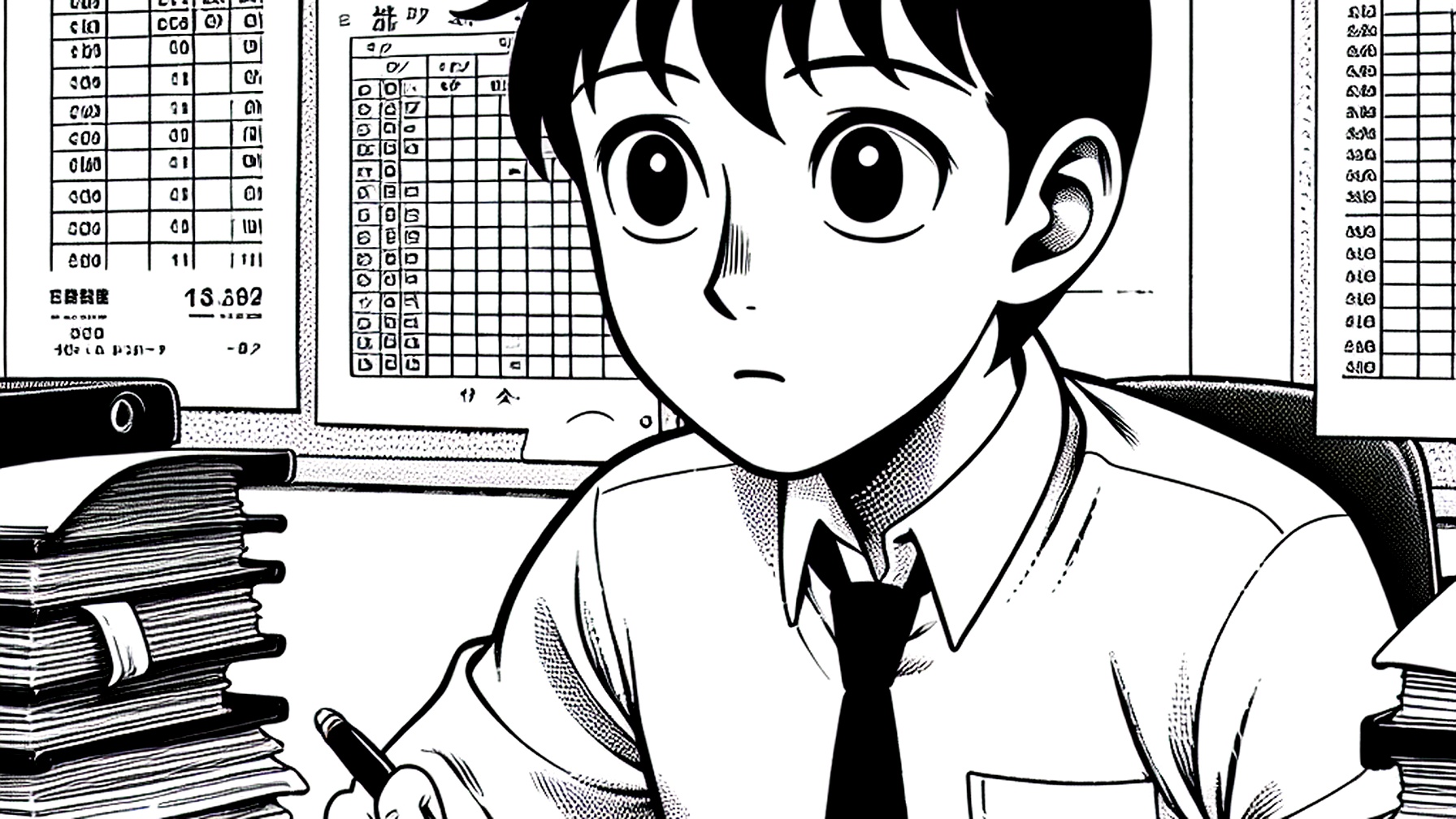
まず押さえておきたいのは、家賃収入と支出のバランスです。毎月のローン返済、管理費、修繕積立金、固定資産税を差し引き、手元に残る現金がプラスかどうかが成否を分けます。不動産経済研究所によると、2025年9月の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円で前年より3.2%上昇しました。仮に7,000万円の物件を金利1.5%・35年返済で購入すると、月々の返済は約21万円になります。一方、同エリアの平均家賃相場はファミリー向けでおよそ23万円です。空室リスクを考慮すると、毎月の手残りはわずか数万円程度になり、修繕費の蓄積が不足しかねません。結果として、キャッシュフローが安定しないケースが多発するのが実情です。
空室リスクと人口動態の関係
ポイントは、人口動態が将来の空室率に直結する点です。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、東京都23区の人口は2035年までは緩やかに増えますが、2040年以降は減少に転じる見込みです。一方で、分譲・賃貸双方の供給は高水準を維持する可能性が高く、新築着工戸数は2024年度も38万戸を超えました。供給が需要を上回れば、家賃は下落し、空室期間は長期化します。つまり、長期保有を前提にする投資なら、将来人口が維持されるエリアかどうかを慎重に吟味する必要があります。地方都市で利回りが高い物件に飛びつくと、人口減少により入居者確保が難しくなり、結果として「マンション投資 いらない」という後悔につながりやすいのです。
節税効果と出口戦略の誤解
実は、節税メリットだけを理由に投資を決断するのは危険です。不動産所得の赤字を給与所得と損益通算して税負担を減らす手法は有名ですが、税制改正により適用条件が年々厳しくなっています。2025年度も減価償却期間の見直し議論が続き、高額物件を短期間で償却するスキームは難度が高まりました。さらに、物件を売却して利益を確定する際には譲渡所得税が重くのしかかります。購入から5年以内なら税率39.63%、5年超でも20.315%が課税されるため、売却益を想定していた計画が狂うことも珍しくありません。したがって、節税と出口戦略を組み合わせたシナリオほど慎重な試算が欠かせます。
生活設計とリスク許容度の見極め方
基本的に、投資判断は家計全体の安全余裕度とセットで考えるべきです。金融庁の「資産形成シミュレーション」では、年収の20%を投資に回しつつ、6カ月分の生活費を現金で確保するモデルが推奨されています。この指標を用いると、年収600万円の世帯で年間120万円が投資限度額の目安になります。一方、マンション投資の自己資金は物件価格の2〜3割が一般的で、都内物件なら1,000万円以上を用意するケースも少なくありません。つまり、自己資金が家計に占める割合が大きすぎると、収入減や金利上昇に耐えられなくなります。リスク許容度を数値化し、株式や投資信託と比較したうえで「それでも挑戦するか」を判断することが、後悔しないための近道です。
まとめ
ここまで、資産形成の多様性、キャッシュフローの現実、人口動態、税制、リスク許容度という五つの視点からマンション投資の必要性を検証しました。これらを総合すると、自己資金と家計への影響を冷静に計算し、長期的な人口動向まで視野に入れられる人だけがマンション投資に向いていると言えます。もし不安が残るなら、少額から分散投資できる金融商品で経験を積む方法も立派な選択肢です。最後に、投資は手段であって目的ではありません。自分の暮らしと将来像に照らし合わせ、「本当に必要か」を丁寧に見極めてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 金融庁 家計調査 – https://www.fsa.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 人口推計 – https://www.ipss.go.jp
- 国税庁 譲渡所得税ガイド – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp

