家賃相場が高い東京でアパート経営を始めたいものの、どのエリアを選べば良いか分からず一歩踏み出せない人は多いはずです。立地は長期の収益を左右する最重要ファクターであり、選び方を誤ると空室と家賃下落の二重苦に陥ります。本記事では東京都内での立地選定に焦点を当て、初心者でも実践できる判断基準と最新データの読み解き方を解説します。読み終える頃には、自分の投資目的に合ったエリアを自信を持って絞り込めるようになるでしょう。
なぜ東京でアパート経営が選ばれるのか
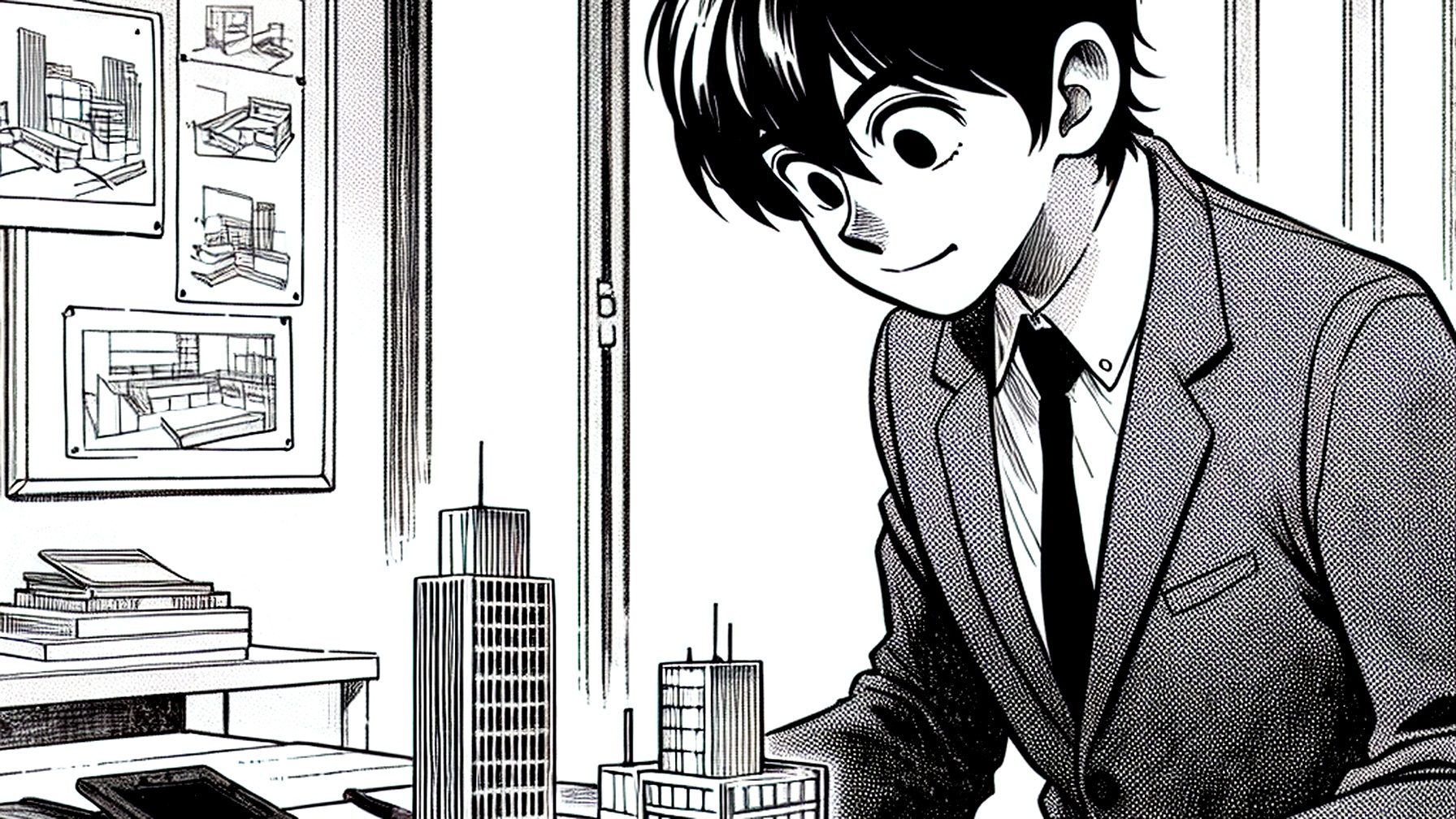
重要なのは、東京特有の人口動態と賃貸需要の安定性を理解することです。東京都の総人口は2025年1月時点で1,408万人と横ばいですが、20〜34歳の若年単身層は23区を中心に微増しています。総務省の住民基本台帳移動報告によれば、23区への転入超過は昨年比1.2万人増で、地方からの流入が依然として強い傾向です。
この若年層はワンルームや1Kなど小規模物件を求めることが多く、建物規模より立地を重視します。つまり、家賃が高くても通勤利便や生活利便が優先されるため、適切な駅徒歩圏を押さえれば安定した入居率が期待できます。国土交通省の2025年7月住宅統計では、全国空室率が21.2%であるのに対し、東京23区の木造アパートは13%台にとどまっており、需要の底堅さが数字にも表れています。
一方で、都心部の土地価格は高止まりし、利回りは5%前後が一般的です。郊外なら7%台も狙えますが、将来の空室リスクが跳ね上がる点を忘れてはいけません。東京でアパート経営が支持されるのは、表面利回りよりも長期安定収益に価値を置く投資家が多いからだといえます。
立地選定の基本指標を押さえる
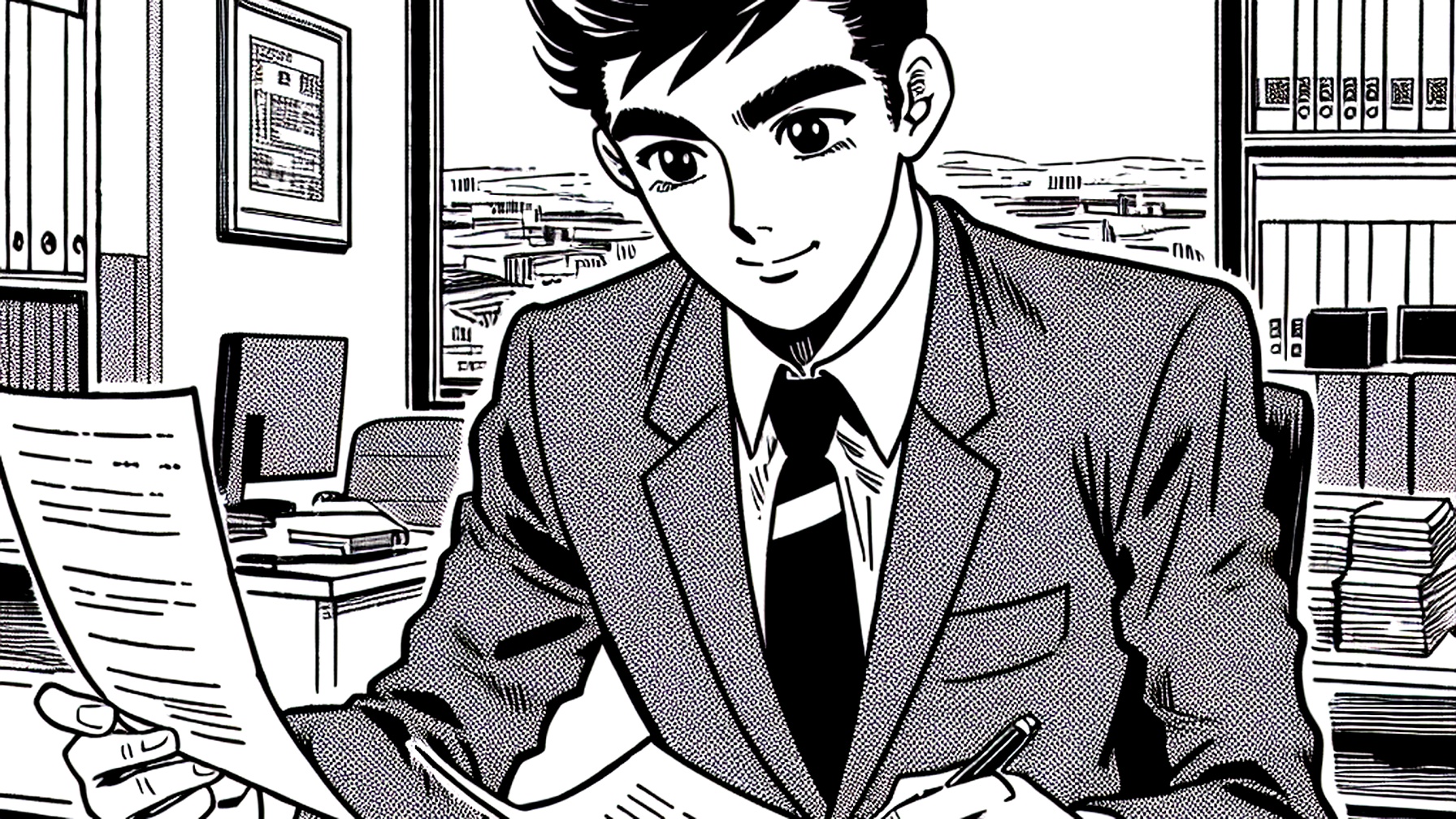
まず押さえておきたいのは、駅距離・乗降客数・生活インフラという三つの指数です。駅徒歩10分圏内は入居者募集の反響が約1.8倍になるとの日本賃貸住宅管理協会の2024年度調査があります。乗降客数は、10万人以上の駅で空室期間が平均1.2ヶ月短縮されるデータも示されています。
ただし、単純に「駅に近い=優良」ではありません。例えば都心ターミナルに直結する急行停車駅でも、周辺にスーパーマーケットや病院が乏しければ長期居住を敬遠されるケースがあります。生活インフラは、スーパーマーケットまで徒歩5分以内か、夜23時まで営業しているかを最低ラインに設定するのが経験上の目安です。
さらに、東京都都市整備局が公開する都市計画図で、将来の再開発予定や用途地域の変更を確認しておくと安心です。用途地域が第一種低層住居専用の場合、商業施設が増えにくく利便性の伸びが期待薄となります。数字と都市計画情報を組み合わせ、現在だけでなく5年後10年後の姿を推測することが賢明です。
駅距離だけで判断しないエリア分析
実は、駅徒歩15分を超えても競争力を保つエリアが存在します。代表例が世田谷区の「等々力」や杉並区の「永福町」で、緑地面積が多く治安も良好なため、ファミリー層の長期定着率が高いことが特徴です。こうした地域では、家賃単価は周辺平均よりやや低下しますが、入居期間が4年以上と長期化するため、結果として空室損失が圧縮されます。
一方で、駅近でも短期退去が続くパターンが台東区や新宿区の一部に見られます。週末の騒音や観光客の多さが敬遠され、単身者が1年未満で退去するケースがあるからです。言い換えると、表面的なアクセスの良さよりも、居住環境の質が収益に直結します。
エリア分析を行う際は、国勢調査の町丁目別人口推移と警視庁公開の犯罪発生マップを照らし合わせると実態が把握しやすくなります。また、近年は位置情報アプリによる昼間人口データも公開されており、昼夜間人口差が小さい街は生活関連店舗が継続的に出店する傾向が強いです。こうした複合的な視点で「長く住みたい街か」を見極めましょう。
2025年時点の需要トレンドと賃料動向
ポイントは、都心集積の加速と郊外二極化の進行です。三菱UFJリサーチの2025年4月家賃指数では、千代田・港・中央の平均募集家賃が前年比4.1%上昇した一方、多摩北部では0.8%下落しました。これは在宅勤務の浸透で「会社から近いコンパクトな住まい」を再評価する動きが影響しています。
賃料上昇が続くエリアほど利回りは下がるものの、空室リスクは低減します。キャッシュフローの安定を優先するなら湾岸や城東エリア、キャピタルゲインも狙うなら再開発が進む品川・高輪周辺が注目されています。区画整理と新駅開発が予定されており、2029年開業予定の品川地下駅は既に地価を押し上げています。
一方で、都心回帰の裏で狙い目となるのが“選ばれる郊外”です。横浜線沿線の町田やJR中央線の国立は大学と研究施設が集中し、安定した賃貸需要があります。東京都心へ乗り換えなしでアクセスでき、駅前再開発に伴い生活利便が向上しているため、今後も家賃の下支えが期待できます。
リスクを抑える物件購入の進め方
まず、融資条件と利回りのバランスを冷静に見極めることが欠かせません。2025年度の日本政策金融公庫では、耐用年数が残存15年以上の木造アパートに対し、2.1%固定金利・最長25年の融資が提供されています。自己資金2割を入れると返済比率が抑えられ、金利上昇局面でもキャッシュフローが黒字を維持しやすくなります。
購入の流れは「物件選定→収支シミュレーション→金融機関打診→現地調査→売買契約」が一般的ですが、現地調査は最低2回行うと失敗が減ります。平日昼と土日夜に訪れ、騒音やゴミ捨て状況を確認するだけで、長期入居の障害がないか見極められます。
空室対策としては、Wi-Fi無料設備と宅配ボックス設置が効果的です。日本郵便の2025年2月調査によると、宅配ボックス設置物件の入居決定速度は未設置の1.4倍でした。初期費用は一戸あたり6万円前後ですが、家賃を月500円上乗せするだけで2年半で回収できる計算になります。
最後に、管理会社の選定も収益に直結します。管理手数料は家賃の5%が相場ですが、リーシング力や設備提案力が高い会社は空室日数を削減し、実質利回りを底上げしてくれます。複数社の実績を比較し、空室率と平均入居期間の実データを提示させることがポイントです。
まとめ
東京でのアパート経営を成功させるカギは、短期の利回りにとらわれず、将来の人口動向と生活インフラの伸びしろを読む立地選定にあります。駅徒歩や乗降客数といった定量指標に加え、居住環境や再開発計画など質的要素を多角的に評価しましょう。そして、堅実な融資条件と設備投資で空室リスクを抑えれば、家賃上昇を取り込みながら長期安定収益を実現できます。まずは気になるエリアを一つ選び、平日と休日に歩いてみることから始めてみてください。実地調査こそ、紙の数字を確信へと変える最短ルートです。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp/statistics.html
- 東京都都市整備局 都市計画情報 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 2025年 – https://www.stat.go.jp/
- 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場データ 2024年度 – https://www.jpm.jp/
- 日本政策金融公庫 2025年度 融資制度概要 – https://www.jfc.go.jp/

