不動産投資ローンを検討し始めると、「保証人は必要なのか」「保証会社との違いは何か」といった疑問が必ず浮かびます。もし条件を誤解したまま契約してしまうと、後から追加保証を要求されたり、金利が上がったりするリスクがあります。本記事では、初心者でも理解できるよう不動産投資ローンと保証人制度の仕組みを整理し、2025年9月時点の融資動向まで踏まえて解説します。読み終えるころには、自分に合った借入方法を判断し、金融機関との交渉を有利に進めるための視点が身につくはずです。
不動産投資ローンの基本構造
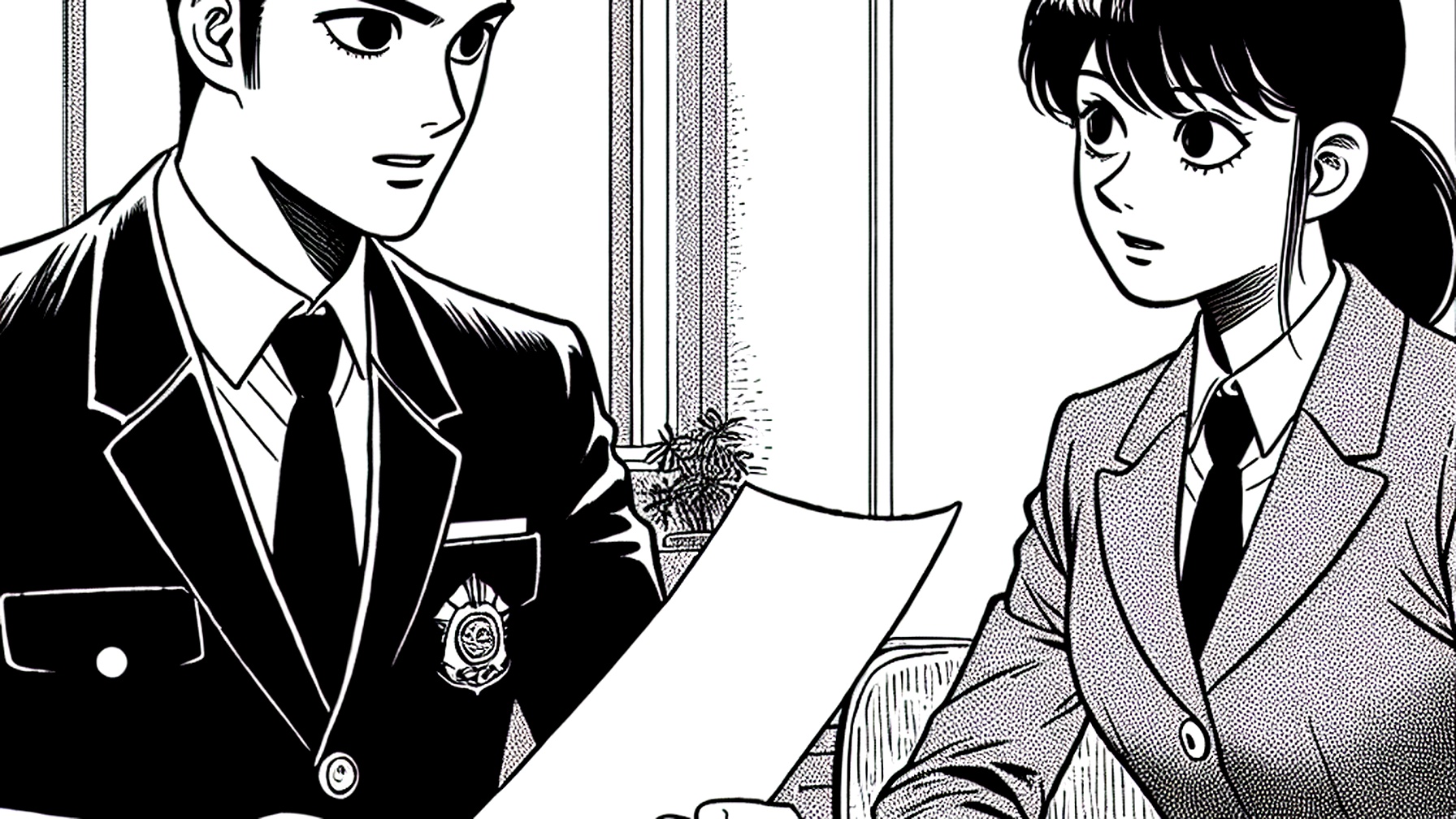
まず押さえておきたいのは、投資用ローンが自宅用ローンと根本的に異なる点です。不動産投資ローンは家賃収入を返済原資と見なすため、物件の収益性と申込者の与信力の両方が審査対象になります。また、住宅ローン控除のような居住用の優遇は適用されません。
日本銀行の「貸出・金利動向」(2025年6月)によると、個人向け投資ローンの平均金利は変動1.8%、10年固定2.7%前後です。自宅用ローンより0.5〜1.0ポイント高いのは、空室や賃料下落のリスクを金融機関が織り込んでいるためです。つまり、利回り試算の際には調達金利をやや高めに設定しておくと、資金計画が狂いにくくなります。
さらに、金融機関は融資実行と同時に「保証」を必須条件とする場合が多いです。保証の形式には「人的保証」と「保証会社保証」があり、それぞれメリットと負担が異なります。ここから先は、この二つの違いを丁寧に見ていきましょう。
保証人制度の仕組みと役割
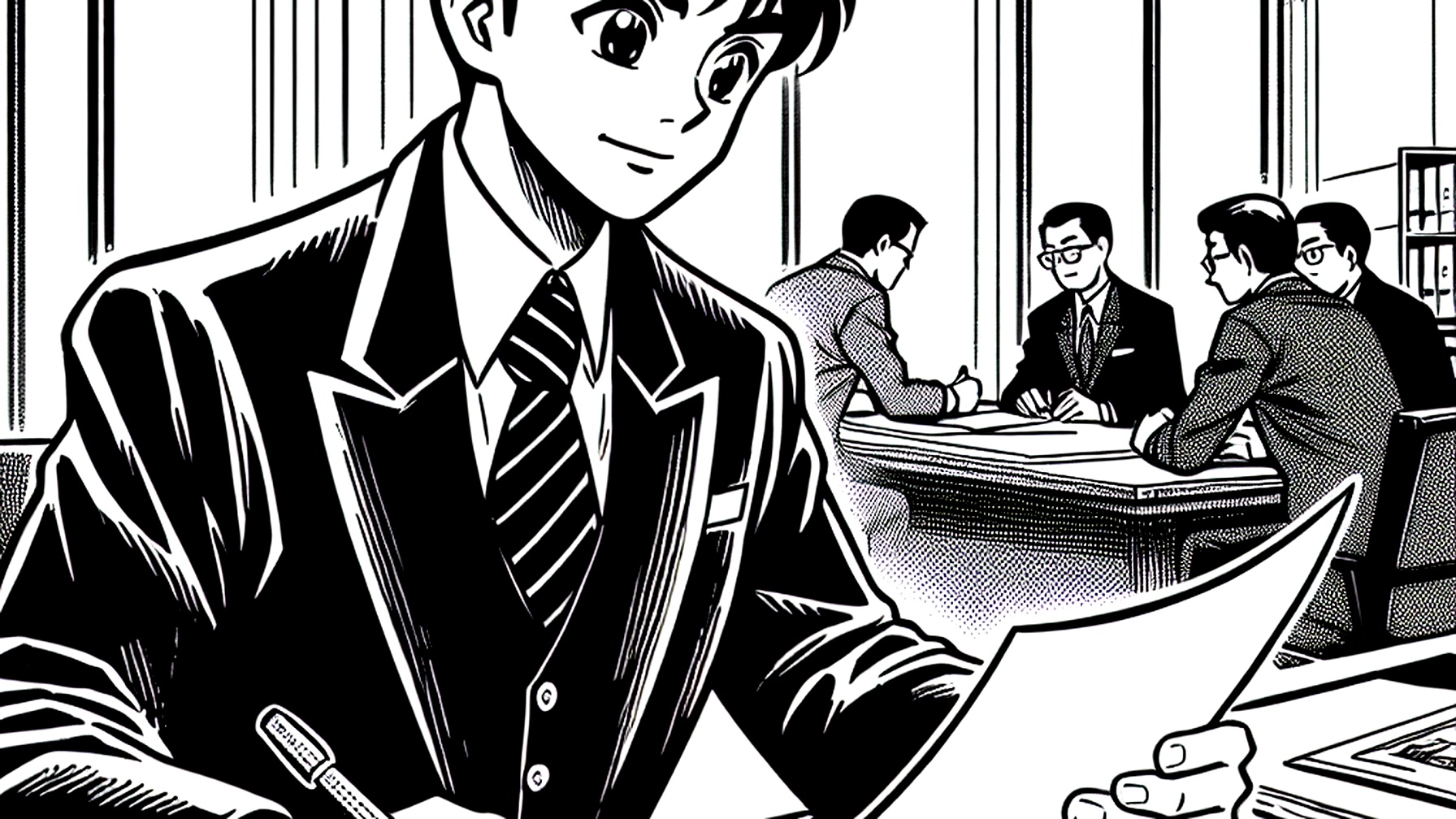
重要なのは、保証人が単なる「念のための連帯署名」ではないという事実です。保証契約は民法の改正(2020年施行)によって極度額の設定が義務化されましたが、投資ローンの場合は債務全額を極度額とみなすケースがほとんどです。つまり、万一返済不能に陥れば、保証人にも債務の全額が請求されます。
加えて、保証人は「連帯保証人」であることが一般的です。連帯保証人は主債務者と同列に責任を負い、催告の抗弁権(先に本人へ請求してほしいと言える権利)を放棄します。そのため、家族や友人に頼む場合は説明責任が非常に重く、関係性にも影響しかねません。
一方で、人的保証を付けると金利や手数料が下がる場合があります。特に地域金融機関では「保証人を入れてくれるなら金利を0.2ポイント優遇」という提案が残っています。金利負担と人間関係リスクをどう比較するかが、投資家にとって大きな判断材料になります。
不動産投資ローンで保証人が必要なケース
ポイントは、保証人が必須か任意かが金融機関ごとに異なることです。都市銀行やメガバンクは保証会社の利用を原則とし、人的保証は求めません。しかし、地方銀行や信用金庫では以下のような条件で保証人を要求する例があります。
- 融資額が1億円を超え、かつ自己資金が物件価格の10%未満
- 新設法人で決算実績がなく代表者保証も不足している
- 物件の収益還元評価が低く、担保余力が薄い
これらに該当しなければ、保証会社のみで対応できるケースが増えています。国土交通省「不動産価格指数」(2025年3月)では、地方都市の収益物件価格が横ばいで推移しており、担保評価に不安がある物件が増加傾向です。そのため、地方物件を狙う投資家ほど保証人要件に注意が必要と言えます。
保証会社利用との違いと比較ポイント
実は、多くの投資家は保証会社を使った方がトータルコストを抑えられることに気づいていません。保証会社とは、保証料を支払う代わりに返済不能時のリスクを肩代わりしてくれる専門業者です。保証料は融資額の2.0〜2.5%が初回一括で、もしくは年0.2%程度を分割で支払います。
人的保証と比べた主な違いは三つあります。第一に、債務不履行時の追求が本人にとどまり、家族や知人に波及しにくい点です。第二に、保証料は経費計上できるため、税務上のメリットがあることです。第三に、借換え時や追加融資時に保証審査が簡易化されやすく、スピード感を持って資産拡大を図れます。
一方で、保証会社を利用すると金利が0.1〜0.3ポイント上乗せされる場合があります。全国銀行協会の2025年9月資料でも、保証料込みの実質金利は平均2.1%と発表されています。したがって、保証料と金利差を合算した「総返済コスト」を必ずシミュレーションすることが欠かせません。
2025年度の融資環境と賢い準備法
まず押さえておきたいのは、2025年度の金融行政方針で地域銀行の資産査定が厳格化された点です。金融庁は不良債権化リスクのある投資ローンに対し、自己資本比率の追加積み増しを求めています。この影響で、一部の地方銀行は保証人を付けない融資への慎重姿勢を強めています。
しかし、対策はシンプルです。具体的には自己資金を2〜3割用意し、物件収支を金利3%・空室率20%の厳しい条件でシミュレーションしておくことです。ここまで準備しておくと、保証会社のみでも十分と判断されるケースが増えます。また、金融機関の担当者にキャッシュフロー表と長期修繕計画を示すと、返済能力への信頼が高まり、保証人不要の提案を引き出しやすくなります。
さらに、法人化を検討する場合は代表者保証の扱いに注意が必要です。2023年の「経営者保証改革プログラム」の対象は事業性融資であり、投資ローンは原則外ですが、決算書の健全性を示せば保証人免除を認める銀行もあります。賃貸経営を事業として位置付け、期末に内部留保を残すことが将来の交渉力を高めるポイントになります。
まとめ
本記事では、不動産投資ローンにおける人的保証と保証会社の違いを中心に、2025年の融資環境まで整理しました。人的保証は金利優遇を得やすい半面、人間関係リスクが大きいです。対して保証会社はコスト増となるものの、リスクを限定でき、税務メリットも見込めます。結論として、自己資金を厚くし、物件収支を厳しく見積もるほど保証会社のみで借りられる確率が高まります。まずは複数の金融機関でシミュレーションを取り、総返済コストを見比べたうえで、自分に合った保証形態を選択してください。
参考文献・出典
- 日本銀行「貸出・金利動向」2025年6月 – https://www.boj.or.jp
- 全国銀行協会「個人向け融資金利データ」2025年9月 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省「不動産価格指数」2025年3月 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁「金融行政方針」2025年度版 – https://www.fsa.go.jp
- 中小企業庁「経営者保証改革プログラム」2023年 – https://www.chusho.meti.go.jp

